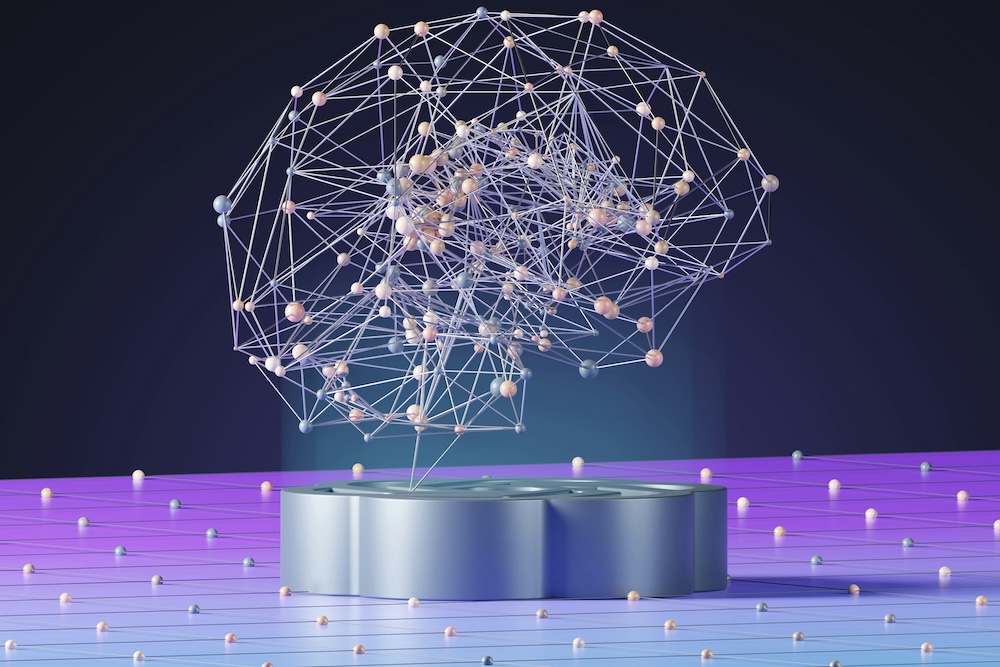デジタルコンテンツの著作権問題

Photo by Eugene Zhyvchik on Unsplash
デジタルコンテンツの著作権問題とは(Understanding Issues about Copyright of Digital Content)
デジタルコンテンツの著作権問題とは、インターネットの普及やSNSの拡大といったデジタル化の進展により、コンテンツが容易にコピーされ、共有されることから生じる著作権侵害の問題を一般的に指します。
特に、侵害コンテンツ(海賊版)の流通により、創作者が自身の作品で生計を立てる権利が侵害されることで、社会に流通するコンテンツの量や質が低下する恐れが指摘されています。
目次
デジタルコンテンツとは?(Understanding Digital Content)
デジタルコンテンツ協会によると、「デジタルコンテンツ」とは、デジタル形式で消費者に提供されるコンテンツを指します。これには、動画、静止画、音声、文字、プログラムなど、様々な形式で構成された情報が含まれています。デジタルコンテンツは、DVDなどのパッケージ、ネットワーク配信、劇場上映、放送などのメディアを通じて流通されます。
デジタルコンテンツは知的財産であり、著作権という知的財産権の対象となります。著作権は作品が創作された時点で自動的に発生し、その後の一定期間にわたり、創作者は著作権法に基づく権利を行使できます。
数字で見るデジタルコンテンツの著作権問題(Facts & Figures)
- 2023年、日本のコンテンツ産業の市場規模は13兆3,597億円(前年比102.3%)に達し、前年に続いてプラス成長となった。デジタルコンテンツ協会が2001年に調査を開始して以来、最高記録を更新した(デジタルコンテンツ協会)
- 2023年、コンテンツの種類別(日本)では、市場規模が最も大きいのは動画の4兆2,318億円で、次いで静止画・テキストが2兆8,628億円、複合型が2兆6,870億円、ゲームが2兆1,969億円、音楽・音声が1兆3,811億円となった(デジタルコンテンツ協会)
- 2023年、メディアの種類別(日本)では、ネットワークが過去最高の5兆5,583億円、放送が3兆2,745億円、パッケージが2兆7,596億円、劇場・専用スペースが1兆7,674億円となった(デジタルコンテンツ協会)
- 2023年、日本のデジタルコンテンツ市場は、前年比102.6%増の10兆3,270億円となり、コンテンツ産業全体に占める割合は77.3%となった(デジタルコンテンツ協会)
- 巨大海賊版サイト「漫画村」では、約3,000億円相当の出版物が無料で読まれ、その結果、漫画家や出版社の収入や売上が大幅に減少したという試算がある。また、日本最大級の海賊版リーチサイト「はるか夢の址」では、1年間の被害額が約731億円に達するとの試算も報告されている。(文化庁)
- 「漫画村」や「はるか夢の址」のサイトが閉鎖された後も、依然として多くの海賊版サイトが存在しており、2019年11月時点のアクセス数上位10サイトだけで、月間利用者が6,500万人に達していた(文化庁)
デジタルコンテンツの著作権問題の現状(Current Situation)
近年、デジタルコンテンツはインターネットを通じて拡大し、その流通範囲はグローバル化しています。SNSの普及などにより、個人の創作活動が活発化し、新しい文化やビジネスが誕生しています。
コンテンツの複製や送信が簡単になり、その利用は著作者の利益や文化の形成に大きな影響を及ぼしています。加えて、著作権侵害の形態も多様化しています。
侵害コンテンツ(海賊版)の流通
インターネットの進展により、音楽、映画、マンガなど、さまざまなデジタルコンテンツが国境を超えて流通しています。一方で、これらのコンテンツは、創作者の許可なしに無断でコピーされ、動画共有サイトや個人のウェブサイトで配信されることがあります。
このように、創作者の権利である著作権を侵害し、無断でインターネット上で配信されるコンテンツは「侵害コンテンツ」または「海賊版」といいます。海賊版による被害は、漫画、雑誌、写真集、文芸書、専門書、ビジネスソフト、ゲーム、学術論文、新聞など、幅広い分野の著作物に広がっています。
正規のサイトは、会費制などの有料サービスを導入するなどして収益を得ており、その収益は創作者に還元され、新たなコンテンツ創作の資金となります。対照的に、侵害コンテンツはほとんどが無料で利用可能で、その収益は創作者に還元されません。創作者は十分な報酬を得られないため、コンテンツ創作への意欲が低下し、その結果、良質なコンテンツが生まれず、社会に流通するコンテンツの量や質が低下する恐れがあります。

Photo by Bank Phrom on Unsplash
「デジタルコンテンツのアンチコモンズ問題」
著作権法第1条は、次のようにその目的を定めています。
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする
文化の発展に貢献するためには、著作者の権利を守りながら、コンテンツの利用を促進することが求められます。
しかし、デジタルコンテンツの利用における権利処理の煩雑さが原因で、その利用が敬遠されるというケースがあります。この問題は、大阪公立大学の金野教授によって「デジタルコンテンツのアンチコモンズ問題」として説明されています。
この問題は、一つのコンテンツに対して複数人が権利を持ち、それぞれが他者の二次利用を拒否できる状況で、そのコンテンツの利用が難しくなり、その結果、適切かつ活発な利用が阻害されるというものです。金野教授は、この問題を過去のテレビ番組の再放送や再販に例え、テレビ局や制作会社、出演者全員から利用許諾を得る必要があるため、権利処理が煩雑になり、再放送が断念されてしまうことだと説明します。
コンテンツを合法的に利用したい場合でも、その利用のためのプロセスが煩雑であれば、資源の効率的な活用を妨げ、権利者や潜在的消費者の利益を損なう恐れがあります。
AIによる著作物
最近では、音楽や小説などの大量の知的財産データを使用して、新しい作品を創作するAIの開発とその利用が現実となってきています。このようなAIが創作した作品が果たして著作物として認められるのか、もし著作物と認められた場合には、その著作権が誰のものなのかについて議論が行われています。
デジタル時代に対応した著作権の確立
著作権法は、アナログコンテンツが主流だった時代に基本が定められたため、デジタルコンテンツに適切に対応することが課題となっています。現在も海賊版などの問題が存在し、著作権は十分に機能していない状態です。デジタルコンテンツが広く流通する現代において、著作権法が実質的に機能しなければ、法律上で保護されていても創作者の権利を守ることはできません。
デジタル技術の進展とインターネットの急速な普及により、創作者がコンテンツの使用状況を監視し、違反者に対して罰則を科すことが非常に難しく、高いコストがかかるようになりました。その結果、著作権が十分に機能せず、コンテンツの無断利用や、逆にコンテンツ利用に伴う権利処理の煩雑さが顕在化しました。コンテンツ制作者は、監視や罰則の実施を断念することも少なくありません。
著作権が十分に機能する状態とは、権利内容や権利者の情報が簡単に得られ、利用状況を監視し、違反者に適切な罰則を科すことが物理的、経済的に可能な状態を意味します。立法や権利付与が行われていても、違法行為の監視と違反者への罰則が機能していなければ、著作権は実質的に意味を持たないことになります。
監視や罰則にかかるコストの削減や、権利処理の簡素化は、海賊版問題や「アンチコモンズ問題」の改善に繋がると考えられています。
デジタルコンテンツの著作権問題への取り組み(Action)
「インターネット上の著作権侵害等への権利行使支援事業」を開始
2025年1月から、インターネット上での著作権侵害に対して、個人クリエイターなどの権利行使(削除申請、侵害者特定、損害賠償請求など)のための弁護士費用等を支援する取り組みが始まりました。このプロジェクトは、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)の「共通目的事業」として実施されるもので、SARTRASの委託を受けた一般社団法人日本ネットクリエイター協会(JNCA)が運営します。文化庁が設立した相談窓口での個別相談を通じて、著作権侵害の可能性が高い事例が対象となります。
DRM(デジタル著作権管理)
DRMとは、第三者によるデジタルコンテンツのコピー、編集、配布などを制限し、制作者や関連企業などの権利者を保護するための技術や仕組みのことで、国内外で広く利用されています。
主に、データを秘密の符号化方式で記録することで、特定のソフトウェアやハードウェアのみで再生できるようにし、コピーや再利用を防止する技術を指します。
映画や動画、音楽、書籍、ゲームなどを対象としており、各コンテンツの不正なアクセスや利用を防ぐことを目的としています。
クリエイティブ・コモンズ(CC)
クリエイティブ・コモンズは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を提供する国際的NPOおよびその関連プロジェクトの総称のことを指します。2001年に米国で始まり、日本でも普及しているライセンス体系です。DRMとは異なり、著作者が許可しない利用を技術的に制限するツールではありません。
CCライセンスは、デジタル時代に適応した新しい著作権の仕組みであり、著作者が、この条件に従えば自分の作品を自由に利用しても構わない、と意思表示するためのツールです。著作者自身がその作品の利用許可範囲を明確に示し、作品の再利用を容易にすることを目的としています。情報を共有する際に著作権法が障害となる場合がありますが、CCはそのような法的問題を避けるために設計されています。
このツールを活用することで、創作者は著作権を保持しつつ、作品を自由に流通させ、利用者は示されたライセンス条件に従い、再配布やリミックスなどを行うことができます。
CCライセンスには6種類の組み合わせがあり、著作者は自分の作品をどのように流通させたいかを考慮し、最適なライセンスの組み合わせを選択することになります。例えば、原作者のクレジット表示を条件に、営利目的での二次利用も許可するライセンスや、原作者のクレジットを表示し、非営利目的で改変を行わないことを条件に作品の再配布を許可するライセンスもあります。
CC支持者を含むオープンインターネットの推進派の間では、知識や文化は広く共有されるべきであり、著作権の過度な制限が創造や学習の機会を妨げるという考えが存在します。一部には、インターネットの自由を重視し、学術論文や政治的発言などの作品は、検閲や営利目的による過度な制約を受けず、誰でも無料で広く利用できるべきだとする主張や、海賊版対策を名目に、当局や企業が恣意的な情報制限を行う可能性があると指摘する声もあります。
著作権法改正
2020年に施行された「著作権法およびプログラムの著作物に関する登録特例法の一部改正法」は、インターネット上での海賊版対策や著作物の適切な保護および利用促進を目的としています。海賊版対策強化の一環として、海賊版へ誘導する「リーチサイト」の規制や、海賊版の違法ダウンロード対象範囲の拡大が決定されました。これにより、リーチサイトの直接規制が可能となり、侵害コンテンツへのアクセスの抑制が目指されています。
また、2023年には「著作権法の一部を改正する法律」が成立し、デジタルトランスフォーメーション(DX)に対応した著作権制度の見直しが行われました。改正の背景として、一般の人々が自ら制作したコンテンツをインターネット上で公開する機会が増えていること、また、過去の作品を新たな形で活用したいという需要も高まっていることが挙げられます。
主な改正点は以下の3点です。
(1)著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設
既存のコンテンツの利用促進を目的に、集中管理がされておらず、利用可能かどうかの著作者の意思が明確でない著作物について、一定の要件を満たした上で文化庁長官の許可を得て補償金を支払えば、一時的に利用できる仕組みです。また、新制度の手続きを簡素化・迅速化するため、文化庁に認定を受けた民間機関も手続きの運営を担うことができます。
(2)立法・行政における著作物等の公衆送信等の権利制限規定の見直し
国会や行政機関の内部で、立法や行政業務のための内部資料として、著作権者の許可を得ることなく、著作物をメールやクラウドなどの公衆送信を利用して共有できる制度が導入されました。さらに、特許審査など迅速な判断が求められる行政手続きでも、公衆送信を可能にすることで、効率的な審査を実現しようとするものです。
(3)海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直し
著作権侵害による損害賠償請求訴訟において、著作権者の立証負担を軽減するため、損害賠償額の算定方法が見直されました。著作権侵害があったことを前提に、権利者が本来得られたはずのライセンス収入を損害賠償として請求しやすくする仕組みです。例えば、海賊版が大量に流通し、正規販売の規模を超えた場合でも、ライセンス機会の喪失による損害額として認定されるようになりました。
デジタルコンテンツの著作権問題に関連するアイデア(IDEAS FOR GOOD)
IDEAS FOR GOODでは、最先端のテクノロジーやユニークなアイデアで、デジタルコンテンツの著作権問題に取り組む企業やプロジェクトを紹介していきます。
著作権に関連する記事の一覧
【参照サイト】文化審議会 「デジタルトランスフォーメーション(DX)時代に対応した著作権制度・政策の在り方について 」
【参照サイト】デジタルコンテンツ協会「『デジタルコンテンツ白書2024』 発刊」
【参照サイト】デジタルコンテンツ協会:ホームページ
【参照サイト】著作権委員会 第 4 部会 「デジタルコンテンツの保護と利用についての研究」
【参照サイト】金野和弘「デジタルコンテンツの著作権処理に関する研究-コモンズ問題とアンチコモンズ問題-」『2007年度日本社会情報学会JSIS&JASI合同研究大会研究発表論文集』(2007): 128-31.
【参照サイト】ぎょうせいオンライン「DX時代におけるデジタル・コンテンツ著作権」 (金井重彦、髙橋淳、宮川利彰著『DX時代におけるデジタル・コンテンツ著作権』一部抜粋記事)
【参照サイト】Adobe「DRM(デジタル著作権管理)とは?重要性や仕組み、課題をわかりやすく解説」
【参照サイト】政府広報オンライン「『侵害コンテンツ』は許さない! マンガやアニメ、映画や音楽、ゲームなど、コンテンツの将来を守るために!」
【参照サイト】文化庁 著作権侵害対策情報ポータルサイト
【参照サイト】文化庁 著作権侵害対策情報ポータルサイト 「著作権の基本と海賊版」
【参照サイト】政府「インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー及び工程表について」
【参照サイト】NTT Smart Connect. DRM(デジタル著作権管理)
【参照サイト】文化庁 「SARTRAS 共通目的事業『インターネット上の著作権侵害等に対する個人クリエイター等による権利行使の支援』を開始します」
【参照サイト】文化庁「令和2年通常国会 著作権法改正について」
【参照サイト】https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r02_hokaisei/
【参照サイト】文化庁「令和5年通常国会 著作権法改正について」
【参照サイト】クリエイティブ・コモンズ・ジャパン:ホームページ
【参照サイト】e-gov 著作権法
【参照サイト】文部科学省「著作権法の一部を改正する法律案の概要」