「難民認定」とは?認定の仕組み、日本国内と世界の受け入れ状況比較

Photo by Julie Ricard on Unsplash
世界の67人に1人。この数は、戦争や紛争、迫害などにより、自らの意思とは無関係に故郷を追われた人々を指す。命の危険を逃れ、家や仕事、そして時には家族とも離れて他国へ避難せざるを得なかった人の数は、2024年末時点で約1億2,320万人に達した(UNHCR)。そのうち、子どもは約4,900万人で全体の約40%を占める(UNHCR)。
人々が難民や避難民として逃れざるを得ない背景には、さまざまな要因がある。戦争や内戦、迫害、政治的、宗教的、民族的、ジェンダー的な理由によって、命を脅かされる人々が後を絶たないのだ。特に、スーダンの武力衝突、ウクライナでの戦争の長期化、コンゴ民主共和国やミャンマー、ベネズエラなどの不安定な情勢、そして政権移管後も混乱が続くシリアでは、難民の増加が続いている。
さらに近年は、気候変動による干ばつや豪雨、自然災害、食糧難といった人道危機も、人々の移動を加速させている。こうした複雑化する背景を踏まえたいま、難民に関する正確な情報と理解、そして持続的な支援の仕組みが、これまで以上に求められている。
そこで本稿では、「難民」とは誰を指すのか、日本で難民として認定されるまでのプロセス、制度の実情と課題、そして支援の現場について、わかりやすく解説していく。
難民(Refugees)とは誰のことか?
戦争や紛争、宗教や民族、政治的意見、性別や性的指向など、さまざまな理由で迫害を受け、命の危険から逃れるために国を越えて他国へ逃れざるを得なかった人々を「難民」と呼ぶ。
この「難民」は、1951年に採択された「難民の地位に関する条約」および、1966年採択の「難民の地位に関する議定書」によって、国際的に次のように定義されている。
「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」
日本でもこの定義を踏まえ、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」により、同様の定義を採用している。これに該当し、政府によって難民として認められた人々は「条約難民」と呼ばれ、国際的保護を受ける対象となる。
迫害の具体例
では、ここでいう「迫害」とは具体的にどのような行為を指すのか。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、以下のような行為を迫害の具体例の一部として挙げている。
- 大規模な暴力や戦争行為、民族浄化や集団殺害
- 拷問、強姦、性暴力
- 子どもを含む強制的な徴兵や徴用
- 恣意的な逮捕・拘束、強制失踪、人質行為
- 人間としての尊厳を傷つける非人道的な扱い
これらはすべて、生命や自由、尊厳を脅かす深刻な人権侵害であり、難民認定における重要な判断基準となる。ただし実際には、こうした危害が制度上「迫害」または「迫害のおそれ」として認定されなければ、難民として保護を受けることはできない。
そのため、難民制度がどこまで現実の苦境を反映できているのかが問われている。また、ここで挙げた例に限らず、広範囲にわたる深刻な危害が「迫害」と見なされる可能性があることにも留意したい。
「国内避難民」とは
一方、同じような理由で住む場所を追われながらも、国境を越えていないために、国際条約上の「難民」として保護を受けられない人々もいる。こうした人々は「国内避難民(Internally Displaced Persons:IDPs)」と呼ばれる。
1990年代、国内避難民の保護の重要性を国際社会に訴えたのが、日本人で初めて国連難民高等弁務官に就任した故・緒方貞子氏である。彼女の働きかけにより、国内避難民も含めた包括的な人道支援の体制が徐々に構築されていった。
2024年時点で、国内避難民の数は世界全体で約7,350万人にのぼり、移動を強いられた人々の6割以上を占めている(UNHCR)。特にスーダン、コンゴ民主共和国、ウクライナ、ミャンマー、イエメン、レバノン、ハイチでの増加が顕著である。
さらに近年は、自然災害や気候変動による避難も深刻化している。2024年には干ばつや洪水などの影響で、新たに約4,580万人が国内避難民となり、その年の国内避難民のうち約7割を占めた(UNHCR)。

Photo by Maria Teneva on Unsplash
難民認定とは?制度とそのプロセス
「難民認定」とは、難民として逃れてきた人が、本当に難民として国際的な保護を受けるべき立場にあるかを審査・判断する制度である。命の危険を逃れてやってきた人々が、受け入れ国の保護を正式に受けられるかどうかを左右する、極めて重要なプロセスだ。
各国は前章で説明した難民条約(難民の地位に関する条約・議定書)上の定義に基づき認定を行っている。
日本における難民認定制度の成立と管轄
日本は1981年に難民条約に加入し、翌年にその国内法整備として「出入国管理及び難民認定法(入管法)」を施行。以降、法務省の出入国在留管理庁が難民認定を担当している。
日本に逃れてきた人が難民認定を希望する場合、地方出入国在留管理局で申請を行い、面接を受ける。申請者が条約難民の定義に該当すると判断されれば、「難民」として認定され、一定の法的保護と社会的支援を受けることができる。
難民認定のプロセス
申請
地方出入国在留管理局に対し、難民認定の申請書を提出
審査
難民調査官との面接を通じて、申請者の事情が精査される
判断
認定または不認定の通知
不認定時:不服申立て(審査請求)
不認定通知を受け取った者は、その通知を受けた日から原則として7日以内に法務大臣に対して不服申し立てを行うことができる
難民と認定された場合に受けられる支援
難民として認定された人は、以下のような権利や支援を受けられる。
- 在留資格「定住者」の原則付与
- 永住許可要件の一部緩和
- 難民旅行証明書の発行(日本再入国が可能)
- 定住支援プログラムへの参加(日本語教育、日本の生活習慣・保険衛生教育、職業訓練先の斡旋など)
- 社会保障制度へのアクセス(国民年金、健康保険、児童扶養手当など)
これらは、難民が日本社会で安定的に生活し、自立していくために必要な基盤となる。
日本の難民認定状況と国際的な比較
2024年、日本における難民認定申請者数は1万2,373人で、前年から約1,450人の減少となった。また、難民不認定処分に対する審査請求件数も3,273人と、前年比で約37.6%の大幅な減少が見られた。
一方で、難民条約に基づく認定とは別に、迫害のおそれがあるものの、条約の定義には該当しないと見なされた人々に適用される「補完的保護制度」への申請者数は1,273人と、前年のほぼ2倍にあたる約87.8%の増加となった。
難民認定や補完的保護に関する一連の手続きを経て、2024年に日本での在留が認められた人は合計2,186人。その中で、難民(条約難民)として認定された人が190人、補完的保護対象者として認定された人が1,661人、そして難民・補完的保護のいずれにも該当しなかったものの、人道的な理由から在留が認められた人が335人である。

Photo by Hannah Busing on Unsplash
さらに、第三国定住制度を通じて日本での定住が認められた「定住難民」は、2024年に47人であった。これらは主にミャンマー難民であり、タイやマレーシアなどの難民キャンプから受け入れられた人々が含まれる。なお、この定住難民の中には、受け入れ後に正式に難民(条約難民)として認定された人もおり、条約難民数とは一部重複する可能性がある。
日本では1982年に難民条約および議定書が発効し、それ以降、出入国管理及び難民認定法に基づく難民認定制度が運用されている。しかし、条約難民として認定される人数は国際的に見て極端に少なく、2024年には難民申請者数1万2,373人のうち、難民認定されたのは190人、累計で認定された難民は1,610人にとどまっている(出入国在留管理庁)。こうした現状は、日本の難民認定の厳格さや審査プロセスの課題を反映していると考えられる。
国際比較
2024年末時点で、ドイツには約270万人の難民が登録されており、欧州最大の難民受け入れ国としての地位を維持している。新規難民申請は約22万9,800件で前年比30%減となったが、ウクライナからの難民は2022年以降120万人を超えている。ドイツはUNHCRの主要なパートナーであり、資金調達や政策面で重要な役割を果たしている。
フランスでは約15万8,000件の難民申請を受け付け、認定率は38.8%(上訴含む全体では49.3%)と前年より上昇した。2024年末時点で登録されている難民は約72万人で、ウクライナなどからの難民が多い。
イギリスには約52万人、カナダには約27万人の難民が登録されており、それぞれ欧州およびアメリカ大陸における主要な難民受け入れ国としての役割を継続している(UNHCR)。
※ 各国の難民の総数(難民登録者数や難民として認定された人数など)は公開されていることが多いものの、各国の「難民認定」や「庇護希望者(asylum seeker)」の定義や認定基準、集計方法が異なるため、日本の「条約難民」の定義に照らし合わせて、公式に認定された人数の年別比較データを正確に得ることは困難である。また、補完的保護やその他の保護制度も存在するため、単純に比較できない場合が多いことに留意したい。
日本で難民と認定された人々の実例
日本で難民と認定されるケースは多くはないが、実際に認定された事例には、深刻な人権侵害の恐れがある状況が確認されている。以下に、2つの事例を紹介する。
事例1:少数民族に属する留学生(「人種」や「政治的意見」を理由に迫害される恐れがあると認められた例)
ある少数民族に属する者が、日本への留学を終えて母国へ帰国した際、母国の警察から不当な監視や尋問を受け、パスポートを取り上げられ強制的な思想教育も課された。その後、日本に戻った本人は、再び帰国すれば政府から拘束・収容される可能性が高いとして難民申請を行い、人種や政治的意見を理由とする迫害の恐れがあると認定された。
事例2:平和的抗議活動に参加した教師(政治的意見に基づく活動により危険にさらされた例)
出身地で続く紛争に関連して、平和的な抗議活動に参加した女性教師が、当局から逮捕状を出され、自宅では兵士による性的暴行を受けた。帰国すれば再び命や身体の安全が脅かされるとして難民申請を行い、政治的意見を理由とする迫害の恐れがあると認められた。
日本の難民認定における課題
日本の難民認定制度には、運用や法的枠組みの面でさまざまな課題が指摘されている。本章では、認定基準の解釈、立証の困難さ、制度の運用体制、制度の目的に関する意識の問題という4つの視点から現状を整理する。
- 認定基準の解釈と国際的水準とのギャップ
難民条約は、迫害を理由に自国を離れた人々を国際的に保護するための枠組みであり、日本も1981年にこれを批准している。ただし、条約で定められた難民の定義は抽象的で、具体的な判断基準については各国の裁量に委ねられている。そのため、難民認定の運用には国ごとに違いが生じているのが実情である。
日本における課題は、こうした定義の解釈が他国に比べて狭く、国際的な基準との間にギャップがあると指摘されている点にある。たとえば、「個別把握論」と呼ばれる日本の解釈では、当局から「個人的に」標的とされていなければ迫害とは認めないとされ、難民とみなされない傾向がある。
また、迫害の定義そのものも限定的であると指摘されており、他国では重大な人権侵害とされる強制労働などが、日本では認定の対象外とされるケースもある。このような解釈の狭さが、難民保護の実効性を損ねているとの指摘がある。
- 立証するハードルの高さ
日本の制度では、申請者自身が、母国で迫害を受けた、あるいはそのおそれがあることを、客観的な証拠に基づいて立証することが求められている。しかし、迫害から命がけで逃れてきた人々にとって、証拠を携えて出国するのは現実的には非常に困難である。実際には、自身の安全や、母国に残る家族への報復を避けるため、証拠書類をあえて廃棄して逃れるケースも少なくない。
こうした背景から、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は、すべての事実が立証できない場合でも申請者に有利な解釈、いわゆる「灰色の利益」を認めるべきだとする立場をとっている。しかし、日本の運用ではこの考え方が十分に反映されておらず、説明に多少の矛盾があったり証拠が不十分だったりする場合、申請者の主張が信頼できないと判断されることが少なくない。
たとえば、家族が目の前で暴行や殺害されたような深刻な体験について、長時間にわたって細部を繰り返し問われる中で、記憶の揺らぎや説明の変化が「一貫性に欠ける」と評価されるケースがある。申請者が抱えるトラウマや、面接官に対する警戒心といった心理的要素が十分に考慮されていないという指摘もある。
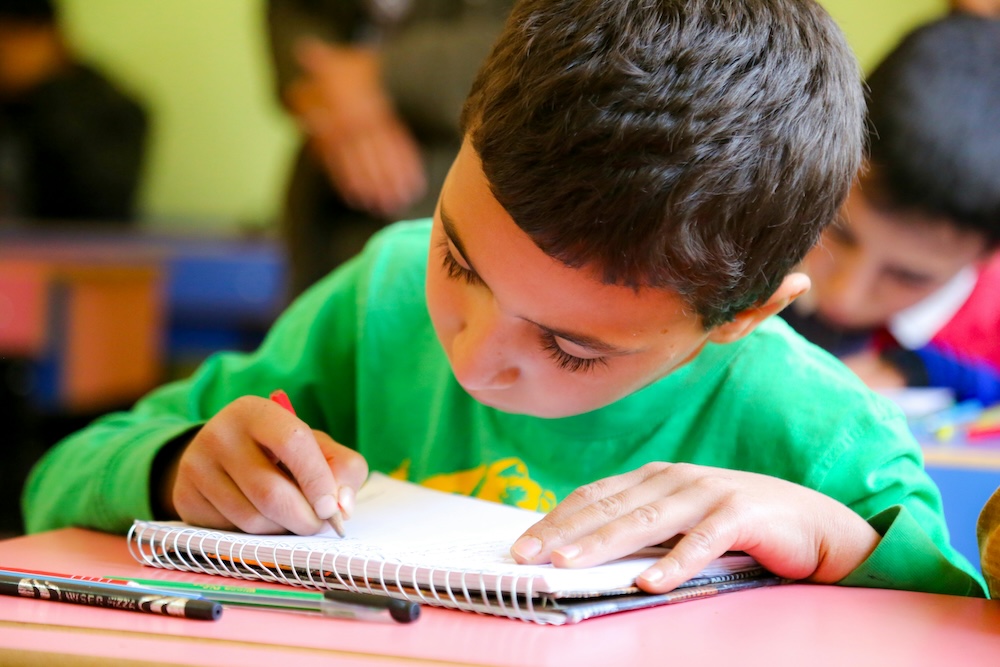
Photo by Salah Darwish on Unsplash
- 「保護」ではなく「管理」の視点が強い制度運用
日本では、難民認定の実務を法務省の出入国在留管理庁(入管)が担当しているが、そのために難民の保護よりも出入国管理の観点から制度が運用される傾向が生まれており、そのバランスが課題とされている。たとえば、空港で難民申請を申し出た人が上陸を許可されず、収容や送還の対象となる事例もある。
一方で、難民条約では「ノン・ルフールマンの原則(non-refoulement)」という原則がある。これは、迫害や命の危険がある国へ個人を送還してはならないという原則で、最も重要な規定のひとつとして位置づけられている。
本来、難民制度は人道的な観点からの保護を目的とするものであり、治安維持の視点とは分けて設計されることが理想とされている。難民審査は独立した第三者機関が担い、心理的ケアや社会統合も視野に入れた包括的な支援体制が求められている。
- 制度設計と運用の目的に関する課題
現在の日本の制度では、難民として逃れてきたとしても、認定されなければ十分な保護を受けることは難しい。申請中の生活支援制度も限定的であり、日本語教育や医療費支援、就労資格の面で多くの制約がある。また、一部の申請者は在留資格を持たないまま長期間にわたって収容されるケースもある。さらに、難民申請から結果が出るまでに数年を要することも少なくない。
難民認定制度は、本来、将来的に迫害を受けるおそれがある人を守るための極めて重要な人道的セーフネットであり、理念に基づく慎重かつ適切な対応が求められる。制度の誤用・濫用を防ぐ視点も重要だが、保護を必要とする人が見過ごされることのないよう、運用の透明性や審査体制のあり方を含め、制度の目的が実効的に果たされるための継続的な見直しが必要とされている。

Photo by Kyle Glenn on Unsplash
苦境にある人を保護するその他の制度
日本の難民認定制度にはさまざまな課題が指摘されているものの、近年では政府や市民社会による取り組みも進んでいる。また、「条約難民」認定に加えて設けられている、補完的な保護制度も存在する。
第三国定住プログラム
2010年度からは、アジアで初めて「第三国定住」プログラムが導入された。これは、出身国への帰還も、一次庇護国での定住も困難な難民に対して、第三の国での安全な生活再建の機会を提供するもので、「恒久的解決策」の一つとして評価されている。
補完的保護対象者認定制度
入管法の改正により、2023年12月から運用が始まった「補完的保護対象者認定制度」は、難民条約上の定義には該当しないものの、迫害や拷問、命の危険などの重大なリスクにさらされている人々を対象に保護を行う制度である。
2024年には、この制度に基づき1,661人が「補完的保護対象者」として認定されており、従来の難民認定数を大きく上回る規模となっている。
人道的配慮による在留許可
さらに、難民や補完的保護対象者に該当しない場合でも、人道的な観点から出身国に戻すことが適切でないと判断された場合には、「在留特別許可」や「在留資格変更許可」が個別に付与されることがある。これは、戦争や紛争などの理由により、自国への帰還が困難な人に対して適用される場合がある。
まとめ
日本の難民認定制度には、定義の解釈の幅や立証の困難さ、運用上の課題があり、本来の目的である「保護」が十分に果たされていないとの指摘がある。初回の審査で不認定となった後、裁判を経て認定に至るケースがあることも、現行制度の限界を示しているといえる。
一方で、日本の制度上の「難民」に該当しない人が申請する事例も報告されており、法務省はこうした「制度の濫用」への対応として、近年、制度の厳格化を進めている。しかしながら、制度の濫用に関する報道が過熱する傾向も見られ、難民申請者に対する偏見や誤解を助長しているとの懸念もある。
難民保護と制度の厳格化は、本来どちらか一方を優先すべきものではなく、両立を図る必要がある。制度の不適切な利用を抑制しつつも、「本当に保護を必要とする人を確実に救う」仕組みの整備が、いま求められている。

Photo by Hosien Azour on Unsplash
UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)をはじめとする国際機関や支援団体は、世界各地で人道的支援に尽力しており、私たち一人ひとりの支援がそうした活動を支えている。正確な情報に触れること、難民問題に関心を持ち続けること、定住支援プログラムへの参加やUNHCRへの寄付などが、困難な状況にある人々を救う力となる。
そして、自分の力ではどうしようもない状況に巻き込まれ、命からがら自国を離れなければならなかった難民を含め、すべての人が人間として尊厳を持って生きていくために、いま私たちに求められているのは「立ち止まって、考える力」である。
同じ国、同じ地球に生きる私たちは、「人種」「言語」「性別」「国籍」などのわかりやすいカテゴリーによって分断され、その分断を煽る言説が支持を集めている。その中で、難民に対しても偏見や誤解が広がりやすい土壌が形成されてきている。
さらに、異なる意見を即座に「キャンセル」する風潮は、あらゆる領域や局面で意見が交わされる機会を奪い、「他者」を理解しようとする姿勢や、「誰かの苦しみを、自分に関わる問題として受け止める力」を弱めてしまっている。だからこそ、政治的な立場や考えが違っても、共通の課題を見据え、共に改善していこうとする姿勢が求められている。
人が人として、安心して暮らせる場所を得られるように。関心と行動の積み重ねこそが、難民を取り巻く現状を変える力になる。
【参考サイト】UNHCR Global Trends report 2024
【参考サイト】UNHCR Germany
【参考サイト】UNHCR France
【参考サイト】UNHCR Canada
【参考サイト】UNHCR UK
【参考サイト】UNHCR「難民認定」
【参考サイト】UNHCR Internally Displaced People
【参考サイト】UNHCR 「国際的保護に関するガイドライン 12:1951 年難民の地位に関する条約第1条 A(2)および/または 1967 年難民の地位に関する議定書および難民の地位に関する地域的文書における定義における武力紛争および暴力の発生する状況を背景とした難民申請」
【参考サイト】UNHCR Refugee Data Finder
【参考サイト】UNHCR「日本の難民認定手続きについて」
【参考サイト】国連UNHCR協会/公式サイト
【参考サイト】外務省「国内における難民の受け入れ」
【参考サイト】出入国在留管理庁「令和6年における難民認定者数等について」
【参考サイト】出入国在留管理庁「難民認定制度」
【参考サイト】出入国在留管理庁「難民等と認定した事例等について」
【参考サイト】出入国在留管理庁「我が国における難民保護の状況等」
【参考サイト】出入国在留管理庁「令和6年における難民認定者数等について」
【参考サイト】出入国在留管理庁「我が国の難民等の保護状況」
【参考サイト】難民支援協会「日本の難民認定はなぜ少ないか?-制度面の課題から」
【参考サイト】難民支援協会「はじめて知る『補完的保護とは何か?』」
難民支援協会「難民申請者への偏見を助長しうる入管庁発表資料に対する意見」
【参考サイト】NHK「難民に準ずる保護 去年1年間1661人 年間認定者数を初公表」
【参考サイト】日本経済新聞「良品計画、ウクライナ難民に就労機会提供」
【参考サイト】World Vision「日本の難民認定制度|認定率の世界比較と認定以外の難民問題の解決法も」
