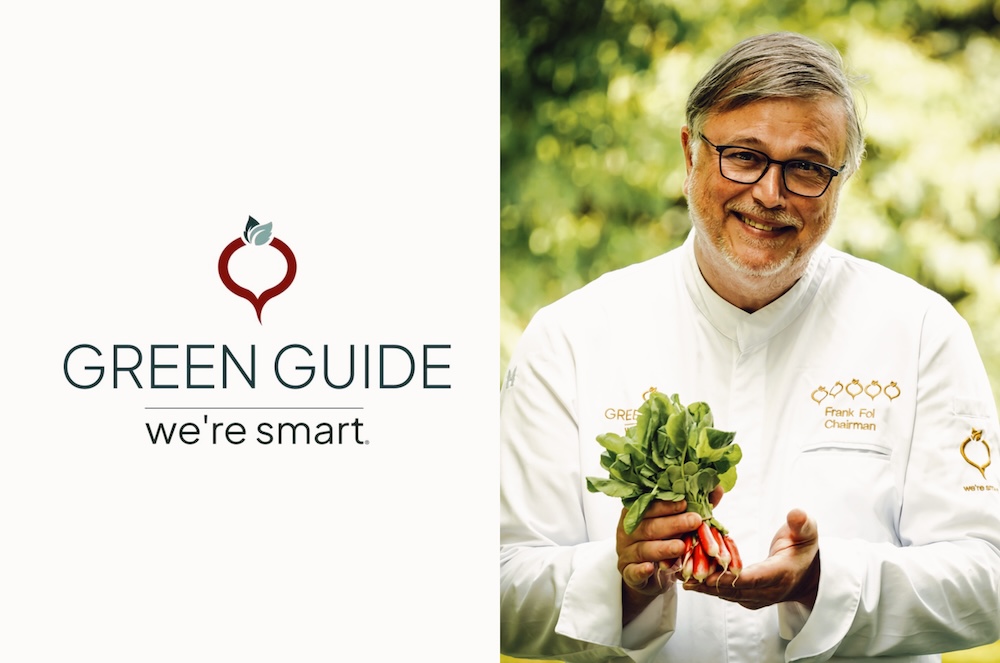食糧問題

Photo by Megan Thomas on Unsplash
食糧問題とは(What is Food Insecurity?)
食糧問題とは、食糧不足や食糧アクセスの不均衡、飢餓など、食糧に関するさまざまな課題を包括的に示す言葉です。
英語では、食糧問題に関連して、「食糧不安(Food Insecurity)」、「食糧不足(Food Scarcity)」、「食糧危機(Food Crisis)」といった用語が一般的に使用されています。これらの用語は、それぞれ異なる視点を持ちながらも、意味が重なる部分があり、また互いに関連しています。
「食糧不安」とは、人々が健康で活動的な生活を送るために必要な、安全で栄養価の高い食料への十分なアクセスが確保できない状況を指します。この状況は、食糧そのものの不足や、食糧を手に入れるための資源(経済的、物理的、社会的)の欠如によって引き起こされます。主に個人や家庭レベルで議論されることが多く、人々の生活や健康に具体的にどのような影響を与えるかに焦点を当てています。また、「食糧不安」は、食糧への安定したアクセスを評価する指標としても用いられています。
「食糧不足」は、利用可能な食糧の量が需要量を下回る、物理的な食糧不足を指します。一般的に、「食糧不安」に含まれる要素、またはその一因として考えられます。
「食糧危機」は、一般的に短期的で急激に進行する深刻な食糧問題を意味します。例えば、自然災害、紛争、貿易制限、または市場価格の急騰によって引き起こされ、国家的または国際的なスケールで議論されることが多いです。このような「食糧危機」は、食糧不安をさらに悪化させる要因となります。
食糧問題は飢餓(※)だけを指すわけではありません。その影響として、多くの国で栄養不足と肥満が同時に存在している状況が見られます。例えば、経済的に余裕がなく安価な食べ物しか入手できない場合、カロリー摂取が過剰になりつつも必要な栄養素が不足することがあります。その結果、肥満や糖尿病などの慢性疾患にかかるリスクが高まります。
この記事では、食糧問題の要因や背景、人々の生活に及ぼす具体的な影響を明らかにするとともに、私たちにできる取り組みを考察していきます。
※本記事内で「飢餓(hunger)」は、食料エネルギーの不足によって引き起こされる不快感や苦痛を伴う身体的な感覚を指します。また、「飢餓(hunger)」が「栄養不足(undernourishment)」と表現される場合もあります。
※「食料」と「食糧」の違い: 「食料」はすべての食べ物を指し、「食糧」は米、小麦、トウモロコシなどの主食を指す。
目次
数字で見る食糧問題(Facts & Figures)
- 世界食糧計画(WFP)が活動する、データが入手可能であった世界74か国において、3億4,300万人もの人々が急性の飢餓に苦しんでいる。(WFP)
- 世界の飢餓は、2019年から2021年の間に急激に増加し、2023年まで高い水準を維持している。(FAO)
- 2023年において、世界59の調査対象国・地域の人口の21.5%、約2億8,200万人が、緊急の食糧・生活支援が必要な、高水準の急性食糧不安の状況にあった。(WFP)
- 2024年7月に飢饉が確認されたガザとスーダンを中心に、南スーダン、ハイチ、マリの一部で、最大190万人が飢饉※の危機に直面していると推定される。(WFP)※ 本記事内で「飢饉(Famine)」は、飢餓の最も深刻な段階を指し、餓死や病死のリスクが高い状態を意味する。
- 急性の飢餓に瀕している3億4,300万人のうち65%は、脆弱な国や紛争が起こった国にいる。(WFP)
- 2022年、世界では10億5,000万トンの食品が廃棄された。(UNEP)
食糧問題の現状(Current Situation)
国連食糧農業機関(FAO)が飢餓に関する調査を開始した1974年以降、人口増加や都市化、技術革新、経済のグローバル化などにより、食料の生産・流通・消費を取り巻く環境は大きく変化してきました。しかし、食糧問題は依然として解決されておらず、栄養不足が深刻化する一方で、過体重や肥満の増加を含む栄養不良の世界的な傾向が懸念されています。
FAOの食料不安経験尺度(FIES)では、食糧不安の深刻度を以下の3段階に分けています。
- 食糧安全または軽度の食糧不安(Food security or mild food insecurity)
量・質ともに十分な食糧が確保されている状態。ただし、将来的な確保が不確実な場合は軽度の食糧不安に陥る。 - 中程度の食糧不安(Moderate food insecurity)
食糧を入手することは可能だが、その量や質を落とさざるを得ない状況。 - 深刻な食糧不安(Severe food insecurity)
食糧が完全に尽き、1日以上食事を取れない状態が続く状況。
深刻な食糧不安にある人々は、日常的に食糧が不足し、飢餓に苦しんでいると考えられます。FAOでは、このような状況にある人々を「飢餓人口(the hungry)」と呼んでいます。
食糧不安と肥満のパラドックス(The Food-Insecurity Obesity Paradox)
中程度の食糧不安に直面している人々は、食糧の確保が不安定なため、他の基本的な生活ニーズを犠牲にしなければならない場合があります。例えば、経済的な制約により、安価で質の低い食品を選ばざるを得なかったり、必要な量の食品を購入できなかったりすることで、栄養不足や肥満につながることがあります。
米国では食糧不安の悪化と肥満の増加に関連性が見られ、この現象は一般に「食糧不安と肥満のパラドックス」と呼ばれています。これは、食糧不安が肥満の発症に寄与している可能性を示唆するものです。この現象には、以下の2つの主要な説明があります。
- 食糧不安に直面している人々は、高カロリーで手軽に入手できる食品を選ばざるを得ないため。
- 食糧不安に直面している人々は、健康的な食生活や運動のための知識、時間、資源が不足しているため。
超加工食品(Ultra-processed foods)は、エネルギー密度が高く、飽和脂肪酸、糖分、塩分を多く含むため、肥満や心代謝性疾患のリスクを高めるとされています。特に米国では、低所得層における摂取量の多さが指摘されています。これは、時間的制約や経済的問題から、比較的高価である新鮮な野菜や果物を入手したり、自炊したりするハードルが高いためだと考えられています。このような食生活では、1日のカロリー摂取量を満たしていても、健康維持に必要な栄養素が不足する傾向があります。

Photo by Robin Stickel on Unsplash
さらに、飢餓や食糧不安に直面している子どもたちは、肥満や糖尿病などの慢性疾患にかかるリスクが高いとされています。これは、食糧が安定的に確保できないストレスや、長期間にわたる栄養不良が引き起こす生理的な変化によるものだと考えられています。その結果、多くの国で栄養不足と肥満が共存する、一見矛盾した現象が生じているのです。
この現象に関するメカニズムを科学的に調査し、提唱された理論が資源不足仮説(Resource Scarcity Hypothesis)です。この仮説では、「肥満は、社会的地位の低い人に特異的におこる、食糧供給の脅威に対する生理的に調節された反応である」と説明されています(※1)。この研究によると、高カロリー食品が入手できる環境において、食に対する不安が高まると、社会的地位の低い人々はエネルギー収支がプラスになる傾向がある一方で、社会的地位の高い人々にはこの現象が見られないといいます。
食糧問題の背景と要因(Background & Factors)
食糧問題は、さまざまな要因が複雑に絡み合って引き起こされます。
紛争
紛争は食糧生産を中断させるだけでなく、人々を安全な住居や収入源から引き離し、人道的支援の提供を妨げる要因となっています。避難を余儀なくされた人々は、雇用、生計、食糧、住居へのアクセスが制限され、人道支援に依存する形で深刻な食糧不安にさらされます。
現在、深刻な飢餓に直面している3億4,300万人のうち半数以上が、脆弱な政治体制の国や紛争地域に暮らしています。特に、中東、東アフリカ、中央アフリカ、西アフリカ、カリブ海諸国、南アジア、東ヨーロッパでの暴力と不安定さが重大な懸念事項です。
気候変動
気候変動は、世界的な飢餓増加の主要な原因のひとつです。技術の進歩にもかかわらず、悪天候や地政学的紛争、政策変更により、食糧生産は依然として大きな影響を受けやすい状況にあります。
2024年には記録的な暖冬が観測され、地域によって収穫量の減少や増加といった極端な影響が出ています。これにより、農業システムの脆弱性が顕在化し、気候変動による需要と供給のバランスの崩壊が一層懸念されています。国際的な協力による気候変動への対策が急務です。
肥料価格の高騰
肥料価格の上昇は、食糧価格の高騰や農産物の量的・質的低下を招き、結果として食糧不安を悪化させるリスクを高めています。
国内供給を増やし価格を抑えるため、各国が食糧や肥料に対する貿易制限を強化するケースが増えています。しかし、これにより一部の地域では食糧不安が悪化する傾向が見られます。特にロシアによるウクライナ侵攻以降、貿易制限政策が急増しており、2024年12月時点で17か国が22件の食品輸出禁止措置を、8か国が12件の輸出制限措置を実施しています。
肥料のアクセスが制限されることは、食糧価格のさらなる上昇や貧困の拡大を引き起こす可能性があり、国際社会における調整と対応が求められています。

Photo by Polina Rytova on Unsplash
食糧問題への取り組み(Action)
世界的な食糧問題の解決には、政府、金融機関、民間セクター、個人が協力して取り組む必要があります。この問題に取り組むためには、食糧問題の根本的な原因に対処することが不可欠です。平和構築の努力が重要であり、安全な食糧アクセスを確保するためには、政治的・外交的な解決策が求められます。また、食糧システムのレジリエンスを強化し、気候変動への適応と、質の高い安全な食糧生産を促進することも必要です。
WFP(世界食糧計画)は、83か国の政府と連携し、国家のセーフティネットや栄養を重視した社会的保護を構築することで、より多くの人々に緊急食糧支援を届けています。さらに、気候保健プログラム「R4ルーラル・レジリエンス・イニシアチブ」を通じて、2023年までにアフリカ、アジア、ラテンアメリカ、カリブ海諸国の18か国で約55万世帯の支援を行いました。
また、プラン・インターナショナルは、平等で公正な世界を実現するために活動している国際NGOです。スーダンにおける「食料危機下の子どもの栄養改善」プロジェクトでは、2023年の武力衝突の影響を受けた人々や難民への支援を行っています。支援を必要とする人は、紛争前は1,580万人、紛争後は2,470万人に増加しました。難民キャンプでは、子どもや妊娠中・授乳中の母親への栄養改善支援、栄養教育、給水スタンドの設置などを行っています。
食糧問題に関して私たちにできること(What We Can Do)
世界の食糧問題を解決するためには、個人の取り組みも欠かせません。私たちにできることは、以下のようなものがあります。
食品ロス削減
食品ロス(フードロス)とは、まだ食べられる食品が捨てられてしまう状況を指します。日本では、2022年に食べられるのに廃棄された食品は472万トンにのぼり、これは2022年に世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた食糧支援量480万トンとほぼ同じです。このうち、食品関連事業者から出た食品ロスは236万トン、一般家庭から出た食品ロスも236万トンでした。私たちができる取り組みとして、食品を無駄なく利用したり、必要な分だけを購入したり、フードバンクに寄付したり、食べ残しを減らすことで、食品ロスの削減に貢献できます。
フェアトレード商品の選択
消費者がフェアトレード商品を選ぶことは、生産者に公正な利益を分配する手助けになります。「買い物は投票である」という言葉の通り、私たちの購買選択がフェアトレードの促進につながり、生産者からの搾取を防ぎ、彼らの食糧状況を改善することに貢献できます。
団体への寄付
食糧問題に取り組む団体や研究機関に寄付をすることにより、彼らの活動を支援し、食糧問題解決に向けた取り組みを加速させることができます。
食糧問題を改善するアイデア(IDEAS FOR GOOD)
食糧問題を解決するために、できることは何でしょうか?
IDEAS FOR GOODでは、最先端のテクノロジーやユニークなアイデアで食糧問題解決に取り組む企業やプロジェクトを紹介しています。
食糧危機に関連する記事の一覧
【参照サイト】Global Network Against Food Crise. ‘Global Report on Food Crises (GRFC) 2024’.
【参照サイト】World Food Programme. ‘WFP 2025 Global Outlook’.
【参照サイト】World Food Programme. ‘A global food crisis’.
【参照サイト】World Bank Group. ‘Solutions to Food Insecurity’.
【参照サイト】Food and Agriculture Organization of the United Nations. ‘Hunger and food insecurity’.
【参照サイト】Hojatollah Kakaei, Heshmatollah Nourmoradi, Salar Bakhtiyari, Mohsen Jalilian, Amin Mirzaei. ‘Chapter One – Effect of COVID-19 on food security, hunger, and food crisis’. COVID-19 and the Sustainable Development Goals (2022): 3-29.
【参照サイト】政府広報オンライン「今日からできる!家庭でできる食品ロス削減(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201303/4.html)
【参照サイト】UNEP. ‘UNEP Food Waste Index Report 2024 Key Messages’.
【参照サイト】ワールド・ビジョン 「食糧問題とは? 世界の食糧問題の原因と解決策を考えよう」
【参照サイト】天神和泉 日本貿易振興機構 「食糧高騰の背後に、ロシアによるウクライナ侵攻の影(アフリカ)」
【参照サイト】Dhurandhar EJ. ‘The Food-Insecurity Obesity Paradox: A Resource Scarcity Hypothesis’. Physiol Behav. 162 (2016): 88-92.
【参照サイト】プラン・インターナショナル「飢餓問題に対して私たちができることは?世界の現状や飢餓の原因」
【参照サイト】消費者庁 「食品ロスについて知る・学ぶ」
【参照サイト】消費者庁 「令和4(2022)年度食品ロス量推計値の公表について」
【参照サイト】Leung, Cindy W, Aarohee P Fulay, Lindsey Parnarouskis, Euridice Martinez-Steele, Ashley N Gearhardt, Julia A Wolfson. ‘Food insecurity and ultra-processed food consumption: the modifying role of participation in the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)’. The American Journal of Clinical Nutrition. Vol 116, Issue 1 (2022): 197-205.
【参照サイト】IFPRI. ‘Food Crises’.