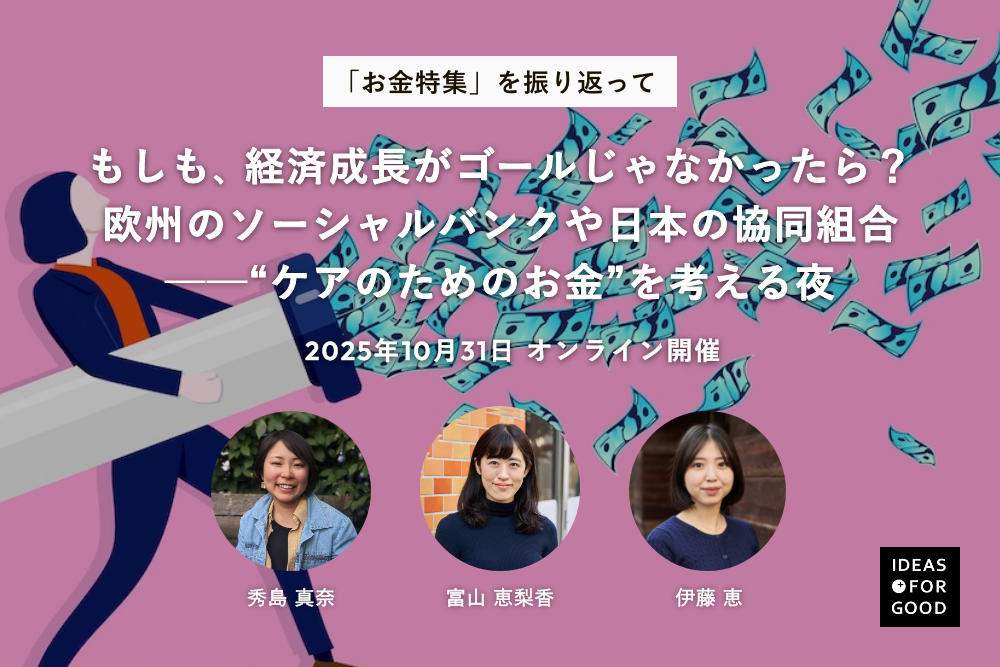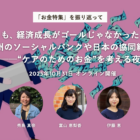【特集】幸せなお金のありかたって、なんだろう?今こそ問い直す、暮らしと社会の前提
お金は、ただの紙切れでも数字でもない。生き方や価値観、人間関係、社会制度にまで影響を及ぼす「見えざる力」だ。便利で、時に残酷で、そして人間的なこの仕組みは、いつから私たちの当たり前になったのだろう。自己責任が求められる働き方、そして「お金がない」ことを理由に後回しにされる福祉や環境対策──議論は世界中で交わされているが、日々の暮らしの中でお金の本質を見つめ直す機会は少ない。だからこそ今、問いたい。「お金」とは何か、そして私たちはそれとどう向き合っていけるのか。本特集では、経済だけでなく、文化人類学や哲学、コミュニティの現場など多様な視点からお金の姿を捉え直す。価値の物差しを少し傾けてみた先に、より自由でしなやかな世界が見えてくることを願って。
「利子はいらない。ただ、成功を応援したい」
スイスの小さなソーシャルバンク、Freie Gemeinschaftsbank(フライエ・ゲマインシャフトスバンク、直訳すると「自由共同銀行」)では、投資家のおよそ5人に1人が“利子ゼロ”を選んでいる。お金を増やすよりも、「誰を、どの取り組みを支えたいか」を軸に資本が動く──そんな金融が現実に機能している。
金融大国スイスといえば、多くの人が思い浮かべるのは巨額の資産を運用するプライベートバンクや、UBSやクレディスイスといった巨大銀行の名だろう。2023年、UBSによるクレディスイスの合併で、その一強体制はいっそう鮮明になった。だがその影で、わずか40人ほどで運営されるFreie Gemeinschaftsbankは、数字ではなく“人と人との関係性”を資本の基盤に置くユニークな銀行として2024年に40周年を迎えた。
利子や担保といった金融の常識を揺さぶり、愛や信頼を軸に経済を組み替える試み。そんな銀行が本当に存在するのか。その舞台裏を、経営を担うMax Ruhri(マックス・ルーリ)氏に聞いた。

Max Ruhri氏 (c)Oliver Baumann
巨大金融の国で、小さな“関係性の銀行”をたずねる。はじまりと転機は?
Q. Freie Gemeinschaftsbankは、2024年に創立40周年を迎えました。当初、どのようにして人々が集まり、この銀行を設立することになったのでしょうか。
私たちの創設の歴史は、ドイツ初のソーシャルバンクであるGLS銀行と深く重なっています。最初にスイスで財団が立ち上がり、その活動を支えるために「自分たちの銀行をつくろう」という動きが生まれました。当初の焦点は、有機農業やシュタイナー学校(※)といった、既存の銀行ではなかなか融資を受けられない分野の支援でした。
※シュタイナー学校:思想家ルドルフ・シュタイナーの教育哲学にもとづく学校で、子どもの個性や創造性、内面的な成長を大切にする教育を行っている。テストの点数よりも、芸術や体験を通じた学びを重視しているのが特徴。
設立にあたっては、特にGLS銀行出身のギゼラ・ロイター氏が初期から参画したことは、大きな追い風となりました。また、最初の業務責任者はスイスの伝統的なプライベートバンク出身で、同僚たちと共に1984年に銀行免許を取得。その後もしばらくは非常に小規模な運営が続きました。私自身が2010年に入行したときも、従業員は20人ほどで、提供できるサービスも限られていました。
その後、いくつものマイルストーンを経て銀行は発展してきました。第一の転機は、新しい銀行システムへの移行です。これによってカードやインターネットバンキングを提供できるようになり、通常の銀行と同様の主要サービスをカバーできるようになりました。
第二は、私たち独自の信託融資(Treuhanddarlehen)が金融市場監督局によって審査され、信頼性のある金融商品として認められたことです。
第三は、2017年の自社ビルへの移転。拠点を持つことで、社会に対して存在感を示せるようになりました。そして最後に、2015年以降、国際的なネットワークであるGABV(Global Alliance for Banking on Values)やISBとの連携を始めたことも、大きな一歩でした。
Q. 銀行業務について、Freie Gemeinschaftsbankの重点分野は何ですか?
Freie Gemeinschaftsbankの融資の柱は、創立以来ほとんど変わっていません。代替教育(シュタイナー教育を実践するヴァルドルフ学校など)、有機農業、共同住宅プロジェクトの3つです。さらに近年は、社会施設や障害者施設の拡充にも力を入れています。いずれも、通常の銀行ではリスクが高いと判断されやすく、資金が届きにくい分野。しかし社会にとって不可欠なこれらの活動を支えることこそ、私たちの存在意義だと考えています。
Freie Gemeinschaftsbankには、他ではあまり見られないユニークな金融商品があります。それが信託貸付(Treuhanddarlehen)です。仕組みは次のようにシンプルです。
1. 銀行がプロジェクト一覧を提示する
2. 顧客(口座を持つ個人投資家)が投資したいプロジェクトを選ぶ
3. 銀行と顧客、銀行とプロジェクトの間でそれぞれ契約を結ぶ
4. 金利や担保などは当事者同士が個別に交渉
5. 銀行は仲介と事務処理のみを担い、年0.5〜0.75%の手数料を受け取る
この仕組みによって、顧客の資金は直接プロジェクトに流れ込みます。顧客にとっては「意義ある投資」となり、プロジェクトにとっては財政的な安定を広げることにつながります。銀行は“お金を回す主体”というより、“社会を支える仲介者”としての役割を果たしているのです。
Q. なぜこのような商品を始めたのでしょうか?きっかけは何ですか。
信託貸付は、銀行創立当初から存在していました。もともとはGLS銀行をはじめ、他のソーシャルバンクでも取り入れられていたモデルです。特に自己資本が乏しかった創立期には、大口資金を確保するために共同融資の形でこの仕組みを活用していました。
10年前に新しい法的枠組みに移行しましたが、30年以上続いている信託貸付もまだ残っています。通常は最低3年や5年といった期間を設けていますが、実際には投資家が解約を希望しない限り長期間継続することが多いのが特徴です。
最低投資金額は5万スイスフラン程度からで、プロジェクトによって異なりますが、近年は特に余裕資産を持つ顧客が利用する傾向にあります。

Freie Gemeinschaftsbankの資金によって運営されているJasmin Blaser氏の農場 (c)Michael Fritschi
「利子ゼロ」という選択。関係性が資本を動かす
Q. この商品で驚かされるのが、約20%の顧客が0%利子を選択しているという事実です。どうしてこのような「魔法」が起こるのでしょうか。
これは教科書に書かれている理論ではなく、実際に私たちの現場で起きていることです。たとえば、家族経営の小さな農場が、有機農業に挑戦し、膨大な労力と情熱を注いでいる姿に感動した投資家が、「私は利子などいらない。とにかくこのプロジェクトの成功を応援したい」と考えることがあります。資金の流れを通じて、人々の考え方や価値観そのものが変わっていくのです。
私たちの仕組みでは、あらかじめ最大金利が定められているものの、その範囲内で利子率は投資家自身が完全に自由に決められます。銀行が口を出すことは一切ありません。「もし利子収入が必要なら利子を選んでください。必要なければ、ご自身で決めてください」と伝えるだけです。
こうして生まれる“自由な選択”のなかから、約5人に1人の投資家が無利子を選びます。それは数字上の損得を超えた、人とプロジェクトを信じる姿勢の表れであり、資本のあり方に新しい可能性を示しています。
Freie Gemeinschaftsbankは、資金の行き先を「見える化」することで、投資家とプロジェクトのあいだに対話の場を生み出しています。その過程で、人々は“与える側と受け取る側”という対立的な関係ではなく、共に未来をつくる協働者として向き合うようになります。こうして、資本を介した関係性の中に「贈与経済」の精神が息づいていくのです。
「この人たちは本当に素晴らしい取り組みをしている。純粋に応援したい」──そう思える関係性があってはじめて、利子を求めない投資という選択が生まれるのです。逆に言えば、もし関係性がなければ、この動きは決して起こりません。

Freie Gemeinschaftsbankの資金によって運営されているJasmin Blaser氏の農場 (c)Michael Fritschi
Q. 2024年年次報告では +7.4%(前年 +29.2%)の成長をみせました。信託貸付が人気な理由は何かあるのでしょうか。
金利状況に強く左右されるのは事実ですが、投資家は資金の行き先を正確に把握でき、人やプロジェクトを直接的に知ることができる点に魅力的に感じるようです。また、プロジェクト側も、銀行を通じて広く紹介されることで知名度が高まり、マーケティング効果も得られます。さらに多くの投資家は無利子で投資を選ぶため、調達コストを通常の融資よりも大幅に抑えることができます。
資金の流れを透明化し、投資家・プロジェクト双方にメリットをもたらす仕組み。それが信託貸付の強みであり、長年にわたり支持されてきた理由なのです。
プロジェクト側は、銀行への融資相談から始まることが多いです。信託貸付に選ばれる案件は、必ず銀行が自らも融資を行ったプロジェクトに限られます。つまり「リスクの高い案件を投資家に押し付ける」のではなく、「私たち自身も投資したいと考えるほど良い案件です」と自信をもって紹介しているのです。

投資先のプロジェクトを紹介する年1回のイベントの様子。(c)Michael Fritschi
危機を越える力。数字よりも“関係”を軸に
Q. これまでに、どうやって危機を乗り越え、レジリエンスを高めてきたのでしょうか?
2007年時点では株式取引をしていなかったため、金融危機の影響はほとんど受けませんでした。実体経済と密接に関わっていたことで、顧客・銀行ともに安定していたのです。ただしその後の低金利・マイナス金利政策は大きな試練で、規制強化による事務負担の増大や従業員へのプレッシャーが課題となりました。
パンデミックでは、危機対策本部を設け、チームを分けて交代勤務するなど柔軟に対応しました。ワクチンをめぐる意見の違いが分裂を生む懸念もありましたが、「法を守り、民主主義と個人の責任を尊重する」という一貫した姿勢を貫くことで、チームのモチベーションを維持することができました。
ロシアによるウクライナ侵攻では、金利上昇が銀行を支えた一方、顧客はエネルギー価格の高騰や消費者の節約志向による打撃を受けました。特にオーガニック食品分野は深刻でした。そこで私たちは市場変動に慎重に対応し、金利の調整も急激ではなく緩和的に進めることで、顧客と共に影響を最小化する道を模索しました。
こうした対応の根底にあるのは、経済活動を単なる数値や利益のやりとりではなく、人間同士の関係性の延長として捉えるという哲学です。それが私たちのレジリエンスを形づくってきたのだと思います。
現状は比較的良好です。スイスには数年前から「小規模銀行制度」があり、この枠組みを通じて小規模銀行は一定の規制緩和を受けられるようになりました。加えて、政府側も「小規模銀行の構造は、むしろ少数の巨大銀行よりもレジリエンスが高い」と評価し始めています。そのため、意外に思われるかもしれませんが、スイスはソーシャルバンクにとってEUよりも活動しやすい環境にあるといえるでしょう。

Image via Freie Gemeinschaftsbank
“自然な成長”という戦略。バランスで拡がる
Q. 今後10年の展望を教えてください。Freie Gemeinschaftsbankにとって、意図的な成長は必要なのでしょうか。
「成長」をどう捉えるかは、私たちにとって非常に重要なテーマです。銀行業界では必要最低規模が年々上昇しており、スイス国内には従業員3人ほどの極小銀行も残っていますが、全体的な潮流は規模拡大にあります。その一方で、私たちは無理に成長を追うつもりはありません。
大切なのは、自然な成長です。預金残高、融資残高、自己資本など、銀行経営に関わるあらゆる指標のバランスをとりながら、健全に広がっていくことを重視しています。数値的な拡大だけではなく、「人と人との関係性を軸にした銀行であり続けること」こそが、これからの10年にわたって守りたい私たちの成長のかたちです。
編集後記
Freie Gemeinschaftsbankと信託貸付(Treuhanddarlehen)に出会ったのは、2025年8月、Institute for Social Bankingが開催したサマースクールでのことだった。Maxの話を聞くや否や、多くの参加者が驚きの声をあげた。「そんなことが本当に可能なのか?」──担保はどうするのか、リスクはどう扱うのか、金利はどう決まるのか。次々に質問が飛び交った。
サステナブル金融に日々関わるソーシャルバンカーでさえ、このモデルには新鮮さを覚えたようだ。ある参加者が「なんて美しいモデルなんだろう」と漏らしたとき、私も深くうなずいた。そこには、愛や情熱なしには成立し得ない、きわめて人間的な金融の姿があったからだ。銀行はあくまで脇役に徹し、環境を整え、事務を担う。主役は、資金を託す投資家と、未来をつくるプロジェクトオーナーにある。
数字や効率を超えて、人と人との関係性が資本を動かす金融。そんなあり方が日本でも実現する日が、待ち遠しくはないだろうか。
【参照サイト】Freie Gemeinschaftsbank