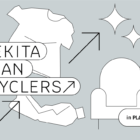都市の中に点在する、空き地や空き家などの未利用空間。日当たりが悪い、不便、騒音がひどい……経済的な効率を追い求めるシステムの中で“外部化”されたそれらの空間は、一見すると価値がないように思える。しかし、実はそんな場所にこそ、都市が内に秘める創造性を引き出すヒントが眠っているのかもしれない。
都市の「余白」とも言える未利用空間に、同じように効率という正義のもとで「ごみ」というレッテルを貼られたものを持ち込み、それらを使った“あそび”やアップサイクルを通じて一日限りのゆたかな時間をつくり出す。そんなコンセプトをもとに横浜市・相鉄線「星川」駅構内の空きスペースで3月15日に開催されたのが、「星天めぐる芸術祭2025〜めぐるを、あそぶ。〜」だ。
当日は、アートやデザインなどに携わる市内の事業者たちが集まり、パブリックアートや体育館の改修工事で出た床材のアップサイクルワークショップ、コーヒーかすを使ったアート体験など、多様なコンテンツが提供され、多くの人で賑わった。

当日の様子
本記事では、イベントの最後に開催されたスペシャルトークイベント「プレイスメイキングとしてのブリコラージュ ~循環をあそぶ都市~」から、当日の対話を紐解いていく。ゲストとして登壇したのは、文化人類学者の中村寛さん(多摩美術大学)、本イベントの主催であり、クリエイター向けのコワーキングスペース「PILE」を運営する津田賀央さん(Route Design合同会社)と、同じく主催のCircular Yokohama(ハーチ株式会社)から加藤佑さんと永野祐子さんだ。
場づくりや都市利用における、“あそび”の重要性とは何か。さらに、日本の祭文化に息づくブリコラージュ精神、横浜だからこそできる余白のあるまちづくりの可能性まで、幅広く議論された。
目次

左から、加藤佑さん、中村寛さん、津田賀央さん、永野祐子さん
ブリコラージュ精神を刺激する、“あそび”のある場って?
「ブリコラージュ」とは、フランスの人類学者、クロード・レヴィ=ストロースが1962年に発表した著作『野生の思考』の中で紹介された概念だ。必要なものをその場にあるあり合わせの道具や材料を用いて手づくりすることを意味する。「いまここにあるもので何とかする」というアプローチは、限られた資源の中で全ての人々のウェルビーイングの実現を目指すサーキュラーエコノミー(循環経済)の考え方にもつながる。
このブリコラージュの概念を地域の未利用空間におけるプレイスメイキング(場づくり)の取り組みに活かすことで、外部化された場所を都市の循環を実現するための拠点に変えることができないか?そんな問いとともに、イベントが始まった。
中村さん「“ブリコラージュ”には、『寄せ集めて自分でつくる』、『器用仕事』といったようにいろんな訳がありますが、今風に言うなら、DIYの精神に近いものかもしれません。それは、都市空間から少し距離を置いて自分の暮らし方を自分で選んでいるような人たちがごく自然に実践してきたことでもあります。
特に、環境負荷が小さい循環型の暮らしを目指すときに、外から新しい方法を持ち込むのではなく、すでに内側にある様式を掘り下げてみたり、手元にあるものから始めてみたりする姿勢がとても大事になると思っています。そういう意味で、ブリコラージュという概念はサーキュラーエコノミー的な視点とも親和性が高いし、環境問題を考える上でも大きな突破口になると感じています」

(左)中村寛さん
中村さん「それと、“あそび”──プレイ。この概念も人類学者や哲学者がずっと考えてきた奥が深いテーマで、最終的には“人間の本質に関わること”ではないかと言われています。
私たちは日々、仕事や労働に多くの時間を費やしていますが、思い返せば子どもの頃はずっと遊びに夢中でしたよね。これからAIがいろんな仕事を担うようになる時代に、最後に“人間らしさ”が残るとすれば、そのヒントは“あそび”の中にあるんじゃないか──そんな風に思ったりもします。
津田さんが運営されているコワーキングスペースの『森のオフィス』や『PILE』には、すごくいいバイブスがあるなと感じていて。“あそび”という言葉を特に意識しているわけではないかもしれませんが、空間の中に自然と流れている“余白”や“やわらかさ”が、まさにプレイの要素として機能しているように思います」
津田さん「たしかに、僕たち自身が“あそび”の感覚を持っているというのもありますし、空間の中に“余白”としての“あそび”を残しておくことは、すごく大切にしていますね。
以前勤めていた広告会社やメーカーでは、まずはしっかり計画をしてからでないと物事を進められないという文化がありました。でも、個人や少人数のチームでは、計画通りにいくことの方が少ないのです。すると自然と余白が生まれて、先のことが決まっていない中で場づくりをしていくことになり、その中であるものを使って即興的に演じたり、想像したりしていくようになる。それが結果的に、すごくブリコラージュ的な空間になっていくんだと思います。
『森のオフィス』では、さまざまな人の思いや考え方が、そのまま空間に反映されています。また、クリエイターのためのコワーキングスペース『PILE』では、“試行錯誤”をテーマにしています。とにかく試行錯誤し続けられる空間であることを大事にしていて、ルールも“会話とコラボレーションの空気感を止めない”ということだけにしています。あとはもう、レイアウトも自由に変えていいし、何を持ってきてもいい。
中村先生に感じていただいた空気感は、そういう“みんなでつくっていく”雰囲気から生まれているのではないかと思います」
永野さん「そういえば、私が通っていた美大のアトリエって、結構カオスだったんです。みんな自由に机のレイアウトを変更しちゃうし、よく見ると、誰かがつくった変な置物がインテリアになっていたりして(笑)。その“ごちゃまぜ感”が大好きだったのですが、今思えば、それも“余白”と“あそび”のある空間だったのかもしれません」

森のオフィス

PILE外観 / Image via PILE

PILE内観 / Image via PILE
ごちゃまぜの空間は、人間の“個”もゆるませる
中村さんはさらに、“あそび”のある空間を作り出す要素として、そこに集まってくる「人」も重要なのではないかと続ける。同時に、そうした人=「個」は、常に変化しない絶対的なものではなく、場所や状況によってゆらぐ自由さを持った存在でもあるという。
中村さん「アルベルト・メルッチというイタリアの社会学者が書いた『プレイング・セルフ』という本では、“セルフ(個)”という一つのアイデンティティとされてきたものに“プレイング”という概念をかけあわせて、いわゆる“あそびのある個”みたいなものを描いています。読んでいくと、軸がありつつも“余白的なあそび”があるような、ぶれのある“個”が出てきて、近代がつくり上げてきた“個”という幻想を緩めていくような感覚があります」
津田さん「自分のアイデンティティって、いろんな方面から見たときに少しずつ変わってくるものだと思います。“プレイ”って、“演じる”という意味もありますよね。そういう意味では、“ロール(役割)”に近い感覚もあると思っています。同質の人たちの中にいると、自分の“個”や“役割”についても単一的な側面しか見えなくなってきます。でも、コワーキングスペースのような余白のある場所で多種多様な人と出会うと、自分のアイデンティティが別の側面から見えてきたり、役割自体が変わってきたりすると思うのです」
中村さん「人と人との距離感って、場づくりにおいてすごく大事ですよね。そう考えると、場の規模感も、ブリコラージュやプレイを生み出す要素として大切なのかもしれません」
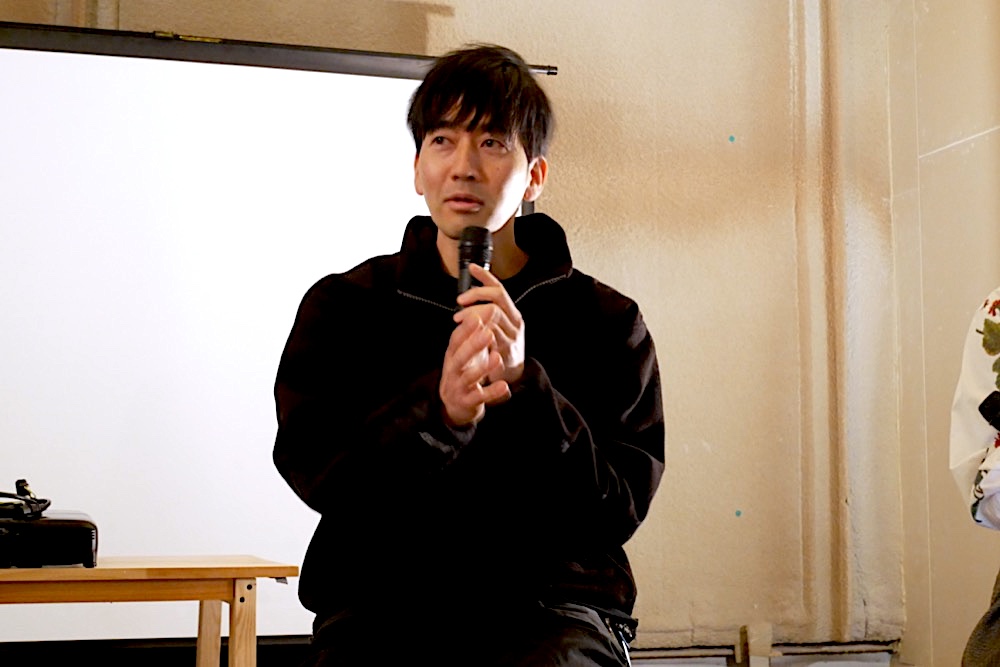
津田賀央さん

PILEによる、横浜ビジネスパーク(YBP)のクリスマスを彩ったクリスマスアート作品をポーチにアップサイクルするワークショップ。

決めないから、続く。都市をゆるめる「祭」のブリコラージュ精神
ここで加藤さんが、今回のイベントのメインテーマである、「名前も住所も定まっていないこの空間をどう活用するか」という点について改めて触れた。
加藤さん「何かをつくるということと、場づくりやまちづくりはつながっていると思いますし、ありあわせのもので何とかするという考えは、循環という視点でも重要です。また、“あそび”という視点では、余白があるほうが多様な人を招きやすく、結果として多様な視点が混ざることで素材や空間が内に秘めている新しい価値が発見される可能性が高まりますよね。その際に、ブリコラージュという概念は非常に有効だと感じました。ゼロから新たにつくるのではなく、今あるものからどのような価値を引き出すかが、循環の本質だと思っています」

イベント開催前の会場の様子。

(左)加藤佑さん
津田さん「“今あるものを活かす”って、“意味を再設計する”ことでもありますよね。昔つくられたものは、その当時の目的や価値観に基づいていたと思いますが、それを今の視点で見直して、もう一度使ってみる。むしろ、今だからこそできる意味づけを通して、違う役割を持たせていく。それもすごくブリコラージュ的な発想だと思います。
場所についても同じで、都市には使われていない区画や光の当たらない部分がたくさんあります。そうした場所の意味を捉え直すことで全く違う見方ができ、都市の有効活用につながるのではないでしょうか」

横浜市内の公共建築物の古材をアップサイクルする「REYO(リヨー)」による、市内の体育館の床材を家具にアップサイクルするワークショップの様子

津田さん「ただ、それを実現するには、時代の変化を捉えてスピーディに動く必要があります。じっくり計画しているあいだに意味が変わってしまう。だから、“とりあえずやってみよう”くらいのノリで、軽やかに場所を動かしていくことも大事だと思います」
中村さん 「ロンドンやベルリン、ニューヨークなんかでは、市民が自分たちで社会環境をレクリエーションする文化が根づいており、使われていない空間がクリエーターにとって魅力的な場になっています。一方、東京は条例などの多くのハードルがあり、空間を自由に使える余地が少ないと感じます」
永野さん「綺麗につくられた箱を渡されて『はい、どうぞ』と言われるとむしろ力が入ってしまい、“あそび”がなくなってしまうような気がします。完成されたギャラリーよりも、かつての発電所をクラブに変えて若者が自由にナイトパーティーをするといったような、余白のあるブリコラージュ的な都市の使い方は魅力的ですよね」

永野祐子さん
中村さん「一方で、日本って昔からお祭りが受け入れられてきた国でもあります。お祭りってただ楽しいだけのものではなく、実は社会のヒエラルキーを一時的にひっくり返してしまうような強い力を持っているんです。また、もともと神事としての要素もあるから、たとえばその日だけ賭け事が許されるといったように、いろんなルールが一時的に“解放”されるんです。
そういう何でもありの空気がお祭りでは許容されているのに、都市空間でクリエイターが場所を使おうとすると、いきなりレギュレーションがすごく厳しくなるのは不思議ですよね。お祭りだからという理由で、多少うるさくても大目に見てもらえるような許容度が都市のなかにもあったら、もっといろんな価値が生まれると思うんですよね」
津田さん「僕は今住んでいる長野県の富士見町で、いわゆる奇祭と呼ばれている御柱祭に参加したことがあるのですが、実際に地域の一員として関わってみて感じたのは、あれだけ長く続いている伝統の中に、とても自由さがあるということだったんです。
というのは、御柱祭のやり方は全て口伝なんです。千年続いていると言われると、同じやり方が守られているように思いがちですが、実際には時代ごとに語り手が変わっていて、その価値観が色濃く反映されている。つまり、その時その時で、曖昧に、でも確かに変化してきた。それってすごくブリコラージュ的だと思うんですよね」

御柱祭の様子 / 撮影:津田賀央
津田さん「ですから、御柱祭にマニュアルをつくってしまったら、きっとどこかでつまらなくなって、終わってしまうのではないかと思っています。なんとなく『昔からこうしてるからやってる』っていう曖昧さとか、『なんでかわからないけどやってる』っていう空気感が、むしろ続いていく理由なんじゃないかと。そうやって柔らかく変化していけることこそが、本質的な強さなんじゃないかと感じています。
それって、場づくりにも通じるところがあると思っていて。計画通りにやろうとすると、どこかで終わってしまう。でも、変容を前提にしていると、失敗すらも次の形につながって、どんどん魅力的なものになっていくんじゃないかな」


アートプロジェクト「似て非works」による、廃材を活用したアップサイクル展示
横浜だからこそできる、ブリコラージュ的まちづくり
決めないからこそ、続く──日本に根付く祭の文化の中に息づいていたブリコラージュ的精神から、都市の使い方におけるヒントが紐解かれた。最後に加藤さんから、ここまでの議論を踏まえ、横浜という場所だからこそできる“余白”や“あそび”の可能性について、それぞれの登壇者に問いかけた。
中村さん「横浜って、“これが横浜らしさだ”っていうイメージが、あまり定まってこなかったように思います。でも掘っていくと、たとえば商店街の歴史や、関内のアート拠点など、魅力的なストーリーがたくさんあるんです。
ですから、たとえば『この場所を歩いてみたら面白かったから、こんな使い方をしてみたい』といった、“未利用空間”を活用する提案が集まるような仕組みがあれば、沿線やローカルエリアがもっと豊かになるはず。歩きながら『ここ使えるかも』って想像できると面白いのではないでしょうか」

Circular Yokohamaによる、コーヒーかすアート体験

津田さん「この会場がある相鉄線沿線は、いわゆるベッドタウンという印象が強くて、外から見るとあまり語られることが少ないエリアかもしれません。でも実際にスペースを開いてみると、本当に魅力的な人がたくさんいたんですよ。働く場所ではなく、住む場所だからこそ、表に出てこなかった価値がたくさんあったんです。スペースをきっかけにそういう人たちが自然と集まり、場にあるモノを持ち寄って遊び始めて、そこからマルシェが生まれたり、アートイベントになったりしています。
去年もこの高架下の壁を使ってパブリックアートを展開したのですが、実は“遊べる公共空間”って、身近なところにあるんですよね。みなとみらいのように整備された都市とはまた違って、この地域にはまだ余白がある。だからこそ、まだ見えていない魅力や人の力を引き出していける気がしています」
永野さん「星川周辺って、やっぱり住宅地が中心ですよね。でもだからこそ、世代を超えた交流の場もつくれるんじゃないかと思っていて。
たとえば江東区には、学童・高齢者支援・子育て広場を一体化した複合施設『深川縁道』という場所があったり、藤沢にはアパートと医療・福祉・地域の拠点を組み合わせた『のびしろハウス』という場所があったりしますが、横浜でも、そんな“ごちゃまぜ”のプレイスをつくることができたら面白いですよね。
私は銭湯が大好きなんですが、それはおばあちゃんたちがすごく気さくに話しかけてくれて、そこが異世代とつながれる貴重な場になってるからかもしれません。そんな場がもっとあると良いなと思うんです」

トークセッションの様子
加藤さん「これまでの話を聞いて改めて思うのは、“予定調和ではない出来事”が起こるからこそ、場に価値が生まれるということです。予期せぬハプニングや偶発性は扱いづらいものとして排除されがちですが、むしろそれがあるから場が面白くなり、意味が深まっていく。
この空間のように、日当たりが悪いとか、活用しづらいと思われていた場所ほど、見方を変えれば“あそびがい”があるし、想像力をかき立ててくれる。一見価値が低そうに見える場所こそ、別の視点から見たときに新しい意味を持ち得る。そこに循環的な価値の再発見があると思うんです。
そして、そういう場所に新しい意味を持たせていくには、今日のようにいろんな人が集まって、それぞれの多様な視点や経験を持ち寄ることが欠かせないのではないでしょうか。ブリコラージュ的に組み合わせていくからこそ、新しい使い方が自然に生まれてくる。そういう瞬間って、やっぱり面白いですよね。
都市をきれいに形づくるというよりも、使いながら、遊びながら、変化を楽しむ。横浜というまちには、そんな“あそびがいのある余白”が、まだまだたくさん残っている。これからも、そんな“あそび”のある都市づくりを一緒に考えていけたらと思います」
編集後記
開港160年を超えた横浜では、都市のシンボルとも言える臨海部・みなとみらい21地区の開発がひと段落しつつある。かつて何もなかった場所に美しいまちが形成され、その景観は市民のシビックプライドにも大きく貢献しているが、一方でかつてそこにあった余白はなくなりつつある。
それゆえに、常に“あそび”や自由な表現を好むクリエイターたちは、新たな余白を求めて徐々に市内の内陸部へと向かっているのかもしれない。今回のイベント会場となった星川は、ちょうど東部の臨海部とみどりが豊かな内陸部の“あいだ”に位置し、横浜が抱える多様性が出会いやすい場所でもある。その意味で、今回この場所で本イベントが開催されたことは、ある種の必然とも言えるだろう。
都市における循環が実現するためには、すでにあるものや「ごみ」というレッテルを貼られた資源が、価値ある資源として発見されなおす必要がある。そのためには、多様な価値観を持つ人々が集まりやすい、余白としてのプレイス(場)が必要だ。その場は、いつも一時的で、可変的で、だからこそ自由に「あそぶ」ことができる。そして、計画や予定調和という概念から解き放たれた“あそび”の中で発揮される人々の創造性こそが、新たな循環を生み出すインスピレーションとなるのだ。
創造的な循環都市を実現するためのヒントが詰まった一日だった。

登壇者集合写真
【関連記事】【3/15】星天エリアにて「星天めぐる芸術祭 2025 〜 めぐるを、あそぶ。〜」を開催します
【関連記事】高架下が循環の遊び場に変わる1日。星天めぐる芸術祭 2025 〜めぐるを、あそぶ。〜【イベントレポート】