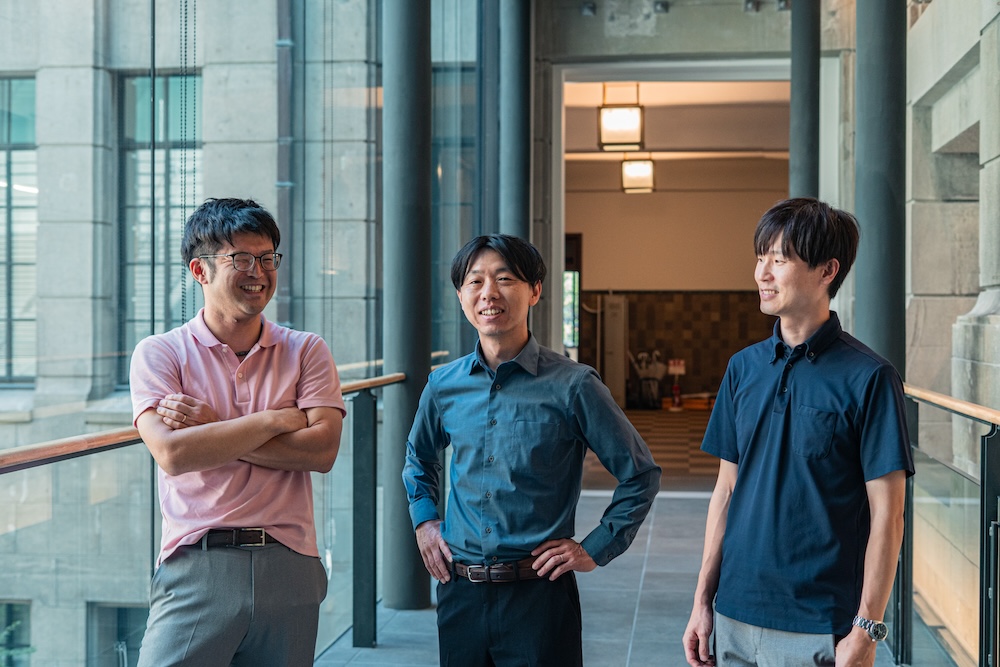【京都サーキュラーエコノミー特集】
本特集は、IDEAS FOR GOODと京都市の連携による、京都のサーキュラーエコノミーの今とこれからを考える特別企画。千年の都・京都に脈々と受け継がれてきた「しまつのこころ」の精神や循環型の暮らし、モノづくりの文化を、どのように未来の京都を形づくるイノベーションへと発展させ、次の1000年へ続く循環型の事業を創造できるのか。京都市、市内事業者、京都市政策推進アドバイザーの安居昭博氏とともに、サーキュラーエコノミーの視点から見た京都の価値と可能性を模索していく。(京都サーキュラーエコノミー特集トップ)
「千年の都」と称され、日本の文化首都として繁栄し続けるまち、京都。誇り高き伝統と歴史を身にまとい、世界中から観光客を惹きつけ、新旧の融合により未来に向けた革新を生み出し続ける京都に、いま一つの新しい波が起ころうとしている。
それが、サーキュラーエコノミー(循環経済)だ。製品やサービスの設計段階から廃棄や汚染を取り除き、素材や製品をできる限り高い価値を維持したまま循環させ続けることで、経済成長と同時に環境や地域の再生を目指すこの新しい経済社会システムへの移行に向けて、京都市は新たな事業を開始した。
京都市は、2000年度に82万トンあったごみの半減に向けて、2015年の「しまつのこころ条例」改正をはじめ、市民や事業者との協力により様々な取組を進めてきた。その結果、2024年度には約36.5万トンまで減少させるなど、大きな成果を挙げている。現在、2030年度までの京都市循環型社会推進基本計画「京(みやこ)・資源めぐるプラン」のもと、持続可能な循環型社会の実現に向けて着実に歩みを進めている。
しかしサーキュラーエコノミーとは、単なる資源循環の推進ではない。産官学民の多様なステークホルダーが協働しながら循環型の価値創造を通じて産業構造を変革し、地球上の限られた資源と生態系システムの中で全ての人々の持続可能な繁栄を目指す、システミック・チェンジである。
京都市は、2025年の秋からサーキュラーエコノミーをテーマとする市内事業者向けのラーニングプログラム「Circular Business Design School Kyoto(サーキュラービジネスデザインスクール京都)」を開始する。本プログラムは、京都の産業や文化、自然に古くから根付く循環型の叡智を紐解きながら、未来のイノベーションに向けたエッセンスを見出し、参加者や専門家らとともに新たな循環型のビジネスモデル創造に取り組む「学び」と「実践」の共創型プログラムだ。
本記事では、京都市がサーキュラーエコノミーへの移行を目指す背景や本プログラムの狙いについて、京都市環境政策局 環境企画部 環境総務課の木村公則さん、櫻井太郎さん、池田智大さんに話を聞いた。
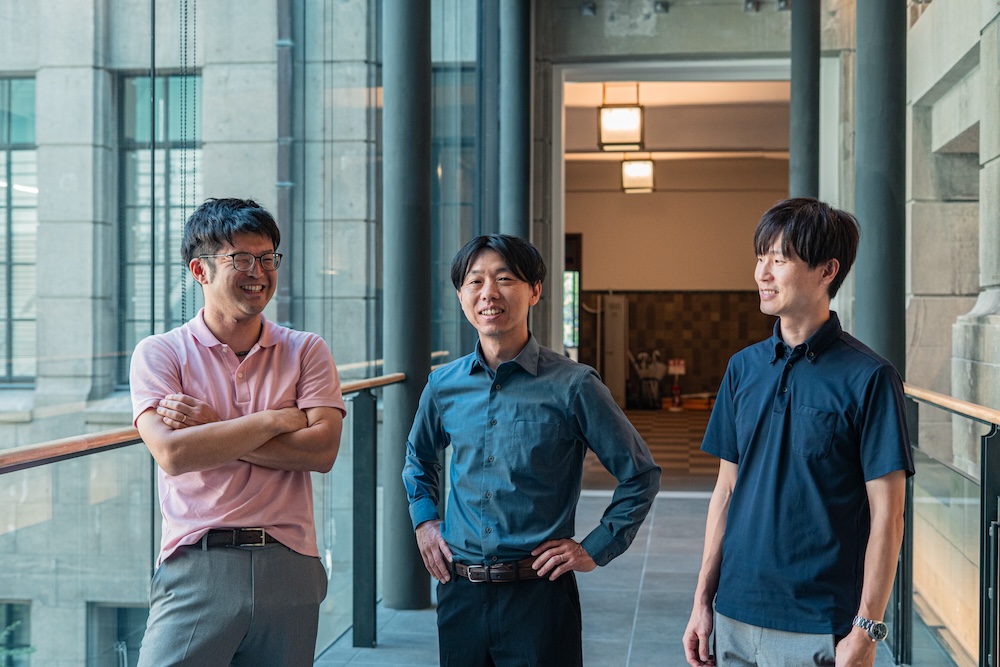
左から、櫻井太郎さん、木村公則さん、池田智大さん
話者プロフィール:
木村公則(きむら・まさのり)
京都市環境政策局環境企画部 環境総務課 課長
櫻井太郎(さくらい・たろう)
京都市環境政策局環境企画部 環境総務課 係長
池田智大(いけだ・ともひろ)
京都市環境政策局環境企画部 環境総務課 主任
1200年の文化を強みに、環境と産業を調和させる
「しまつのこころ」という言葉に象徴されるように、モノや資源を無駄にすることなく大切に使い続ける文化が1200年余りの歴史を通じて人々の暮らしに脈々と受け継がれてきた。そんな京都にとって、「サーキュラーエコノミー」や「循環」という概念は決して新しいものではない。黒染めや金継ぎといった伝統的な工芸や技術には循環型のモノづくりの本質が詰まっており、最近ではこれらの産業に新たに従事する若手職人や後継者も登場している。
また、すでに京都市内では、使用済み衣類の循環を目指すプロジェクト・RELEASE⇔CATCH(リリースキャッチ)や食品ロス削減に向けた生ごみコンポスト、循環をテーマとした循環フェスや都市と循環といったイベントなど多種多様なプロジェクトが展開されている。そのような中、なぜ京都市は新たにサーキュラーエコノミーの基盤づくり事業に至ったのだろうか。
櫻井さん「京都市では2021年に策定された『京都市行財政改革計画(2021-2025)』においてサーキュラーエコノミーを都市の成長戦略の一つとして位置づけ、2023年にはサーキュラーエコノミーの国内における第一人者である安居昭博氏をアドバイザーとしてお迎えし、昨年には現在我々が所属するサーキュラーエコノミーの担当が始動しました。
サーキュラーエコノミーは経済政策の側面もあり、これまでの環境分野にとどまらない施策を検討する必要があったことから、事業者様へのヒアリング、本市の産業関係部署への相談等を経て、一から事業を検討しました」
木村さん「京都市内では、環境に配慮した企業経営の風土が根付くほか、連携先となる大学やNPOをはじめとした中間支援組織などの多種多様なプレーヤーが存在し、サーキュラーエコノミーへの移行に向けた素地は整っていると感じていました。一方で、その認知やサーキュラーエコノミーをテーマとしたネットワークが十分でない現状を知り、ラーニングプログラムを軸に据えた今回の事業を実施するに至りました。
なお、サーキュラーエコノミーへの移行促進は、2025年3月に策定された、2027年度までに取り組む政策等を示した『新京都戦略』において、『リーディング・プロジェクト』の一つに位置づけています」
サーキュラーエコノミーへの移行には、気候変動や生物多様性、廃棄物などの環境課題に加え、産業をはじめとして、まちづくりや文化といった分野横断型のアプローチが求められる。京都市が従来の政策の枠組みを超えて「サーキュラーエコノミーの基盤づくり事業」を実施する背景には、京都が持つ歴史や文化資産を強みとしながら環境政策と産業政策を融合させることでまちの新たな未来を作り出すという意志があるのだ。

サーキュラーエコノミーは、未来を切り拓くためのビジネスチャンス
こうした思いを具現化するべく、新たに2025年秋から展開が予定されているのが、サーキュラーエコノミーをテーマとする市内事業者向けのラーニングプログラム「Circular Business Design School Kyoto(サーキュラービジネスデザインスクール京都)」だ。まだ資源循環や環境配慮をコストや負担と捉えている事業者も多い中、同プログラムを企画した背景にはどのような狙いがあるのだろうか。
櫻井さん「まさに、環境=コストといった考え方を変えたいという思いがこのプログラムの根底にあります。環境に関する取り組みを『何かを我慢する、しんどいもの』で終わらせてはいけないという強い意志です。経済活動や地域コミュニティ、文化といった様々な分野に環境という要素をポジティブに付加していくことで『環境』そのものの存在価値を高めていきたいのです」
木村さん「一気に事業を転換するのは非常に難しく、現実的ではないと思っています。ただ、ピンチをチャンスに変える。将来、資源枯渇などにより、規制強化や様々な制約が必ず訪れると思います。そうした遠くない将来のリスクに備えるという意味でも、サーキュラーエコノミーに関する学びは重要だと考えています」
実際に、欧州では2019年に公表された欧州グリーンディールの柱の一つとして2020年に新・循環経済行動計画が策定され、同計画で定められた重点分野(電子・情報通信、バッテリーとモビリティ、包装パッケージ、プラスチック、繊維、建築)やそれらをまたぐ形で矢継ぎ早に法規制が導入されている。2024年に施行されたESPR(エコデザイン規則)、2025年から適用されるCSRD(企業サステナビリティ報告指令)など、市場のルールが変わる中で多くの企業が対応を迫られているのだ。
これらの流れに合わせる形で日本でも2020年5月には「循環経済ビジョン2020」が、2023年3月には「成長志向型の資源自律経済戦略」が策定され、2025年の「第五次循環型社会形成推進基本計画」ではサーキュラーエコノミーが国家戦略として明確に位置付けられた。そして2025年5月には「資源有効利用促進法」の改正案が可決されるなど、移行の実現に向けた法整備も急速に進んでいる。
「国策に売りなし」という言葉もあるが、このように国家戦略や法規制が大きく変わるタイミングは、新たなビジネスやイノベーションが生み出しやすい絶好の機会でもある。
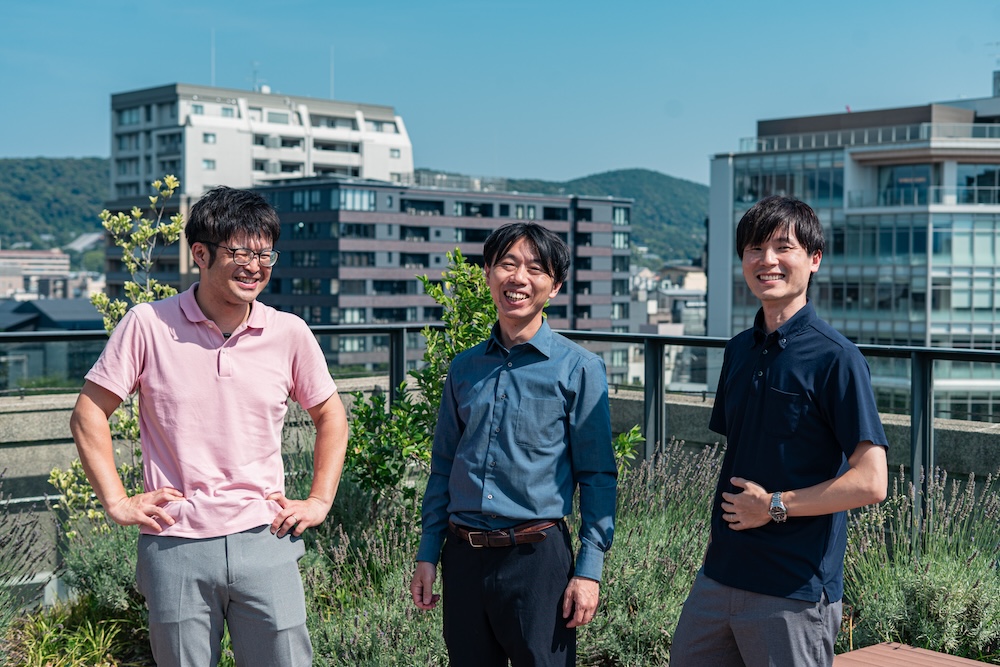
櫻井さん「事業者の方々には、サーキュラーエコノミーを未来を切り拓くための『ビジネスチャンス』として捉えてほしいのです。以前にお話を伺った、サーキュラーエコノミーを実践する企業の方が『企業の事業をすべて変える必要はない。ただ、将来のリスクヘッジとして事業の10%、20%でも循環の要素を取り入れることが、企業の健全性を保つことにつながる』とお話されていました。サーキュラーエコノミーは環境配慮というより未来を生き抜くための経営戦略そのものなのです」
池田さん「最終的には消費者として『こういう商品なら買ってみたい』と思えるものをこのプログラムを通じて生み出していきたいですね」
ここ数年で日本国内でも循環型ビジネスモデルへの移行に取り組む企業やスタートアップの数も増えてきており、サーキュラーエコノミー分野に投融資をしたいという投資家や金融機関の意向も高まってきている。最初から完成したビジネスモデルを目指すことは難しいが、この大きな波に乗り出すきっかけとしてこのプログラムを活用することで、いずれ訪れる市場の変化に対して先手を打つことができるはずだ。
分野の壁を越えた協働が、新たなビジネスチャンスをもたらす
今回のプログラムでは、京都市内に限らず日本や世界のサーキュラーエコノミーの最前線で活躍する専門家やメンター陣らによるサポートに加え、すでに多くの市民や事業者により実践が展開されている市内の中心部や、京都のまちづくりを支えてきた林業のまちであり、里山の循環を体感できる京都市北部・京北でのフィールドワークが展開される。
また、循環型ビジネスモデルの創造に欠かせない多様なパートナーとのマッチングや、仲間を集めるためのネットワーキング、循環型ビジネスモデルの将来的な社会実装に向けたプロトタイプ制作まで、多様かつ立体的なプログラム構成を通じてこれからサーキュラーエコノミーに取り組みたいと考える事業者を後押しする内容となっている。本プログラムに参加する価値を分かりやすく要約すると、どのような点にあるのだろうか。
櫻井さん「大きく三つの価値があると考えています。一つ目は、多様な専門家・メンターから直接アドバイスをもらいながら、プログラムを通じてプロトタイプの創出を目指すことです。二つ目は、伝統産業からスタートアップまでサーキュラーエコノミーを実践する現場を巡るフィールドワークで、京都市で培われてきたリアルな循環の知見に触れられることです」
木村さん「そして三つ目が、既存の業界、コミュニティではつながることが難しかった異業種の多様なプレイヤーとの出会いです。サーキュラーエコノミーをテーマに、業界を超えたプレイヤーが参加する。これまでに見られないプログラムです。参加者も特定の業界に偏らない、化学反応を誘発する場づくり、仕掛けを準備しています。チャレンジングな試みではありますが、ここから生まれる新しい連携、協業、サーキュラービジネスの創出に私たちも大いに期待しています」

櫻井さん「『環境』を基軸に産業的なアプローチを試みるという点が面白いと考えています。集まった方々の間でどんな化学反応が起きるのか。どんな次の一手が見つかるのか。プログラムから生まれたアイデアの種が一つでも多く社会実装されることを期待しています」
本プログラムは、同市の環境政策局が多様な分野のハブとなり、環境の視点で産業や文化をつなぐことで循環型のビジネスモデル創造を支援するという点に特徴がある。この多様な人々がつながる場のデザインは、サーキュラーエコノミーを実現する上で欠かせないアプローチの一つだ。多様な視点や価値観を持つ人々が交わるほど、自然と既存の資産や廃棄物などから新たな価値が発見される可能性も高まり、循環型ビジネスモデルの実現可能性は高まっていくからだ。
プログラムを通じて京都市内に循環型のエコシステムが構築され、そこに加わる人々がお互いに影響を及ぼし合いながら新たな事業を創発し、その点が線となり、面となり、システミック・チェンジを実現していく。このプログラムの先に京都市が見据えるのは、循環を軸とする新たな京都の成長の可能性である。
池田さん「このプログラムは、私たち行政にとっても大きな挑戦です。ぜひ、参加者の皆さんにも、私たちと一緒にチャレンジしていただけたら嬉しいです。ご応募をお待ちしています」

編集後記
古くより循環型の暮らしやモノづくりが根付いてきた京都という都市の未来に似合うのは、やはり循環型の未来だ。しかし、時代が変わり大量生産・消費・廃棄が当たり前となり、気候変動や資源制約など様々な課題が顕在化する現代において、その未来を創り出すためには、文化や伝統に埋め込まれた叡智を紐解き、その本質を引き継ぎながら未来に向けた革新を生み出すという丁寧かつ大胆な作業が欠かせない。そして、その道のりは決して平坦ではないだろう。
しかし、サーキュラーエコノミーという新たな経済社会システムの中で次の1000年の繁栄を享受するためには、先んじてその挑戦に乗り出す必要がある。幸運にも、今回のプログラムではその挑戦を本気で支えてくれる行政職員、地域の中間支援組織やパートナー、専門家らがいる。
この変化のタイミングで新たなビジネスチャンスを掴みに行きたいという事業者の方は、ぜひプログラムへの参加を検討してみてはいかがだろうか。ぜひ、10年、100年、1000年先の社会を展望し、自社そして京都の未来につながる新たな出会いと事業創造のヒントを見つけてほしい。
【2025年10月開始】Circular Business Design School Kyoto
京都には1200年の歴史の中で育まれた「しまつのこころ」や循環型の暮らし、モノづくり文化など、時代を超えて輝き続ける資産がある。気候変動や生物多様性の保全など地球規模の課題が深刻化する中で求められる循環型の未来を実現するには、これらの叡智を現代に活かし、未来につなぐ創造力が必要だ。そこで、IDEAS FOR GOODを運営するハーチ株式会社では、京都というまちに根付く循環型の叡智と最先端のサーキュラーエコノミー知見に基づく未来志向を掛け合わせることで、ともに欲しい未来を描き、実現するための学習プログラムを2025年10月より開催。「Decode Culture, Design Future 叡智をほどき、革新をしつらえる」──伝統の先に続く循環型の未来を、京都から。
ウェブサイト:https://cbdskyoto.jp/
Photo by 佐々木明日華
京都市環境総務課からのお知らせ
今回取材した京都市環境総務課では、サーキュラーエコノミーの推進と併せて「身近な環境問題」をテーマに、日常で実践できる環境保全アイデアをSNSで動画を発信中!
Instagram:@kyoeco.kyoto
Facebook:きょうえこ
TikTok :@kyoeco.kyoto