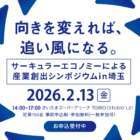リモートワークで働く場所を選べるようになった人がいる一方、介護や職種の制約から特定の場所を離れられない人がいる。頻繁な出張をこなす同僚を見て焦りを感じる人もいれば、転勤という会社の命令に人生を左右され、辟易としている人もいる。
私たちの日常に当たり前のように存在する「移動」。それは、誰にとっても平等なものなのだろうか。
社会学者の伊藤将人氏は、現代社会を「移動階級社会」というレンズを通して読み解く。それは、移動できる能力や機会が、社会的な階級や格差と密接に結びつき、人々の人生の選択肢を規定してしまっている社会の姿だ。
「一見個人的に見える移動は、実は社会的で政治的、経済的なものである」そう語る伊藤氏との対話から、見過ごされてきた格差を考え、より公正な社会を築くためのヒントを紐解いていく。
話者プロフィール:伊藤将人(いとう・まさと)
 1996年長野県生まれ。日本学術振興会特別研究員(DC2)を経て、2024年4月から国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員・講師。地方移住や関係人口、観光など地域を超える人の移動に関する研究や、長野県・新潟県を中心に持続可能なまちづくりのための研究・実践・産学連携事業に携わる。著書に『移動と階級』(講談社、2025、単著)『数字とファクトから読み解く 地方移住プロモーション』(学芸出版社、2024、単著)、『モビリティーズ研究のはじめかた――移動する人びとから社会を考える』(明石書店、2025年、共著)がある。
1996年長野県生まれ。日本学術振興会特別研究員(DC2)を経て、2024年4月から国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員・講師。地方移住や関係人口、観光など地域を超える人の移動に関する研究や、長野県・新潟県を中心に持続可能なまちづくりのための研究・実践・産学連携事業に携わる。著書に『移動と階級』(講談社、2025、単著)『数字とファクトから読み解く 地方移住プロモーション』(学芸出版社、2024、単著)、『モビリティーズ研究のはじめかた――移動する人びとから社会を考える』(明石書店、2025年、共著)がある。
あなたの選択肢を決める、見えない物差し「移動可能性」
議論の出発点は、社会の姿を映し出すレンズの解像度を上げるためのキーワード「移動可能性」だ。これは単に移動の回数や距離を指すのではない。「どれだけ自由に移動が可能か、そのポテンシャル(潜在的な能力)のことを指す」と伊藤氏は語る。それは、人生の選択肢の「幅」を測る指標に他ならない。
現在の日本において、この「移動可能性」は、収入や資産といった社会階層、そしてジェンダー、さらに大都市部とそれ以外の地域間格差という軸によって大きく偏在しているという。
「過去と比べて、誰もが移動しやすくなった時代であることは間違いありません。しかし現代では、グローバルエリートと呼ばれる人たちは歴史上最も移動しており、一般的な層との格差は、むしろ拡大しているとさえ言えるでしょう」
重要なのは、過去との比較ではなく、同じ時代を生きる人々の間に存在する格差だ。この見えざる格差の存在を認識することこそが、議論の出発点となる。

伊藤氏の講演の様子
テクノロジーが加速させる、新たな分断
この「移動可能性」というレンズを通して現代の働き方を見つめると、新たな分断の輪郭が浮かび上がってくる。例えば、新型コロナ禍を経て普及したリモートワーク。それは、場所に縛られない働き方を実現し、ポジティブな影響をもたらした一方で、その恩恵は決して平等には分配されていないのが現状だ。
「日本国内で考えると、現状テレワークを導入できているのは、東京をはじめとする大都市圏に集中し、企業規模が大きく、ホワイトカラーで、年収が高い層に偏っています。もともと社会的に有利な立場にいる人たちが、より使いやすいツールの一つになっているのです」
テクノロジーそれ自体には、善も悪もない。社会がそれをどう使い、どう受容するかで、その価値は決まる。現状のリモートワークは、移動できる人をさらに移動しやすくし、そうでない人との格差を広げる方向に作用している側面がある。
さらに、伊藤氏はリニアモーターカーのような新たな高速交通網も例に挙げ、「移動をめぐる公正さ」を問いかけた。
「今後リニアモーターカーも日本で走り始めますが、誰がリニアに乗って移動するかというと、主には東京から大阪に移動する人。しかし、リニアが通ることによって自分の生活環境が変化するのは、まったく違う層の人々だと思います。例えば、リニアの線路が通る予定である静岡では、近隣の河川や生態系への影響など、水をめぐる状況も大きく変わってしまうようです。つまり、交通インフラの恩恵を享受できる人と、交通インフラの整備に伴う負担を強いられる人は別なのです」
なぜ「移動する人」が賞賛されるのか?
技術的な格差だけでなく、私たちの内面に根付く価値観もまた、「移動階級社会」の構造を強化している。それは、「移動する人」を称賛し、その能力を高く評価する社会の風潮だ。
例えばビジネスの世界では、「足で稼ぐ」という言葉に象徴されるように、「頻繁な出張や海外赴任をこなす人は仕事ができる」といった価値観が根強く存在する。移動と個人の能力を同一視するこの風潮は、なぜこれほどまでに強力なのだろうか。

Image via Shutterstock
「それは、移動というものが、個人がすぐに直接的にコントロールできる、主体的・自発的な行動の最たるものだと思われているからです。裏を返せば、その移動さえしないあなたは、成功しないし、自発性がない、と見なされてしまう。こういう論理になっているのです」
SNSの普及もこの価値観を後押しする。Instagramを開けば、留学や旅行、出張といった「非日常」の移動を楽しむ友人たちの姿が目に入る。結果として、「みんな移動しているのに、自分はできていない」という焦燥感が生まれ、移動することが強迫観念のようになっていく。
そして、この「移動する人」を理想化する眼差しは、ビジネスの世界に留まらない。昨今の「地方移住」をめぐる言説にも、その歪みは顕著に表れている。移住者は地域活性化の担い手として注目を集めるが、その裏側で、これまで地域を支えてきた人々の存在が見過ごされていないだろうか。
「移住者が地域を救う存在として理想化されがちですが、彼らが関わりたいと思う地域が存在するのは、そこに定住している人々がいるからです。田んぼの草刈りのような日常的な営みが見過ごされ、移住者という『移動する側』にばかり光が当たってしまうのです」
ビジネスにおける出張や転勤、そして地方移住。場面は違えど、そこには「移動する側」の華やかなストーリーばかりが称賛される。
そして、この価値観は、いつでも移動できる健康な身体を持つ人々を暗黙の前提としている。誰もが移動できるわけではない。その想像力の欠如が、見えない生きづらさを生んでいるのだ。
ジェンダー化された移動の不自由さ
この「移動できる身体」を前提とした社会の眼差しは、さらにレンズを「ジェンダー」に変えることで、その非対称性を露わにする。痴漢の恐怖、あるいはケア役割による物理的な制約。歴史的に男性中心的に設計されてきた都市インフラや社会構造は、女性や性的マイノリティの人々の「移動可能性」に大きな影響を与えてきた。
伊藤氏が注目するのは、現代特有の現象だ。例えば、地方から都市の大学へ進学しようとする女子学生に対し、親が治安や犯罪など一人暮らしのリスクを心配するあまり、よかれと思って移動を制約してしまうケースがあるという。
「凶悪な犯罪の割合自体は減少傾向にあるにもかかわらず、メディアで個別の事件が大きく報じられることで、不安が増幅されます。娘を思うがゆえに、その子の移動可能性に制約をかけてしまう。これは非常に現代的な問題です」
さらに、今後深刻化するのが「ケアと移動」の問題だ。介護は、特定の拠点にとどまって行うことが多いが、それはつまり移動の制限となる。介護の担い手は依然として女性に偏る傾向がある。その意味で、女性は男性に比較して自由な移動をすること、そして移動によって得られたかもしれない何かを手放す可能性が高くなるのだ。
つながりが生む「ネットワーク資本」という希望
「移動」のあり方や価値観そのものを見直す。その上で、物理的な移動が困難な人々を孤立させないための希望の鍵として、伊藤氏が挙げるのが「ネットワーク資本」という考え方だ。それは、オンライン・オフラインを問わず、他者とつながり、情報を得たり支援を受けたりできる関係性のことである。
「孤立や孤独の問題は、移動の課題と密接に関わっています。イギリスで始まった『社会的処方』のように、薬ではなく人とのつながりを処方するアプローチが日本でも注目されています。医師と患者だけでなく、地域と人をつなぐ『リンクワーカー』のような役割が、今後ますます重要になるでしょう」
企業が駐在員の配偶者の孤立を防ぐ仕組みを考えたり、自治体がUターン移住者へのサポートを手厚くしたりすることも、ネットワーク資本を育む具体的な一歩だ。そして何より、移動の実態をデータに基づいて正しく把握し、多様な人々が参加する場で議論を重ねていくこと。その地道なプロセスこそが、誰もが取り残されない社会への道筋となる。
移動をめぐる課題は、今、自分に関係がないと感じる人にとっても、決して他人事ではない。病気、介護、加齢。人生のステージが変われば、誰もが移動の不自由さに直面する可能性があるのだ。
「今は他人事かもしれないけれど、誰にとっても自分事なんです。その想像力を持つことが、すべての始まりです」
編集後記
頻繁に国境を越えて移動する友人たちに刺激を受け、また自分も「移動」を通じて研鑽を積もうとする一方で、介護を理由に特定の場所を離れられない親戚の顔を思い浮かべる。まさに周りにいる誰もが、そして筆者自身が伊藤氏の著書のタイトルでもある「移動階級社会」の当事者だ。
今回のインタビューで心に残った「移動の課題は、誰にとっても自分事」というメッセージ。今は自由に移動できているとしても、病気や介護、あるいは自身の加齢によって、その自由は永遠ではなくなる。そしてもしいま「移動可能性」が担保されていると感じたとしても、それは自身の努力だけで得られたものではない。それを支える社会の仕組みや、自分が生まれ落ちた環境に依るところも大きいだろう。
だからこそ、まずは隣にいる人の「移動」に想像力を働かせることから始めたい。その想像力が、いつもの景色を少しだけ違って見せてくれるはずだ。
【参照サイト】伊藤将人(Ito Masato)のプロフィールサイト
【関連記事】「誰もが住みやすいまち」のために、まず女性の声を聞く。『フェミニスト・シティ』著者を尋ねて【多元世界をめぐる】
【関連記事】飛行機に乗れるのが特権ならば、陸路の長距離移動は「超特権」か?
Featured image created with Midjourney (AI)