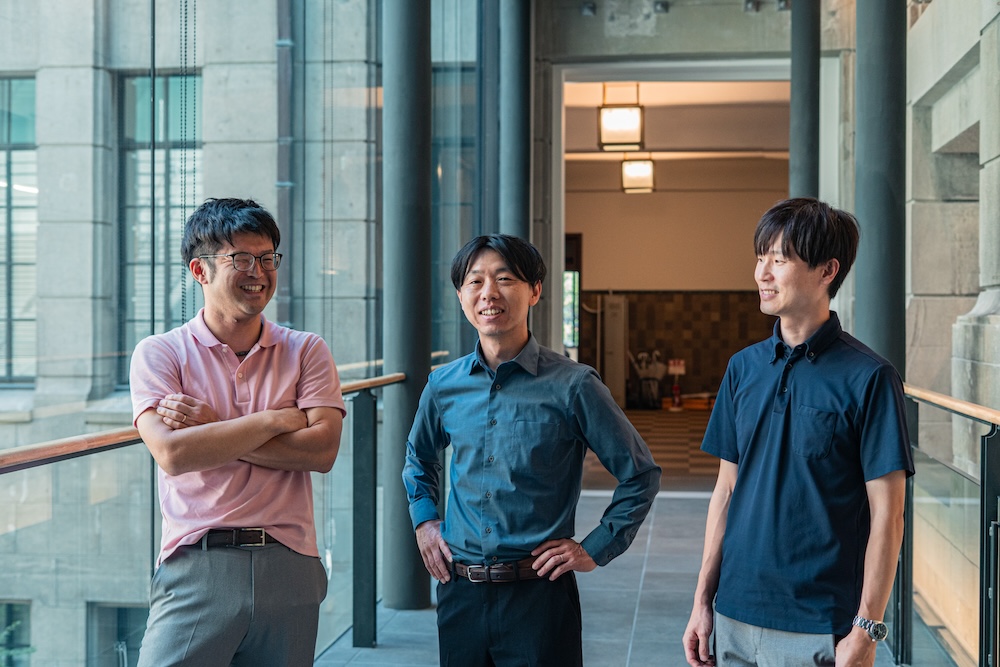【京都サーキュラーエコノミー特集】
本特集は、IDEAS FOR GOODと京都市の連携による、京都のサーキュラーエコノミーの今とこれからを考える特別企画。千年の都・京都に脈々と受け継がれてきた「しまつのこころ」の精神や循環型の暮らし、モノづくりの文化を、どのように未来の京都を形づくるイノベーションへと発展させ、次の1000年へ続く循環型の事業を創造できるのか。京都市、市内事業者、京都市政策推進アドバイザーの安居昭博氏とともに、サーキュラーエコノミーの視点から見た京都の価値と可能性を模索していく。(京都サーキュラーエコノミー特集トップ)
クローゼットの奥で眠る、シミが付いてしまったお気に入りのシャツ。日焼けで色褪せた、思い出のブラウス。まだ着られるはずの服を「もうさすがに人前では着られない」と諦め、手放してはいないだろうか。
そんな衣服が、捨てられる運命から救出され、新たな命を吹き込まれる場所が京都にある。創業150年を超える京黒紋付染の老舗・馬場染工業だ。
同社は、着物文化の衰退という危機において、黒紋付の黒染めの技術を「洋服の染め直し」に応用するという大胆な一手で乗り越えた。服の再生を通して、ものを大切に長く使う文化をも再生しているのだ。その哲学と、伝統を未来へつなぐための革新の記録について、5代目の馬場麻紀さんに話を聞いた。
話者プロフィール:馬場麻紀(ばんば・まき)
 上田安子服飾専門学校を卒業後テキスタイルデザイナーとして勤務。2008年より五代目・柊屋新七を継承。洋裁の技術を生かし着物の染めから洋服の染替えを中心に移行。息子の六代目と共に奥深い黒染めを追求する。
上田安子服飾専門学校を卒業後テキスタイルデザイナーとして勤務。2008年より五代目・柊屋新七を継承。洋裁の技術を生かし着物の染めから洋服の染替えを中心に移行。息子の六代目と共に奥深い黒染めを追求する。
「黒より黒い黒を」父が追い求めた、カラスの濡羽色
馬場染工業の歴史は、明治3年(1870年)、版籍奉還の喧騒のなかで幕を開けた。
「私たちは明治3年創業で、初代は岐阜から京都に来て黒染めの工房を構えました。当時は天然染料で染めていて、黒といっても実際は茶色に仕上がる“茶染め”が主流だったんです。2代目の頃になると、国鉄の制服が紺色だったこともあり紺染めが中心になりました。さらに3代目の時代には化学染料が入ってきて、少量の染料で今までにないほど深くて美しい黒が出せるようになり、黒染めが事業の柱になっていきました」
大きな転機は4代目である父の代に訪れる。ある葬儀の場で、父は自社の黒紋付を見て、黒染めのはずがグレーに見えると感じたという。そこから「どうにかして黒い色を出せないか」と染料屋と二人三脚で研究を重ね、「カラスの濡羽色」を理想に2年かけて独自の漆黒「秀明黒(しゅうめいぐろ)」を完成させた。

「完成した時は、日本全国から『こんな黒い色、すごい』という声が届きました。1ヶ月で3万点もの依頼が来たと聞いていて、どうやってこなしたのかと思うくらい、大騒ぎだったのを覚えています」
この圧倒的な黒「秀明黒」の登場は、業界に大きな衝撃を与えた。当時、京都に130軒ほどあった同業者の間でもその名は瞬く間に広がり、馬場染工業の技術と名声を不動のものにした瞬間であった。
黒く染まる工場と、次なる歴史
しかし、時代の流れは残酷だった。黒紋付や黒の着物を着る文化そのものが衰退し、工房の仕事は少しずつ減っていった。
「家業を継ぐ気はまったくありませんでした。洋服が好きで、テキスタイルデザイナーの仕事をしていましたし、工房の片隅で自分で作った小物を売っている方が性に合っていました」
そんな時、黒の探求者であった父が余命2年との宣告を受ける。150年の歴史に幕が下りようとしていた。ある日、麻紀さんが工房を覗くと、父が代々継ぎ足してきた染料を釜から流し捨てていた。
「後継ぎもいないから、もうやめる」

工場が、真っ黒に染まっていく──そんな光景を目の前にして、麻紀さんはとっさに「もったいない、私がやります」と口にしていた。
「父は口では『しょうもないことを』と言いながらも、少しだけ染料を残してくれました。後から父の日記を見たら、私が継ぐと言ったことを喜んでくれていたと知りました」
墨汁で汚れたベストが教えてくれたこと
父から工房を託されたものの、洋服の専門家である麻紀さんにとって、着物の染めは未知の領域だった。
「洋服の染め方は知っていましたが、きちんとした着物の染めは全くわかりませんでした」
昔この工房で働いていた職人に頭を下げ、「これはなぜこうするのですか?」と質問を重ねながら、一つずつ技術を身につけていった。
「新しい方向性を思いつくきっかけをくれたは、当時中学生だった娘です。買ったばかりの白いベストに墨汁をつけて帰ってきて、『お母さん、黒く染めて』と言ったんです。その時に『あ、これだ』と閃きました。染め直したら新品のようになって、娘もとても喜んでくれました」
その出来事をきっかけに、麻紀さんは自ら簡単なホームページを作り、洋服の黒染めサービスを開始。まだインターネットがそれほど普及していなかった時代だったものの、少しずつ注文が増えていったそう。その一歩が、馬場染工業が「着物」から「洋服」へと時代のニーズに合わせて軸足を広げる契機となった。
クレームは事業を磨くチャンス
洋服の黒染めサービスを始めた当初は、失敗も少なくなかった。
「ウールのセーターを縮ませてしまったこともありましたし、染め上がったスーツをプレスせずに返して『こんなシワシワで着られるか』と怒られたこともあります。それでも、怒られたときはチャンスだと思っています。言われたことを改善すれば、次は同じことで怒られなくなりますから」
スーツのシワを指摘されたことをきっかけに、美しいプレス仕上げを標準サービスに。さらに、洋裁技術を生かし、単なる染め直しに留まらない対応を実現している。
「ほつれがあれば直せますし、必要に応じてリペアも提案できます。縫製ができるのが私の強みなので、染めだけでなく、綺麗にお直しが終わっているというところまで、今はできるようになっています。『染め直しに出したら、新品のようになって返ってきた』といったお客様が手を叩いて喜ぶ様子を直接見られることが、私の1番の喜びなんですよ」
捨てられるはずだった服が、持ち主の想像を超える姿に生まれ変わって戻る──その真摯な姿勢は口コミで広がり、顧客の輪を着実に広げていった。

時代と対話する黒が、未来を描く
現在、馬場染工業は6代目となる息子・健悟さんへとバトンを渡しつつある。麻紀さんが洋服に合う「自然な黒」を追求してきたのに対し、6代目の時代になると、アパレルメーカーから「他よりも黒い黒にしてほしい」と依頼されるようになったという。その要望に応え、父(4代目)が開発した秀明黒を洋服向けに調整し、洋服でも映える黒を表現する技術を生み出した。
「昔のやり方だけで着物ばかりやっていたら、うちはもうとっくになくなっていたと思います。時代に合わせて変えてきたから、ここまで続けられたんです。
今後は、アパレル店で『売れ残った』『展示中に日焼けして売れなくなった』『色間違いで廃棄にしないといけない』などの事情でお困りの商品を黒く染め直して新しい企画として売り出すなどの協業にも期待しています。京都に多いホテルや旅館で、使わなくなった館内着などを黒染めしてリユース品として売り出してほしいですね」
そう語る麻紀さんは、工房でのワークショップなどを通じて「捨てる時代から、大切に使い続ける時代へ」と変化する現状を伝えることにも意欲を見せる。歴史や文化を学ぼうと多様な世代が集まる京都だからこそ、その可能性は大いに広がっていくだろう。

左から6代目の馬場健悟さん、5代目馬場麻紀さん
茶染めから紺染め、そして黒染めへ。着物の黒から洋服の黒へ。そして自然な黒から再び秀明黒へと至るまで、時代ごとの声を受け止め、変化を続けてきた。
「変えてはいけない部分と、変えていかなければならない部分があります。守るところは守るし、変えるところはきちんと変える」
一着の服を蘇らせることから始まった挑戦は、今や伝統産業そのものを蘇らせるという大きな挑戦へと広がった。色褪せた服に再び深い黒を吹き込むように、馬場染工業は古都の伝統に新たな色をまとわせ、「守るための変化」を生み出している。
編集後記
私たちは伝統という言葉に、どこか不変で静的なイメージを抱きがちだ。しかし、麻紀氏は「伝統を守ることは、変わり続けること」だと語る。馬場染工業の歩みは、伝統とは時代のニーズという激流の中で、本質という舵を握りながら航海を続ける、動的な営みであることを教えてくれたのだ。
クローゼットに眠る一着の服は、単なる「もの」ではない。自分の記憶や家族の物語を宿した媒体でもあるだろう。それを「黒く染め直す」という行為は、資源を循環させることが重要視される中でものをより長く使い続けるための後押しであり、思い出を大切にしながら未来に向けて再び物語を紡いでゆく、希望ある選択なのかもしれない。
【2025年10月開始】Circular Business Design School Kyoto
京都には1200年の歴史の中で育まれた「しまつのこころ」や循環型の暮らし、モノづくり文化など、時代を超えて輝き続ける資産がある。気候変動や生物多様性の保全など地球規模の課題が深刻化する中で求められる循環型の未来を実現するには、これらの叡智を現代に活かし、未来につなぐ創造力が必要だ。そこで、IDEAS FOR GOODを運営するハーチ株式会社では、京都というまちに根付く循環型の叡智と最先端のサーキュラーエコノミー知見に基づく未来志向を掛け合わせることで、ともに欲しい未来を描き、実現するための学習プログラムを2025年10月より開始。「Decode Culture, Design Future 叡智をほどき、革新をしつらえる」──伝統の先に続く循環型の未来を、京都から。
ウェブサイト:https://cbdskyoto.jp/
【参照サイト】京の黒染屋(馬場染工業株式会社)
Photo by 佐々木明日華
Edited by Natsuki