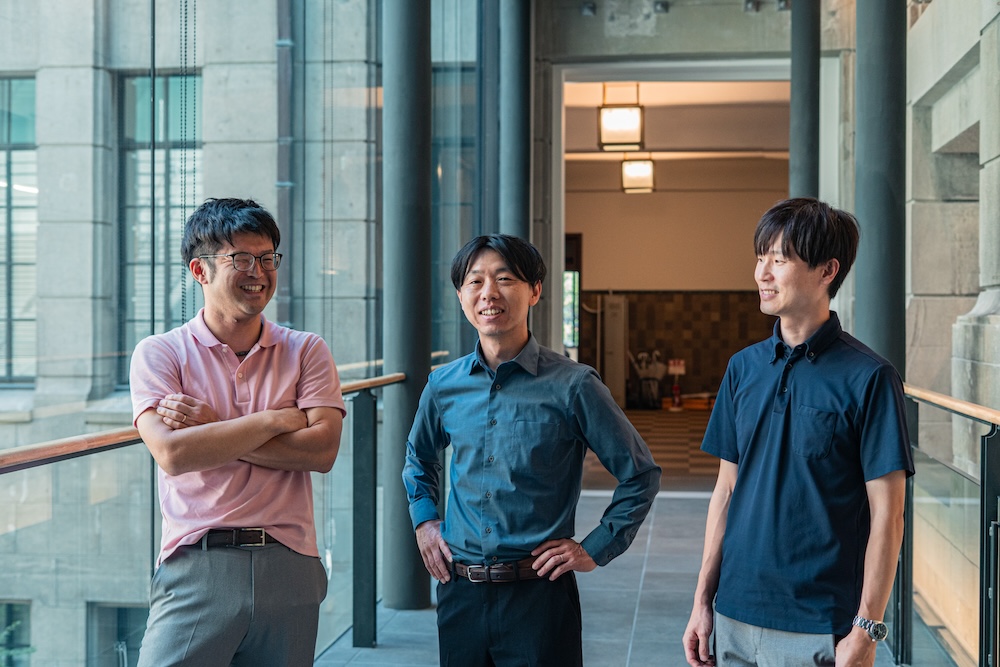【京都サーキュラーエコノミー特集】
本特集は、IDEAS FOR GOODと京都市の連携による、京都のサーキュラーエコノミーの今とこれからを考える特別企画。千年の都・京都に脈々と受け継がれてきた「しまつのこころ」の精神や循環型の暮らし、モノづくりの文化を、どのように未来の京都を形づくるイノベーションへと発展させ、次の1000年へ続く循環型の事業を創造できるのか。京都市、市内事業者、京都市政策推進アドバイザーの安居昭博氏とともに、サーキュラーエコノミーの視点から見た京都の価値と可能性を模索していく。(京都サーキュラーエコノミー特集トップ)
京都駅から徒歩2分。「千年先も続く心地よさを追求する」というコンセプトに基づき、世界中から訪れるゲストを持続可能かつ特別な宿泊体験でもてなしているのが、京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社が運営するホテル、「THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)」だ。
環境・社会・経営の持続可能性を評価する宿泊施設向けの品質認証制度・サクラクオリティ「An ESG Practice認証」の「3御衣黄ザクラ」を、2022年に国内で初取得した同ホテルの実践は、ハードからソフトにいたるまで持続可能な循環型の取り組みを多数見ることができる。
建物には京都の美しい山々をモチーフとする緑化や太陽光発電による自然エネルギー、京都の豊富な地下水脈を生かした井水活用システムが導入されており、夜になるとフロントでは実質再生可能エネルギー由来の電力を用いて展示されたデジタルアートがゲストを迎え入れる。
屋上では養蜂が展開され、地域の生物多様性保全に貢献するとともに、ハチミツを使用したメニューも数量限定で提供されている。また、規格外の野菜や大豆ミートを活用した食事や食品ロス削減に向けた取り組み、廃棄予定の食器のリカラーによる再利用など、厨房では食の持続可能性が徹底的に追求されている。
さらに、タイガー魔法瓶とのコラボレーションにより市内初となる「使用済みステンレス製ボトルの回収と再資源化」に回収拠点として参画するほか、ホテルオリジナルデザインのステンレス製ボトルの貸出しも実施。その他、カーボンフリー観光のためのレンタサイクルや客室のプラスチック製アメニティの見直しなど、ゲスト満足度を追求しながら資源の有効利用や循環も徹底している。
これらの THE THOUSAND KYOTO のサステナビリティを牽引してきた立役者が、総支配人である櫻井美和さんだ。THE THOUSAND KYOTO は、どのようにホテルの提供価値である「心地よさ」という概念をアップデートし、現在の持続可能な循環型ホテルへと進化を遂げてきたのだろうか。櫻井さんにこれまでの歩みとこれからの未来について聞いた。
話者プロフィール:櫻井美和(さくらい・みわ)
 2014年京阪ホテルズ&リゾーツ入社後、THE THOUSAND KYOTOで婚礼・宿泊部長を歴任。2019年GOOD NATURE HOTEL KYOTO開業に伴い総支配人に就任。2021年よりTHE THOUSAND KYOTO、京都センチュリーホテル総支配人を務め、2024年7月常務取締役就任。
2014年京阪ホテルズ&リゾーツ入社後、THE THOUSAND KYOTOで婚礼・宿泊部長を歴任。2019年GOOD NATURE HOTEL KYOTO開業に伴い総支配人に就任。2021年よりTHE THOUSAND KYOTO、京都センチュリーホテル総支配人を務め、2024年7月常務取締役就任。
一人の心地よさから、社会の心地よさへ
長らくホテル業界で経験を積んできた櫻井さんは、約10年前よりTHE THOUSAND KYOTOの開業に参画。その間に現在では京阪グループのビオスタイル事業のフラッグシップであり、日本のサステナブル・ホテルの代名詞とも言える「GOOD NATURE HOTEL KYOTO」の立上げを担当。2025年現在ほどSDGsやサステナビリティという概念が浸透する前から、未来を見据えた本質的なホスピタリティのありかたを追求してきた。
THE THOUSAND KYOTOでは2022年7月に「サステナブル・コンフォート」というコンセプトを打ち立て、大きな変化に踏み出した。その背景には何があったのだろうか。
「もともと当ホテルは『パーソナル・コンフォート』を掲げ、デジタルネイティブで洗練された30代をターゲットに設定していました。しかしコロナ禍を経て、自分が快適であれば良い『Me』の考え方から、皆が良い状態を望む『We』の考え方へとお客様の価値観がシフトしたと感じ、ターゲットをより社会や環境への意識が高いコンシャス・リーダーたちへ変更しました」

「ホテルの名前であるTHE THOUSAND KYOTOは『千年の都・京都の千年ホテル』を意味します。京都自体がサステナブルな都市ですから、その名を冠する以上、私たちもサステナビリティにしっかりと取り組むべきだと考え、『パーソナル・コンフォート』から『サステナブル・コンフォート』へとコンセプトを進化させたのです」
「102のアクション」が灯した、従業員一人ひとりの意志
しかし、コンセプトやターゲットを変えただけで、すぐに変化が起きるとは限らない。大きな目標に対して具体的なアクションも伴わせるべく、櫻井さんは思い切った施策を行った。
「何から手をつければ良いか分からない従業員も多かったので、まず『1年間に100のアクションを起こす』という目標を掲げました。アクションワードとして『Think 1000 year comfort.』を定め、地域のためになるなどの指針に沿ったアイデアを全従業員から募集したところ、858個ほど集まりました」
「その中で、実現可能なものからどんどんと実行し、最終的には1年間で102個のアクションを達成しました。この取組みを通じて従業員一人ひとりの環境意識が変化したことが何よりの成果だったと思います」
さらに、アイデアの実践期間には、部門ごとの達成状況をグラフで可視化し、チームごとに一丸となって取り組んだという。これらの工夫が、従業員一人ひとりがサステナビリティを「自分ごと」として捉え、業務の中で何ができるかを考えるきっかけになったという。サステナビリティが一部の担当者のものではなく、全従業員の共通言語となっていったのだ。
ひととミツバチが協働するホテル
冒頭で紹介した様々なアクションの中でも特にゲストから好評を得ているのが「都市養蜂」だ。ホテルの屋上にはミツバチの巣箱が置かれ、従業員が運営の主体を担っている。「はちみつマイスター」の資格を取得したスタッフもいるという。
「都市養蜂は、見学したいというお客様が年間何組もいらっしゃいます。最近ではツアーも作り、学校からの見学依頼もありますね」
ここで採れるハチミツは「THE THOUSAND HONEY」と名付けられ、2024年には約130キロもの収穫があり、レストランのメニューや限定商品としてゲストに提供されている。
「近隣の東本願寺の飛び地にある渉成園では、この養蜂を始めてから梅の実が多く実ったような気がします。収穫した梅とはちみつでシロップを作り、ドリンクとして提供するなど、地域とのつながりも深まっています」
人間だけではなくミツバチも仲間に迎え入れ、ゲストの体験だけではなく地域の生態系も同時に豊かにしていく。人間中心を超えて多種に豊かさをもたらすホテルとも言えるかもしれない。

屋上にある都市養蜂|Image via THE THOUSAND KYOTO

ホテルでは客室にペットボトルを置かず、ステンレスボトルを貸し出している
ホテルは、循環を生み出す拠点へ
ホテルの厨房からも、料理だけではなく様々な循環の物語が生まれている。ホテルの食器には洋食器メーカー・ニッコー社のボーンチャイナ(牛の骨を原料に含むお皿)が使われている。このボーンチャイナの原料に、植物の育成に欠かせない「リン」が含まれていることに着目したニッコー社は、廃棄予定の食器から作る肥料「ボナース」を開発した。
この肥料は同社の系列である琵琶湖ホテルが長年取り組む「山野草プロジェクト」の農園の畑で活用され、そこで育った野菜がホテルで提供されるという循環が始まっている。
櫻井さんは「まだビジネスとして確立するには至っていませんが、生育は明らかに違うと聞きます。ホテルの生業の中でこうした循環を生み出せるのは、非常に重要だと考えています」と、その手応えを語った。
次世代の声が映し出す、ホスピタリティの未来
しかし、こうした先進的なサステナビリティ実践が、常にゲストから歓迎されるとは限らない。特に大きな壁となったのが、やはりアメニティの問題だ。客室に歯ブラシなどを常備しないという決断により、一部のゲストから厳しい声を受けることもあった。それは、日本に根強く残る「アメニティ=おもてなし」という文化の象徴だったのかもしれない。
同ホテルは、クレームを寄せる一人ひとりに、自らのコンセプトを丁寧に粘り強く説明し続けた。そんな中、一つの象徴的な出来事が起こったという。
「現代の子どもたちは、学校教育でSDGsを学んでいるので、意識が非常に高いです。以前、アメニティの用意がなかったことにご意見をくださったお母様とお祖母様がいらっしゃったのですが、その横にいた小さなお子さんが『ママ、歯ブラシ持ってきてないの?私は持ってきたよ』と。その一言で場が収まったのです。まさに時代が変わってきている象徴だと感じました」
気候危機や生物多様性の喪失が未来の話ではなく実感できる現在進行形の問題へと変わりつつあるなか、ゲストの意識も確実に変化してきている。かつては「コスト」と捉えられがちだったサステナビリティが、今やゲストに選ばれ続けるための条件へと変わりつつあるのだ。
「サステナビリティの取り組みには確かにコストがかかります。お客様の意識の変化によりリネン交換を希望されない方が増えるなど、コスト削減につながる側面もありますが、プラスチック製品は安く品質も安定していますし、国産やローカル食材を使えば全体のコストは上がります。しかし、結局はサステナビリティなしにはお客様から『選ばれない』時代になってきています。本質的な取り組みを続けることが、ホテルの価値を高め、未来のお客様に選ばれ続けるために不可欠だと信じています」

Image via THE THOUSAND KYOTO
編集後記
サステナビリティとは、何かを我慢し続けることではない。本来は、他者や環境、そして未来の世代へと想像力を広げ、新たな「心地よさ」を発見し、循環させていく創造的な営みなのだ。THE THOUSAND KYOTOは、私たちが本当に目指すべき「心地よさ」とは何なのかを、様々な先進的実践を通じて教えてくれている。
また、千年先を見据えた事業のコンセプト、変革に向けた従業員の巻き込み方、様々な事業者との連携による循環型のプロダクトやサービス、体験の創出、サステナビリティとコストの考え方にいたるまで、事業者の視点でも同ホテルから学べる点は多い。
私たち人間も、結局は地球という「ホテル」を一時的に訪れているだけの「ゲスト」にすぎない。どうすれば、この美しい地球を次世代につなぎ、美しく去ることができるのか。そのヒントを掴みたい方は、ぜひ一度THE THOUSAND KYOTOを訪れてみてはいかがだろうか。
【2025年10月開始】Circular Business Design School Kyoto
京都には1200年の歴史の中で育まれた「しまつのこころ」や循環型の暮らし、モノづくり文化など、時代を超えて輝き続ける資産がある。気候変動や生物多様性の保全など地球規模の課題が深刻化する中で求められる循環型の未来を実現するには、これらの叡智を現代に活かし、未来につなぐ創造力が必要だ。そこで、IDEAS FOR GOODを運営するハーチ株式会社では、京都というまちに根付く循環型の叡智と最先端のサーキュラーエコノミー知見に基づく未来志向を掛け合わせることで、ともに欲しい未来を描き、実現するための学習プログラムを2025年10月より開始。「Decode Culture, Design Future 叡智をほどき、革新をしつらえる」──伝統の先に続く循環型の未来を、京都から。
ウェブサイト:https://cbdskyoto.jp/
【参照サイト】THE THOUSAND KYOTO
【関連記事】レストランのサステナビリティを支える。洋食器メーカー「ニッコー」が描く、循環する食器の未来
Photo by 佐々木明日華
Featured image via THE THOUSAND KYOTO