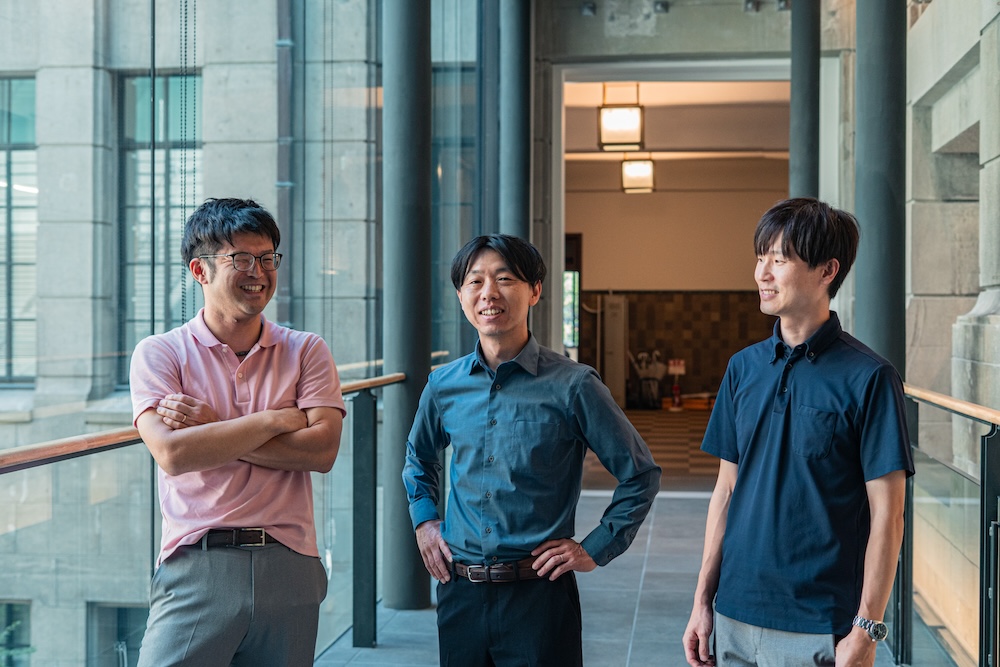【京都サーキュラーエコノミー特集】
本特集は、IDEAS FOR GOODと京都市の連携による、京都のサーキュラーエコノミーの今とこれからを考える特別企画。千年の都・京都に脈々と受け継がれてきた「しまつのこころ」の精神や循環型の暮らし、モノづくりの文化を、どのように未来の京都を形づくるイノベーションへと発展させ、次の1000年へ続く循環型の事業を創造できるのか。京都市、市内事業者、京都市政策推進アドバイザーの安居昭博氏とともに、サーキュラーエコノミーの視点から見た京都の価値と可能性を模索していく。(京都サーキュラーエコノミー特集トップ)
私たちが日常の中で手に取る、一枚のダンボール。商品を包むただの箱というイメージを持つかもしれない。しかし実は、資源循環という観点から見ると、ダンボールは回収率95%を誇り(※)、軽量なため輸送コストも低く、環境負荷が比較的小さい素材と言えるのだ。
京都で創業65年を迎えるダンボールメーカー・洛西紙工(らくさいしこう)株式会社は、高いリサイクル率を誇るこの素材を最大限に活用しようと、意外なアイデアも交えた新たな使い道を模索している。さらに、ダンボールという「手段」を用いて、短期利益だけにとらわれない長期視点での購買の文化醸成を目指すという。
そんな洛西紙工株式会社の取締役・小田智英さんに、事業の具体を聞くと共に、政府の経済戦略においても一目置かれる循環経済の実現に向けて、ダンボールが果たし得る役割について聞いた。
話者プロフィール:小田智英(おだ・ともひで)
 1991年栃木県生まれ。早稲田大学卒業後、TOTO株式会社で6年間営業職を務め、2020年洛西紙工株式会社に入社。ダンボールを使いながらも梱包資材にとどまらない新たな価値を創出し、教育や防災、環境など地域社会の課題解決に取り組んでいる。
1991年栃木県生まれ。早稲田大学卒業後、TOTO株式会社で6年間営業職を務め、2020年洛西紙工株式会社に入社。ダンボールを使いながらも梱包資材にとどまらない新たな価値を創出し、教育や防災、環境など地域社会の課題解決に取り組んでいる。
社会に価値を生む「手段」としてのダンボールとは
洛西紙工の事業の中心は、創業の1960年から現在まで変わらず、商品を梱包し、守り、運ぶためのダンボール箱の製造だ。しかし小田さんの視線は、箱そのものだけでなく、その先にある社会との繋がりへと注がれている。
「ダンボールの魅力は、多くの人にとって『身近な素材』であることです。そして、あまり知られていませんが、日本ではすでに95%以上の回収率を誇る、循環性能が高い素材でもあります。また加工がしやすく、箱以外の様々な形に変えられる点も特長です。
私は創業者ではなく、家業を継いだ立場で、もともとダンボールが作りたくてこの業界に入ったわけではありませんでした。だからこそ、単に利益を追求するだけでなく、私たちの強みであるダンボールを『手段』としてこの会社が社会にどのような価値を残せるのかを常に考えています。そう考えた時に、用途を梱包資材だけに限定してしまうのは非常にもったいないと感じたのです」


その想いは、具体的なアクションとなって結実してきた。例えば、製造工程で出るランダムな端材を集めた知育工作キット「SDKids」。これは、奈良県の株式会社高木包装との繋がりがきっかけとなり、その後、京都芸術大学の学生やマルシゲ紙器をはじめとする地域企業と連携したことで中身がさらに充実し、業界の枠を越えた取り組みとして形になったという。
環境負荷の低い素材だからこそ、社会のためにさらに活躍できる場はないか。その模索が、ダンボールの可能性を広げている。
価格競争から価値創造へのシフト
しかし、こうした社会的な価値は、従来のビジネスの物差しでは測りにくい。さらに、差別化の難しいダンボール業界は、1円でも安いものが選ばれる価格競争の激しい業界だ。その中で、洛西紙工はあえて社会的インパクトという新たな価値基準を掲げ、世の中に問いを投げかける。
「例えば、京都市の入札案件があったとします。仮に私たちの製品が競合より1円高かったとしても、私たちの製品を通じて、京都の子どもたちの未来を創る教育活動が支えられるという、数字には表れない価値があります。私たちの製品を買っていただくことが、間接的な社会貢献に繋がる。そうした関係性を、お客さんと共に作っていきたいと思っています」
短期的な経済合理性だけを重視するか、それとも長期的な社会価値も視野に入れるか。これは「どちらの未来に“投票”するか」という問いかけでもあるのだ。そんな長期的な視点は、長い歴史のなかで、関係性や企業の姿勢を重んじてきた京都の文化に既に根付いていると、小田さんは捉えている。
「僕は京都出身ではないですが、祖父母が京都にいて、お客さんの中には50年以上付き合いのある企業もあります。他の地域にもあるかもしれませんが、京都では特に、経済合理性だけでなく、持続可能性を考えて判断しているように感じます」
需要の高まりと、インパクト可視化の壁
このように、同社主体での開発や発信と同時に、ダンボールという素材に対する世の中の期待の高まりもすでに感じているという。
「最近は多くのお問い合わせをいただきます。用途も使う人も様々で、『展示会の什器を作りたい』『イベントで使う机や椅子がほしい』といったご相談が多いですね。特に展示会で数日しか使わないブースは、木工で作るとコストがかかり、イベント後の廃棄も大きな問題になります。
その点、ダンボールは軽くて輸送効率も良く、使用後はリサイクルできます。最近のサステナビリティへの関心の高まりもあってか、こうしたニーズは増えていると感じます」

一方で、用途が広がっているからこその課題にも直面している。
「いま一番の課題は、ダンボールを選ぶ理由を明確に伝えきれていない点です。たとえばダンボール什器の競合は、木工など他の素材業界。軽い・丈夫・安いといった短期的なメリットだけでなく、材料の調達から製造・輸送、廃棄までのサプライチェーン全体で見たときに、社会にとってどれだけの影響があるのか。その価値を数値で示したいのですが、中小企業が製造プロセスの中で一つひとつの工程におけるインパクトを算出するのは非常に難しく、まだ道半ばです。
環境に良いという情緒的な価値だけでなく、経済合理性とのバランスを取りながら価値を『見える化』することが、現在の大きな課題です」
購買は未来への意思表示
私たちの社会は、日々の何気ない購買行動によって成り立っている。ただ、「買い物は投票だ」と分かっていても、環境負荷について知識があっても、毎日、価格だけでなく手放す時のことまで想像して買い物するのは難しい。
「プラスチック製の安価な製品を買うとき、それを将来廃棄するコストや環境負荷まで想像する人はまだ少ないかもしれません。だからこそ、製品を選ぶときに、どのような循環を生み、誰の将来に繋がっているのかという背景を伝え、コストや環境負荷も見える化していくことが、私たち企業に必要な努力だと思っています」
作る側が変わるべきか、買う側が選ぶべきか──その議論の前で立ち止まることなく、洛西紙工は、まず自らが「手触り感のある循環のストーリー」の語り部となることを選んだのだ。
「消費者が通販で受け取ったダンボール箱が、形を変えて自分の子どものための製品として手元に戻ってくる。そんな国内での資源循環のストーリーをもっと感じられるようになれば、手放すときのことまで考えてものを選ぶ意識が自然に育っていくのではないかと思います」

編集後記
洛西紙工の挑戦を紐解いていくと、その根底に「学びを共にする」というテーマが見えてくる。それは前述の端材を使った知育キットや、自社のインパクトを「見える化」する姿勢に加えて、地域の高校生との連携プロジェクトにも共通している。学生が考案したダンボール製品のアイデアを製品化し、その利益を高校生・学校・企業の三者で分配することで、実感ある商品作りの機会を生み出しているのだ。
ダンボールを単なる「商材」として捉えるのではなく、ダンボールを「媒介」として誰とどんな学びを生むことができるかを考える。そんな広い視野を持ちながら、同社は循環経済に向けて、着実で、長期的で、常に地域に根ざした一歩を踏み出す。経済合理性だけではない京都の文化基盤が、現代社会に新しい豊かさのヒントを与えてくれるようだ。
【2025年10月開始】Circular Business Design School Kyoto
京都には1200年の歴史の中で育まれた「しまつのこころ」や循環型の暮らし、モノづくり文化など、時代を超えて輝き続ける資産がある。気候変動や生物多様性の保全など地球規模の課題が深刻化する中で求められる循環型の未来を実現するには、これらの叡智を現代に活かし、未来につなぐ創造力が必要だ。そこで、IDEAS FOR GOODを運営するハーチ株式会社では、京都というまちに根付く循環型の叡智と最先端のサーキュラーエコノミー知見に基づく未来志向を掛け合わせることで、ともに欲しい未来を描き、実現するための学習プログラムを2025年10月より開始。「Decode Culture, Design Future 叡智をほどき、革新をしつらえる」──伝統の先に続く循環型の未来を、京都から。
ウェブサイト:https://cbdskyoto.jp/
【参照サイト】洛西紙工株式会社
【参照サイト】ダンボール端材を利用した知育キット 「SDKids 京都版」の販売開始(2023年9月)
Photo by 佐々木明日華
Edited by Natsuki