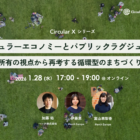大阪・関西万博で特別人気を博したイタリアパビリオン(以下、イタリア館)を、縦横無尽に歩き回っていたロボット。画面には、それを操縦するこどもの姿が写っている。

これは、入院・自宅療養中でなかなか遠出が叶わないこどもたちが、AIアバターロボットを使って万博のパビリオン内をめぐり、世界中からの来場者とリアルタイムに交流できる試み。その名も「どこでも万博」だ。名前の通り、全国の自宅・病院から来場でき、こどもたちがスマートフォンやタブレットでロボットの操縦をすることでイタリア館を自由に歩き回る体験ができるものである。
「どこでも万博」は、これまで大阪市総合医療センター、イタリアの小児病院など病院の福祉施設15団体との協業を経て、累計4,105名に万博の体験を届けてきた。2025年8月に発表された万博初の国際賞「万博イノベーション・アワード」では、ソーシャル・イノベーション部門で受賞。高い革新性に加え、イタリアとの文化交流発展へのポテンシャルが高く評価された結果だった。
この取り組みはどのように始まり、なぜ多くの人に愛されることとなったのか。「どこでも万博」の総合プロデューサー、戸田愛さんに話を聞いた。
話者プロフィール:戸田愛(とだ・あい)
 「旅を通じて人と学びをつなぐ」旅行会社とことこあーす株式会社 代表取締役。大手旅行会社で添乗員を経て、1,000組以上のオーダーメイド旅行をプロデュース。世界30カ国150人の海外在住日本人と連携し、“お友達を訪ねるように”世界と出会う交流共創型ガイドサービスを展開。家族5人での世界一周経験をもとに、大阪・関西万博『どこでも万博』総合プロデューサーを務め、親子留学「EARTH留学」を開発し、“学びの旅”を創り出している。
「旅を通じて人と学びをつなぐ」旅行会社とことこあーす株式会社 代表取締役。大手旅行会社で添乗員を経て、1,000組以上のオーダーメイド旅行をプロデュース。世界30カ国150人の海外在住日本人と連携し、“お友達を訪ねるように”世界と出会う交流共創型ガイドサービスを展開。家族5人での世界一周経験をもとに、大阪・関西万博『どこでも万博』総合プロデューサーを務め、親子留学「EARTH留学」を開発し、“学びの旅”を創り出している。
旅に出たくても出られないこどもの「できない」を解消するには
普段は、旅行会社「とことこあーす」を営み、病気や障害のある人々の旅をサポートするNPO法人「リスタート・トラベル」の代表理事でもある戸田さん。
彼女が「どこでも万博」の総合プロデューサーを務めることになった背景には、長男の陽輝(はるき)さんがダウン症の「スペシャルキッズ」として生まれたことや、それでも旅を通してこどもの可能性を広げたいという思いで「とことこあーす」を立ち上げてきた経験があった。
2018年、小学2年生だった長女の「家族で世界一周したいな」というつぶやきがきっかけで、家族5人での世界旅行を実現。8か月間で21か国を巡った。制限のある状態でも旅行に行った陽輝さんは、言葉や文化の壁を越えて多くの人と出会い、自分の気持ちを伝える力を身につけていったという(※1)。

戸田さんと、息子の陽輝さん。イースター島にて
「どこでも万博」の企画は、そんな経験のある戸田さんが、大阪市立総合医療センターの小児脳神経内科医である岡崎伸さんに出会ったことで始まった。
「岡崎先生は、病気や障害などのあるスペシャルキッズを持つ親御さんが、色々な場面で旅に出ることを諦めているのを認識していました。そんなときに、ダウン症のこどもを連れて世界一周した面白い人がいるぞ、という噂を聞きつけてくださって(笑)。意気投合したのが6年前でした。
私自身、長男が生まれたときは、もう旅に行けるのが当たり前ではないと思い、さまざまなことを諦めた経験がありました。だからこそ、今回の万博に行くのを最初から諦めている人にも、新しい人や価値観に出会える体験を届けられたら、とイメージが湧いたんです」
しかし、自社だけではこどもたちに万博での体験を届けることはできない。そこで、ヘルスケアテックの知見や、ロボティクス技術を持つ5社で提携した「スペシャルキッズ未来構想チャレンジコンソーシアム」を結成。共同で「旅に出たくても出られないこども」の課題に挑むことにした。
「イタリア館との連携については、とあるイベントで政府代表の方とお話しする機会があったとき、『こどもたちにこんな体験をしてもらいたい!』と、飛び込み営業をしたような形でした。完全に初対面だったのですが、その場で『感動した、一緒にやろう』と言ってもらえたんです」
イタリア館を闊歩するロボット、temi
戸田さんはその後、「どこでも万博」総合プロデューサーに就任し、演出プログラムの企画開発、ユーザー体験のサポート、パビリオンとの連携調整など、多岐にわたる役割を担うこととなった。
イタリア館内には、こどもの目線くらいの高さのロボットtemi(テミ)を配置。こどもたちは病室からtemiを遠隔操作し、館内を冒険しながら古代ローマ時代の彫刻や絵画などを鑑賞したという。また、音声通話を通してイタリア館を訪れる人々と交流できる仕掛けづくりも行われた。

「万博では、来場者同士で交流することはあまり無かったのですが、このロボットがいたことで、パビリオンを見に来ていた人たちが興味を持って画面を覗き込んでくれたり、手を振ってくれたり、こどもたちに『どこから来たの?』と話しかけてくれたりしたんです」
小児医療のプロである岡崎さんのつながりからさまざまな医療機関での体験を実施し、支援学校や自治体など合計44回の体験を提供。メディアにも数多く取り上げられ、ラジオCMの収録にも、特発性後天性全身性無汗症や肢体障害などを抱えるこどもたちに協力してもらい取り組んだ(※2)。
「こどもたち自身も、この体験を通して『もっと自分もこんなことがしたい』と先々の目標を立て、それを楽しみにできるようになっていました。親御さんから『これまで無理だと思っていたから挑戦もちゃんとさせてこられなかったけれど、うちの子はこんなに(意欲的に計画を立てたり挑戦したり)できるんですね』という声をいただき、本当に良かったと思っています」

これからも、ワクワクする体験のために
一方、今後も取り組みを広げるにあたっては、スペシャルキッズを持つこどもの親、という当事者以外の人々にも、もう一歩踏み込んで関わってもらいたいという。そのためにも「その人が、自分ごとにできるポイントを見つけたい」と語る戸田さん。
「イタリアの人々と接するなかで、彼らが(当事者であるかどうかにかかわらず)未来のために良いことを応援しよう、という姿勢だったことが印象的でした。今回の『万博イノベーション・アワード』受賞をきっかけにまた取り組みが広がり、病気や障害など特別なニーズのある家族だけでなく、たとえば施設に入っている高齢者の方や、何かの事情があって遠出ができない方々が楽しめるものになったり、安全だと思える範囲が広がったりする体験を届けられたらと思っています」

戸田さんらが今回のプロジェクトで得たノウハウや連携の資産は、万博終了後もスぺシャルキッズたちの未来の体験のために活用されていく予定だという。今回の取り組みは、複数社の知見とテクノロジーが共感によってつながった、社会包摂のモデルケースと言えるだろう。
※1 どこでも万博にかける想い─とことこあーす 戸田さんのメッセージ
※2 ラジオCM制作の裏側─どこでも万博 note
【参照サイト】どこでも万博