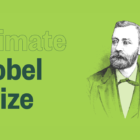2024年のパリパラリンピックでは、車いすテニスの小田凱人選手や上地結衣選手が金メダルを獲得し、障害者スポーツへの注目が高まっている。しかし、実際のスポーツ参加率を見ると、一般の人々と障害者の間には依然として大きな差がある。
2024年度のスポーツ庁の調査によると、20歳以上で障害のある人のうち、週1日以上スポーツを実施する人の割合は32.8%だ。2013年の18.2%からは大幅に増加したが、同年の全国平均(約52.5%)とは依然とし約20ポイントの差がある(※1, 2)。この背景にあるのは、健康上の理由だけではなく、運動する場所や機会の不足、家族や介助者の負担、経済的な負担などの要因だ。
さらに、あまり広く知られていないのは精神的な障害のある人々も、身体的な理由からスポーツに参加しにくい現状があること。例えばダウン症のある人は、足の甲の幅が広い、指の間が離れているなど、足の形に特徴があることが多く、市販の靴では合わない場合がある。実際に、既製品の靴でマラソンに参加し、水ぶくれを起こすこともある。「履ける靴がない」ことが、スポーツ参加の障壁となっているのだ。
こうした中、スポーツメーカーのアディダスが実施している「アディダス321」プロジェクトが注目されている。ダウン症のある人にとって使いやすいスポーツシューズの開発をしているのだ。
View this post on Instagram
プロトタイプの開発には、ダウン症アスリート、クリス・ニキッチ選手らが参加。ニキッチ選手は、ダウン症のある人として初めてトライアスロン競技「アイアンマン」を完走した実績を持つ。開発されたシューズは2026年の発売が予定されており、同年のキャンペーンではニキッチ選手がイメージモデルとして起用される予定だ。
「アディダス321」では、シューズ開発以外にも、ダウン症のあるアスリートの社会的認知を高める取り組みも行っている。2023年には、世界有数のマラソン大会であるボストンマラソンと連携し、ダウン症のあるランナーのために「321番」のゼッケンを確保した。この番号は、21番目の染色体が3本あることに由来し、ダウン症を象徴する数字である。
今回アディダスは、日常生活では気づきにくい障壁を可視化・啓発するだけではなく、特定のニーズに真摯に向き合い製品開発にも踏み込んだ。誰もがスポーツを楽むことができるために、具体的な変化を生み始めたと言えるだろう。
一人ひとりが抱える課題は決して単純ではない。だからこそ、こうして現実の声に耳を傾けた商品づくりが社会の障壁を取り払うための力強い一歩になるはずだ。
※1 令和6年度「障害児・者のスポーツライフに関する調査」
※2 スポーツ実施率:スポーツ庁
【参照サイト】Adidas Runner 321
【関連記事】広がる活躍の場。ダウン症のある人々が“自分らしく”働く事例3選【世界ダウン症の日】
【関連記事】脳の多様性から生まれる、唯一無二のデザイン。バルセロナ発のクリエイティブ組織「La Casa de Carlota」