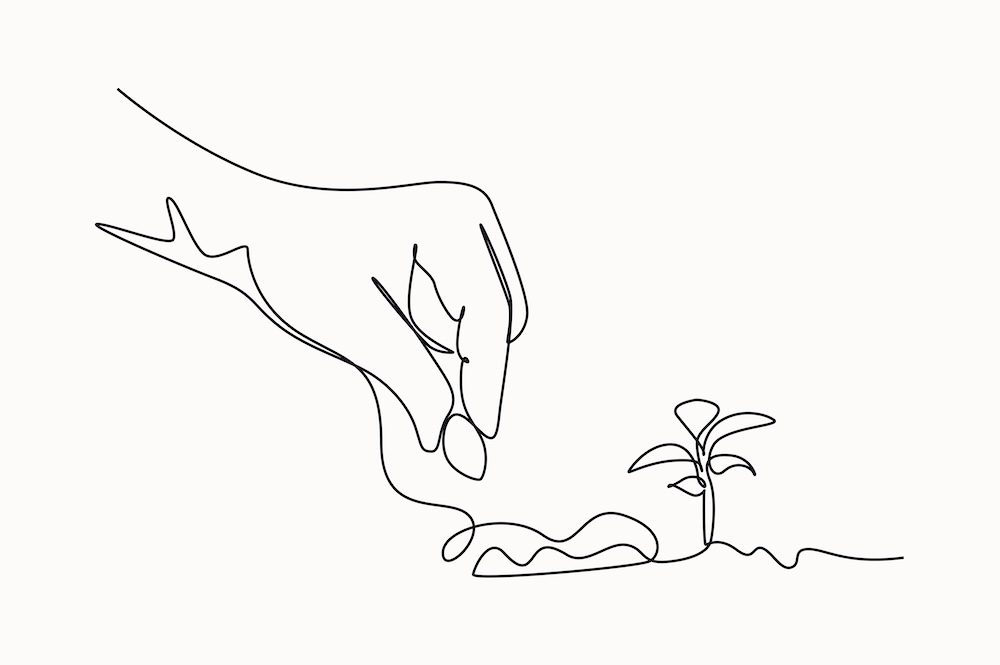言論の自由

Photo by Patrick Fore on Unsplash
言論の自由とは
言論の自由(Freedom of Speech)とは、個人が自らの意見を自由に表現し、他者と共有することのできる権利のこと。「報道の自由」や芸術表現、さらには政治的な抗議や批判も含まれる広義の「表現の自由」の一部です。
私たちは、自分の考えを述べたり、他者の意見を聞いたりすることで社会に参加し、社会を形作っています。民主主義の社会が健全に運営されるためには、意見の異なる人々が対話し、議論し、妥協し合いながら意思決定に関与する必要があります。
誰でも自由に、(特に人と違うような)自分の考えを発信できるということは、そうした民主主義の根幹を支える柱でもあります。自分の暮らしや社会の課題に関心を持ち、情報を得て、それに基づいて判断を下すには、自由に言論できる空間が不可欠なのです。
国際的には、言論の自由は世界人権宣言第19条などに明記されており、多くの国の憲法でもその価値が保障されています。
「すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む」
出典:国連広報センター「世界人権宣言テキスト」
日本においては、憲法第21条で「表現の自由」が保障されています。
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」
出典:日本国憲法
ただし、すべての言論が無制限に許されるわけではありません。差別や暴力を扇動する発言、あるいはヘイトスピーチのように他者の権利を著しく侵害する言動については、国際法の下でも一定の制限が認められています。ただし、こうした「表現の自由」の制限は、法律に基づき、かつ必要最小限であることが求められています。時の権力者の都合によって恣意的に運用されることがないよう、私たちは常に注意を払う必要があります。
また、現実には、言論の自由が保障されていない国や地域、団体も見られます。反体制的な発言を行った市民やジャーナリストが投獄されたり、永住権を剥奪されたり、あるいは命を奪われたりするケースもあります。「国家安全保障」「宗教」「テロ対策」などを名目に、言論を封じ込める法整備を進めている国も少なくありません。
目次
言論の自由の制限は何が問題なのか(Issue)
言論の自由の制限は、民主主義の根幹を揺るがします。民主主義は、異なる意見の対話や議論を通じて合意を目指す制度であり、その前提として表現の自由が不可欠です。ところが、最終的に多数決で決定するという仕組みが都合よく利用され、本来重視されるべき「議論を通じて合意を目指す」というプロセスが無視されることがあります。合意のプロセスを経ずに多数決が乱用され、少数意見が排除されるという事態が、「民主主義」の名のもとに生じるのです。そうした状況は、反対意見や批判の声を封じ込め、少数者の表現を圧殺する構造を生み出します。
このようにして、民主主義が自らの手で表現の自由を抑圧することは、制度そのものの自己否定に他なりません。だからこそ、健全な民主主義を支えるのは、自分と異なる意見の自由を守ろうとする姿勢です。
表現の自由が制限される社会では、都合の悪い事実が「フェイク」とされ、議論を封じる権力者が台頭しやすくなります。こうした状況は、討議やエビデンス、ロジックを軽視し、迅速かつ表面的な「決定」を重視する風潮と結びつき、民主主義の本質を形骸化させる危険性を孕んでいます。つまり、形式的には選挙が行われ、議会が存在していても、実際には自由な議論や意見交換が行われず、権力者の思惑通りに決定がなされる状態を生み出すリスクが高まるのです。
言論の自由にまつわる現状(Current Situation)
法律によって言論・表現の自由が保障されているとはいえ、実際にその自由が健全に機能しているかどうかは別問題です。日本においても、海外においても、言論の自由が適切に守られていない事例や、言論の自由が悪用されるケースが見られます。
誹謗中傷の事例
特定の発言に対して、賛成の声だけではなく批判的な反応が返ってくること自体は、自由な言論空間において自然な現象です。しかし、発言の結果として命を狙われたり、脅迫を受けることは、言論の自由が健全に保障されている状態とは言えません。
たとえば、日本では最近、生理用品の無料配布を推進する動きが始まっていますが、公共のトイレに生理用品を置いてほしいと、X(旧ツイッター)で発信した議員に対して、約8,000件にも及ぶ殺害予告や2,000件以上の誹謗中傷が寄せられました。スコットランドをはじめ、すでに公共施設での生理用品の無償提供が一般的になっている地域もあるなかで、日本でも社会的認知が進みつつある中で起きた出来事でした。このように、単に生活の困難を軽減しようとする建設的な提案に対して、攻撃や暴力的な反応が返ってくる状況は、言論の自由が健全に機能している状況とは言えません。
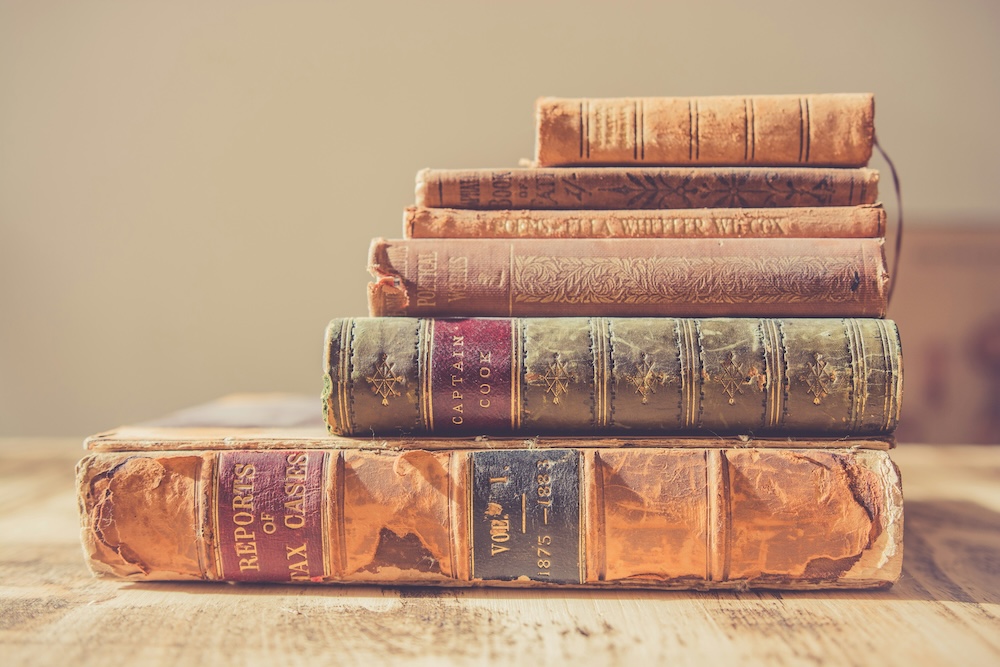
Photo by Chris Lawton on Unsplash
ここでしばしば持ち出されるのが、「誹謗中傷も言論の自由の一部だ」という議論です。しかし、この考え方には見過ごせない問題点が含まれています。この議論に関連して、「寛容のパラドックス」という概念があります。これは、「多様性」や特定の価値観を支持しようとするとき、すべての意見に無条件に寛容でなければならない、という矛盾に陥るリスクを指しています。つまり、ある価値観に対して寛容になろうとすることが、逆にそれに反する暴力的・破壊的な意見に対しても寛容にならなければならない、という無限のループに陥ることがあります。
誹謗中傷や暴力的な脅迫が「言論の自由」として無条件に許容されるのであれば、本来守るべきだった穏やかで平和的な意見表明やマイノリティの声が、かえって沈黙させられることになりかねません。
ガザ紛争に関わる言論の自由の現状
ガザ紛争における表現の自由の制限は、国際社会において深刻な問題として議論されています。国連人権理事会が2024年に公表した報告書によれば、ガザ地域ではジャーナリストの殺害や報道機関の破壊、国際メディアへのアクセス制限などが発生しており、表現の自由が著しく損なわれていると指摘されています。これにより、ガザにおける状況を世界に伝えることが困難になり、国際社会に向けた情報発信というメディアの役割が制約を受けていると報告されています。
また、デモや抗議活動に対する規制も強まっており、ヨーロッパや米国では特定の国を支持するデモやシンボルの禁止措置が取られる事例が報告されています。国連人権理事会の報告書を作成したカーン氏は、こうした一律的な禁止措置について、必要性、均衡性、非差別の原則を満たしておらず、国際人権基準に照らして正当化できないと指摘しています。さらに、メディア、学界、芸術界においても、ガザ紛争に関連する意見の発表が難しくなっており、知的自由や表現活動への圧力が高まっている状況が報告されています。
米国現政権と大学の対立
米国現政権下(2025年)において、大学が政権方針に従わなかった場合に、連邦政府からの資金提供停止や税制優遇措置の見直しが示唆される事例が報告されています。
資金提供の凍結により影響を受ける可能性がある研究には、がんの全身転移の分子メカニズムに関する研究、感染症の蔓延予測、多発性硬化症やアルツハイマー病、パーキンソン病のリスク軽減を目指す研究などが含まれています。
2023年10月以降のガザ紛争を背景に、米国国内では大学キャンパスでのデモや、ガザ紛争に関連する政府批判が活発化しました。これに対し、現政権は「ユダヤ人学生の権利保護」を理由に、大学に対する対応を進めました。
ハーバード大学に送付された政府の書簡には、公式には「反ユダヤ主義への対応の不備」を是正するためとされていますが、特定の学生や教職員の発言抑制、研究内容や採用方針、教育内容への介入、政府に批判的な学生の活動制限に関する要請が含まれています。
具体的には、以下のような要求が含まれています。
- 「学生と任期なし教員の持つ権力を縮小」し、「終身在職権を持つ教授陣および大学の上級指導層に権限を与え、さらにとりわけ、大学の学術的使命に最も献身し、この書簡に示された改革(現政権が求める改革)に忠実に従う者のみを選出すること」
- 2025年8月までに、「米国憲法と独立宣言に刻まれた米国の価値観に反対する学生を入学させないよう、留学生の募集・審査・入学許可を改革すること」
このような対応は、大学における学問の自由や自治に影響を及ぼし、学術研究や教育活動の独立性を損なう可能性があると指摘されています。いうまでもなく反ユダヤ主義は断固として非難されるべきものであり、ハーバード大学学長でありユダヤ人でもあるアラン・ガーバー氏も、政府からの書簡に対する声明の中で「反ユダヤ主義の高まりに正当な懸念があることは十分に認識しています。反ユダヤ主義に効果的に対処するには、理解、意図、警戒が必要です。ハーバード大学は、そのような取り組みに真剣に取り組んでいます」と表明しました。そのうえで、大学は政府からの要請に一律には従わない方針を示しました。
現在、紛争に関する意見表明や特定の政府批判が「反ユダヤ的」と解釈され、処罰や規制の対象となるケースが増加していると報告されています。この状況については、反ヘイト対策の枠組みを超え、言論の自由や学問の自由が政治的に利用されているとの指摘もあります。このような事態は、民主主義国家としての基本原則に関わる重要な問題であるとして議論がなされています。
この対立は、「反ヘイト対策」と「言論の自由」の境界線が曖昧になり得ることを示唆しており、政治的意向が学問や思想の自由に影響を及ぼす可能性が指摘されています。

Photo by Pascal Bernardon on Unsplash
言論の自由に関する議論(Controversy)
言論の自由は、民主的社会の基盤であり、個人の基本的権利として保障されるべきものです。しかし現実には、政府に批判的な発言が「ヘイトスピーチ」などと位置付けられ、恣意的に抑圧される危険性もあります。国連の人権専門家は、暴力的過激主義への対策が、しばしば表現の自由を制限する口実として利用される事例に懸念を示しています。
特に、ジャーナリスト、政治的反体制派、活動家、人権擁護者らが、「過激派」や「テロリスト」として時の政権によって分類され、不明確な法的根拠に基づき拘束される事例が報告されています。こうした動きは、表現の自由に影響を及ぼすだけでなく、公共の利益に資する情報へのアクセスを制限する結果にもつながると指摘されています。
国際社会においては、ヘイトスピーチへの対応として一定の言論規制を支持する立場が存在します。この立場は、世界人権宣言や自由権規約に基づき、表現の自由も無制限ではなく、他者の権利や自由を侵害する活動に対しては制限が認められる、という原則に根ざしています。
すべての言論が無制限に許容されるわけではなく、差別や暴力を扇動する発言、あるいは重大な人権侵害をもたらすヘイトスピーチについては、厳しく対処されるべきだと広く認識されています。
一方で、こうした規制は、あくまで法律に基づき、かつ必要最小限にとどめられなければならないとされています。なぜなら、「ヘイトスピーチの規制」や「法的救済措置」が本来の目的を逸脱し、正当な政府批判や建設的な意見までを、政治的目的で抑圧する手段として利用されるリスクがあるためです。つまり、発言が恣意的かつ短絡的に「犯罪」と見なされ、統制や投獄へとつながる可能性が懸念されているということです。
たとえば、平和を訴える主張や戦争反対の意見が「政府批判」や「敵対国への加担」と歪められ、処罰の対象とされることや、特定のマイノリティを擁護する建設的な発言が、「別の集団に対する差別」と解釈され、制裁の対象となる事態も起こり得ます。
ヘイトや差別に対抗するためには、表現の自由を安易に制限するのではなく、市民教育や啓発活動を通じて寛容と多様性の尊重を促進することが大切です。言論の自由が脅迫や報復によって萎縮しない社会を実現するために、その価値と意義を守る努力が求められています。

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash
言論の自由を守るためにできること(What we can do)
言論の自由を本質的に守るためには、反対意見にも耳を傾ける寛容さと、他者の基本的人権を脅かすような言動には毅然と対応する厳しさ、その両方が求められます。このバランスを取ることは容易ではありませんが、だからこそ、不断の議論と熟慮を通じて、より健全で開かれた言論空間を築いていくことが、社会の一員としての私たちの責任です。
そのために、私たち一人ひとりが情報を見極める力を高めることが不可欠です。近年、自分にとって不都合なニュースや意見を「フェイク」と決めつけたり、すぐに白黒をつけて「キャンセル」して排除する傾向が強まっています。しかし、あらゆる物事が単純に白黒で割り切れるわけではありません。
日々膨大な情報が流れる中で、それらを無批判に受け入れたり、短絡的に理解しようとする傾向があります。こうした姿勢は、問題の複雑なニュアンスを軽視し、性急な判断や他者の意見に耳を貸さない姿勢を助長し、さらには差別につながる危険をはらんでいます。さらに、自分の考えに合う情報だけを信じ、異なる意見を排除するようになれば、知的謙虚さ(Intellectual Humility)や論理的・批判的思考力は次第に失われていきます。その結果、感情的な言説に流されやすくなり、ポピュリスト的な政治家が支持を集め、市民ではなく彼ら自身に都合の良い政策が推し進められる危険性が高まります。
こうした状況が進行すれば、やがて市民の声そのものが「都合が悪い」として権力によって封じ込められる危険性もあります。だからこそ、私たちは自らの判断力を鍛え、選挙においても誰が良識ある候補者なのかを冷静に見極めることが重要です。
本物の民主主義は、誰もが自由に意見を述べられる環境によって支えられています。しかし、もし意見表明が脅迫や誹謗中傷、あるいは暴力によって封じられるなら、それはもはや民主主義とは言えません。もっとも、差別や暴力の扇動、ヘイトスピーチは「自由な意見」とは言えず、明確に非難されるべき行為です。「言論の自由」を盾にして差別的・排他的な言説を広めたり、特定の集団をスケープゴートにしたりすることは、結果的に自らが将来排除される社会を支持することにつながります。
しかしながら、こうした表現をどのように規制すべきかについては、慎重な議論が求められます。なぜなら、規制が過剰になれば、まっとうで建設的な意見すら、時の権力によって恣意的に封じられる危険性があるからです。
だからこそ、言論・表現の自由とその規制との間にある複雑なバランスについて、私たち市民一人ひとりが社会の一員として絶えず議論を重ね、考え続けることが不可欠なのです。
言論の自由に関するアイデア(IDEAS FOR GOOD)
IDEAS FOR GOODでは、最先端のテクノロジーやユニークなアイデアで言論の自由の課題に取り組む企業やプロジェクトを紹介しています。
言論の自由に関連する記事の一覧
【参照サイト】総務省「『言論の自由を守る砦』に関する国民の権利と議論すべき論点」
【参照サイト】国際連合広報センター「ヘイトスピーチを理解する:ヘイトスピーチ VS 言論の自由」
【参照サイト】United Nations. ‘UN expert warns combat against violent extremism could be used as “excuse” to curb free speech’.
【参照サイト】東京新聞「『トイレにナプキンを』と訴えただけで殺害予告8000件 杉田水脈氏からも攻撃…生理のつらさが共感されない恐怖」
【参照サイト】金子匡良「『表現の自由』って何だろう?」『国際人権ひろば』 No. 148 (2019).
【参照サイト】法務省「ヘイトスピーチに関する裁判例」
【参照サイト】United Nations. ‘The Rabat Plan of Action’.
【参照サイト】日本国憲法
【参照サイト】United Nations. ‘Freedom of expression also under fire in Gaza war, rights expert says’.
【参照サイト】New York Times. ‘Trump Threatens Harvard’s Tax Status, Escalating Billion-Dollar Pressure Campaign’.
【参照サイト】New York Times. ‘What Harvard Has Set the Stage For’.
【参照サイト】‘Protesters Chain Themselves to Columbia Gates, Calling for Activists’ Release’.
【参照サイト】Amnesty International. ‘Freedom of Expression’.
【参照サイト】Harvard University. ‘Upholding Our Values, Defending Our University’.
【参照サイト】国連広報センター「世界人権宣言テキスト」
【参照サイト】BBC「アメリカのユダヤ人とパレスチナ人、どちらも恐怖と憎悪に直面」
【参照サイト】Letter Sent to Harvard
【関連記事】「報道の自由度ランキング」日本の順位、評価基準は?守るためにできることまで、徹底解説