
駐車スペースを“近所のオアシス”に。ウィーンで広がる住民主体の小さな公園づくり
街を自分の手で自由に変えて良いと言われたら、何を作りたいですか?オーストリアのウィーンでは、市民自らの手で駐車スペースを「小さな公園」に帰るプロジェクトが広がっています。

【10/16開催】気候危機時代の“しなやかな”デザイン思考。実社会の課題解決に、Design Beyond Humansを(Climate Creative Cafe 20)
クリエイティビティで気候危機に立ち向かうプロジェクト・Climate Creative。今回は「気候危機時代の新しいデザイン思考」“をテーマに、Design Beyond Humansについて考えます。

「女性の休日」が社会を動かす。“ジェンダー先進国“アイスランドの運動を描く映画が公開
ジェンダー平等先進国として広く知られる北欧のアイスランド。その原動力となった女性同士の連帯による歴史的なムーブメント「女性の休日」を追ったドキュメンタリー映画が、10月25日に全国で公開されます。

【10/9開催】Sustainable Media Futures 〜AI時代の新しい持続可能なメディアの形をプロトタイプするフューチャーセッション〜
AIという「巨大メディア」の登場でメディア環境は激変。効率化の一方で環境負荷や偏見再生産など課題も浮上するなか、フューチャーセッションを通じてAI時代の持続可能なメディアの形を探るイベントを開催します。

ニッチな領域で環境に貢献する。バイオマス樹脂で塗料を作る中国塗料
私たちの生活に必要なものを運ぶ船舶。その船舶の塗料に三井化学のバイオマス樹脂を採用した、中国塗料株式会社の取り組みや企業哲学を取材しました。

「ジェンダーボンド」市場が5年で5倍超に急成長。アイスランドやJICAも発行
「金融」でジェンダー平等を。女性を支える「ジェンダーボンド」市場が5年で5倍超に急拡大しました。アイスランドの国家発行や日本のJICAの取り組みも。お金が社会を良くする力になる、その壮大な可能性とは?
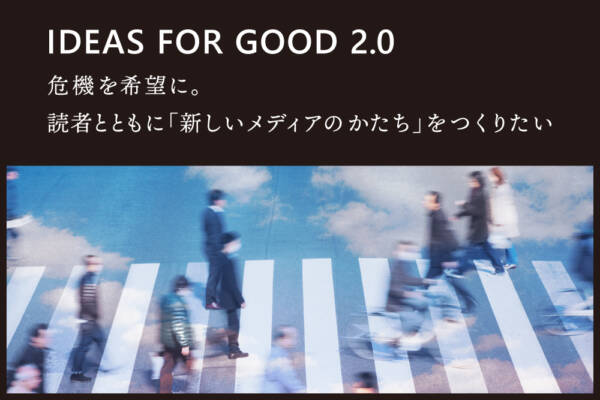
【クラファン開始】IDEAS FOR GOOD 2.0 危機を希望に。読者とともにつくる「新しいメディアのかたち」
IDEAS FOR GOODは創刊10周年を前に、クラウドファンディングに挑戦します。AI時代に直面する経済的・社会的な危機を「希望」に変え、読者とともに新しいメディアのかたちを編み直す試みです。

育休中の社員にも、同僚にも手当を支給?グッドニュース5選【2025年9月後半】
日々飛び交う悲しいニュースや、不安になる情報、ネガティブな感情を生む議論に疲れたあなたに。心が少し明るくなる世界のグッドニュースを5つピックアップしてお届けします!【育休中の社員と同僚に手当支給?】

里山に息づく絹産業の美しさと希望。ドキュメンタリー『森を織る。』
桑の葉を食む蚕、糸を紡ぐ手、里山の暮らし……映画『森を織る。』は、絹と人、自然が織りなす「つながり」を映し出します。失われゆく産業の中に見えた、美しさと希望とは?

ニュージーランド政府「人口が10万倍になった」と発表?嘘のようで本当の人口が示す、命の危機
2025年9月、ニュージーランド政府は「人口が10万倍になった」と発表しました。一体どんな計算ミスがあったのかと思いきや、これは生物多様性の危機をユーモアと共に、けれども真摯に伝える作戦だったのです。

給料をもらいながら学ぶ「修理の学校」フランスに開校。VEJAが挑む、環境と社会の同時修復
「一足の靴を直すことは、社会を修復することにつながる」失業と貧困に苦しむ街ルーベで、VEJAが立ち上げた“修理の学校”。給料を得ながら学べる新しい教育モデルとは?

環境・社会・経済、すべてを再生へ。「リジェネラティブ」を定義するガイダンスをコーヒー業界が公表
近年浸透している、リジェネラティブという言葉。しかし、何が・どのように再生されたら、リジェネラティブと言えるのでしょうか?コーヒー業界は、この言葉を共通言語として用いるためのガイダンスを公表しました。

暑すぎた夏から「適応」を考える。脱炭素だけでは、未来の地球に住めないとしたら?
異常な暑さだった今年の夏。もしこれが「日常」となってしまうとしたら、私たちは今の行動だけで十分なのでしょうか。今こそ考えたい気候変動の「適応策」を具体例と共に捉えます。

IDEAS FOR GOOD制作ドキュメンタリー『リペアカフェ』、9月27日大阪・関西万博で上映
IDEAS FOR GOOD制作のドキュメンタリー映画『The Repair Cafe(リペアカフェ)』が、2025年9月27日、大阪・関西万博「サーキュラーエコノミー研究所」で上映されます。

AIと人間の“あいだ”にある可能性。二項対立を超えて
排除か依存か。その二択を超えて、人間とAIはどう共生できるのか。「契約的共同創造(covenantal co-creation)」という新しい視点から、両者の“あいだ”に芽生える知性と創造性を探ります。

BBC・脱成長ドキュメンタリー制作者が語る、社会変革の兆し。「成長しない豊かさ」を議論する糸口は?
2025年7月にBBCが公開し、13万回再生されたドキュメンタリー「Could ‘degrowth’ save the world?:脱成長は世界を救えるか」。その制作者に撮影のきっかけや想い、上映会を通じて気づいたことを聞いてみると、意外と気づいていない社会の可能性が見えてきました。
