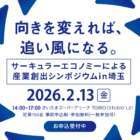ノルウェーの首都オスロは、気候変動対策や持続可能な都市開発において国際的な評価を受けている環境先進都市である。自転車インフラの整備、EV推進政策、炭素排出量の削減など、数々の取り組みが注目を集めてきた。
その中心地からフェリーで南へ約20分。船は静かなフィヨルドを進み、都市の輪郭が遠ざかるにつれて、景色はビル群から深い森へと変わっていく。到着したのは、Nesodden(ネスオッデン)という町だ。ここには、オスロ中心地の近くに身を置きながら、自然に寄り添う暮らしを求める人々が暮らしている。

ネスオッデンのフェリーターミナル|Image via Shutterstock
そしてこの町で、サーキュラーエコノミーの実践が広がりを見せている。資源を循環させるだけでなく、人と人、自然と経済をつなぎ直すような動きが、草の根から生まれているのだ。
案内役を務めたのは、Cynthia Reynolds(シンシア・レイノルズ)さん。彼女はCircular Regionsというプラットフォームを通じて、理論と実践をつなぎ、地域と世界を橋渡しする存在であり、Circular Economy Coalitionの創設者でもある。
今回はシンシアさんの案内のもと、ネスオッデンに点在する様々な循環型プロジェクトを視察した。本記事では、ネスオッデンで出会った事例を通じて、サーキュラーエコノミーの次なる可能性を探る。

案内してくれたシンシアさん
海と共に暮らす。Kollektivbryggaで見たサーキュラーな関係性
ネスオッデンのフェリーターミナルから歩いてすぐの場所に、「Kollektivbrygga(コレクティブ・ブリッガ)」と呼ばれる共有桟橋がある。かつて漁業と海運の拠点だったこの場所は、現在ではネスオッデン市の支援のもと、地域の海洋活動とサーキュラーな取り組みの拠点として再生され、3つの非営利団体が拠点を構えている。
この場所でまず紹介されたのが、地元のカヤッククラブ「Nesodden Kajakklubb」だ。ここでは地域住民が自然と一体になるアクティビティとして、日常的にカヤックを楽しんでいる。単なるスポーツ施設ではない。フィヨルドの生態系や水質への意識を育てる場としても機能しており、人と自然の距離を縮める場所となっている。また「カヤック・アズ・ア・サービス」により、900人を超える地域のメンバーが、自分で購入・所有することなくカヤックを利用できている。

Image via Shutterstock
次に紹介されたのが、「Indre Oslofjord Undervannsklubb(インドレ・オスロフィヨルド潜水クラブ)」。この団体では、スキューバおよびフリーダイビング用の機材がメンバーに向けて共有・整備されており、個人で所有することなく利用できる仕組みが整っている。若者たちはフリーダイビングの講習を通じて海中世界について学び、成長にあわせたサイズの機材にもアクセスできる。また、プラスチックごみの回収など海洋保全活動にも積極的に関わっているのがポイントだ。
さらにこの取り組みは、Circular Regionsのプロジェクト「Unge Under(海の若者たち)」における事例としても紹介されており、所有よりアクセスを重視する姿勢と、教育・環境保護とを組み合わせた実践的な事例となっている。
「Marinreparatørene(マリン・レパラトーレネ)」もこのエリアの重要な存在だ。廃棄される船やマリン装備を修理・再利用することで、海洋産業におけるサーキュラーエコノミーを体現している。単なる修理事業にとどまらず、技術の継承や若者の雇用機会の創出にもつながっており、「海とともに生きる」ための新しい経済のかたちを提示している。
見過ごされてきた川から変革を起こす。Plastic Piratesの挑戦
オスロ・フィヨルドに流れ込む海洋ごみの多くは、内陸から流れる川に由来し、その中でも、フィヨルドのさらに下流に位置するリエル川は、ノルウェーで最も深刻なプラスチック汚染河川とされている。この現実に真正面から向き合っているのが、市民団体Plastic Piratesだ。彼らは地道な清掃活動と社会的な意識啓発を組み合わせて取り組みを進めている。
Plastic Piratesはボランティア主体の団体で、ノルウェー各地に支部を拡大しながら、「日曜日に川およびフィヨルドをきれいにする」というシンプルな行動を重ねている。活動の始まりは、リエル川が「ノルウェーで最もプラスチック汚染された川」と報道されたこと。メンバーのDag Reynolds(ダグ・レイノルズ)さんは、「その記事がきっかけで、みんな目を覚ました」と振り返る。
清掃活動では、川岸のプラスチックごみを回収し、一時的に見えるところにおいておくことを大切にしている。「ごみを1・2日そのまま置いておくことで、どれほどひどい状態かを誰もが目にできる。可視化は意識を変えるための第一歩です」とダグさんは語る。

ダグさん
SNSやメディアを通じた情報発信を続けるうちに、次第に地元住民の参加が増えていった。学校や自治体、そして環境NGOも協力し、収集したごみの分類や発生源の特定も行っている。調査の結果、この地域のプラスチックごみの多くが農業由来であることが明らかになった。
「最初に現れた農家の一人は、自分の農場周辺が清掃対象外だと知ると、自らごみを集めてコンテナ一杯にしました。さらには川の反対側が気になり、隣人にも声をかけて一緒に清掃したのです」とダグさんは語る。こうした草の根の行動が、地域全体の意識を変え始めている。
清掃活動は、社会的包摂の側面も持つ。Plastic Piratesは、刑務所から出所後に社会復帰を目指す人や、薬物依存からの回復途上にある人々にも門戸を開いている。
最近では、Plastic Piratesの活動とは無関係に、ごみ袋を持って清掃する人が増えているようだ。リエル川が「自分たちの川である」という意識が広がっていると、ダグさんは語る。
廃材から社会を再生する、Remonter
ネスオッデンを拠点とするRemonterは、自治体が運営する社会的企業であり、「サーキュラーエコノミー」と「社会的インクルージョン」という二つの文脈を交差させる取り組みを展開している。廃棄される建材や衣類、家具などをアップサイクルするだけでなく、就労支援を必要とする人々の社会参加を支えるプラットフォームとしても機能しているのだ。

Remonterの活動の中核は、「再構築=Re-mounting」というコンセプトにある。取り組みの対象は、解体現場などで発生する良質な建築資材や、廃棄予定の衣類・布地・家具など。これらを新たな製品や什器として「再構築」する。特徴的なのは、再利用可能な素材を地元で調達し、地元で再加工し、地元で再流通させるという地域完結型の仕組みを目指している点だ。
また、Remonterでは、若者、長期失業者、移民、障害を持つ人々など、従来の労働市場にアクセスしにくい人々が訓練生として受け入れられ、素材の解体・分類・加工・製品化といった一連のプロセスに関わることで、職業的なスキルを培っている。
「私たちの役割は、持ち込まれるモノや関わる人々の中に、“金(きん)”を見つけることなんです」スタッフはそう語る。Remonterでは、価値が失われたと見なされた素材や人に、もう一度可能性を見出そうとしている。
素材として扱われるのは、寄付された衣類や古いカーテン、端材など。例えば、少量の糸くずや端切れをねじってつくる座布団や、ベッドリネンを裂いて手編みしたマット、廃紙から手漉きする紙製品など。これらは一点物の製品であると同時に、参加者のスキルと誇りの結晶でもある。
実際に作業を行うスタッフは「同じ作業を黙々と繰り返すことには、どこか瞑想のような静けさがある」と語っていた。制作のプロセス自体が、手を動かすことで得られる集中と安心、他者とのつながりを生む時間となっている。

Remonterの現場には、完璧を求めるのではなく、トライアンドエラーを前提とした柔軟で包摂的なマインドセットが息づいている。そのプロセス自体が、循環型社会の構築に向けた実践として、地域の中に確かな土台を築いている。
「修理する社会」はつくれる。ネスオッデン市が生み出す循環型コミュニティ
静かな森と海に囲まれたネスオッデンでは、サーキュラーエコノミーは単なる環境政策ではなく、暮らしそのものの哲学として根づきつつある。その中心を担っているのが、Nesodden Kommune(ネスオッデン市)だ。
注目すべきは、行政と住民、事業者が水平な関係でつながる仕組みが実現しつつある点。たとえば、地域の高校に隣接する複合施設では、授業時間外に一般住民にも開放されるメイカースペースがある。そこには3Dプリンターやレーザーカッター、さらには陶器用のプリンターまでそろい、誰でも自由に使うことができる。

案内してくれたシンシアさん(左)、ネスオッデン市特別コンサルタントのアネットさん(中)、ネスオッデン市共創コーディネーターのオスカーさん(右)
この施設をつくるにあたり、自治体のスタッフが最初に取り組んだのは、「使われていなかった空き時間の見える化」だった。市の支援を受けつつ、ボランティアと行政の共同組織を立ち上げ、地域住民が自由に鍵を持ち、好きなときに使えるような開かれた制度を整えた。こうした柔軟な設計思想の背景について、「何か新しいことを始めるには、たいていお金だけでは足りない。情熱やインスピレーション、それを面白がる人の存在が必要なんです」と共創コーディネーターのオスカーさんは語る。
このような思想は、北欧初のスマートな「ものの図書館」であるTingenesBibliotekや、「リペア・デイズ(修理イベント)」といった取り組みにも反映されている。TingenesBibliotekでは、ドリルやテント、調理器具などを地域住民同士が貸し借りできるようになっており、Repair Daysでは、壊れた電化製品や衣類を持ち寄り、地域の人々と一緒に修理するイベントが開催されている。
ネスオッデン市は、これらの取り組みを町の中心部に集める上で重要な役割を果たしてきた。こうして形成された「サーキュラー・ラーニング・アリーナ」では、案内役のシンシアさんが中心となり、世界中から訪れる研究者や実践者を受け入れ、ヨーロッパをはじめとする各地のプロジェクトをつなぐ役割を担っている。

案内してくれたベンディクさん。ネスオッデンの自然資源を活かしたプロジェクトに携わる。
さらに、これらの取り組みを支える情報基盤として整備が進められているのが、地域全体の活動を可視化するデジタル・コミュニティ・プラットフォームだ。スポーツ、文化、ボランティアなどあらゆる分野の団体がここに登録され、横断的な連携が生まれている。
このプラットフォームは、地域全体を一つの「生きたネットワーク」として動かしていくうえで、重要な基盤になっているようだ。このネットワークを活用し、最近では屋外シネマの設置や、オープンマイクイベントなど、地域の多様な人々が「足を運びたくなる場づくり」にも力が入れられている。
人の顔が見えるスケールの町で、循環を生む人の輪
今回のネスオッデン滞在を通して、あらためて気づかされたことがある。それは「歩けば知り合いに会えるスケール感」が持つ力だ。森や海がすぐそばにある自然との距離。そして、点在するプロジェクトが「Circular Region」というプラットフォームに丁寧に記録・可視化されていること。こうした要素が、サーキュラーエコノミーというコンセプトを、実体ある生活の中に根づかせている。
何より印象に残ったのは、筆者らを笑顔で、そして快く迎え入れてくれた人々の姿だ。初対面であっても、遠くから来た人々の関心や問いを誠実に受け止め、案内し、語ってくれた。そうした姿勢そのものが、この地域に流れる「循環する価値観」を物語っているようだった。
サーキュラーエコノミーという言葉は、ときに理念や技術の話に終始してしまうことがある。しかし、ネスオッデンで感じたのは、それが「暮らし」になるために、最後に必要なのは人のつながりだということだった。制度や機械が循環を支えるとしても、それを動かすのは人の思いであり、関係性だ。町の中で重ねられる、日々の選択と対話。そこにこそ、未来へのヒントがあるのだろう。
【参照サイト】Circular Regions
【関連記事】ノルウェーの首都オスロ、世界初のゼロエミッション都市へ