経済成長を止めてはならない──いつから、私たちはこの考えを“当たり前”のものとして受け入れてきたのだろうか。その前提のもとで、現代社会ではインフレや格差の拡大、気候危機が深刻化している。一方、この前提そのものを問い直す考え方として「脱成長(Degrowth)」をめぐる議論が、世界で着実に広がりつつあるのだ。
この複雑で、時に誤解されがちな概念を、映像を通じて社会に問いかけようと試みた人物がいる。BBCで長年活動し現在は個人ジャーナリストとして活躍するアルバロ・アルバレスさんだ。2025年7月、アルバロさんは、脱成長を探求する旅を一本の短編ドキュメンタリーとして結実させ、13万回再生(2025年9月現在)を超える作品を世界に送り出した。
なぜ今、脱成長が重要なのか。開かれた議論のきっかけをつくるために、どのような物語が求められるのか。BBCでの動画公開を実現し、対話の輪を広げるアルバロさんに話を聞いた。
話者プロフィール:Alvaro Alvarez(アルバロ・アルバレス)
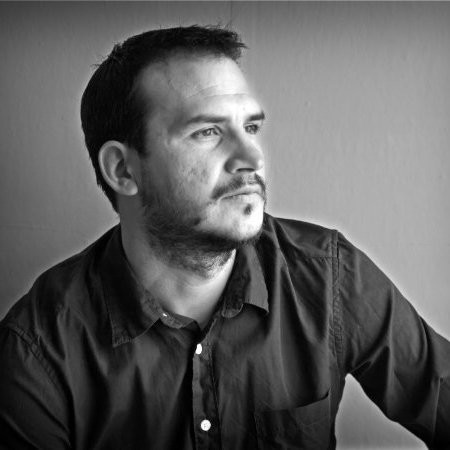 ジャーナリスト、ドキュメンタリー映画制作者、コンサルタント。短編デジタルビデオから国際ドキュメンタリーまで、幅広いコンテンツを15年以上制作。アルゼンチン生まれ、スペイン育ち。スペインの新聞「エル・パイス」で勤務した後、2011年にロンドンのBBCワールドサービスに参加。キューバ、メキシコ、ペルー、中国、エジプトなどを訪れ、様々な課題を取材。脱成長に焦点を当てた最新ドキュメンタリーでは、バルセロナでの活動を掘り下げ、その学術的基盤と、脱成長の原則を実践する人々の取り組みの両方を検証した。(ウェブサイト:https://www.alvaroalvarez.media/)
ジャーナリスト、ドキュメンタリー映画制作者、コンサルタント。短編デジタルビデオから国際ドキュメンタリーまで、幅広いコンテンツを15年以上制作。アルゼンチン生まれ、スペイン育ち。スペインの新聞「エル・パイス」で勤務した後、2011年にロンドンのBBCワールドサービスに参加。キューバ、メキシコ、ペルー、中国、エジプトなどを訪れ、様々な課題を取材。脱成長に焦点を当てた最新ドキュメンタリーでは、バルセロナでの活動を掘り下げ、その学術的基盤と、脱成長の原則を実践する人々の取り組みの両方を検証した。(ウェブサイト:https://www.alvaroalvarez.media/)
脱成長は複数の現代危機をつなぐ視点
「脱成長は世界を救えるか(Could ‘degrowth’ save the world?)」──これが、アルバロさんが作成した短編ドキュメンタリーのタイトルだ。2025年7月8日、約20分のこの動画がBBC公式YouTubeで公開されると、瞬く間に反響が広がった。
脱成長とは、広義には「生産と消費の縮小によるエコロジカル・フットプリントを削減することであり、ウェルビーイングを確保しながら公平な方法で民主的に計画されるもの」と定義される。ドキュメンタリーでは、その脱成長の研究が盛んなスペイン・バルセロナ自治大学やジローナ県での実践例を扱う。フィールドワークに出かけ、脱成長的なアプローチをとるガーデンや民間組織を訪れ、様々な人と対話していくのだ。
※ YouTubeの自動翻訳で日本語字幕の表示可能
アルバロさんが「脱成長」という言葉に初めて出会ったのは、2022年頃のこと。書店で偶然手に取った一冊の本『The Future is Degrowth: A Guide to a World Beyond Capitalism』がきっかけだった。長年ジャーナリストとして国家間格差などの社会的な課題を追いかけ、故郷アルゼンチンを含むラテンアメリカのドキュメンタリーも撮影した彼にとって、その本が提示する視点は衝撃的だったという。
「読み始めてすぐに、なぜ今まで脱成長という概念を知らなかったのだろう、と驚きました。その本では、私が長年取材してきた社会的な課題が、生態学的な危機にはっきりと結びつけられていたのです。
特に興味深かったのは、その本がさまざまな危機を絡めて描き出していたところ。気候変動には常に関心を持っていましたが、そこまで深く掘り下げて考えたことはありませんでした。そんな私にとって脱成長は、気候変動を、経済や私たちの生活など誰にとっても身近で具体的な側面と結びつけてくれたのです」
そこから、アルバロさんは脱成長の資料を読み耽る中で、欧州においてスペイン・バルセロナが脱成長議論の中心地であることに気づく。当時、そのことを不思議に思ったことから、脱成長の映像制作が始まった。
難解なトピックを「伝える」物語の見せ方
当初、アルバロさんは脱成長について10分ほどの短編映像にすることをBBCに提案した。
「企画のプレゼンテーションをまとめて、退職後も時々一緒に仕事をしていたBBCの部署に提案しました。すると驚いたことに、彼らは本当に強い関心を示してくれたんです。ある人は『ずっと誰かが脱成長の企画を持ち込んでくれるのを待っていた』と言ってくれました」
予想以上の熱量を背負って取材は進み、最終的に約20分の中編ドキュメンタリーとして完成。しかし、その制作過程は「どうすればこの複雑なテーマを、関心のない層にまで届けられるか」という問いへの挑戦の連続だった。
「私とBBCのチームが避けたかったのは、専門家がただカメラに向かって理論を語るだけのドキュメンタリーでした。脱成長というアイデアについて語るだけでなく、その価値観と重なる生き方を実践している人々の、掴みどころのある具体例を見せることが不可欠だと考えていました」

脱成長の学部が存在するバルセロナ自治大学で経済学と経済史を教えるホアン教授|出典:https://www.youtube.com/watch?v=596dU6pDEU8
そこでアルバロさんがカメラを向けたのは、利益の最大化だけを目的とせず、人々のニーズを満たすために運営される住宅協同組合や、モノの図書館、パーマカルチャーを実践するリトリート施設。そして脱成長を研究する学生たちによるイベント。こうした実践の現場を映し出すことで、経済を民主化し、ウェルビーイングを追求する社会の姿を描き出そうとした。
「脱成長において、協同組合が非常に重要であることに気づきました。協同組合は多くの解決策やアイデアをもたらし、経済やビジネスに関わる人々がそこから学ぶことができると考えています。そして、住宅協同組合のような組織が実現してほしいと思っています」

取材でアルバロさんが訪れたバルセロナの住宅共同組合の部屋|出典:https://www.youtube.com/watch?v=596dU6pDEU8
「広い読者を持つBBCに向けて映像を制作する中で、誰にとっても最も分かりやすい物語をどう構築するかについて深く考えていました。GDPとは何かを説明する必要はあるけれど、それに10分も費やせば視聴者は退屈してしまう。脱成長の複雑な要素を分かりやすい物語に翻訳するのは、とても骨の折れる作業でしたね。
時折、『この動画は脱成長について十分に掘り下げていない』と言う人もいます。ただ、このドキュメンタリーの目的は、概念を深く掘り下げることではなく、好奇心を刺激し議論や対話を巻き起こすこと。そして、実際に人々が調べ始めるよう刺激することなのです」
実は、人々は新たな社会を議論する準備ができている
アルバロさんの狙い通り、このドキュメンタリーは世界各地の上映会や大学の授業で「対話の触媒」として機能している。およそ20分という長さが、議論を始める前の導入としてほど良い規模感だったのだ。

Image via Alvaro
ドキュメンタリーには、脱成長というトピックに対する批判的な意見も意図的に取り入れた。これは、BBCがいつも重視するポイントでもあるという。「脱成長の社会的な実現可能性は本当にあるのか」という問いも挟むことで、多様な立場を巻き込んで議論の土台を築こうとした。
「私は、誰にも反論するつもりはなく、ただのメッセンジャーにすぎません。脱成長の専門家でも、脱成長の修士号を持っているわけでもありません。ただ、このテーマに強い情熱を持っているのです。人々の目を開き、できるだけ多くの人にこのアイデアを届けたいと思っています。
そうすれば、みんなで一緒に判断できるでしょう。もし脱成長が良いアイデアではないと判断されるなら、それはそれで良い。少なくとも、一部は取り入れられるかもしれない。いずれにせよ、今の仕組みがうまくいっていないことは明らかですから」
つまり動画が問いかけるのは、脱成長に賛成か反対かという二元的な視点ではない。ほつれ始めている現代の仕組みを変えていくために、脱成長から何を学べるか。そんな建設的な問いなのだ。
「主流メディアにおける経済に関する報道のほとんどは、成長を前提とした従来の経済学に基づいています。だからこそ、これまでほとんど光が当てられてこなかった脱成長のようなオルタナティブな視点が広がるためのプラットフォームを作ることが重要です」

Image via Alvaro
こうしてアルバロさんが行動を起こし続ける後ろ盾にもなっているのは、「実は多くの人が変化を望んでいる」という実感だ。
「ガーディアン紙の記事で、『多くの人が気候変動に対して政府にもっと行動してほしいと思っているものの、自分は孤立していると考えている』と書かれていました。つまり、多くの人が同じように考えているにもかかわらず、仲間がいないと思い込んでいるのです。
人々は、オルタナティブについて語り合う準備ができています。ただ、それを始めるきっかけが必要なのかもしれません。実際に、私の上映会に来た人の多くはこうしたアイデアにかなり興味を持っていました。もともとは脱成長に興味がなかった人も、上映後『なるほど、脱成長は素晴らしい話だけれど、どう実現するの?』と質問してくれました。そして、その解決策や答えはすでに存在しているのです」
編集後記
どこからこの動画を知ったのか、筆者は記憶にない。それほど、この動画は環境問題に関心を寄せる人々の間で話題となり、共有され、さまざまなプラットフォームで広がった。これまでアクティビストや研究者が着実に基礎を築いてきたムーブメントが、インターネットという現代社会のツールをのっとって世界へ伝播したかのようだ。
一方で、脱成長の実践は一筋縄では行かない。近年の脱成長の議論は欧州を中心に巻き起こった。この動画も、欧州中心的すぎる視点に陥る懸念があったという。その上でアルバロさんは、「そもそも脱成長とは、資源を過剰に消費してきた“豊かな国”でこそ実践されるべきものです。今回の動画では、まずその中心地の一つで何が起きているのかを具体的に示すことが重要だと判断したのです」と語った。
誰の視点から、どんな実践を起こしていくべきなのか──大きな責任の伴う問いと共に、私たちは経済の「成長神話」を乗り越えようとしている。アルバロさんがカメラを手に、出会ってきた脱成長の「今」の片鱗は、その長い道のりの後押しとなるはずだ。
【参照サイト】Could ‘degrowth’ save the world? | BBC News
【関連記事】研究者に聞いた、脱成長のいろは。日常の実践は「WANT」じゃない軸の発見から
【関連記事】自治体が「脱成長」を目指す。スペイン・ジローナ市の気候変動対策













