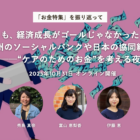※この記事は、著者・Alex Lopez氏によって2025年2月25日にPost Growth Perspectivesに寄稿されたもので、クリエイティブコモンズライセンスのもと、許可を得て翻訳・IDEAS FOR GOOD向けに一部編集したものです。
近年、「再生可能エネルギー・コミュニティ(Renewable Energy Communities:REC)」への関心が高まっている。これは、地域の経済的・社会的・環境的利益のために、エネルギーを共同で管理する法人形態であり、必需インフラであるエネルギーに対する市民の主体的な関与のモデルとして広く受け入れられてきた。では、同じ発想を「お金」に応用することはできないだろうか。
スペイン・バスク地方の市民協同組合「Ekhilur(エキルール)」は、地域経済を強化する革新的なアプローチを実践している。地域通貨を新たに発行するのではなく、すでに存在するユーロを活用しながら、地域の中でお金がより長く、何度も使われるようにすることを目指しているのだ。そのために、スペイン銀行の監督下で運用される独自のキャッシュレス決済システムを導入し、日々の買い物や取引が地域内で完結するような仕組みを整えている。
この取り組みは、ギプスコア県エルナニという人口約2万人の町で、小規模事業者の取引のあり方を変えてきた。開始から2年余りで、取引件数は20万件以上、累計売上は500万ユーロ超に達し、ユーザーは1,400人以上、参加事業者は125にのぼる。
お金の流れを市民がデザインする協同組合モデル「Ekhilur(エキルール)」
Ekhilurの特徴は、その技術的な仕組みにとどまらず、運営主体が市民による非営利の協同組合である点にある。営利企業ではなく、地域住民自身が資金を出し合い、「一人一票」の原則に基づいて意思決定を行うことで、地域の経済インフラを自らの手でつくり出している。出資金は誰もが参加しやすいように10ユーロと低く設定されており、Ekhilurのネットワークがある自治体に住んでいる非組合員も、一部の機能に限られるものの、システムの利用が可能だ。協同組合には市民だけでなく、自治体や地域の商店も参加しており、地域経済の設計を共に担う構造となっている。
決済インフラとしてのEkhilurは、スペイン銀行の監督下にある電子マネー機関(EMI)と提携しており、すべての取引は法定通貨であるユーロを用いて行われる。つまり、地域通貨を新たに発行するのではなく、すでにあるユーロの「流れ方」に着目し、その循環を地域内にとどめることで、経済の自律性とレジリエンスを高めようとしているのである。
加えて、Ekhilurでは商店や自治体によって資金提供されるキャッシュバック制度があり、ユーザーが支払いを行うたびに一定額が還元される。このキャッシュバックはネットワーク内でのみ使用可能であるため、地域内の商取引が自然と活性化する構造になっている。経済的インセンティブを通じて、人々の購買行動が「地域を応援する行動」として位置づけられているのだ。Ekhilurは、テクノロジーと協同の力を組み合わせ、「お金の使い方」そのものを再設計する挑戦であり、成長に依存しない経済の可能性を実証しようとしているのである。
お金は、最適化可能な「社会的合意」
こうした仕組みは、単なる決済手段の工夫にとどまらず、そもそも「お金とは何か」「どのように使われるべきか」という根本的な問いを私たちに投げかけてくる。Ekhilurの実践は、お金がただの数値やモノではなく、社会の中でどう流れ、どう使われるかによって価値を持つ「社会的な合意」であることを、あらためて気づかせてくれるのだ。
現代の市場経済においてお金は不可欠なツールであるが、地域の富に与える影響は、その「流れ方」と「集中のされ方」によって左右される。あまりに当たり前の存在となったお金について、私たちは普段、立ち止まって考えることがない。しかし、お金とは突き詰めれば「社会的合意」にすぎず、その設計次第で、地域にとってより有益な仕組みに最適化することができる。
お金がすぐに大手プラットフォームや金融市場に流出してしまえば、雇用創出や地域経済を活性化する力は失われてしまう。反対に、お金が地域内で循環し続ければ、小規模事業の発展を促し、経済的自立性を高め、地域全体に経済的なチャンスをもたらすとも言えるだろう。
お金が地域経済を強くする方法とは?
お金を町の中を流れる「川の水」として捉えてみよう。地域内にお金を長く留めるには、主に二つの方法がある。
- 水を1カ所に貯めるダムを作る(伝統的な地域通貨モデル):この方法は一見効果的に思えるが、ダムの容量には限界があり、いずれ水を放流せざるを得ない。
- 水路や曲がりくねった流れ(Ekhilurのアプローチ)をつくって、水が地域のあちこちを通りながら流れ続けるようにする:これにより、多くの人々がその恩恵を受けることができる。
Ekhilurが運用するローカル決済システムは、この「水路」として機能する。お金がすぐに地域外へ流出せず、地域内の商店や団体、個人事業主などとの取引に回ることで、地域経済の底上げにつながる。
さらに、Ekhilurは単なる決済インフラにとどまらず、ボーナス制度によるロイヤリティプログラムを提供し、自治体や事業者の積極的な関与を促している。また、地元の生産者をネットワークに組み込み、地域内で供給と需要をつなぐことで、サーキュラーエコノミーの推進にも貢献。こうして、地域の事業者と消費者の双方にとって利益となる経済の循環が生まれているのだ。
「互恵モデル」を支える主な担い手
この仕組みが機能するためには、以下のような複数の担い手の協力が不可欠である。
- 市民:参加事業者での支払いにローカル決済を活用することで、地域の経済構造を強化すると同時に、個人的な経済的メリットも得られる。
- 地域事業者:この決済システムを導入することで、顧客の定着率が高まり、事業者間の連携も生まれる。
- 自治体:補助金や助成金、委託費などの公的支出をローカル決済で行うことで、地域経済に直接的なインパクトを与えられる。また、住民税や各種手数料の徴収にも活用可能だ。
- 団体・協会:地域内での資金の受け取りと管理を行うことで、地域の連帯経済を支え、社会的なつながりを強化する。
実際にこの仕組みにより、地域の団体へ6,000ユーロが還元されており、お金が経済的機能を維持しながらも社会的インパクトを生み出すことが証明されている。
「流通」と「蓄積」。お金の真価とは?
この取り組みの目標は、お金を「地域に留める」ことではなく、「地域内で流通させ続ける」ことである。1,000万ユーロを金庫に眠らせておくよりも、100万ユーロが10回地域内を回るほうが、雇用や取引、プロジェクトが次々と生まれ、豊かさが広がる。
重要なのは、こうしたお金の循環が持続的かつ生産的な経済活動につながるような仕組みをどう設計するかである。それはつまり、大企業や投資家への富の集中を促すのではなく、地元の商業、雇用、コミュニティ活動を支える方向に経済を動かすということだ。
ネットワーク効果がもたらす地域間の連携
Ekhilurモデルのもう一つの特長は、地域同士がつながり、ネットワーク効果を生む点にある。地域が自律的に経済を管理し、互いに強め合うことで、分散型でレジリエントな経済構造が育まれる。
地域により多くのお金を留めることができれば、中小企業がその資金を改善、雇用、イノベーションに再投資できるようになり、地域からの富の流出が抑えられる。これは、上から押し付けられた仕組みではなく、各地域が主体となって経済の方向性を決め、グローバルな課題に柔軟に対応できる仕組みである。
本当の意味での持続可能な経済へ。お金の再設計
再生可能エネルギーの分野では、すでに市民がエネルギーを自らの手に取り戻す動きが始まっている。それならば、「お金」についても、同じように考えることができるのではないか。
Ekhilurのような取り組みは、お金の流れ方を見直すことで、地域にポジティブな影響を与えられることを示している。重要なのは、既存の経済システムのルールを上手に活用しながら、地域経済の再構築と、公平で連帯的な社会の実現を目指すことだ。
お金そのものが「富」なのではない。お金とは、モノやサービスにアクセスするためのツールにすぎない。したがって、誰がどれだけお金を持っているかが、市場経済への参加機会を左右している。実際の例が下記だ。
- お金があれば、エネルギー、食料、住居にアクセスできる。
- お金がなければ、これらの資源が存在し、十分にあっても、それらにアクセスすることはできない。
この視点から見ると、お金は商品そのものではなく、アクセスの権利に似ている。教育や医療へのアクセスが多くの社会で基本的な権利と見なされているように、公正で平等な交換手段へのアクセスもまた、基本的な権利として考えられるべきではないだろうか。
このビジョンは、お金が価値を生み出す役割については触れておらず、商品のアクセス手段としての機能について述べている。しかし、お金がこれらの資源の使用を調整する鍵として機能するならば、次のような問いが浮かび上がる。
- 通貨システムの設計が、経済の機能や地球の資源の使用に影響を与えることができるだろうか?
- お金とその経済的ダイナミクスを再設計すれば、消費モデルを変革できるだろうか?
気候と生態系の危機は、私たちが使うエネルギー源を変えるだけでは十分ではなく、資源がどのように抽出され、変換され、配分されるかを定義する経済モデルを再考しなければならないことを示している。おそらく、真に持続可能な移行には、(他の多くのこととともに)お金自体を変革することが必要である。それは、物理的限界から切り離された通貨システムから、それらを考慮に入れたシステムへの移行である。
メディア紹介:Post Growth Perspectives
Post Growth Perspectivesは、Post Growth Instituteによって創設されたオンライン雑誌であり、その使命は、人間のシステムが生態的制限の中で繁栄する世界への移行をリードする手助けをすることです。自然のシステムの知恵に触発され、私たちは、地域社会とグローバル経済におけるお金、権力、資源の循環を促進するアイデア、プログラム、連携を祝福し、支援し、発展させます。
URL:https://medium.com/postgrowth
アイキャッチ:Image created on Midjourney (CC-BY-4.0)
【関連記事】持ち家でも、賃貸でもない。バルセロナで広がる協同組合住宅とは?
【関連記事】フランスの協同組合が、地方の“儲からない”空き家を改修。市民による市民のための居場所づくり
Edited by Erika Tomiyama