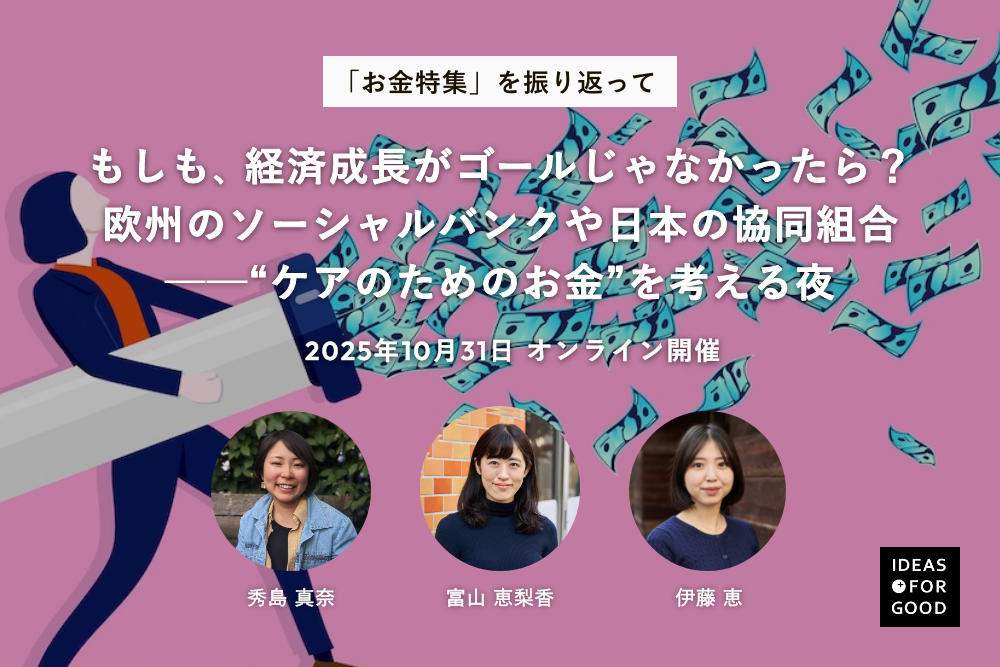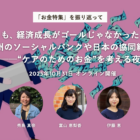特集「お金と私たち。見えざる力を問い直す」
お金は、ただの紙切れでも数字でもない。生き方や価値観、人間関係、社会制度にまで影響を及ぼす「見えざる力」だ。便利で、時に残酷で、そして人間的なこの仕組みは、いつから私たちの「当たり前」になったのだろう。物価高騰や格差、資本主義のゆくえ──議論は世界中で交わされているが、日々の暮らしの中でお金の本質を見つめ直す機会は少ない。だからこそ今、問いたい。「お金」とは何か、そして私たちはそれとどう向き合っていけるのか。本特集では、経済だけでなく、アートや哲学、コミュニティの現場など多様な視点からお金の姿を捉え直す。価値の物差しを少し傾けてみた先に、より自由でしなやかな世界が見えてくることを願って。
気候危機、広がる格差、心の健康問題。私たちはかつてないほど物質的に「豊か」になったはずなのに、なぜ社会はきしみ、未来への不安は増すばかりなのだろうか。その根源には、社会の進歩を「GDPの成長」という単一の指標で測り、それを至上の目的としてきた、ひとつの“神話”がある。もし、その神話自体を疑い、まったく新しい「繁栄」の物語を描き直せるとしたら。
英国サリー大学に拠点を置く研究センター「Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity(CUSP)」は、まさにその問いに挑んでいる。今回は、CUSPの中でも特にユニークな視点を持つ二人の研究者に話を聞いた。一人は、社会システムが経済成長に依存する構造を研究し、ポスト成長社会のあり方を探るクリスティン・コーレット・ウォーカー氏。もう一人は、社会学と人類学を専門とし、アートや創造性が社会を変える力に着目するアナスタシア・ルキアノフ氏だ。
CUSPの研究者が科学の目で解き明かす、「繁栄」の新しいかたちとは。
話者プロフィール:Christine Corlet Walker(クリスティン・コーレット・ウォーカー)
 CUSPの研究員で、生態経済学を専門とする政治経済学者。地球の限界内で万人のニーズを満たす強靭な福祉システムの構築方法を探求し、特にポスト成長経済学や社会ケアの問題に取り組む。研究成果を基に欧州委員会への政策提言や英国議会での法案修正を行うなど、政策への関与も深い。ケンブリッジ大学、エディンバラ大学で修士号を取得。
CUSPの研究員で、生態経済学を専門とする政治経済学者。地球の限界内で万人のニーズを満たす強靭な福祉システムの構築方法を探求し、特にポスト成長経済学や社会ケアの問題に取り組む。研究成果を基に欧州委員会への政策提言や英国議会での法案修正を行うなど、政策への関与も深い。ケンブリッジ大学、エディンバラ大学で修士号を取得。
話者プロフィール:Anastasia Loukianov(アナスタシア・ルキアノフ)
 CUSPの研究員。社会学と人類学を専門とし、サステナビリティ、ビジュアル・リサーチ、デジタルメディアの交差点で研究を行う。アートやSNSを含む「ビジュアル」が、持続可能な未来への移行において果たす役割を探求。イメージがいかにしてより良い未来を想像させ、実現する力を持つのかを、Instagramの分析や参加型映画制作などの手法で研究している。マンチェスター大学、サリー大学で学位を取得。
CUSPの研究員。社会学と人類学を専門とし、サステナビリティ、ビジュアル・リサーチ、デジタルメディアの交差点で研究を行う。アートやSNSを含む「ビジュアル」が、持続可能な未来への移行において果たす役割を探求。イメージがいかにしてより良い未来を想像させ、実現する力を持つのかを、Instagramの分析や参加型映画制作などの手法で研究している。マンチェスター大学、サリー大学で学位を取得。
経済成長なき繁栄は可能か。豊かさを問い直すCUSPの原点
二人が所属するCUSPの活動の原点には、ディレクターであるティム・ジャクソン教授が2009年に発表し、世界的な議論を巻き起こした著書『Prosperity Without Growth(成長なき繁栄)』が投げかけた、根源的な問いがある。それが「経済成長なき繁栄は可能か」というものだ。この問いは、経済成長と環境負荷を切り離す「デカップリング」を目指すだけでは気候危機は解決できないという厳しい現実を直視し、経済の目的そのものを問い直すという、CUSPの思想の根幹をなしている。
この根源的な問いに答えるため、CUSPはまず、社会が使う「ものさし」そのものに疑問を投げかける。クリスティン氏は、従来の経済学が前提としてきた豊かさの定義をこう説明する。
「これまでの経済学は、人々の豊かさを『選好充足モデル』で説明してきました。より多くの収入を得て、欲しいモノやサービスをより多く購入できること、それが幸福であり繁栄だとされてきたのです。しかし、このモデルは『多ければ多いほど良い』という、環境的に持続不可能で、直感的にも違和感のある前提に立っています」

Image via Shutterstock
CUSPが目指すのは、富(Wealth)ではなく、ウェルビーイング(Well-being)に焦点を当てた繁栄だ。アナスタシア氏は、繁栄を「人々が健やかに成長できる条件が与えられたときに起こるもの」と定義し、その具体的な中身をこう語る。
「もちろん、食卓に食べ物を並べられることや、良い住まいに住めるといった物質的なものは非常に重要です。しかし、それ以外にも、良好な人間関係、余暇の時間、質の高い職場といった、多くの人々が『良い人生とは何か』と問われたときに語るであろう、あらゆる要素が本来の『繁栄』に含まれるのです」
問題は、アナスタシア氏が語るような、人間にとって不可欠な豊かさの側面が、現在の経済システムでは無視されていることだ。石油流出事故の例は、その矛盾を象徴している。石油流出の処理費用はGDPを一時的に押し上げる一方で、私たちや自然のウェルビーイングは著しく損なわれる。このように、経済成長と人々の豊かさは必ずしも一致しないのだ。だからこそ、CUSPは繁栄という社会のOSそのものを書き換えようとしている。
社会システムに潜む「成長依存」という構造的脆弱性
CUSPの独自性は、なぜ私たちの社会がこれほどまでに経済成長に依存しているのか、そのメカニズムを科学的な手法で解き明かす点にある。
その好例が、クリスティン氏が取り組んだ介護システムの研究だ。マクロ経済の視点から資金の流れを分析し、現場で働く介護従事者へ質的インタビューを実施。これにより、金融化された介護システムが、利益追求のために労働者を疲弊させ、ケアの質を低下させているという「生きた現実」を明らかにした。アナスタシア氏は、こうした学際的なアプローチの重要性をこう語る。
「質的インタビューは、古典的な経済学者からは拒絶される研究方法です。しかし、CUSPのように異なる分野の研究者が集う環境にいることで、経済学者もその利点に気づき、取り入れ始めることができます。他の学問分野で使われている手法を取り入れることで、経済学という学問自体も進歩させ、他では得られなかったような新しい洞察を生み出すのです」
「これは未来の話ではない」とクリスティン氏は続ける。ポスト成長社会で何が起こるか、ではなく、成長を前提としたシステムが「今、ここで」既に多くの人々のウェルビーイングを損ねているのだ。
クリスティン氏が関わったフィンランドとイタリアの年金制度を国際比較した研究では、より格差が少なく公平な制度を持つフィンランドの方が、低成長下での安定性が高いことが示された。これらの事例研究から見えてくるのは、社会保障のようなセーフティネットさえもが経済成長を前提に設計されており、ひとたび成長が止まれば、システム全体が機能不全に陥るという構造的な依存だ。
CUSPは、この「成長依存(Growth Dependence)」の構造を丹念に解き明かす。そしてその構造の解明は、単なる政策変更に留まらない、より根源的な社会の転換へと私たちを導いていく。
ケアを社会の基盤に。未来を想像し直すための新しい物語
科学的な分析の末にCUSPがたどり着いたのは、社会の「常識的な物語(Common Sense Narratives)」を転換する必要性だ。そして、その変化の兆しは、すでに社会の様々な場所で見え始めている。
政治のレベルでは、かつては過激な思想と見なされたポスト成長の考え方が、現実的な選択肢として議論されるようになった。クリスティン氏は、数年前に参加した欧州委員会での経験を振り返る。
「研究・イノベーション総局の局長が『欧州委員会内では、ポスト成長モデルの正当性は証明された』と語ったのです。問題は、いかにしてこの移行を実現できるか、という点に移っていました」この言葉は、政策決定の現場で地殻変動が起きていることを象徴しているだろう。
私たちの暮らしのレベルでも、変化は起きている。アナスタシア氏は、コロナ禍以降に広がった、自家製パン作りやスローライフへの関心の高まりを指摘する。それは、必ずしも高い達成を求めるキャリアではなく、日々の生活の質を大切にしたいという価値観の表れだ。
しかし同時に、彼女は「グラインド(猛烈に働くこと)」を賛美し、物質的な富の蓄積を煽るカウンターの動きも強まっていると分析する。これは、クリスティン氏が指摘する「古い経済の物語の崩壊」に対して、社会が二極化しながら反応している姿そのものだ。
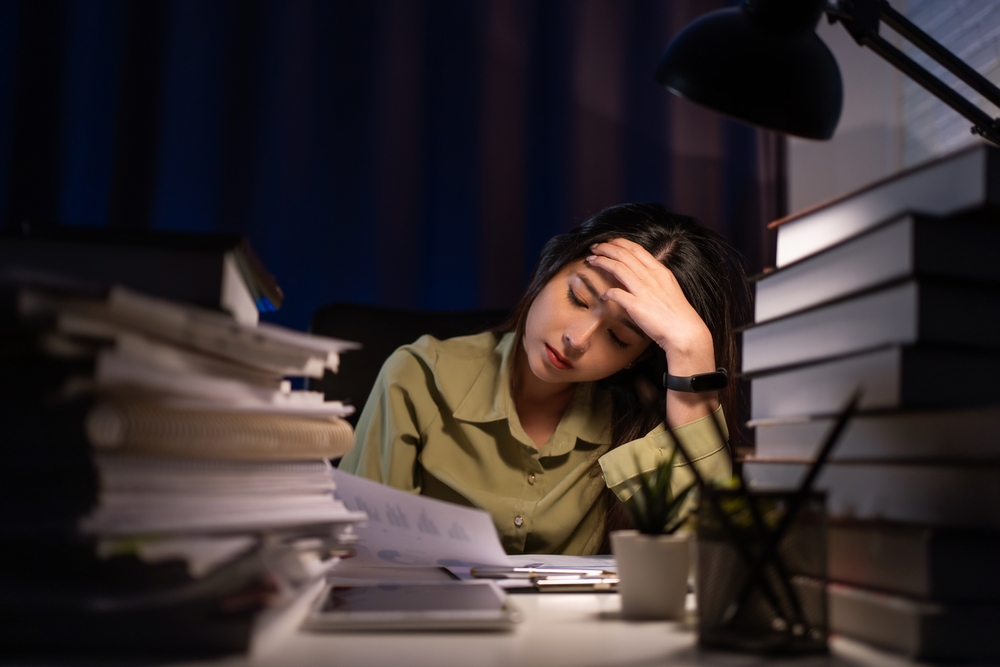
Image via Shutterstock
このような変化の萌芽を確かなものにするために、CUSPが新しい物語の中心に据えるべきだと提言するのが「ケア」である。クリスティン氏は、その核心をこう語る。
「私たちの生活において、ケアは見えなくされています。しかし、家事、育児、介護、隣人との助け合いといったケア労働がなければ、生産的な経済活動は成り立ちません。経済は社会の頂点にあるのではなく、ケアや健全な環境がその土台なのです」
彼女が示すこの構造は、まさに経済という家が、ケアという土台の上に成り立っている姿を思い起こさせる。このヒエラルキーの転換こそ、CUSPが提示する最も重要な視点だ。経済を頂点から降ろし、社会の土台を支えるケアや環境を正当に評価する。それは、アナスタシア氏が語る「生産性」の概念の問い直しにもつながる。効率やスピードだけが生産性ではない。関係性に時間をかけ、丁寧に暮らしを営むこと。それ自体が、豊かな社会を育むための重要な「生産性」なのだ。
CUSPは、この新しい物語をアカデミアの中だけに留めず、欧州委員会との対話や、英国の地方議会と連携した食料不安解決プロジェクトなど、現実社会との橋渡しを積極的に行う。彼らの挑戦は、こう問いかけている。経済という家を、より強固で温かい土台の上に再建するために、私たちはどんな物語を紡ぎ始められるだろうか、と。
編集後記
今回の取材で最も印象的だったのは、CUSPの研究者たちが語る言葉の根底に流れる、人間への深い洞察と共感だった。経済を冷たい数字の学問としてではなく、人々の「生きた経験」と結びついた、血の通った営みとして捉え直そうとする姿勢に、何度も頷かされた。
特に、クリスティン氏が語る「ケアこそが経済の土台である」という思想の核心は、「経済は、ケアや環境という土台の上に立つ家」というメタファーで考えると、私たちの社会が立つ危うい足場を的確に言い当てている。私たちはこれまで、家の装飾や階数を増やすこと(=経済成長)に夢中になるあまり、その土台が蝕まれていることに気づかずにいたのかもしれない。
アナスタシア氏が触れた、コロナ禍以降の「スローライフ」への関心の高まりは、日本でも多くの人が感じるところだろう。「thrive(スライヴ)できる条件を整える」という彼女の言葉は、個人の自己責任に帰結させず、社会全体の構造としてウェルビーイングを考えることの重要性を教えてくれる。
CUSPの探求は、遠い英国の研究所の話ではない。それは、私たち一人ひとりが「本当の豊かさとは何か」を自問し、新しい社会の物語を紡ぎ始めるための、確かなヒントを与えてくれる。
【参照サイト】The Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity (CUSP)