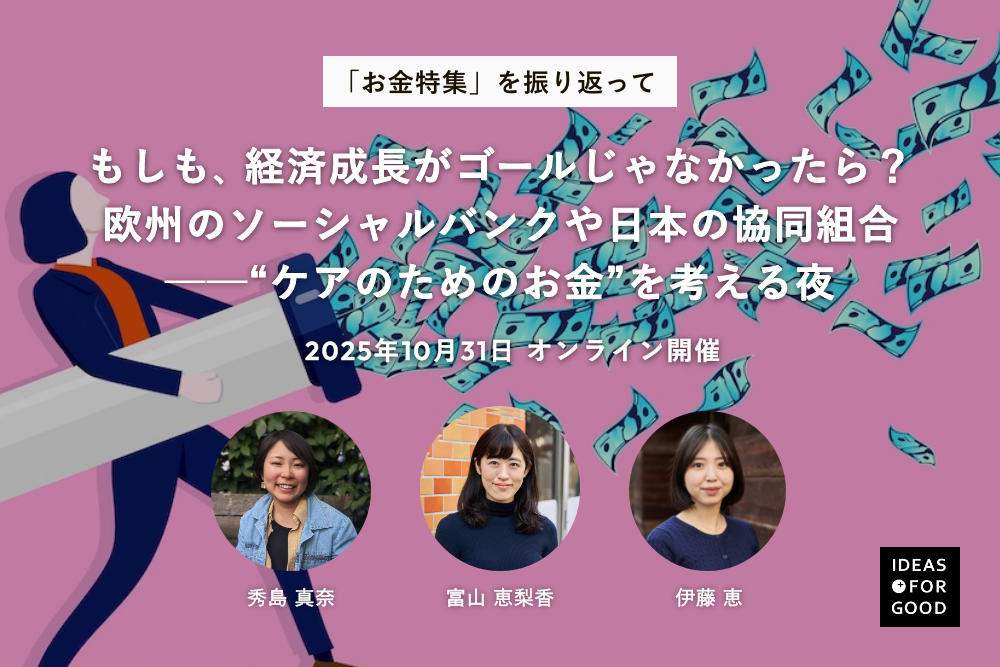【特集】幸せなお金のありかたって、なんだろう?今こそ問い直す、暮らしと社会の前提
お金は、ただの紙切れでも数字でもない。生き方や価値観、人間関係、社会制度にまで影響を及ぼす「見えざる力」だ。便利で、時に残酷で、そして人間的なこの仕組みは、いつから私たちの当たり前になったのだろう。自己責任が求められる働き方、そして「お金がない」ことを理由に後回しにされる福祉や環境対策──議論は世界中で交わされているが、日々の暮らしの中でお金の本質を見つめ直す機会は少ない。だからこそ今、問いたい。「お金」とは何か、そして私たちはそれとどう向き合っていけるのか。本特集では、経済だけでなく、文化人類学や哲学、コミュニティの現場など多様な視点からお金の姿を捉え直す。価値の物差しを少し傾けてみた先に、より自由でしなやかな世界が見えてくることを願って。
お金では動かせないけれど、なくてはならない営みがある──沖縄・宮古島の最北端、海風が吹き抜ける狩俣集落では、草刈りや高齢者の送迎、祭りの準備といった“小さな仕事”が、人と人をつなぎ、暮らしを守ってきた。市場経済では価値に換算されにくいその営みは、今、若者たちの手で事業へと生まれ変わろうとしている。

その挑戦の名前が、「かりまた共働組合」だ。合言葉は「つなぐ心」。若い世代が自らの手で地域活動を盛り上げ、地域住民による地域住民のための経済を取り戻そうとしている。
2022年10月の労働者協同組合法施行を追い風に、同年12月、沖縄県で初の協同組合として誕生。住民が出資し、地域の課題を「仕事」として生み出す仕組みは、かりまた共働組合の代表理事・根間太一さんにとって、集落を内側から立て直すカギだった。
彼らが見据えるのは、利益では測れない価値を守り抜くこと。今の日本が立ち返るべき、暮らしと経済の“原点”への挑戦である。
根間太一(ねま・たいち)さん 労働者協同組合かりまた共働組合 代表理事
 沖縄県宮古島市狩俣出身。地元の高校を卒業後、大学進学のために大阪へ。IT系企業へ就職後、宮古島へUターン移住。その後は狩俣集落で地域の可能性を探るため、27歳でかりまた代表組合の代表理事に就任。組合活動は3年目を迎え、地域の組合員とともに新たな事業展開や、他地域との共同事業の展開に向けて日々奔走している。
沖縄県宮古島市狩俣出身。地元の高校を卒業後、大学進学のために大阪へ。IT系企業へ就職後、宮古島へUターン移住。その後は狩俣集落で地域の可能性を探るため、27歳でかりまた代表組合の代表理事に就任。組合活動は3年目を迎え、地域の組合員とともに新たな事業展開や、他地域との共同事業の展開に向けて日々奔走している。
祭りも学校も。縮小を続ける暮らしの風景
宮古島市の最北端にある狩俣は、広大なサトウキビ畑と豊かな海に囲まれており、農業と漁業を主な産業とする、自然豊かな小さな集落だ。近くには観光地として知られる西平安名崎があるが、狩俣は市内中心部から唯一孤立するように離れており、若者の流出と少子高齢化が急速に進んでいる。

宮古島から北向け(写真下部)に細く伸びる地形の狩俣地域(集落は写真右下) 筆者撮影
狩俣で生まれ育ち、Uターンを経て現在も地域の中心で活動を続ける根間さんは、「かりまた共働組合」の代表理事として仲間とともに新しい未来づくりに取り組んでいる。同共働組合では、空き家や高齢化、担い手不足といった多様な課題に対して、地域の人材を生かしながら事業を組み立てているのが特徴だ。
そんな彼が日々強く抱いているのは、少子高齢化や空き家の増加に揺れる故郷の現実への危機感だ。特に、集落にある住居の約3割は空き家となり、灯りの消えた家々が夜道に影を落とす。人が住まなくなった家では、仏壇や庭木に手が入らず、雑草が伸び放題になる。年を追うごとに、集落の夜は暗く、静かになっていった。

狩俣集落から宮古島市内につながるのはたった一本の県道230号線。
地域行事を支えてきた青年会は、担い手不足で活動を休止。伝統行事の海神祭(通称ハーリー)は、一部のプログラムを縮小しながら、なんとか継承されている状況だ。
さらに、地域内の幼稚園は休園中。数年後には中学校の入学者がゼロになり、子どもたちは他学区まで通わざるを得ない将来がすぐそこまできている。こうした状況は、旧盆など家族行事で狩俣に帰省する人や新たな移住者を迎える体制が整備できないだけでなく、家族ごと狩俣を離れるケースも増え、急速な人口減少に拍車をかけている。

狩俣地域の重要な伝統行事「海神祭」は、大漁祈願や航海安全の祈りを込めて行われる。若い世代の人口減少により、かつての盛り上がりは徐々に薄れつつある 筆者撮影
地域に根付く“協同”の精神。120年の歴史が育んだ土壌
いま、若者の流出や少子高齢化で縮小が進む狩俣。しかし、この集落にはそれ以前から“協同”の文化が息づいていた。台風や干ばつといった自然の厳しさを何度も乗り越えてきた歴史の中で、助け合いは生活の知恵として培われてきたのである。120年以上の歴史をもつ自治会と、地域住民190人の出資で運営される共同購買店「マッチャーズ」が、その象徴だ。

地域に愛される集落唯一の買い物の場マッチャーズ 筆者撮影
「マッチャーズ」という名は、宮古島の方言で「お店」を意味する「マッチャー」と、共同売店を意味する「ズ」を掛け合わせたもの。創業当初は、生活必需品を安定して手に入れるための“村の冷蔵庫”のような存在だったが、今では地域の交流拠点としても機能している。2023年度の売上は1億4,000万円を超え、利益は買い物券などの形で組合員に還元される。まさに地域のためのお店といえる存在だ。
根間さんは、この仕組みにこそ地域を持続させるヒントがあると語る。
「私たちの活動は、全く新しいものではないんです。狩俣の人々が昔から紡いでくれた暮らしや地域経済の仕組みを、次の世代へつなぐ。それが私たちの役割です」
かりまた共働組合は、新しい法制度のもとに生まれた組織でありながら、その精神は「マッチャーズ」が体現してきた地域経営のあり方を確かに継承している。そして2022年10月に施行された労働者協同組合法は、その挑戦に大きな追い風となった。
「お金」よりも「つなぐ」価値、信頼と協働が育む地域の力
貨幣価値には変えられないが、暮らしに欠かせない必要な仕事は過疎地域に多く存在する。狩俣では、高齢者や子どもの送迎、集落内の草刈り、地域行事の準備──市場経済では価値に換算されにくいこれらの営みは、経済的利益を優先する現代では見過ごされがちだ。市内中心部まで車で約30分かかるため、移動手段のない住民への支援は特に重要だが、担い手不足が深刻化している。
「以前は学生や高齢者向けに市内までの送迎サービスや、沖縄TOYOTAさんとの実証実験としてシェアカーの導入を行っていました。そこで課題に浮かび上がったのが、事業継続のための経済的コストの高さでした。こうした事業は大きな利益にならないため、大手企業の参入は難しい。だからこそ、地域が抱える課題を直接的に解決できるのは、やはり住民の視点と力だと思っています」
かりまた共働組合は、こうした“採算が合わない”仕事を事業として成立させるため、宮古島市からの委託事業や補助金を活用し、作業を担う住民への報酬は原則「時給1,000円」に設定している。これは、労働への正当な対価であると同時に、地域内で雇用を生み出すことで、事業の持続可能性を高めているのだ。
また、現在は空き家となった古民家をリフォームし、かりまた共働組合が運営する住居や宿泊施設の準備を進めている。改修工事には、狩俣地域にゆかりのある事業者が関わり、地域事業によって雇用と経済循環を生み出す。
「狩俣には、困ったときに信頼して相談できる人が必ずどこかにいます。まさに、餅は餅屋。それぞれの強みや専門性を生かせる関係性が既にあるのです。大工仕事が得意な人、会計に明るい人、料理が上手な人。そうした個々の力を仕事として組み合わせることができれば、地域内で経済が循環し、移住者や二拠点生活者にとっても魅力的な“居場所”が生まれる。だからこそ、信頼でつながる関係人口を、もっと広げていきたいのです」

電気自動車での地域住民の送迎サービス。持続的な活動再開に向けて事業体制を整備している。
地域の未来を育む「信頼資本」。世代を超えた“本音の対話”
都会では薄れつつある、肩を寄せ合う距離感。狩俣には、その距離を越えて世代をつなぐ「信頼資本」が息づいている。かりまた共働組合の活動は、この信頼とつながりを土台に成り立ち、さらに広がろうとしている。
組合の中心メンバーは30〜50代だが、20〜30代で地域に関わるのはわずか10人ほど。それでも中高年世代と自然に協働できる背景には、住民同士の関係性の深さがある。
地域の先輩たちは若者の意見に耳を傾け、若者も意見をはっきり伝える。大人も子どもも生まれた頃から互いを知り、飲み会や地域行事では肩を寄せ合う間柄。歯に衣着せぬ対話を通して、先輩たちからは厳しくも愛のある助言をもらうことも多い。日々のやり取りが信頼と対等な関係を育ててきた。
根間さんは、この濃密な人間関係を他地域の人にも体感してほしいと願っている。地域住民から信頼を得ることは、新しく狩俣に関わる人にとって、仕事や居場所を築くための土壌になる。そして何より、狩俣に暮らす人そのものが、この地域の唯一無二の魅力なのだ。

地元漁港での場面。20代から80代までが一つのチームとなり、漁へ出る。 筆者撮影
地域資源を「仕事」に変える、かりまた共働組合の新たな挑戦
かりまた共働組合が目指すのは、狩俣の人・自然・産業といった地域資源を最大限に活かし、住民自らが持続可能な地域経営を築くことだ。大型商業施設のように多額の利益を追うのではなく、この地に根付く資源を“仕事”へと変え、地域内で経済を循環させる。
現在進行中の挑戦は、大きく三つある。
一つ目は、狩俣在住の漁師が収穫した名産もずくをブランド化し、ECサイトで販売する取り組みだ。狩俣のもずくは繊維が太く歯ごたえが良いことで評判があり、販売を通じて収入の向上とファンづくりを目指している。現在は50キログラムの活用からスタートし、今後さらなる販路拡大を図っていく予定だ。

組合員の中には、もずく漁師と兼務で活動するメンバーも在籍。狩俣産もずくのブランド力強化と、漁師やもずくのファンづくりに注力していく
二つ目は、空き家を地域の拠点に変える活用事業である。国土交通省の補助金を活用し、古民家を賃貸や民泊へと改修し、狩俣を訪れる人の滞在先とする。これにより地域の活性化を促し、移住のハードルを下げる狙いがある。根間さんは「完全移住ではなく、二拠点生活や月1回訪問でも良い。防犯や交流の役割も果たせるので、少しずつ関係人口を広げたい」と語る。

賃貸住宅用に、空き家を現在リフォーム中。一緒に地域を盛り上げる関係人口を受け入れる場としたい 筆者撮影
三つ目は、狩俣での暮らしを体感する滞在型研修の開催だ。地域住民との交流を通じて集落の空気感を肌で感じてもらい、関係人口づくりのきっかけとすることを目指している。住民と交わることで地域や人への理解が深まり、狩俣のファンづくりにもつながっていく。
これらの挑戦はすべて、狩俣に根付く資源を守りながら、新たな経済の芽を育てる試みでもある。
関係人口の創出で地域の子どもたちに夢ある未来を
かりまた共働組合の最終目標は、若い世代が安心して活動できる“土台”をつくることだ。狩俣に帰省したり、地域のために活動したい若者を支援し、子どもとおもしろい大人がつながる場づくりを構想している。
実際、狩俣で30年以上営業が続く宿には、何十年も前からさまざまな経歴や背景を持ったお客さんがリピーターとして訪れる。そのお客さんが結婚して親子で再訪し、地域の子どもたちと仲良くなることもめずらしくない。地域のコミュニティスペースとしての役割を果たしてきた宿のあり方を、かりまた共働組合として将来へ受け継いでいきたいと考えているという。
「地域内外の子どもと大人が手を組んで、新しいビジネスを生み出せたらおもしろいな、と。子どもたちは関心があることを自然と吸収するので、可能性は無限大。狩俣の大人は子どもが大好きで寛大なので、これも地域の強みとして活用していきたいですね。大人との出会いが子どもの世界や夢を広げ、いつか地域に還元してくれるかもしれないですよね」

かりまた共働組合の役割は、今後の狩俣を担う若者と子どもたちの可能性を広げていくことだと語る根間さん 筆者撮影
現在、狩俣の小中学校は複式学級で、廃校の危機にある。だからこそ、地域外から訪れる“おもしろい大人”が関係人口として関わることで、子どもたちの未来は広がると根間さんは信じている。今後はもずく漁体験や星空観察会など、地域産業や自然を活かした体験プログラムの提供も計画中だ。設立3年目を迎えた組合は、自治会活動を補い、地域に新しい担い手と活力をもたらそうとしている。
ここでの土台づくりは、子どもや若者だけでなく、地域に眠る資源を仕事として育てる挑戦へとつながっている。

サトウキビ畑が広がるのどかな集落の今後が楽しみだ 筆者撮影
日本の縮図「狩俣」から、私たちの未来を問う
狩俣が直面する課題は、決して他人事ではない。それは日本の多くの地域が抱える課題の縮図であり、ひいては、経済合理性ばかりを追い求めてきた現代社会そのものの写し鏡でもある。
「新しいことを生み出したわけじゃないんです。これは、かつて日本のどの地域にもあった、住民同士が助け合い、支え合う共同体の姿です」
根間さんのその言葉は、私たちに問いかける。効率や利益だけを物差しに、私たちは何を失ってきたのだろうか。そして、これからの未来に、何を手渡していきたいのだろうか。
かりまた共働組合の挑戦は、その答えが一つではないことを示している。地域の歴史に学び、そこに住む人々の顔を思い浮かべ、自分たちの手で未来をつくる。その小さな実践の積み重ねこそが、やがて社会全体を動かす大きなうねりになるのかもしれない。
「効率」よりも「関係性」や「必要性」を基準とすることで、利益動機だけでは拾えない地域のニーズを拾い上げ、地域にとっての価値を最大化するこの試みは、すでに外部からも大きな注目を集め、その有効性を証明し始めている。
この物語を、あなたはどう読み解き、自身の暮らしや仕事にどう活かすだろうか。狩俣の挑戦は、今、私たち一人ひとりにバトンを渡している。
【参照サイト】かりまた共働組合
【参照サイト】かりまたもずく
Edited by Erika Tomiyama