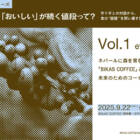IDEAS FOR GOOD2.0 危機を希望に。読者とともに「新しいメディアのかたち」をつくりたい〜IDEAS FOR GOODはクラウドファンディングに挑戦しています〜
2015年から、社会を「もっと」よくするアイデアを届けてきたIDEAS FOR GOOD。けれど、世界も、メディアのあり方も、この数年で大きく変わりました。私たちもまた「伝える」だけでは届かない時代の中で、迷いながら、探りながら、新しいメディアのかたちを模索しています。完璧ではない。でも、未完成だからこそ、まだできることがある。このメディアを存続させ、次の時代へと手渡していくために──どうか、この挑戦にご参加いただけたら嬉しいです。
▶️クラウドファンディングページも覗いてみてください。
「もし、コーヒー一杯が2,000円になったらどうする?」
そんな問いに、あなたはなんて答えるだろうか。
かつては贅沢品とされていたコーヒーは、今やいつも身近にある飲み物となった。しかし、その裏側にある生産地の現状や、気候変動がコーヒーの生産に与える影響の深刻化などはあまり知られていない。

そうしたなか、2025年9月、IDEAS FOR GOODは、「ネパールに森を育むBIKAS COFFEEと考える、未来のためのコーヒーの値段」と題し、イベントを開催した。【全6回体験シリーズ】あなたの「おいしい」が続く値段って?~作り手との対話から、食の“価値”を問い直す旅~の第一回目である。
会場は、東京都江戸川橋にあるコーヒースタンド「BIKAS COFFEE(ビカスコーヒー)」。ここでは、森を育みながら作物を育てるアグロフォレストリー農法で生産されたネパール産のコーヒーが提供されている。さらに、誰でも現地のコーヒーの木のオーナーになることができる「想いを植えるコーヒー植樹」やキャンピングカーで全国にコーヒーを届ける活動など、生産と消費の現場をつなぐ活動を行っている。
そんなBIKAS COFFEEとともに開催したイベントのテーマは、「未来のためのコーヒーの値段」。イベントの前半、ファウンダーの菅勇輝さんからは、同社が扱う豆の生産地・ネパールのリアルな現状や、気候変動の影響でコーヒーの供給が大幅に減少すると言われる「コーヒーの2050年問題」についてなど、多岐にわたる話を伺った。さらに、後半では、コーヒーと私たちの関係性を問いかける対話を通して、一人ひとりが新たな問いと出会い、向き合った。

会場にいなかったあなたも、自身とコーヒーの関係に想いを馳せながら、本記事を読み進めてもらえたら嬉しい。
消費者と生産者をつなぐ、BIKAS COFFEEが生み出す好循環
イベント前半では、BIAKS COFFEEの立ち上げ人である菅さんによるトークセッションが行われた。まずお話してくださったのが、BIKAS COFFEEの代名詞ともいえる活動「想いを植えるコーヒー植樹」について。年に数回、BIKAS COFFEEのスタッフとコーヒーの木のオーナーは、ともにネパールのコーヒー農園を訪れている。長年訪れてきたハルパン村と2025年に始まったダリンボット村という2つの村で、これまで計3,000本ほどのコーヒーの木を植樹してきたという。
日本で暮らす消費者と、ネパール現地の農家たち。普段顔が見えない人同士がつながることで、現地の村にも良い循環が生まれていると菅さんは言う。
「若いときにインドで出稼ぎをしていた一人の農家さんが、そこでコーヒーを初めて飲んで感動したことをきっかけに、自分の村でコーヒーを育て始めました。その方は、それまでは単に収入を得るために生産していましたが、日本から来るコーヒーの木のオーナーと出会っていく中で、『コーヒーの木が誰かの喜びに繋がっていると感じるようになった』と言ってくれるようになりました。
さらに、最近では農家さんたちの間で『あれやりたい、これやりたい!』と色々な想いが出てきています。コーヒーの生産量を増やしたいと、環境を汚染しにくいナチュラルプロセスという製法での生産に取り組む人が出てきたり、家畜の糞尿を肥料とするためにヤギを育てる人が出てきたりと、農家さんがやりたいことがどんどん生まれ、価値に変わってきています」
コーヒーを通して生まれ、日本中に広がる新たな価値
2019年の誕生から数年。今や多くの人を巻き込み、ひとつのコミュニティとして社会にポジティブなインパクトをもたらしているBIKAS COFFEEは、日本でも、コーヒーを通じて貢献を続けている。2024年にスタートした「BIKAS CAMPING CAR」では、スタッフとコーヒーの木のオーナーたちが、日本各地にBIKAS COFFEE、そしてネパールの発展を届けていく取り組みを行っている。

写真左・ファウンダーの菅さん
菅さんが持続可能なコーヒーを届け続ける理由。そこには、「誰かの暮らしを豊かにしていきながら、自分たちの生活も豊かにしていきたい」という想いがあった。
「コーヒーは日々、多くの人が手に取るもの。だからこそ、身近な一杯から自分がやりたいことが広がり、それが社会をよくすることにつながってほしいと思ったんです。単なるコーヒー屋ではなく、コーヒーにかかわる人のありのまま、ありたい姿、存在価値を認めながら、みんながやりたいことを形にしていく。このアクションを通じて社会に貢献できる関係人口を増やしていきたいんです。
また私たちは、木を植え、森を管理しながら、そのあいだの土地でいくつかの農作物を栽培するアグロフォレストリーという農法で生産を行っているのですが、最近は『アグロビレッジ』という言葉をよく使うようになりました。『本当の価値はどこにあるんだろう?』と考えたとき、本来、農村の自給自足の生活自体が、自分たちの生活を豊かにしていくようなものだと感じています。だからこそ、アグロフォレストリーとネパールの農村の暮らしが融合した『アグロビレッジ』という概念も届けていきたいと思っているんです」

BIKAS COFFEEのコーヒーを生産しているネパールのハルパン村
現地で活動を続けてきた菅さんは、ネパールのコーヒー生産地の様子を「農園というよりも、生活の中にコーヒーがあり、森が育まれているところに暮らしがある」と表現した。農と暮らしは地続きのようになっていて切り離せず、かかわり合っている。ネパールの農村のような持続可能な暮らしのあり方は、日本の地方にも残っているからこそ、そうした村の暮らしの価値が、コーヒーを通して間接的に伝わっていけばいい。そんなふうに菅さんは言葉を漏らした。
生産現場でリアルに実感した「コーヒーの2050年問題」
ネパールでも日本でも、コーヒーを通してさまざまな価値が生まれ、広がっている。その一つ、BIKAS COFFEEで販売されている「チェリーシロップ」は、本来捨てられていたコーヒーの実の部分を資源として活用して商品化されたもの。無価値だったものを新たな価値に変えた取り組みだ。この商品開発の背景には、2030年代以降、気候変動により生産適地が大幅に減少し、2050年にはその生産量が半減すると言われる「コーヒーの2050年問題」があった。
「ネパールの生産現場では、すでにコーヒーの病気が増え、収穫量がこれまでの3分の1ほどにまで減少しており、世界中でも同様の現象が起きています。年々収穫量が減り続けるなか、農家さんの収入を少しでも上げたいという想いもあり、コーヒーの実(コーヒーチェリー)を買い取り、シロップとして販売することにしました。収穫量の変化は、気候変動だけが要因だとは言い切れませんし、さまざまな要因があると思います。ただ、実際に収穫量は減っていますし、一杯2,000円になる日もそう遠くないでしょう」
近い未来、今まで通り、手軽にコーヒーを買うことはできなくなるかもしれない。だが、どんな未来が訪れても、BIKAS COFFEEは人々にコーヒーを届け続ける。なぜなら、本当に届けたいのはコーヒーではなく「理念」だから。農家さんに約束しているのは、コーヒーを通して「生き生きとした暮らしをつくっていくこと」だから。菅さんは、最後にこんな言葉でセッションを締めくくった。
「うちのコーヒーの価格は、大体一杯600円くらい。いくらネパールのコーヒーが良いものでも、安いコーヒーと比べたら値段は張るし、なかなか共感は得られにくいものです。ですが、私たちは、『内発的な発展(ネパール語でBIKAS)』を掲げており、一人ひとりの『やりたい』という気持ちが溢れていけば、味や値段、カフェインの有無ではなく、ストーリーを含めてその価値は広がっていくと考えています。
将来的にはコーヒーの値段は必ず上がり、気軽に飲めなくなるかもしれません。そんなときでも、コーヒーの品質を保ちながら、そこに込められた想いやストーリー、そして理念を届けていきたいと思っています」
「一杯2000円になったらどうする?」コーヒーをめぐるさまざまな問いと向き合う
一杯のコーヒーの裏には、さまざまな物語があり、かかわる一人ひとりの人生がある。単なる飲み物として接するだけでは知り得ない背景の物語に触れ、その価値に気付いたとき、『では、私たちはどうするべきか?』という問いが生まれてくるのかもしれない。
イベントの後半、参加者たちは、IDEAS FOR GOODが用意した、いくつかの「答えのない問い」を巡って対話を行った。
問いの内容:
あなたが支払うコーヒー代、一番受け取ってほしいのは?
コーヒーを買う時、何を基準に選んでいる?
一杯600円のコーヒー、ぶっちゃけ高い?安い?
コーヒーを飲むとき、何を考えて飲んでいる?
フェアトレードの「フェア」って何?
2050年、コーヒーが、一杯2000円になったらどうする?
あなたは、コーヒーに“何”を求めている?
明日から、コーヒーをどんなふうに飲んでみたい?
これらの問いと向き合いながら、それぞれが自分自身のコーヒーとの関係性を問い直したり、新たに浮かんできた問いの答えを探ったりと思い思いに言葉を紡いでいた。ある参加者からは、「お金を多く払えば、それは『フェア』なのか。ほかに対価となるものはないのか」「みんながコーヒー(モノ)のストーリーを語るようになった世界では、どのように価値を判断することができるのか」「コーヒーは本当に嗜好品なのか」といった、本質を問う声が上がっていた。

それを聞いた菅さんは、私たちに、そして自身にこう問いかけた。「この世界に、コーヒーは必要でしょうか?」と。今や人々のそばにあり続けるコーヒーは、嗜好品という概念を超え、欠かせないものになりつつある。だからこそ、その存在価値改めて問い直すことが大事なのかもしれない。菅さんは、最後にこう締めくくった。
「この世界にコーヒーが必要かを決めるのは、僕たち自身の覚悟であり、それを行動で証明していくだけです」
編集後記
筆者自身、参加者の問いについて考えを深めるうちに、さまざまな問いが湧き上がってきた。自分に問いかければ問いかけるほど、また新しい問いが生まれてくる。無限ループのようだが、そんなふうに問いと向き合い続けることから、私たちは逃げてはいけないのだろう。そうやって、ほんの少しずつでも、社会はよくなってくような気がしている。
「新たな取り組みが生まれ、価値が広がっていくにつれて、私たちが飲むコーヒーの奥行きが深くなっていくと感じます」
菅さんはトークセッションの中でそんな言葉を残していた。「物語に触れ、想いを馳せる」そんなコーヒーの飲み方をしたとき、確かに味わいは変わってくるだろう。豆の品質や淹れ方にかかわらず、まるで一人の人生のように深く、豊かな味わいが心と身体のすみずみに広がっていくに違いない。
「あなたはこれから、どのようにコーヒーを飲みたいですか?」
▶次回の【全6回体験シリーズ】あなたの「おいしい」が続く値段って?~作り手との対話から、食の“価値”を問い直す旅~は、【10/26開催】都市の屋上農園を見に行こう!コミュニティガーデンの実践から学ぶ、“食をつくる”がある暮らし。詳細・お申し込みはこちらから
【関連記事】【9/22開催】ネパールに森を育む「BIKAS COFFEE」と考える、未来のためのコーヒーの値段【全6回体験シリーズ Vol.1】
【参照サイト】BIKAS COFFEE