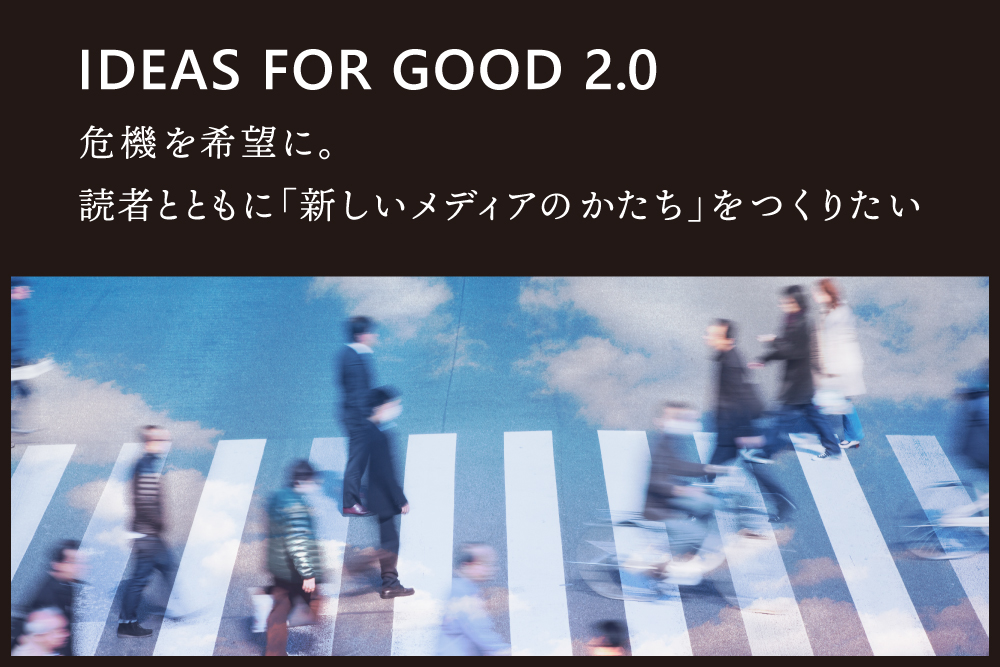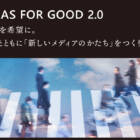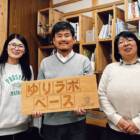IDEAS FOR GOOD2.0 危機を希望に。読者とともに「新しいメディアのかたち」をつくりたい〜IDEAS FOR GOODはクラウドファンディングに挑戦しています〜
2015年から、社会を「もっと」よくするアイデアを届けてきたIDEAS FOR GOOD。けれど、世界も、メディアのあり方も、この数年で大きく変わりました。私たちもまた「伝える」だけでは届かない時代の中で、迷いながら、探りながら、新しいメディアのかたちを模索しています。完璧ではない。でも、未完成だからこそ、まだできることがある。このメディアを存続させ、次の時代へと手渡していくために──どうか、この挑戦にご参加いただけたら嬉しいです。
▶️クラウドファンディングページも覗いてみてください。
編集会議をするとき、イベントの企画を立てるとき、メディアの方向性についてミーティングをするとき。IDEAS FOR GOOD編集部のメンバーが意見を交わす際に、何度も繰り返し登場する言葉があります。それが、「対話」です。
私たちは、自分だけの「正しさ」を振りかざして誰かを傷つけないように、小さな声を取りこぼさないように、もっとほかの見方はないか探求できるように……様々な理由から「対話」が必要だと考えてきました。
そんななかで、ある日、編集部員の相馬がこう呟いたのです。
「私たちはもう何年も“対話を大切にしたい”と言い続けているけれど、そもそも“対話”って何を指すんでしょう?」
今回の記事企画は、そんなふとした一言から生まれたものです。この問いを出発点とした「対話についての対話」の内容をもとに、私たちが大切にしたい「対話」について綴ってみたいと思います。
まず、「対話」と意味の似ている言葉「会話」「議論」との違いを見てみましょう。まず「会話」は、親しい人との日常的なやり取りを指します。共感や安心感を得ることが目的で、意見の一致や深い理解を求めるものではありません。一方「議論」は、主張をぶつけ合い、より正しい答えや結論を導くための行為です。論理や根拠をもとに相手を説得することが重視されます。
これに対して「対話」は、異なる立場の人が互いの考えを持ち寄り、結論を急ぐのではなく、深く理解しあおうとする営みです。
物理学者デヴィッド・ボームは、著書『On Dialogue』の中でこう述べています。
“We are not trying to change anybody’s opinion. Conviction and persuasion are not called for in a dialogue.”
(対話において)私たちは、誰かの意見を変えようとはしていない。確信や説得は、対話には必要とされないのだ。
──『On Dialogue』by David Bohmより
ボームにとって、対話とは勝ち負けを決めることではなく、それぞれの意見や信念をいったん宙に浮かせて見つめることでした。
また、劇作家の平田オリザさんはこのように述べています。
「『会話』は、価値観が近い人同士のやり取り。『対話』は、価値観の異なる人とすり合わせる営みです。AとBの論理がすり合わさり、Cという新しい概念を生み出すのが対話。つまり、対話の後には自分も相手も意見が変わっているのが前提なんです。」
──【上手に伝えたくて】第1話:コミュニケーションは、能力じゃなくてモチベーション。(北欧、暮らしの道具店)より
私たちは、今、「対話」を「相手を変えようとするのではなく、自分の考えや固定観念を一度脇におろして、まっすぐに相手の言葉を聞き、自分の価値観を変えること、あるいは相手とともに新しいものの見方を見つけること」なのではないかと解釈しています。

私たちがつくりたいのは、「正しさ」を競い合いながら一つの答えを出す場ではなく、互いの声に丁寧に耳を傾けられる場です。自分と正反対の人と考えを共有することはもちろん、近しいと思っている人たちの中にも多様性があり、異なる価値観があることを理解したいと思っています。100%わかった気になることや、なんとなく共感して終わることを避け、様々な声にまっすぐ向き合いたいのです。
IDEAS FOR GOODには、「社会をもっとよくするソーシャルグッドなWEBマガジン」というキャッチコピーがあります。そんなコピーの通り、私たちは常々世界を「より良くしていきたい」と思っているわけですが、そもそも「良い」とは何なのでしょうか。きっと、それぞれの人がそれぞれの「良い」を思い描いていると思いますが、そのイメージは少しずつ異なるはずです。
だからこそ、それぞれの「良い」を紐解き、理解しあおうとすること。そして、できる限りすべての人を包括できるような「良い」を探求することが、「対話」の大切な役割なのではないかと思います。
社会に「良い」を実装していくために交わされるのが、最適解を導き出すための「議論」ですが、その前に必要なのが互いの前提や価値観を理解し合うことです。建設的な議論を生むための「前段階=対話」のプロセスにも、私たちはしっかりと向き合いたいのです。
そしてもう一つ──私たちは「わかりあうこと」だけを目指しているわけではありません。「対話」とは、あなたが正しいとも、私が正しいともはっきりさせない、つまり「わからない」を許容することでもあります。むしろ、「わかりあえなさ」をそのまま抱えながら、結論を急がずに「もやもや」とした感覚を抱えていられることこそが大切なのだと思います。その「もやもや」にこそ、まだ言葉になっていない問いや、新しい視点が眠っているはずです。
私たちは、「対話」とは、誰もが社会の作り手になれる営みだと考えています。「対話」の先に決まった答えがないからこそ、誰もが問い、声を発し、その場に関わる余地があるからです。IDEAS FOR GOODは、完璧な答えを示すメディアではなく、問いを手がかりに一緒に考え、まだ“わからない”ことの中にある可能性を一緒に探っていくメディアでありたいと思っています。わかりやすい正解が求められるファストな時代において、あえて「わからない」領域に目を向けること。その中にこそ、次のよりよい社会を形づくる可能性があるのではないでしょうか。
*IDEAS FOR GOODでは、そんな「対話」を大切にする場をもっと増やしていくために、クラファンに挑戦中です。よろしければ、プロジェクトページを覗いてみていただけると嬉しいです。