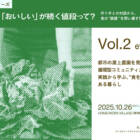孤独や孤立、環境汚染、人口減少、雇用機会の減少、コミュニティの希薄化……都市であれ、田舎であれ、私たちが生きる地域にはさまざまな課題がある。そうした複数の課題を一度に解決してくれる魔法のようなものがあるとすれば──。

「生ごみには、地域のあらゆる社会課題を解決する力があります」
そう話すのは、「都市から小さな循環を作り、拡げていく」ことを目指すローカルフードサイクリング株式会社(以下、LFC)の代表・たいら由以子さん。同社は、バッグ型コンポストの開発などを通して、土の少ない都市でもコンポストを実践できるように普及活動を行い、生ごみの堆肥化(コンポスト)に隠された魅力を世界中に伝えてきた。
IDEAS FOR GOODが企画する全6回の体験イベントシリーズ「あなたの「おいしい」が続く値段って?~作り手との対話から、食の“価値”を問い直す旅」。第二回目のテーマは、「都市の循環とウェルビーイング」。当日は、LFC代表のたいら由以子さんに、活動を始めたきっかけから食と自然と生命のつながり、コンポストを通した循環するまちづくりへの想いまで話を伺った。さらに、イベント後半では、会場となったHOME/WORK VILLAGE屋上のコミュニティガーデンの見学や、世田谷で「循環するまちづくり」を実践するアイデアを出し合うワークショップを実施した。

自分のまちには、どのような課題があり、どのような資源が眠っているだろう。
「生ごみ」が「命の源」に変わる瞬間。父の食事療法で気づいた自然の「基盤機能」
たいらさんはなぜ、「生ごみ」という一見ネガティブなイメージを持たれるようなものに光を当てて活動を始めたのか。イベントの冒頭、その理由を教えてくれた。「食べ物は、『命の源』です」と話すたいらさんが活動を始めたきっかけは、末期がんの父親の食事療法を始めたことだった。福岡市内で無農薬野菜を探し回ったが、なかなか見つからない。そこで、勉強しながら自ら畑を耕し、野菜づくりをスタートしたという。
「父を家に連れて帰ったのに、翌日死ぬんじゃないかという焦りと、世の中どうなってるんだろうという怒りで、どうしていいかわからない状態でした。少しずつ野菜が取れるようになると、その野菜を食べた父の顔色はどんどん良くなって、2年間寿命が延びたんです。食べ物こそが『命』であることを身を持って感じるとともに、今の社会の食や環境のシステムは、なんて持続不可能なのだろうと思いました」

とれたてのハーブを使ったハーブウォーター
若い頃、サーフィンやスキーなど自然のなかでのアクティビティを楽しんでいたたいらさんは、「自然が好きと言いながら、綺麗な野菜や水をスーパーで買い、ごみを捨てる。まるで自然を搾取するような生活をしていた」と振り返る。そんななか、父の病気をきっかけに、食の大切さ、そして現代人のライフスタイルについて構造的な問いを抱くようになったそうだ。
「父の栄養療法中、さまざまな地域を訪れ、都市部ではかかわりがなかったような仕事に触れ、『自然の機能』の大事さに気付かされました。たとえば、雨水は30~40年かけて濾過されて小川になり、海に流れていきます。そこには山の環境も大きくかかわっているのですが、今は針葉樹ばかりで広葉樹が減り、有機物が地面に還らなくなっている。腐葉土が少なく、畑の土も運動場みたいに固い土ばかりです。
そうした基盤機能や全体の機能が下がっていることも、気候変動の影響を悪化させる要因の一つ。土は、すべての生命を還元したり水を浄化したりと、とても大事な機能を果たしていますが、今その機能がなくなってきています。情報は早いけれど、自分たちとモノ、環境、さまざまなつながりが見えなくなり、仕組みもわからないことが多い。私たちは、その構造を考えることすらしなくなってしまいました」

LFCワークショップの様子
現代の暮らしが、自然が持つ土壌や循環機能を劣化させるだけでなく、人間の健康を蝕んでいる。そうたいらさんは指摘する。
「コンポストの普及のためにモルディブを訪れたとき、住民たちにコンポストの方法を教えると病院に入院する数が半分になったんです。暮らしがシンプルになると、栄養や目に見える健康につながっていく。今は暮らしが複雑だから、新たな病気や感染症など原因不明のものも増えています。そんな今こそ、土地から循環をつくっていくことが大切だと思っているんです」
人々をつなぐ「癒しの場所」
コンポストを通じた活動は、人々の健康を守るだけでなく、コミュニティを再生させる役割も担ってきた。たいらさんが福岡で、町内会長や高齢者などと連携してつくったコミュニティガーデンでは、参加者、そして地域のウェルビーイングが劇的に改善したという。
老人性うつだった人、旦那さんが亡くなり引きこもりがちだった人、転倒のリスクから外出を禁じられていた人……。なかなか外に出られなかった人たちも、「ここなら来れるから」と来てくれるようになったそうだ。また、野菜の栽培をきっかけに、公民館のサークルとつながり、空き家を活用したお弁当の配食サービスなども誕生したという。

単なる菜園ではなく、「癒しと楽しみの場」であり、「心理的な安全の場」としても機能するコミュニティガーデンを都会にも増やしていきたい。そうすれば、さまざまな問題が一度に解決できるのはず。そんな想いから、LFCが提唱してきたのが、「半径2キロの循環」。「2キロ」というのは、中学生の行動範囲やニホンミツバチの行動範囲とされており、物事を「自分ごととして捉えることができる」規模感として設定したという。
「毎日ご飯を食べる人は世界中にたくさんいるのに、循環の作り手となる人がほとんどいない。だからこそ、コミュニティガーデンを中心に、循環を作る側を増やしていきたい。食材を作る生産者、健康を考えて調理する人、生ごみでコンポストをするだけの人がいてもいいと思うんです。食材が2キロから30キロ圏内で入手できるようになって小さな循環が生まれていけば、身体的にも肉体的にも健康で、食で病気を予防して寿命が延びる社会にもなっていきます。
今後、世界では人口の3分の2が都市部に居住すると言われています。実際に私も色々な国を訪れてきましたが、都市化すると食糧難になり、どんどん都市の環境は悪くなっていきます。だからこそ、都会から小さな循環を作る流行りを生み出していきたいと思っているんです。土をつくったり野菜を育てたりコンポストしたりしながら、みんなで話す仕組みができるといいのではないでしょうか」
世田谷から循環するまちづくりを。アイデアを生み出すワークショップ
トークセッションの後は、そんな小さな循環を育む具体的な場として、HOME/WORK VILLAGEにあるルーフトップファーム「ART FARM IKEJIRI」を見学した。仲間と共に野菜や果物、ハーブ、花を育てたり、空を眺めてぼーっとしたり、週末にはマルシェやワークショップ、アートイベントを楽しんだりする都会の”里山”のような場所、人と自然がつながるサードプレイスにしていきたいという。

屋上にある「ART FARM IKEJIRI」。誰でも会員になることができる。今は、米や野菜に養蜂、ホップ、ワイン用のブドウまで、さまざまな作物を育てているという。

会員の方が、家庭でできた生ごみ堆肥を大きなコンポストに入れ、菜園に利用
見学の後は、ガーデンで獲れたフレッシュなルッコラを使った軽食を味わいながら、たいらさんが開発した「半径2キロの循環を考えるワークショップ」を行った。お題は、「世田谷を中心に循環するまちをつくるには?」。参加者たちは、世田谷から2キロ圏内の渋谷や下北沢エリアまでの課題と資源を挙げながら、循環の起点となりうるコンポストの設置場所についてアイデアを出し合った。

<まちの課題と資源>
・課題:ご近所付き合いの希薄さ、子どもの土いじりできる場の不足、不登校の子どもの増加など
・資源:飲食店が多い、夜もあかるい、人口が多いなど<参加者から出たコンポストの設置アイデア>
・日常の動線に設置する: マンションの屋上、スーパーの駐車場や駅の高架下、飲食店の近く、コインランドリーなど。わざわざ行く場所ではなく、「いつも通るところ」に設置することで、日常に循環を溶け込ませる。
・多機能ハブとしての活用:土日に人が集まりやすい図書館や公共施設の隣に設置し、農作業に興味がない人もイベントを通じて巻き込む。
・機能の融合:飲食店から出る食品残渣や、犬の散歩の際の排泄物などもコンポストで集め、地域資源として活用する。
事業者や個人、学校、行政……多様なステークホルダーが交わりコンポストを進めていくことができたら、つながりやコミュニティが生まれ、そこに暮らす一人ひとりの生活は豊かになっていくだろう。多くの人が行き交う都市だからこそ、一度生まれた輪は加速度的に広がり、ぐんぐんと人にも地域にも幸せが広がっていくのかもしれない。
LFCは今後、循環を全国に広げるため、堆肥の価値やソーシャルインパクトを伝える「コンポストアドバイザー」という新しい職業をつくり、養成講座をスタートさせる予定だ。2030年までに、1,500ヶ所の循環型コミュニティガーデンをみんなでつくる。そんな目標を目指しながら、コンポストを日本の文化にするためのたいらさんとLFCの挑戦は続いていく。