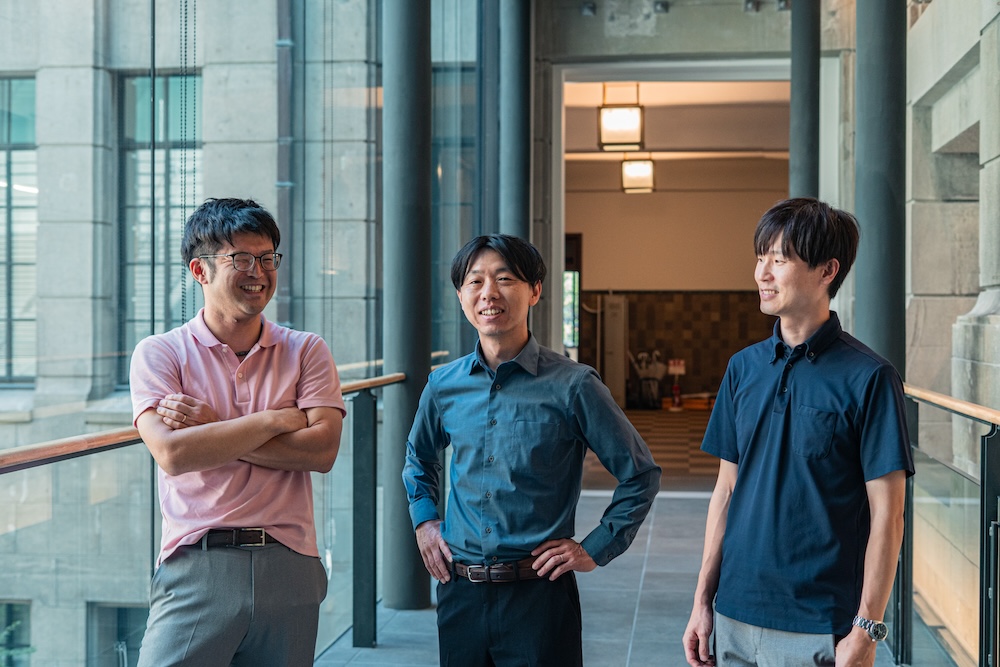単にモノを繰り返し使うことだけが、サーキュラーエコノミーではない。そこには、受け継がれる技術や文化、長い時間をかけて培われた知恵や関係性が土台として存在する。
そんな学びを得るべく、京都市主催・ハーチ運営の実践型サーキュラーエコノミー事業開発プログラム「Circular Business Design School Kyoto(以下、CBDS Kyoto)」の参加者は、秋雨の降る京都市内へ繰り出した。
今回のフィールドワークの舞台は、京都の街なか。室町時代から続く北山杉、顧客と共に作ることに挑戦する数奇屋大工、神社と共にあるあぶり餅屋、そして都市で自然再生に挑む公園。循環が受け継がれ、生まれる現場を巡ることで、過去から未来へと続く「循環」の多様な姿を目の当たりにした。本記事では、そんな1日の学びをお届けする。
北山杉の源へ。600年前の技術に学ぶ、自然との共生の態度
京都市内からバスに揺られ、北へと向かうこと30分。目的地は、京都・中川の中川八幡宮にある北山杉の「親杉」と、その杉から数寄屋(すきや)を手がける大工・簱邦充(はた・くにみつ)さんの工房だ。この日のナビゲーターであるCOS KYOTOの北林さんが「オチを最初に言うと、北山杉は全部クローンなんです」と語り始めた。
そのクローンとは、挿し木技術のこと。室町時代に編み出されたと言われており、ハーバードとMITの博士課程を持つ研究者が「人類初のクローン技術を見に行きたい」と問い合わせてきたほど、世界的に見ても稀有な知恵だという。
北林さん「技術をいかに応用して自然と付き合っていくのかを考えなくては、やはり循環を生むことはできない。その原点がこの北山杉に見られるのではないかと思っています」
中川八幡宮に到着し、中へ歩みを進める。すると突然、木々の中に佇む一本の巨大な杉の木が見えてきた。
簱さん「これが北山杉のオリジン(原型)と言われていて、樹齢は600年ぐらいあります。北山杉は、枝を切ってそのまま地面に刺すとまた同じクローンができる挿し木という方法で昔から生産されています」
この生産方法は、表面がツルッとした磨き丸太や床柱によく使われるボコボコとした「天然絞り」などの特殊な形質を持つ木材を量産するために確立されたもの。DNAという概念すらない時代に、自然の力を深く理解したことで生まれた。人々はこの親木にしめ縄を飾り、感謝を捧げながら、この地で林業を営んできたのだ。
しかし、この知恵や技術も、人の手が入り続けなければ維持できない。山の斜面には、手入れされた北山杉が広がる一方で、枝打ちがされず放置された杉林も散見されるそう。林業のために拓かれた杉林が放置されると、もとの生態系に戻るわけではなく、多様性の乏しい暗い林となり野生動物を街中に導く要因にもなってしまう。
日本全体の林業は安価な外国産木材に押された時代が続いたせいで、現在は、山から木を切り出し、加工し、街へ届けるという産業システムが寸断されてしまったという。簱さんはその現状を憂う。
簱さん「日本は木が多くあるのに海外から輸入しています。これはおかしなことが起きてると思うのです。なぜ日本で循環しないのかなと、ほんまに思います」
一方で、北山杉にはまた異なる問題があるという。それは日本経済の衰退と共に和室離れが進み、茶道人口も減ったこと。これにより、現代では北山杉を使う建築が激減し、その素材自体の存続が危ぶまれている。
先人が自然から学び得た技術と、そこから切り離されたことで生じる現代の課題。北山杉は、木々と人間の交わりの有無で生じる循環の光と影を突きつけていた。
伝統とは、本質を守り新たな価値を紡ぐこと
北山杉の林を後にし、簱さんの工房を訪れた。籏さんは茶室に代表される数寄屋建築を専門とする「数奇屋大工」だ。しかし、手掛けているのは茶室だけではない。先人から伝わる技術を現代建築に合わせて融合させ、人々の心を掴んでいる。
例えば、とある寿司屋の内装では、刈り取った稲を干すための支える柱「稲木(いなぎ)」という名称の栗の古材を、象徴的に一本だけ配置した。

Image via 京こと株式会社
簱さん「寿司屋さんは米が大事なので、米を支えてるという意味で、どうしてもこの一本を柱として入れたかったのです。これは奇をてらうことではなく人の営みでできた侘びた素材に意味を持たせて使うことが数奇(好き)な私なりの遊び心です。普段私たちは『主張し過ぎない建築』というものを目指しています。自然と共存し、自然素材の造形美を残しつつあたかも森や山にいるように感じながらも美意識が詰まっている建築。場のメインを守りながら自然との融合を図る感覚でやっています。数奇屋・茶室など、その主張し過ぎない建築に使われる木材の代表格が北山杉磨き丸太なのです」
素材の声を聴き、空間全体の調和を考える。そのバランス感覚が、数奇屋大工の真髄なのだろう。
近年、簱さんは阪神淡路大震災の教訓から振動実験が行われたときに造られた国宝茶室・待庵の写しを廃棄処分から救い出し、それを「T庵(踊る茶室)」と名付けた。この茶室をヴェネツィアのビエンナーレに持ち込むことも検討されていたという。また、伝統建築の耐震性を科学的に証明するプロジェクトにも関わったそう。石の上に柱を置くだけの「免震構造」は、地震の揺れを受け流すための先人の知恵なのだ。
伝統を守ることは、頑なに一つの方式に固執することではない。本質を理解・維持し、現代の技術や感性と融合させ、新たな価値を創造し続けていくものなのかもしれない。
一度人が手を入れた自然は、人が関わり続けることで循環し、健全な状態が維持される。籏さんのように木々に手をかけ続ける職人の存在は、人と自然が疎遠になることで北山杉が直面する環境課題への一つの応答の仕方を示すのだ。その姿勢に学び、途絶えつつある「自然と共にある循環」をどう現代社会で受け継ぐことができるのだろうか。それを未来へ繋ぐためにはその価値をどう表現できるのだろうか。
すぐには言語化し難い問いを、それぞれが五感で受け取っていたようだった。
地域に寄り添い、千年続く経済圏を紐解く
続いて訪れたのは、北区紫野にある今宮神社。神社の境内を抜けると、そこには向かい合って立つ、平安時代・長保2年(西暦1000年)創業のあぶり餅屋「一文字屋和輔(いちもんじやわすけ)」がある。通称「一和(いちわ)」と呼ばれ親しまれている。
この店の始まりは、祭りの際に神様にお供えしたお餅のお下がりを、参拝者に振る舞ったこと。商売は、あくまでも奉仕から生まれたものなのだ。
25代目女将、長谷川奈生さんが出迎えてくれた。
長谷川さん「ご神饌をあげてそのお下がりをいただくのですが、お餅が硬いので、まず叩いてちっちゃくして焼いて。当時はお砂糖が手に入らなかったので、庶民は白味噌だけの甘さでいただいたら、疫病が鎮まったというのが始まりです。
毎年の祭りには未だに朝早くから起きてご神饌を持っていきます。私たちが動かないとお神輿が動かない。これが代々続くということが、ありがたい」
千年を超える歴史の中で、存続の危機は何度もあったという。店を離れて働き生計を支える人と、ご奉仕のために家を守る人と、役割を分けることでそれを乗り越えてきたそうだ。
また保健所から軒先での餅作りについて衛生面での指導を受け、「千年間、これでお腹を壊した人はいない。保健所よりうちのが古いよ」と笑みをこぼしながらも、現在は屋内での製造へと変化した。時代に合わせて変えていく柔軟さも必要となる一方で、変わらないものが守られている。
長谷川さん「根本は変わらず置いたまま、その時そのときの時代に沿えばいい。ただ、1本の筋だけは入れといてもろて。そうでないと事業が折れる」
ただ事業を続けることが目的なのではない。地域の人に必要とされ守るべきものを守ったからこそ千年続いた。一和の歴史は、経済と文化、コミュニティの調和を映し出しているのかもしれない。
ゼロから「いのちの森」を取り戻す、梅小路公園30年の実験
フィールドワークの最後に、一行は梅小路公園へ向かった。かつて広大な操車場だったこの場所は、30年の時を経て、自然豊かな公園へと生まれ変わった。
「結論として、自然は取り戻せます」という北林さんの言葉と共に公園を進み、奥にある「いのちの森」へと足を踏み入れた。ここでは、人の手による管理を最小限にとどめ、土地本来の生態系を復元するためのさまざまな実験が行われている。
30年前はコンクリートで固められていた場所で、今では600種以上の植物、80種の鳥類、380種の菌類が確認されている。都市の真ん中で、生物多様性が着実によみがえっているのだ。
一方で、公園内の別のエリアでは、土壌が固く締まり、草木も生えない場所もある。そこで北林さんたちが取り組んでいるのが、市民参加型の土中環境改善ワークショップだ。
まず木の周りに杭を打ち、土の中に水と空気の通り道を作る。杭の周りに剪定枝などを格子状に組み(しがらみを作り)その中に落ち葉を詰める。すると、微生物が落ち葉を分解して土中の栄養が豊かになるのだ。こうして、雨水が染み込まず固まっていた土がほぐれ、再び緑が芽吹き始めるという。
北林さん「人間の手を入れて、ちゃんと生物が生きられる状態を作ってあげたら、必ず植物とか動物が応えてくれるんですよね。生きられる環境を整えてあげたら、みんな生きられるんですよ。人間でも一緒です。都合の良いように植物を生やすことはなかなかできなくて、やはり環境を整えることが大事です」
もう一つ課題となっているのが、公園内で開催されるイベントの食品ロス。これを堆肥化して花壇や京都水族館の里山エリアなどで再利用する敷地内での資源循環を目指す「資源がくるりプロジェクト」が進んでいる。ところが「どうせ余ったらコンポストするのだから」と、食品を過剰に発注する出店者が現れたそう。無駄をなくすための仕組みが、かえって食品ロスを助長しかねない状況だという。
北林さん「本来は、どうしても出てしまうごみはコンポストして再利用し、ごみをゼロにしようという意図で始まったのに、その思いを伝える努力を怠ると、すぐに楽な方に流れてしまうんですよね。
これではコンポストに取り組んでいる皆さんの気持ちのサステナビリティが続かない。だから、仕組みを整えるとか、良いことをしているだけでは駄目で、思いが続くように楽しめる形を作らないといけない。今そんな課題に取り組んでいるところです」
梅小路公園での取り組みは、自然再生の希望を示している。それと同時に、やはり仕組みや技術だけでは解決できない、人の意識や行動変容という、サーキュラーエコノミーの実装に向けて乗り越えるべき課題も突きつけたようだ。
未来の世代へ、私たちは何を繋ぐのか
1日の終わりに、参加者たちはこの日の学びを振り返った。気づきとして挙がったキーワードは「揺れながら循環する柔軟性」「生活や文化との再接続」「役割分担と適“材”適所」……多様な観点が飛び交う中、ある問いが投げかけられた。
「果たして本当に千年続ける必要があるのか。何か意味があって必要とされていたから、千年結果的に続いたという方が大事じゃないかと感じた」
北山杉も、数奇屋大工・簱さんの技も、一和のあぶり餅も、続けることだけを第一の目的にしてきたわけではない。自然と向き合い、人の想いに応えながら、コミュニティに奉仕してきた結果として、今に繋がっている。梅小路公園の活動は、その入り口に立っているのかもしれない。
その関係性を築くためのツールのいち要素となっていたのが、循環に通ずるものだったように思い出される。事業を個としてだけで捉えるのではなく、自身がどのような関係性に支えられており、それを次の世代に繋ぐための振る舞いが事業となる。この結びつきの総体が、事業として、また地域としてモノが循環することになるのではないだろうか。


経済合理性だけを追求するのではなく、結果として経済的にも維持できるために、どんなエコシステムの中で自らのビジネスの循環を位置づけるのか──京都の街なかで得た問いを胸に、CBDS Kyotoの探求は続く。
次回は2回目のフィールドワークとして京北に赴く予定だ。生活圏に静かに根付く循環の源泉には、どんな自然と人の営みがあるのか。引き続き記事を通してレポートしていく。
Circular Business Design School Kyotoとは
京都には1200年の歴史の中で育まれた「しまつのこころ」や循環型の暮らし、モノづくり文化など、時代を超えて輝き続ける資産がある。気候変動や生物多様性の保全など地球規模の課題が深刻化する中で求められる循環型の未来を実現するには、これらの叡智を現代に活かし、未来につなぐ創造力が必要だ。そこで、IDEAS FOR GOODを運営するハーチ株式会社では、京都というまちに根付く循環型の叡智と最先端のサーキュラーエコノミー知見に基づく未来志向を掛け合わせることで、ともに欲しい未来を描き、実現するための学習プログラムを2025年10月より開始。「Decode Culture, Design Future 叡智をほどき、革新をしつらえる」──伝統の先に続く循環型の未来を、京都から。
ウェブサイト:https://cbdskyoto.jp/