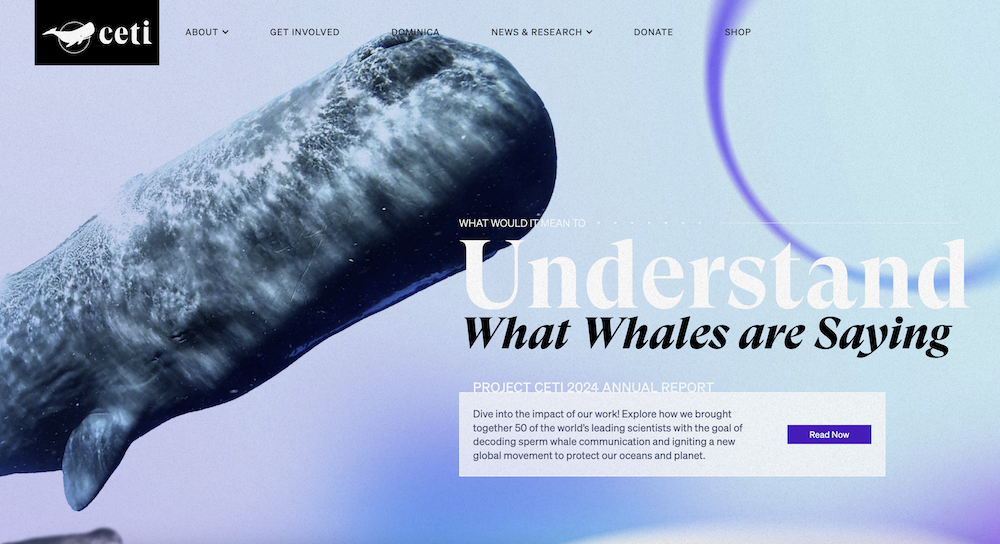気候変動や生物多様性の損失など、地球規模の危機の根源には「人間中心主義」があると指摘されている。しかし、頭では理解できても、日常に根付く社会の仕組みや当たり前に続いてきた慣習を、急に転換させるのは簡単ではない。
一方で、そんな視点の転換をそっと後押しする概念やフレームワークも注目され始めている。その一つが「More Than Human(モア・ザン・ヒューマン)」という概念だ。
ニューヨーク大学(NYU)ロースクールを拠点とする「More-Than-Human Life(MOTH)プログラム」も、この概念を社会へ届けようと活動する組織の一つ。法、アート、科学、そして先住民の知恵といった多様な分野を繋ぎ、人間と人間以上の生命、それらを取り巻く生態系全体の権利とウェルビーイングの向上を目指している。例えば、彼らはこう問いかける──「森が、楽曲の『著作者』になることはあり得るのか」。
あなたなら、これにどう答えるだろうか。そしてなぜ、そう答えるだろうか。
この記事では、MOTHプログラムの創設者であるNYUの法学教授、セサル・ロドリゲス・ガラビート氏への取材を交えながら、モア・ザン・ヒューマンという概念を紐解いていく。記事を読み終えたとき、その質問への自分なりの答えに一歩近づけるかもしれない。
話者プロフィール:César Rodríguez-Garavito(セサル・ロドリゲス・ガラビート)
 地球の権利に関する学者、弁護士、ニューヨーク大学ロースクールのMOTHプログラムの創設ディレクター。同大学法学部教授であり、地球の権利研究行動(TERRA)クリニックのディレクターも務める。気候正義、先住民族の権利、自身が提唱する「more-than-human rights」などに基づき新たな課題解決策や法的措置を世界で推進。こうした貢献は、ロンドン・デザイン・ミュージアムの「More-Than-Human Fellowship」や、MUSEUM FOR THE UNITED NATIONSの「Top 10 Culture for Impact 2024」に選出されるなど、高く評価されている。
地球の権利に関する学者、弁護士、ニューヨーク大学ロースクールのMOTHプログラムの創設ディレクター。同大学法学部教授であり、地球の権利研究行動(TERRA)クリニックのディレクターも務める。気候正義、先住民族の権利、自身が提唱する「more-than-human rights」などに基づき新たな課題解決策や法的措置を世界で推進。こうした貢献は、ロンドン・デザイン・ミュージアムの「More-Than-Human Fellowship」や、MUSEUM FOR THE UNITED NATIONSの「Top 10 Culture for Impact 2024」に選出されるなど、高く評価されている。
「モア・ザン・ヒューマン」の核心とは?
気候危機や生物多様性の損失に社会の意識が向き始めた今、モア・ザン・ヒューマンという概念が重要となってきている。直訳すると「人間以上」という意味になるが、この言葉は何を意味し、どんな社会の切り取り方を提案するのだろうか。
「モア・ザン・ヒューマンという概念は、人間が『生命の網の目(web of life)』の一部として組み込まれているという前提に立ちます。そこには人間だけでなく、人間以外の多種多様な存在やその集合体が含まれ、動物、木、川、森、菌類、植物などと相互に繋がり、依存しているのです。
そんな人間と人間ではない存在のあいだの根本的な相互依存を、個々に切り取らず、その集合体を1つの存在として理解するという考え方が、モア・ザン・ヒューマンが意味するものです」
この言葉は、人間中心的な視点を乗り越えようとする姿勢が特徴だ。
「『人間と環境』『人間と自然』という表現は、人間以外の世界を、あくまで人間の背景として捉える見方です。モア・ザン・ヒューマンという言葉は、そうした二元論を避け、人間が『生命圏』という人間よりも大きなものの中に埋め込まれ、そこに属しているという現実を明確にしようとするものです」
こうした考え方は決して目新しいわけではなく、仏教やタオイズム(道教)といった東洋思想、そして世界中の先住民の伝統文化などに見出すことができるという。
人間があたかも単体で存在するかのように表現するのではなく、相互につながり合い、依存し合い、その関係性によって全体を形づくる前提に立って、物事を表現し直すこと。それが「モア・ザン・ヒューマン」という視点の核心なのだ。
理論と社会の隔たりを繋ぐためのアクションへ
そんな世界の捉え方を、実社会での仕組みづくりやアートを通じて伝えようとするのが、セサル氏の立ち上げた、MOTHプログラム。人間も、人間ではない存在も含め、すべてを支える「生命の網の目」の権利とウェルビーイングを向上させることを目的に行動する、分野横断的な組織だ。
そのアプローチは、法律、菌類学、植物学、海洋生物学といった科学、テクノロジー、そして先住民の知恵など多岐にわたる。これらを融合させ、人間と自然との関係性を再構築するための問いを探求している。
例えば、クジラの保護に向けて、クジラの言語を理解するためのテクノロジー開発において法律面の影響を研究したり、ロンドン・デザイン・ミュージアムでの展示「More Than Human Design Museum」を監修したりと、活動は多岐にわたる。
こうしたアクションの原点になっているのが、次の5つの問いだ。
- 科学的な知見を、地球上の生命をより良く保護するための法制度にどう変換できるか?
- 増加する自然権をめぐる判決や法律の実施を強化し、実質的な効果を発揮するにはどうすればよいか?
- 人間の活動に対する自然の貢献に、私たちはどう報いることができるのか?
- 人間と非人間をめぐる懸念をどう橋渡しして、気候変動や生物多様性の危機に対する断固たる行動に繋げられるか?
- 人間以外の生き物や自然をより広く理解し、関係を築くために、テクノロジーをどのように活用し、その過剰使用を防ぐにはどうすればよいか?
これらの問いに答えるため、MOTHプログラムはアドボカシー、研究、法的措置、教育、アートなど、多様な手法を駆使する。所属するメンバーも、法律家だけでなく、哲学者、科学者、アーティスト、そして先住民のリーダーなど、極めて多彩な顔ぶれだ。彼らは分野や文化の垣根を越えた「コレクティブ(共同体)」として、人間中心主義からの脱却という目標に挑んでいる。

MOTHギャザリングにおける自然、権利、そしてコミュニティの交差点を探るワークショップ(エクアドル領アマゾン、サラヤク地域、2024年)|Photo by Ezequiel Zaidenwerg for NYU MOTH
もし、エクアドルの森が「共著者」として楽曲を作ったら
MOTHプログラムの象徴的な取り組みの一つが、エクアドルを舞台とした「Song of the Cedars(ロス・セドロスの歌)」というプロジェクトだ。
2021年、同国の憲法裁判所は、貴重な原生林であるロス・セドロス森を「権利の主体」として認め、鉱山開発を禁止した。その理由として、この森が住民の水源になっていたことが挙がったという。しかし、セサル氏は「人間の役に立つから、というだけではなく、森そのものの価値が権利に反映されるべきではないか」と考えた(※)。
※ こうした考え方は自然の権利とも重なる部分が多いが、セサル氏は、人間が自然の中に内包されることを強調し、自然の権利よりも広い範囲での権利として「More Than Human Rights(モア・ザン・ヒューマン・ライツ)」という言葉を用いて活動している。
「ロス・セドロスという森は、人間の水源であるという価値だけでなく、ハチドリからアリ、生物多様性の非常に高い地域に存在する蘭に至るまで、この場所に息づく固有の生命体そのものが保護に値するはずなのです」
そこで、セサル氏率いるMOTHプログラムのチームは、森を訪れ、10日間を共に過ごした。その中には、音楽家のコスモ・シェルドレイク氏や、作家のロバート・マクファーレン氏、菌類学者のジュリアナ・フルチ氏が含まれ、彼らは森の中で一曲の歌を作った。その曲に登場するのは、コウモリやホエザル、コオロギ、葉の擦れる音といった森の生き物たちの実際の声だ。
森がなければ、私たちはあれほどの集団的な創造性を発揮することはなかった──そんな経験と気づきから、ロス・セドロスの森を楽曲の「共著者」として認めるよう、エクアドルの著作権当局に申請を届け出た。これにより、森の権利が人間中心的な価値のためではなく、生態系のありのままの価値を重視した権利へ、さらに改善されることを目指したのだ。
「予想通り、当局は『人間しか歌の著者にはなれない』として一度は申し立てを却下しました。しかし私たちは異議を申し立て、現在も審査は進行中です。もしこれが再び却下されれば、私たちはこの件を法廷に持ち込み、最終的には裁判所に訴えるつもりです。そこで、かつて裁判所自らが下した『森の権利』の宣言を支持し、そこから導き出される法的な帰結、つまり森が楽曲の共著者としての権利を持つことを認めるよう求めるのです」

NYU MOTH創設ディレクターのセサル氏(右)は、先住民および非先住民の科学者と共に、自然の権利に関する法的措置のためのフィールドワークを実施している(エクアドル領アマゾン、サラヤク族の居住地、2024年)|Photo by Natalia Arenas for NYU MOTH
この試みは2025年10月現在、まだ決着がついていない。それでも、アートと法律を武器に、人間以上の存在の「創造性」や「主体性」を社会システムの中に位置づけようとするこのアクションは、モア・ザン・ヒューマンという視点を社会に実装するための、力強い一歩と言えるだろう。
「研究と行動を組み合わせ、現実の世界で変化を起こすのに、法律は非常に強力です。なぜなら、法律は現実を秩序づけ、形作る、社会を形成する方法であると同時に、世界についての物語を語る方法でもあるからです」
人間中心的な社会を、変えてゆくための一歩目
ここまで、モア・ザン・ヒューマンの意味や、それを体現する活動の様子を追ってきた。しかし、そうした特別な環境でなくてはモア・ザン・ヒューマンの考えに触れることはできないのだろうか。日々の生活の中で、人間中心的な思考から少し距離を取るために、何か具体的にできることがあるのだろうか。
この問いかけにセサル氏は、シンプルながら多くの人が手放してしまいがちな小さなアクションを提案してくれた。それは「身の回りの存在に、意図的に意識を向けること」だ。

2025年3月に開催されたBioneers Conferenceにて講演を行うセサル氏|Photo by Nikki Ritcher, via MOTH Program
「デジタルスクリーンから離れて、自分の周りにある物理的で感覚的な世界に身を置いてみてください。それは何も瞑想だけではありません。たとえば私にとっては、ハイキングや自然の中を歩くことがとても大事な時間です。
これは、人間がかつて当たり前に行なっていたことを思い出すための練習なのです。デジタルが普及する前、ソーシャルメディアが私たちを分断する前、つまり人間中心的な世界にのみ注意を払うインセンティブが与えられる前、私たちは多くの時間を自然の中で過ごしていました。それはほんの50年ほど前のことです。身近な地域での、具体的で目に見える努力が、私たちがその一部である『モア・ザン・ヒューマンの世界』と再び繋がる助けになると思います」
モア・ザン・ヒューマンの全体を包み込むような視点は、生き物を対等な目線に立たせることで保全活動のアプローチを問い直すだけでなく、人間が人間社会に孤立するのではなく、計り知れない命の支え合いの中で生きていることをも思い出させる。そう知らせることで、一人ひとりを少し解放するような力をも持っているように感じられた。
「人間と環境」「人間と自然」という明確な線引きからの脱却を目指すことは、曖昧さを受け入れることでもある。その余白がゆえに、モア・ザン・ヒューマンという考え方は、それぞれが身を置く自然や社会の中での振る舞いを少しばかりゆっくりに、穏やかにしてくれるのかもしれない。
【参照サイト】More-Than-Human Life Proram
【参照サイト】MOTH Records|Cosmo Sheldrake
【参照サイト】Rights of Nature|Stanford Social Innovation Review
【参照サイト】Researchers are Using AI to Understand what Animals are Saying|TIME
【関連記事】微生物と共に社会をつくる?人間中心ではない「マルチスピーシーズ」の社会がもたらす喜びとは【多元世界をめぐる】
【関連記事】「自然を守る」への違和感。人間と人間以外に切り分ける二元論から脱却するために