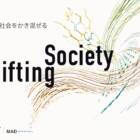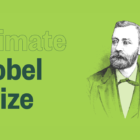日々の暮らしの中で、私たちはどれだけ、使い込まれることで生まれる「用の美」や、一つの物事を突き詰める「道」の精神に触れているでしょうか。
大量生産・大量消費が当たり前となった現代。安価で便利なモノが溢れる一方で、一つの道具が生まれる背景にある物語や、作り手の想いに心を寄せる機会は、少なくなっているのかもしれません。
そんな今だからこそ、私たちは日本の伝統的な手仕事や武道に息づく、古来からの叡智に触れ、その「本当の価値」を改めて問い直してみる必要があるのではないか──こうした想いから、IDEAS FOR GOODの姉妹サイトで、日本のサステナブルな取り組みを英語で発信するメディア「Zenbird」が特別なツアーを企画しました。
テーマは、埼玉県北部に由来する武州正藍染と、剣道。一見すると関係のないように思える二つの文化ですが、その根底には、自然と共生し、人・モノ・場所を大切にする、サステナブルな思想が通底しています。
当日は、110年の歴史を紡ぐ藍染工房と、凛とした空気が流れる剣道場を訪れます。職人の手仕事と、自然の恵みをいただく藍染の循環の仕組みに触れ、道場で竹刀を握り心身を整える時間の中で、礼節や他者を敬う心を体感する。それは、日々の暮らしをより丁寧に、豊かにするためのヒントを見つける旅となるはずです。
本ツアーは、日本語・英語の逐次通訳つきで、どなたでも安心してご参加いただけます。目の前にあるモノの背景にある物語を紐解きながら、私たちの暮らしを見つめ直す時間を、一緒に過ごしませんか。
プログラム内容
藍染工房見学:野川染織工業

Image: Mariko Sato

Image: Mariko Sato

Image: Mariko Sato
まず訪れるのは、1914年創業の野川染織工業。武州正藍染や剣道着ブランド「武州一」で知られる工房です。職人たちが働く藍甕(あいがめ)を間近で見学し、この土地の藍染文化の歴史を学びます。なぜこの伝統がサステナブルと言えるのか、自然との共生やウェルビーイングとの繋がりを考えるトークセッションも行います。
剣道体験:平成館道場

Image: Mariko Sato

Image: Mariko Sato
次に、平成館道場へ移動し、剣道の世界に触れます。専門家の指導のもと、道場での立ち居振る舞いや基本的な礼儀作法、姿勢、竹刀の持ち方、足さばきなどを学びます。一日の終わりには、参加者全員で今日の学びを共有。「道」を探求する精神が、時間厳守や謙虚さ、他者への配慮といった日常の習慣といかに繋がっているのかを考えます。
イベント概要
- イベント名:Learning from Japanese Indigo Dyeing and Kendo: Japanese Approach to Enriching Life(藍染と剣道から学ぶ:暮らしを豊かにする日本のアプローチ)
- 開催日:2025年11月28日(金)
- 時間:13:00~18:00(予定)
- 集合場所:東武鉄道伊勢崎線 「南羽生」駅(埼玉県羽生市)
- 定員:15名
- 言語:英語・日本語(通訳つき)
- 参加費:大人 20,000円/子ども 10,000円(12歳以下)
- 共催:Zenbird
- お申し込み:こちらから(お申し込み時に、Peatixで下記の割引コードを入力いただくと、参加費が5,000円割引となります(大人・子ども共通)割引コード:ZB11AK)
講師

Image: Mariko Sato
野川 雄気 氏
創業110年の歴史を持つ藍染の老舗、野川染織工業・五代目。高品質な剣道着にも用いられる、「武州正藍染」の技を守り伝えている。
雨谷 水紀 氏
いばらき少年剣友会監督として、全国大会優勝者を多数育成。剣道7段。礼節・規律・敬意など、剣道の根幹となる価値観を伝えている。
こんな方におすすめ
- 日本の伝統文化に根付くサステナブルな考え方に触れたい方
- 大量生産・大量消費の社会に、少し立ち止まって考えてみたい方
- 「用の美」や手仕事の価値を体感したい方
- 心身を整え、日々の暮らしを丁寧に見つめ直すきっかけが欲しい方
- 武道や武士道の精神に興味がある方
- 多様な価値観に触れ、物事との向き合い方を深めていきたい方
- 実践の裏側にあるリアルな声を通じて、主体的に学ぶことに関心がある方
【イベントお申し込みページ】Learning from Japanese Indigo Dyeing and Kendo: Japanese Approach to Enriching Life
【関連サイト】Zenbird
【関連記事】藍は生きている。剣道着の文化から「生きる力」をひもとく