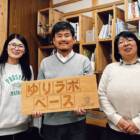どんなにテクノロジーが進化しても、ゼロにはならない交通事故。特に5月〜7月には、通学に慣れてきて油断が生じるためか、子どもの交通事故が多い傾向にある(※1)。アラームや自動ブレーキは100%事故を防げるものではないため、運転者自身が、子どもが飛び出してきそうな場所に注意を払うことが欠かせない。
その「注意」を、運転者個人の意識だけに任せるのではなく、仕組みとしてサポートする方法はないのだろうか。
その一つが、横断歩道への注目を促す「地面埋め込み型ライト」だ。2025年6月23日、大阪府守口市に日本で初めて設置された。赤や青に点灯する通常の信号とは異なり、黄色のLEDライトが道路上で光ることで、歩行者と運転者の両方に車道・横断歩道があることを知らせて注意を促す。特に、目線が下に向きやすい子どもや高齢者でも視認しやすく、自然と横断歩道の存在に気づくことができるのだ。
ライトの種類は3つ。点字ブロックと車道の間に列をなす長方形のライト、横断歩道に沿って車道上で光る丸いライト、そして横断歩道を少し高い位置から照らすポール型のライトだ。
今回ライトが設置された横断歩道は、2つの公園の間に位置し、休日は車道の交通量も多いという。子どもが飛び出しやすいけれど信号機は設置できないような場所では、夕方から夜にかけてこうしたライトが活躍するだろう。

Image via 株式会社CapWorks

Image via 株式会社CapWorks

Image via 株式会社CapWorks
地域住民からは「よく子どもが飛び出したり、車もスピードが早くていつもドキドキしていた。すごく明るくて良いと思う」「これだけ明るいので、ドライバーも横断歩道があるなと分かりやすくなった」と前向きな声が寄せられた。
このほかにも、交通安全に向けた「光」の工夫がある。韓国やシンガポール、ドイツなどでは、2017年頃から地面に埋め込まれた信号機が広がってきた(※2)。しかし今回のような補助としてのライトではなく、赤や青に点灯し信号機そのものとして機能する事例が多く、英メディアBBCが「スマホゾンビ」と表現したように、歩きスマホを助長するのではないかとの懸念の声もあった。信号に従い車との衝突が避けられても、他の事故を招きかねないだろう。
一方で、今回守口市に導入されたライトは、信号機そのものの役割は果たさないからこそ、人が自分自身で車道を確認するよう促す。歩きスマホを前提に設計する安全性もありうるが、この「意識を変える」デザインも重要ではないだろうか。
※1 子どもの交通事故は初夏に多い? 特に要注意の年齢とは – ウェザーニュース
※2 This is how Korea innovates to prevent traffic accidents|KOREA NOW
【参照サイト】【日本初】地面が光る信号!未来型「埋込型信号」が大阪・守口市に登場
【関連記事】思わず安全運転したくなる?フランス西部に突如現れた「走りにくすぎる道」
【関連記事】歩きスマホをテクノロジーで解決?香港の「地面に映る赤信号」