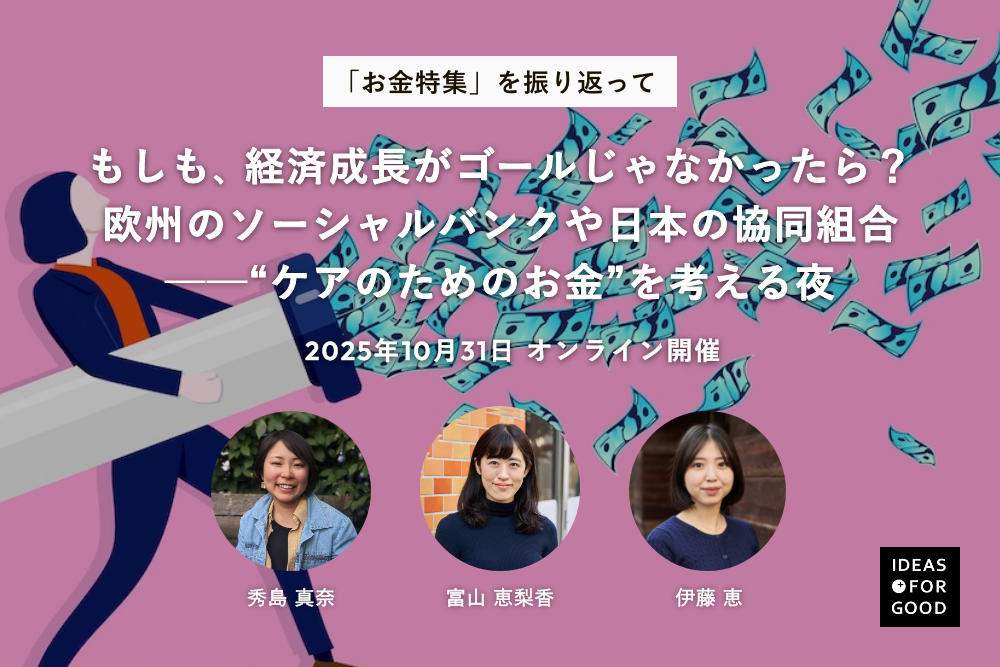【特集】幸せなお金のありかたって、なんだろう?今こそ問い直す、暮らしと社会の前提
お金は、ただの紙切れでも数字でもない。生き方や価値観、人間関係、社会制度にまで影響を及ぼす「見えざる力」だ。便利で、時に残酷で、そして人間的なこの仕組みは、いつから私たちの当たり前になったのだろう。自己責任が求められる働き方、そして「お金がない」ことを理由に後回しにされる福祉や環境対策──議論は世界中で交わされているが、日々の暮らしの中でお金の本質を見つめ直す機会は少ない。だからこそ今、問いたい。「お金」とは何か、そして私たちはそれとどう向き合っていけるのか。本特集では、経済だけでなく、文化人類学や哲学、コミュニティの現場など多様な視点からお金の姿を捉え直す。価値の物差しを少し傾けてみた先に、より自由でしなやかな世界が見えてくることを願って。
社会に良いことをしたい、地域を豊かにしたい。そう願う人々や組織が、いつも壁にぶつかるのが「お金」の問題だ。
短期的な利益や効率性が優先される現代の金融システムの中で、すぐには利益に結びつかない公共的なプロジェクトは、資金を得ることが難しい。この構造的な課題に、「金融のデザインそのものを変える」というアプローチで挑む人物がいる。
スイスを拠点に活動する投資戦略家、トビアス・テメン氏だ。彼が率いる専門投資会社・wait, what.は、「ケアとしての金融」という哲学を掲げる。それは、お金を単なる成長のツールではなく、コミュニティや生態系を育むための道具として捉え直す試みだ。その思想を具現化した官民連携の「Placemaking Investment Fund」は、一体どのようにして公共の価値を育むのか。
金融の常識を問い直す、彼らの挑戦を追った。
話者プロフィール:Tobias Temmen(トビアス・テメン)
 投資戦略家。銀行、公的・民間市場での豊富な経験と、Kellogg-WHU Executive MBAで培ったグローバルな視点を活かし、民間投資と公共イノベーションの架け橋となる創造的な金融モデルを専門とする。創設したExperience Investmentsでは、「Placemaking Investment Fund」を主導。活気に満ち、長期的で持続可能な都市空間を育むため、コミュニティ中心のプロジェクトに資金を供給している。そのアプローチは金融知識と市民的な目的を融合させ、公共セクターのイノベーションを再考する上で重要な役割を担っている。
投資戦略家。銀行、公的・民間市場での豊富な経験と、Kellogg-WHU Executive MBAで培ったグローバルな視点を活かし、民間投資と公共イノベーションの架け橋となる創造的な金融モデルを専門とする。創設したExperience Investmentsでは、「Placemaking Investment Fund」を主導。活気に満ち、長期的で持続可能な都市空間を育むため、コミュニティ中心のプロジェクトに資金を供給している。そのアプローチは金融知識と市民的な目的を融合させ、公共セクターのイノベーションを再考する上で重要な役割を担っている。
金融危機が教えてくれた、お金の本当の役割
トビアス氏のキャリアは、銀行から始まった。金融一家に育ち、ごく自然にその世界へ足を踏み入れた。しかし、2008年の世界金融危機が、彼の運命を大きく変えることになる。
「金融危機が起きたとき、私は自らのキャリアを問い直さなければなりませんでした。このまま銀行業界に留まるべきか、それとも何か別のことをすべきか、と」
この問いをきっかけに、彼はコンサルティングや資産運用の世界へと移り、金融をより戦略的、多角的な視点から見つめ直していく。そこで彼が目の当たりにしたのは、短期的な利益を追求するあまり、長期的な価値を見失っていく金融業界の姿だった。
「より長期的な視点に立てば何が起こるだろうか、と考え始めました。アルプスの環境の変化や、ヨーロッパで部分的に崩壊しつつある食料システムを目の当たりにし、こうした分野における金融の役割を再考する必要があると感じたのです」
この問題意識が、彼を自身の会社wait, what.の設立へと突き動かした。その目的は、イノベーションの最前線に立ち、金融の力を使って社会の持続可能性とポジティブなインパクトを測定し、実現すること。そして、その核心には「ケアとしての金融」という揺るぎない哲学があった。
「私たちは金融を、成長のためだけでなく、ケアのためのツールとして見ています。私たちの哲学は、コミュニティと生態系を再生させ、公共の価値を金融ロジックの中心に置く投資をデザインすることです」
「欲しい未来」への共感が、人を動かす
wait, what.が取り組むのは、地方自治体やコミュニティ志向の開発者が抱える「変革を起こしたいが、旧来の資金調達の仕組みでは動けない」というジレンマだ。特に力を入れているのが、ドイツなどで進む「ブラウンフィールド開発」。かつて石炭産業などで栄えた工業地帯を、現代のサービス産業や居住区へと転換させるプロジェクトだ。
新しい経済システムへの移行を目指すとき、必ず旧来の価値観を持つステークホルダーとの対話が必要になる。彼らをどう説得するのか。トビアス氏のアプローチは独特だ。
「私は、人々は新しいアイデアにまず感情で繋がると強く信じています。数字について語ることもできますが、数字は非常に抽象的です。人々は合理的であろうとしますが、心の底では誰もが笑ったり、感動したりするのが好きなんです。だからこそ、人々が『まさにこれが欲しかったんだ』と言ってくれるようなものを提示することから始めます」

Image via wait, what.
彼は、プロジェクトの初期段階から建築家と連携し、「これが今の姿です。そして、このように変えることができます」と、未来のビジョンを具体的なイメージで示す。美しい建築、緑豊かな広場、人々が憩う風景。その魅力的な未来像が、人々の心を動かし、プロジェクトへの参加意欲をかき立てるのだ。
複雑なシステム論や難解な数字を並べるのではなく、誰もが直感的に「良い」と思える未来への共感を入り口にする。それが、彼の変革の作法だ。
場所の価値を育む、Placemaking Investment Fund
その哲学を具体化したのが、「Placemaking Investment Fund」という仕組み。 きっかけとなったのは、「市の財源が限られる中で、どうすれば民間セクターの投資を公共空間の整備に促せるか」という問いだった。
「不動産を所有する民間企業にとって、その場所をより良くすることは、実は自分自身の利益に繋がります。素敵な場所にはアイデンティティが生まれ、人々が集まってくる。そして、その場所を大切に思う人々は、エリアの価値を維持し、育んでくれるのです」
この考えに基づき、ファンドはコミュニティセンターや公共空間、文化的なハブといった「大切な場所」を支援する。 従来の開発が、安く土地を仕入れて建物を建て、短期的に高く売ることを目指すのに対し、このファンドは長期的な視点に立つ。一般的に開発者は数年でプロジェクトから離れるところを、投資家は10年、20年というスパンで関わり続けるのだ。

Image via wait, what.
「10年後には、建物の周りに木々が茂っていてほしいのです。木々は木陰をつくり、地域を涼しくします。そうなれば、冷房に使う電気も少なくて済む。それは人々の暮らしを快適にし、不動産の価値も高めるのです」
さらに、このファンドは単に金銭的なリターン(ROI)だけを追わない。コミュニティが共有資産を共同で所有・管理する「コモンズベースの金融」の考え方を取り入れ、市民の参加を促す。そして、その成果を「文化的リターン」という新しい指標で評価しようと試みる。
「私たちが注目するのは、時間をかけて何がより強固になるか、です。それは共有された信頼であり、市民参加であり、その場所への帰属意識です。こうした『ソフト』なリターンこそが、レジリエントなシステムの基盤となるのです」
資本の意味を問い直し、未来をデザインする
wait, what.の挑戦は、金融の仕組みだけでなく、「資本」そのものの意味を問い直すことにも及ぶ。
「私たちは、時間、ケア、知識、信頼といったものも、お金と同じくらい価値のある資本だと信じており、私たちの資金調達のデザインはそれを反映することを目指しています」
例えば、建物を設計する際には、若者だけでなく、いずれ誰もが迎える「老い」を見据え、すべての世代が使いやすいユニバーサルなデザインを最初から組み込む。それは一見コストがかかるように見えても、人々が長く住み続けることで不動産仲介業者に支払う手数料が不要になるなど、長期的に見れば経済的な合理性にも繋がる。
もちろん、こうした実験的な試みには困難も伴う。「現在のシステムは、実験ではなく、予測可能性に報いるようにできています。私たちは、まさに橋を架けながらそれを渡っているようなものです」とトビアス氏は語る。
それでも彼が前進し続けるのは、金融をデザインし直すことが、より良い未来の創造に不可欠だと信じているからだ。
「想像力は、私たちを『実現可能なこと』の限界を超えて、『本当に必要なこと』へと向かわせてくれます。そしてデザインは、金融が可能性を制限するのではなく、それを可能にするような、より良い未来のプロトタイプをつくる手助けをしてくれるのです」
金融とは、一部の専門家だけが扱う難解なものではない。それは、私たちの社会のOSであり、想像力とデザインの力によって、誰もが望む未来を実現するための強力なツールとなりうる。トビアス氏の静かな革命は、その可能性を力強く示している。
編集後記
筆者がトビアス氏に出会ったのは、ドイツ・ベルリンで開催されたCreative Bureaucracy Festivalだった。創造的な「新しい公共」を模索するこのフェスティバルで語られた「ケアとしての金融」という言葉は、金融という言葉が持つ、どこか冷たく、数字と利益だけで動くというイメージを根底から覆した。短期的利益ばかりを追い求める投資の限界が感じられる今だからこそ、「ケア」「信頼」「共感」といった言葉で語られる金融の姿は、社会課題解決の全く新しい扉を開く可能性を感じさせた。
特に印象的だったのは、投資の成果を測る「文化的リターン」という視点だ。金銭的な投資収益率(ROI)だけでなく、人々がその場所に抱く愛着や、育まれるコミュニティの絆、市民参加の活発化といった、目には見えない価値をいかに評価し、育んでいくか。この問いは、これからの都市開発や地域創生、そしてあらゆる社会システムをデザインする上で、不可欠な羅針盤となるだろう。そしてそれが結果的に「経済的」利益をも生み出すのだ。
社会が抱える課題の根っこには、実はお金の流れ方が深く関わっている。トビアス氏が語った「想像力が、実現可能なことの限界を超えることを可能にする」という言葉は、壮大な理想論ではなく、現状を変えるための具体的なアプローチだ。お金がないから、制度がないから、と嘆く前に、私たちが本当に望む未来を想像し、その実現のためにどんなお金の使い方、集め方があるのかを「デザイン」してみる。その創造的な視点こそ、より良い社会に向けた、地に足のついた一歩となるのだろう。
【参照サイト】wait, what.
【参照サイト】wait, what. Substack
Featured image created with Midjourney (AI)