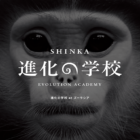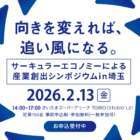生物多様性の危機が世界の共通課題となる中、国際社会は損失を食い止めるための大きな目標を掲げている。例えば、2022年に採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」では、2030年までに陸と海の30%を保全する「30by30」目標などが設定された。
こうした目標を達成し、深刻な事態を食い止めるために不可欠なのが、正確で広範な生物データである。科学者や政府は、種の生息地や個体数、直面している脅威を正確に知ることで、生息地の保護や保全計画の調整、国の政策決定などにおいて、より的確な判断を下すことが可能となるからだ。
しかし、専門家の科学者だけでその重要なデータを集めるには限界がある。なぜなら、限られた研究者と予算では、広大な地球に多様な生物が生息する全ての場所と時間をカバーすることは不可能だからだ。結果として、生物の分布図にはデータのない「空白地帯」が生まれ、絶滅の兆候などを見逃す危険性が高まっている。
その突破口として大きな注目を集めているのが、科学者ではない一般市民がデータ収集や分析に協力する「市民科学(シチズンサイエンス)」というアプローチだ。その歴史は19世紀の鳥類観測記録にまで遡るが、現代ではインターネットとスマートフォンの普及がその可能性を飛躍的に広げ、より多くの人が気軽に関われるようになっている。
この一例が、カナダ・モントリオールのマギル大学の研究者が主導する市民参加型科学プロジェクト「Blitz the Gap(ブリッツ・ザ・ギャップ)」。カナダ国内の生物データを集めることを目的に、2025年の6月1日から10月1日まで開催されている。
参加方法はシンプルだ。市民が収集した生物観察データを共有できる無料アプリ「iNaturalist」のカナダ版をダウンロードし、カナダ国内で撮影した生物の写真を投稿するだけだ。
アップロードされた写真は、アプリが自動で種を特定。その後、科学者が結果を再確認する。こうして集められたデータが、生物種の生息状況の全体像を把握することに役立てられるという。アプリでは生物の専門家や他のユーザーとチャットをすることができるなど、生物好きのオンラインコミュニティとしても機能している。
ただし、こうした市民科学には弱点もある。そのひとつが、データ収集場所に偏りが生まれることだ。一般的に、市民は自宅の庭や近所の公園、アクセスの良い道路沿いといった「行きやすい場所」で生物を観察する傾向がある。その結果、データはどうしても都市部や交通網の周辺に極端に集中してしまうのだ。
Blitz the Gapではこうした現状にも光を当て、市民に向けて優先的にデータ収集すべき場所も示している。例えば、プロジェクトページ内に掲載されている記事では、現在カナダ国内で蓄積されている半分以上の生物データが、都市部を中心とした、たった1%の国土から収集されたものだということを強調。
さらに、こうした状況を解消するため、データ収集の優先度が高い場所や生物多様性保全の観点で優先度が高い場所を示すマップを作成し、ユーザーにそうした場所へ向かうよう促している。

生物データ収集の優先度を示すマップ。緑が最も優先度の高い地域。出典:Blitz the Gap
専門家による研究基盤の強化はもちろん不可欠だ。しかし、私たち一人ひとりがその“眼”となり研究の一端を担うとき、生物多様性の危機は遠い課題ではなく、自分ごとに変わる。その小さなアクションの積み重ねこそが、社会全体の意識を変える大きなうねりへと育っていのではないだろうか。
iNaturalistは、日本でも利用可能だ。次の週末は、自然の豊かな場所に足を運び、道中で出会う植物や昆虫をレンズを通して記録していく…..そんな、未来につながる楽しみ方を選択してみても良いかもしれない。
【参照サイト】iNaturalist.ca
【参照サイト】How Citizen Science Canada is Revealing Canada’s Biodiversity Threats
【参照サイト】Blitz the Gap
【関連記事】データを“聴く”音楽。生物多様性の豊かさと危機を“体感”させる「蛾の歌」
【関連記事】調べるだけで生物多様性に貢献できる検索エンジン「KARMA」
【関連記事】スマホを生物多様性の観測拠点に。ネイチャーポジティブを実現するプラットフォーム【鎌倉投信×バイオーム対談】