「たまたま普通に生まれたやつがイキって見下してんじゃねえよ!」
映画『ノルマル17歳。-私たちはADHD-』の予告編で、ADHDの女子高生・朱里(じゅり)は、定型発達の姉に向かってこう言い放つ。心臓がぎゅっと掴まれるような息苦しさと、鋭い痛みを感じる強烈な台詞だ。

忘れ物をして「なんでそんなこともできないの」と責められたとき。空気を読めずに「普通こうでしょ」と呆れられたとき。そんな「“普通”を求められる痛み」を、誰もが一度は味わったことがあるはずだ。だが、ADHDの特性がある人々にとって、それは毎日のように降りかかる現実である。
ADHDは、発達障害(注意欠如・多動症)の一つで、ケアレスミスや忘れ物が多いなどの「不注意」、じっとするのが苦手な「多動性」、何かを思いつくとすぐに行動に移してしまう「衝動性」といった特性を持つ。
トラブルが発生する頻度は人よりも高く、その程度も比較的重い。それは“怠け”や“努力不足”ではなく、特性ゆえのものだ。だが、細かいミスをするのも、忘れものをするのも、そわそわするのも「少なからず誰にでもある」こと。だからこそ、ADHDやその困りごとによる生きづらさは理解されづらいこともある。
映画『ノルマル17歳。』は、そんな特性による生きづらさを抱えながら生きる2人の女子高生を描いた作品だ。見た目も行動も派手なギャル・朱里(じゅり)と、進学校に通う真面目な絃(いと)。正反対の2人が「普通」というものさしではかられ、縛られ、居場所を見失っていく。その姿を追いながら、「本当の普通とは何か」を探していく物語だ。
今回は、映画『ノルマル17歳。』を手掛けた北宗羽介監督のもとを訪ね、「普通」という概念やそれに対するまなざしについて伺った。
話者プロフィール:北宗羽介(きた・そうのすけ)
 1970年生。映画プロデューサー・映画監督。広告代理店にて勤務後、独立起業。広告制作やIT関連に携わりながら、独立系映画の製作・配給、海外映画のサポート等を行なう。「国際共同製作」を基本路線に、独自の映画製作・配給形態を構築中。「今いかに生きるか」を共通テーマに映画作りを行なっている。
1970年生。映画プロデューサー・映画監督。広告代理店にて勤務後、独立起業。広告制作やIT関連に携わりながら、独立系映画の製作・配給、海外映画のサポート等を行なう。「国際共同製作」を基本路線に、独自の映画製作・配給形態を構築中。「今いかに生きるか」を共通テーマに映画作りを行なっている。
映画作りの原点となった、ある違和感
Q. 映画を撮影することになったきっかけについて教えてください。
映画の企画が始まったのは4年ほど前ですが、そのきっかけはさらに昔に遡ります。
映画監督の仕事で、俳優のマネジメントや演技指導をする機会があるのですが、今から20年ほど前でしょうか──当時「悪気はないけれど頻繁に遅刻や忘れ物をする子が、以前よりもずいぶん増えているな」という感覚があったんですね。そのなかでも、ミスがあまりにも多い子がいたので、もしかしたら背景に何かあるのかもしれないと思い「一度カウンセリングを受けてみてはどうか」と本人に伝えてみたのです。
すると数日後、その子の親御さんから電話があり、「本人に直接そういうことを言うのはやめてくれ」とクレームが入りました。そのときに違和感を抱きました。本人が抱える問題から目を背けているというか……親御さんが自分の子どもに正面から向き合えていないのではないかと感じたのです。そんな状況があるなら何とかしたい、と思ったのを覚えています。

北監督
それから時が経ち、2021年頃、僕は青春映画を作ろうとしていました。若い人たちが「今をいかに生きるか」に葛藤し、もがきながらも道を見出していく、そんなストーリーを描きたかったんです。
映画製作に際しては、全国から企画を公募することにしました。送られてきたのはほとんどが恋愛映画の企画でしたが、その中に一つ、印象的なプロットがあったんですね。それこそが「発達障害を持つ見知らぬ女子高生2人が公園で出会う」ところから始まる短いプロットでした。それを読んだとき、僕の頭の中に物語のシーンが映像として浮かんだんです。そこに過去の経験も重なり、この2人の主人公と、彼女たちを取り巻く人々の映画が作れそうだと直感しました。
ちなみに、プロットを応募してくれた神田凜さんは、自身の過去の経験から、この物語を考えたそうです。神田さんが高校2年生のときの知り合いに、色々と問題を起こす人がいたといいます。あるとき、その行為があまりにひどかったため、彼女はその人に対して、すごく強い態度で当たってしまったそうです。
のちに、神田さんはその人がADHDだと診断されたことを知りました。そのとき、問題の原因となっていたこれまでの言動に納得がいき、その人に対して「もっと別の対応ができたのではないか」とずっと考え続けていたそうです。そんな自身の経験をもとにストーリーを描きたい、と話してくれました。
「普通」に縛られた社会
Q. この映画の上映会のアフタートークにて、監督ご自身が「普通」という言葉に違和感を抱いており、常識や固定観念を崩していくのが映画人としての理念だとお話していました。そう思うようになったきっかけはありますか?
幼いころから大人たちに「みんながやっているからこうしなさい」「こうしないと人に笑われるよ」と押し付けられることに、本能的な反発心がありました。子どもの頃はきちんと言語化できていませんでしたが、「人と同じにされたくない」「人は人、自分は自分だ」という感覚がもともとあったように思います。
「普通/普通でない」という概念や、いわゆる「普通」の側から「普通でない」人たちへ向けられる視線に違和感を持ったのは、おそらく、中学生の頃の体験がきっかけです。
一つ、鮮明に覚えているエピソードがあります。中学生のとき、学校の成績が良かったので、先生たちからはいわゆる「優等生」というレッテルを貼られていました。一方で、俗に「不良」と呼ばれる先輩や同級生とも仲良くしていました。するとあるとき、学校の先生に、「君は不良グループの子たちとも仲がいいから、少し彼らの様子を見ていてくれないか?」といったことを言われたんです。
僕から見ればその人はとても良い人なのに、先生からすると「問題児」だから扱いづらい。だから、「優等生」とされる僕を通して監視させようという意図を感じてすごく反感を覚えたんですよね。
学校の先生が、人のことをフィルター越しに見ている──その事実が、たまらなく嫌でした。いわゆる「普通」の枠からはみ出している人たちを、無理やりその枠に入れるか、それができないならどこか別の場所へ追いやろうとする、そんな考え方が透けて見えて許せなかったのです。
しかし、当時の僕はそんな反発心を表に出さない時期で……「優等生」として「普通」の枠の中にいれば安泰なので、あまりはみ出そうとはしませんでした。でも、事実として自分は「普通を司る側」と「普通からはみ出る側」の間にいるわけですよね。だからこそ、自分自身に対して、すごくもやもやした気持ちを抱えていました。どうすることもできない、でも何かしたい、と。
それで、「表現の中でなら、なんとかできるのではないか」と思い至ったんです。 その頃は漫画家になりたいと思っていましたが、

Q. 撮影の際、気を付けたことはありますか?
ADHDの役を演じる俳優には、「あなたの役はこんな障害を持っているキャラクターだからこう演じてほしい」といったディレクションはしませんでした。「この登場人物は忘れ物が多かったり、うっかりしている頻度が高かったりする」「たまたまそういう特性が強いだけ」で、「背景にこうした特性があるから、こういう性格になって、こんなコミュニケーションの仕方になっているんだ」という伝え方をしたんです。発達障害というのは、あくまで後からラベリングされたもの。だからこそ、障害云々ではなくもともとそういう特性を持った人間なんだ、ということを前提にして演じてもらいましたね。
映画への反響と新たな気づき
Q. 『ノルマル17歳。』にはどのような反響がありましたか?
公開後は、当事者の方から「登場人物が自分そのものだった」と共感する声が多く届きました。また、何度も劇場に足を運ぶリピーターの方もいらっしゃいましたね。ある方は、何年も引きこもり生活をされていたそうですが、この映画を観るために家から長い時間をかけて映画館まで来てくださいましたし、同じく引きこもっていらした当事者の方がこの映画を観てハローワークに行ってみた、というお話も聞いています。
また、当事者だけでなく、その親御さんや学校の先生など、当人の周りにいらっしゃる方も見に来てくださいました。「自分も同じような言葉を口にしていた」という方も少なくなかったです。「同じ過ちが繰り返されないよう、もっと色んな人に見てほしい」という声もあり、映画館での上映が終わった後も、そうした方々による自主上映が続いています。
感じること/感じようとしないこと
Q. 映画への反響のなかで、特に印象に残っているものはありますか?
ポジティブな反応をいただく一方で、作品の中に登場する、ADHDに理解のない周囲の登場人物たちに対し「当事者にここまでひどい態度を取る人はいない」「実際にこんな台詞を言う人がいるわけない」「障害の現実を反映しているとは思えない」といった批判のコメントも受け取りました。実際には、作中の台詞と全く同じような、あるいはもっと辛辣な言葉を口にしたり、きつい態度であたったりしている人がたくさんいる。にもかかわらず、そうしたコメントをしていた方々にとって、映画内の人物たちの言動は「設定」という枠を超えないものだったわけです。
映画なので好き嫌いがあるのは仕方がないことです。しかし、そういった個人の好みとは別に、作品の構成や技術的要素といった「側(がわ)」だけに着目して、その奥底にあるものを「感じない」「感じようとしない」という問題があるのではないかと思ったんです。
「感じない」「感じようとしない」という人の中には、もしかしたら自分の中に強固な「普通」の枠組みを持っていたり、固定化された「良い/悪い」という価値基準の中で生きていたりする人も多いのではないでしょうか。逆に、「感じられる」「感じようとする」ようになると、「自分は間違った認識をしていたかもしれない」「こういう世界もあるんだ」と、自分の中の「普通」を変えることができるのかな、と思うんですよね。
ちなみにこの「感じる/感じない」をテーマに、次回作のドキュメンタリーを制作予定です。
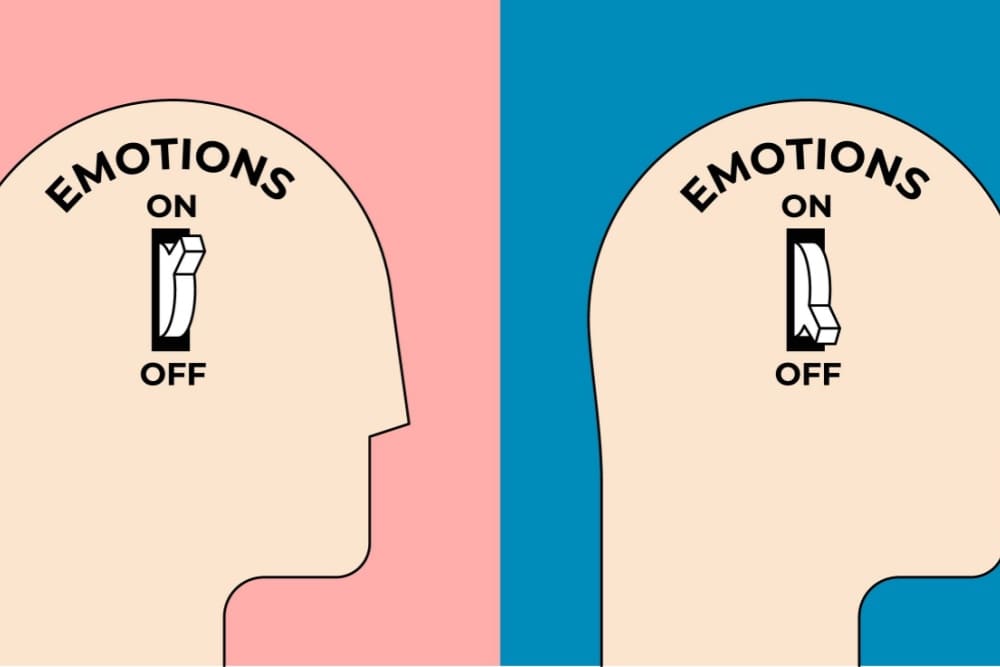
「見ないようにする」という暴力性
Q. 「感じようとしない」ことについて、もう少し詳しく伺えますか?
いわゆる「多様性」という言葉を聞く機会が増えていますが、人々はマイノリティの存在を認識しつつも、やはり見ないようにしている傾向があると感じます。価値観の多様化自体は進んでいるのかもしれません。でもそれは、必ずしも世界が多様になっている、ということとは違う気がしているんです。
今、人々は多様な価値観を持つ大勢の人の中から、自分と同じ価値観を共有する人たちを見つけて集まり、それぞれが小さな世界を形作っているように思います。色々な世界が無数に存在しているのであれば、一見すると、全体としてはものすごく多様に見えますね。
しかし、それらの小さな世界たちは他の世界と関わらずに存在しています。いわばこれは、「孤立化された小さな世界」がたくさん生まれているということでもあるのでしょう。
また、それぞれの世界に当てはまり切れなかった「曖昧な部分」も大きな問題となります。
例えば、発達障害でいうグレーゾーンについて。グレーゾーンは、発達障害の傾向がありつつも、医師からの診断がつかない人たちのことを指します。つまり、彼らは「ここからは健常者/障害者」というようにバシッと世界に線を引くことで零れ落ちてしまう、曖昧なところに存在しているんですね。彼らの場合、いわゆる「普通」の世界にも入り込めるし、「普通」の人々から「あなたたちは私たちとは違う」と言われればそこから簡単に追い出されてしまう。大きな生きづらさを抱えがちです。
あるいは、性別について。現在は多くのセクシュアリティが認知されてきていますが、「この人は○○」「あの人は○○」と細分化されたカテゴリに当てはめようとしてしまうと、そこに当てはまりきらないセクシュアリティが取りこぼされてしまうこともあるでしょう。
価値観が細分化されればされるほど、そこに収まらない曖昧な部分を受け入れる余白がなくなってしまっているような気がします。そうすると、互いに歩み寄ることができなくなり、「引いた目で見れば多様化しているように見えるのに、近づいてみると逆に多様性が失われている」という逆説的な状況が生まれてしまうのではないでしょうか。
人間には本来、グレーな部分、アナログで曖昧な部分がたくさんあります。それなのに、全てを細かく分けてデジタル的に切り分けようとしてしまう──それは、見ない・関わらないようにして「別の世界を遮断すること」「感性をシャットダウンすること」です。これこそが、様々ないさかいや分断の原因になってしまうのではないでしょうか。

「普通」から「本当の普通」へ
Q. 北監督にとって「普通」とはどのようなものでしょうか?
「普通」とは視点によって変わる、単なる相対的な尺度にすぎないと思います。ある集団の中の一つの基準であり、あくまで尺度でしかない。それが「正しい」とか「良い/悪い」ということではありません。多数決が必ずしも正義とは限らないのと同じで、「普通=正しい」と考えるのは危ないと思うんですよね。
逆に、「本当の普通」とは、その「普通」という言葉の本質に気づくことだと思っています。今お話ししたように、「普通」とはあくまで一つの尺度にすぎず、「普通=正義ではない」と理解すること。それが重要なのではないでしょうか。
「わかりあえない」からこそ、映画を
Q. 映画でも描かれているように、「わかりあう」のはとても難しいことに思えます。北監督は「わかりあえなさ」についてどう考えていますか?
人は100%わかりあうことはできないでしょう。
ただ、どうせわかりあえないからといって、今わかりあえている人たちだけで集まるだけならば、それはもう分断の始まりだと思います。そして僕は、その分断を解決するために、芸術的な分野は大きな役割を果たすと考えています。
芸術には、問題を提起し、人の価値観をガラッと変える力があります。何かの芸術に触れてものの見方が変われば、今までわかりあえなかった人が、「わかりあえる人」に変わる可能性が十分にあるのです。
今わかりあえていなくても、「今後どこかでわかりあえるようになるかもしれない人」「わかりあえそうな要素や可能性を持つ人」を、わかりあえる側へと導く──これこそが芸術の世界を変える力だと僕は思っています。
Q. 今後、作品を通じてどのような表現をしていきたいですか?
抽象的で大きな話になりますが、やはり、世界が平和であってほしい、平穏な社会になってほしいと思っています。その力になるような作品を作りたいのです。
映画だけで世界は変わりませんが、映画を観た人の目に映る世界やその人自身は変わっていきます。そして、変わった人がまた別の人を変え、社会全体を変えていく──そんな構造になっているのだと思います。そういうふうに、人が少しずつ変わるきっかけを作りたいのです。人々が生きやすい社会の実現に貢献する、そのために映画を作り続けたい。この想いは変わりませんね。

『ノルマル17歳。』のワンシーン
編集後記
「普通」。嫌い。わかんない。
キービジュアルにも書かれており、この映画の大きなテーマでもある「普通」。それは、個々人の頭のなかにだけ存在しているはずのものだ。たった一つの「普通」なんてない。そうわかっているはずなのに、どういうわけかみんなが同じものを共有しているように思えてしまう。きっと、幼いころから当たり前のように「普通」という概念に囲まれてきたからだろう。
「普通」は目にも見えず、触れることも、聞くことも、嗅ぐこともできない。本当にそんなものがあるのか確かめる術もない。私たちを縛っているのは、そんな不確かな存在だ。それでもなお、「普通」に捉われてしまうのは、社会からのプレッシャーがあまりに強いから。それが、自分でも自分に「ノーマルであれ」という呪いをかけなければならないほどに、私たちを追い込んでいるからなのかもしれない。
「普通」に捉われないように、といっても実際には難しい。だから、無理に気にしないようにしようとは言いたくない。だが、その波に溺れそうになるたびに、思い出すことはできる。「普通」って何?絶対的なものなんだっけ?本当にあるって言い切れる?……そんなふうに、それが実は「存在しない」ことを何度でも確かめ直すのだ。「普通」に実体がないなら、私たちをがんじがらめにすることなんて、できないはず。だからこそ、それだけは、忘れないようにしたい。
【参照サイト】映画『ノルマル17歳。』公式サイト
【参照サイト】映画予告編(YouTube)
【参照サイト】ADHD(注意欠如・多動症)の女子高生たちが生きる道を見つけて行く 映画『ノルマル17歳。― わたしたちはADHD ― 』 4月5日(金)東京・アップリンク吉祥寺にて公開
北監督は、本編でお話しされていた「感じること/感じないこと」をテーマに、発達障害や感覚特性と「感じ取ろうとしない社会」を見つめるドキュメンタリー「Feel/Unfeel 発達障害と日本(仮題)」を制作中だ(2026年春公開予定)。これに伴い、クラウドファンディングも実施している。発達障害・感覚特性がある当事者の方を含め、やさしい世界をつくりたい、受け入れられる余白を作りたいと思う方は、ページを覗いてみてはいかがだろうか。
▶フィール/アンフィール 発達障害と日本(仮題)












