Sponsored by フューチャーセッションズ
来場者2,500万人を超えて熱狂のうちに幕を閉じた大阪・関西万博。「はじめは乗り気じゃなかったけど、行ってみたら楽しかった」「ここはもっとスムーズに運営できそう」など、SNSでもさまざまな声が飛び交っているが、私たちは万博で得た無数の気づきを「これから」に活かすことはできるだろうか。
今回の万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」を実現するコンセプトとして、「People’s Living Lab(未来社会の実験場)」を掲げている。そんな中、万博に行ったことのある人たちが当日の体験を「ただの思い出」に留まらせず、互いに共有し、深掘りし、未来へのインサイト(示唆)につなげるセッションが東京・日本橋のSYNERGYCA共創ラウンジで開催された。

Photo by Kanta Nakamura (Newcolor inc)
主催は、産学官民の垣根を超えた共創の場づくりに取り組む株式会社フューチャーセッションズとコクヨ株式会社。昨今、行政や企業、大学でも共創の場が注目され、年々その数が増えている。一方、施設の存在や単発のワークショップだけで共創が生まれるわけではなく、成果に悩む運営者も多い。2社の有志メンバーは多くの人の共通体験を生み出した万博に着目し、共創対話のワークショップを企画・実施した。
「あなたが万博で発見した『いのち』の『輝き』は?」
セッションではそんな問いが投げかけられ、多種多様な業界の人たちの対話が繰り広げられた。本記事では、セッション当日の議論の様子と、主催者がセッションを終えて振り返った学びをお届けする。
目次
未来志向の対話の場「フューチャーセンター」とは?
目の前の課題だけにとらわれず、未来を見据えて「どうありたいか」からバックキャスティングで、みんなでアイデアを出し合い、実装につなげていく「フューチャーセンター」。世界初のフューチャーセンターは、1996年にスウェーデンの保険会社スカンディア社が設立した。
気候変動や貧困など一国だけでは解決できないことや、地域や企業など当事者だけでは解決が難しいこともある「複雑な問題」に対し、業界を超えた専門家やステークホルダーが集まり、未来志向でオープンに対話するのが特徴である。
オランダでは、国税庁が「シップヤード」というフューチャーセンターを立上げ、世代を超えた税に関する教育、持続可能な社会のための税利用のあり方についての対話・提案を重ねた。変化が求められる社会のなかで、このような場は時代とともに進化し、現在はリビングラボなど市民起点の場も増えている。セクターを超えたイノベーションの場のアライアンス組織であるフューチャーセンター・アライアンス・ジャパンによれば、場のエコシステムが今後重要であるという。
フューチャーセンターに共通するのは、次の4つの要素だ。
- 空間:多様なステークホルダーがいつでも課題を持ち込み、オープンに対話できる場
- ファシリテーター:対話をガイドする役割
- 方法論:対話・未来シナリオ・デザイン思考など目的に応じて活用するもの
- ホスピタリティ:通常の会議とは異なり、人と人との関係づくりを促すこと
これらの4つの要素を持った場では、問題そのものをさまざまな角度から見て、未来を描き、アイデアを出しあい、最終的に集った人たちが「仲間として」協力して次の一歩を踏み出せる状況が生まれる。その一連の流れがセッションと呼ばれるのである。
対話の場に欠かせないのが、参加者が自分ごととして考えられるフレッシュな問いだ。今回東京で開催されたセッションでも、参加者全員が自己紹介を終え、場が暖まってきたところで早速ファシリテーターから「あなたが万博で発見した『いのち』の『輝き』は?」と問いが投げかけられた。
万博での体験を、次の学びへ
万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」。もし「いのち」や「輝き」を自分自身の体験や見たものと結びつけるとしたら、何という言葉が浮かぶだろうか。
セッションではここから少人数のグループに分かれ、各々が自分の体験を振り返り始めた。

Photo by Kanta Nakamura (Newcolor inc)
例えば、今夏の命を削るような猛暑への対策について語る人たち。「サウジアラビアのパビリオンでは、中東らしい建物のおかげで日差しを防げた」「会場のシンボルである大屋根リングの下が日陰で命拾いした」「みんな給水所を探していた」「自販機も詰め替えが間に合っていない」
また、「『いのちの動的平衡館』の中で、『生命はやがて秩序を失い、大きな自然の循環の中に戻る』というストーリーがあったが、自然のシステムの中で人間の存在が他の生物を支えることはできているのだろうか?と思った」「コロンビア館で美しい映像に見惚れていた矢先に、コロンビア国内での上院議員銃撃のニュース。もしこのパビリオンに入らなかったら見逃していたはず」と話す人など、各々が「いのち」を解釈していた。

Photo by Kanta Nakamura (Newcolor inc)
その後、全員で対話を深めるために、対話手法の一つである「フィッシュボウル」を行うこととなった。フィッシュボウルは、参加者の椅子を円を描くように配置し、その中央に置かれた椅子に座った人が対話を始める手法だ。
外側に座る人は耳を傾けながら、もし「自分も話したい」と思えば、内側の一人と入れ替わって円の中に入ることができる。まるで金魚鉢(フィッシュボウル)をのぞくように、内側で交わされる言葉を外側が静かに見守り、ときに輪が入れ替わりながら議論が続いていく。その流動性こそが、この手法の魅力だ。

Photo by Kanta Nakamura (Newcolor inc)
「万博になかったもの」は何か
全員での対話でとりわけ盛り上がった話題が、「帰宅困難」を経験した参加者の体験である。
2025年8月13日夜、大阪メトロ中央線の電気設備トラブルにより運転が見合わせとなり、会場と接続する唯一の鉄道路線が遮断された。夢洲駅は一時閉鎖され、約3万8000人が帰宅できずに会場内で夜を明かす事態が発生した。博覧会協会は来場者に「会場内で待機」を呼びかけたが、情報発信や交通機関との連携が不十分で、多くの人が不安を抱えたまま夜を過ごすことになった。
当事者は語る。
「誰も大声でクレームを言わなかったのは本当にすごいと思いました。『明日仕事なのに困るなぁ〜』くらい。ただ、大阪メトロと万博運営の連携が取れておらず、駅に向かって並んでいた人たちは大混乱。情報がなく、水も手に入らないくらいでした。本当に縦割りだなと思いました」
この「縦割り」という言葉をきっかけに、別の参加者が続ける。「各国パビリオンもそうかもしれません。開催まで互いに内容を明かさず秘密主義で、蓋を開けてみたら結構似通った展示になっていた」「それぞれが自国のプロモーション合戦をするだけじゃなくて、国同士の横の連携があってもよかったのに」
交通による帰宅トラブルから、国際展示のあり方にまで広がった議論。共通していたのは、足りなかったのは「つながり」ではないかという視点だった。

Photo by Kanta Nakamura (Newcolor inc)
フィッシュボウルの中では入れ替わり立ち替わり、さまざまな意見が出た。全体的に「今回だけで終わらせるのではなく、得た学びを次に繋ぐには」「別のエキスポでこれはやりたい」と各々がいち来場者としてではなく、万博という場の作り手として主体的に話していたことが印象的だ。
来場者が作り手になる万博アイデア
さまざまな気づきを受け、セッションの最後では「こんな万博があったら面白そう」という自由な発想でのブレストがあった。各参加者から出てきたアイデアを一部紹介する。
- もしもサポーター制度:万博予約時に「自分ができること(力仕事、救命、言語など)」を登録し、会場で自然に助け合える仕組み。「お客さん」ではなく万博の主体的な参加者となれる。
- ゲリラ防災訓練:予定調和ではない“偶発的なイベント”として災害対応を体験できるプログラム。帰宅困難の経験から、非常時の対策をみんなで考える。
- 国版キッザニア/タイミー:子どもや若者が各国のパビリオンで働き、文化を体験をできる仕組み。食文化や言語を“やってみて学ぶ”参加型にするアイデア。
- 未来万博のタイムカプセル:万博来場者の気づきを蓄積し、次の万博や別の国へと引き継ぐ「レガシー」の仕組み。
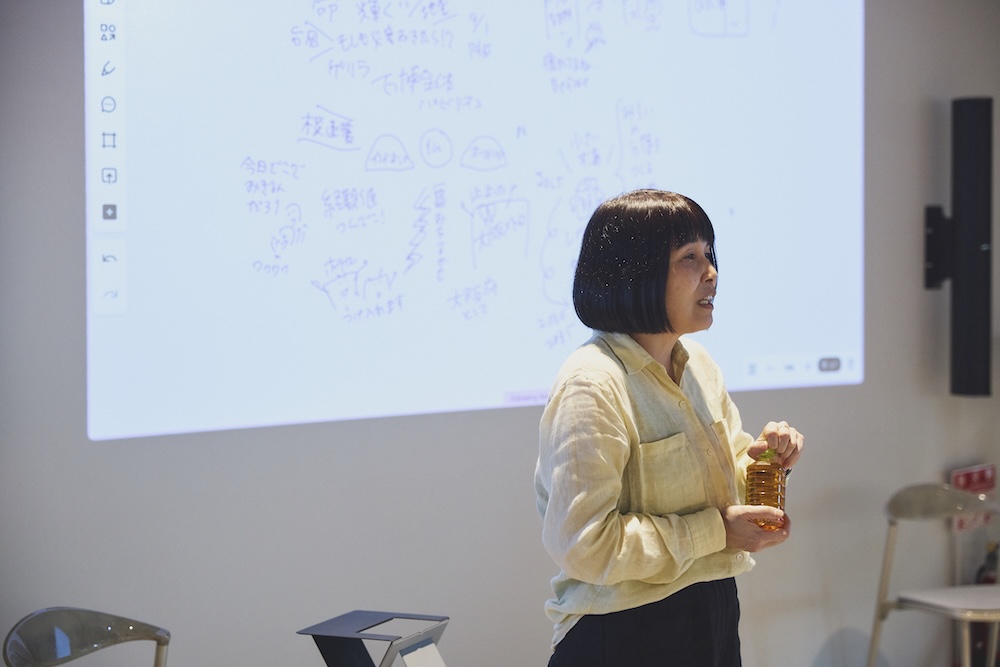
Photo by Kanta Nakamura (Newcolor inc)
1970年の大阪万博や2005年の愛知万博を実際に訪れた人、または親から話を聞いて育った子どもたちは、自らの意思で万博に足を運んでいるという。これは、過去の万博が「楽しかった」からこそ生み出された、ポジティブなレガシーと言えるだろう。
今回の万博も、来場者の声から「もっとこうだったらいいな」を学んだり、開催していた6ヶ月間で日本は何を学んだのかを別の国の万博開催者に共有したり、日本国内における別の大型エキスポの企画・運営に役立てたりできるかもしれない。そんなことを思えるセッションだった。
自発的な対話を生む「良い余白」
大いに盛り上がりを見せ、最後は「万博にみんなで行こうか」などと言いながら幕を閉じた今回のセッション。良い対話の場にするために、運営側はどのようなことを意識していたのだろうか。
セッションの主催者である、フューチャーセッションズ社の芝池玲奈(しばいけ・れな)さんと、コクヨ株式会社の齋藤敦子(さいとう・あつこ)さんに話を聞いた。
芝池さん「参加者の皆さんと話すだけじゃなくて、最終的に次に繋がるようなアイデアを出すことは事前に決めていました。ただ、始まってみると、万博の体験共有のところですでにグループ内の対話が盛り上がったので、あまり『次の流れはこう』と提示しすぎないのも大切なのかなと思いました。私もファシリテーターとしてではなく、いち参加者として楽しくフィッシュボウルに参加していた気がします」

フューチャーセッションズ社の芝池玲奈さん Photo by Kanta Nakamura (Newcolor inc)
齋藤さんも当日の様子を笑顔で振り返る。
齋藤さん「フィッシュボウルは参加者にとってやや高度な手法ですが、芝池さんが皆さんのやりとりを暖かく放置していたことが印象的でした。主体となるのは参加者で、場の力を引き出すのがファシリテーターです。万博での体験を参加者それぞれが話したいという空気がありました」

コクヨ社の齋藤敦子さん Photo by Kanta Nakamura (Newcolor inc)
今後の展望について、芝池さんと齋藤さんは、未来を生きる若い世代ともセッションをしてみたいと語る。実際のセッションの中でも、参加者から「大人だけでなく小中学生、高校生がこの場にいたら、また違う発見があるのでは?」という声が出ていた。万博を見る視点は千差万別。子どもたちは何を受け取ったのかを共有し、未来に繋げたいという。
また、別の参加者や企業とも万博についてセッションをし、協業できると嬉しいと語る。
齋藤さん「普段、一人の生活者として面白いと思っていることや、憤っていることを誰かと交換する機会はあまりないんです。万博はお祭りとしても楽しいですが、『いのち輝く未来社会のデザイン』って実は日本社会において重要なテーマなので、違う立場の人とこうやって対話する“場”があることは本当に大切だと思います。こういう場を増やしていきたいですし、やりたい人を応援したいと思います」
芝池さん「もともと、当社が開催した別のセッションで万博のことを少し語ろうとしたら思った以上に盛り上がったので、今回本格的に企画しようとなったんです。企画もフューチャーセッションズ社だけで考えるのではなくて、コクヨの齋藤さんや、場所を提供してくださったSYNERGYCAの皆さんと共同で作ったからこそ良い時間になったと思っていますし、今後も続けていきたいと思います」
万博が終わっても、実験場は続く
筆者としても、今回のセッションの場作りは学びになった。一般的なイベントや対話の場では、タイムキープや、話が逸れたときの進行管理、ファシリテーターが率先して場を盛り上げたりすることも大切だが、芝池さんは「この次の流れですが、皆さんどうしたいですか?」と参加者に問いかけた。そして参加者の提案によって、その先の対話が進んでいったのだ。
参加者が運営に「次はどうすればいいですか?」「どんな質問を投げかけてくれるんですか?」とお客様目線で頼りきりになっている印象はなく、良い意味で全員が自発的に動いていた時間だった。
万博のコンセプトは、「People’s Living Lab(未来社会の実験場)」。企業が自社の取り組みを見せたり、各国がパビリオンで自国をアピールをするだけの場ではなく、来場者を含めた世界80億人がアイデアを交換し、地球全体の課題解決のために共創する場として作られている。
万博のレガシーは巨大な建造物や技術だけではなく、そこで得られた気づきを次にどう活かすかではないかと筆者は思う。今回のセッションで示されたのは、誰もが未来を語り、実践する主体となり得るということだ。「万博はどうだったか」では終わらない。「そこから何を学び、次にどう動くのか」、その問いこそが、未来社会をデザインする私たち一人ひとりへの宿題なのだ。
【参照サイト】株式会社フューチャーセッションズ
【参照サイト】コクヨ株式会社
SYNERGYCA 共創ラウンジとは?
住友化学株式会社が2021年12月にオープンした施設。自社の技術やアイデアを社会課題の解決に繋げ、産官学の顧客やパートナーが交流する場である。
ラウンジは「集う」「体験する」「交わる」の3つの機能に分かれており、住友化学の技術を体験しながら、参加者同士で議論し、課題解決や新たな事業の可能性を探る場となっている。
【公式サイト】SYNERGYCA 共創ラウンジ












