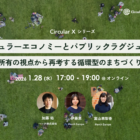かつて武士は、鎧の下に藍染木綿を身につけていた。藍には抗菌作用があり、傷の化膿や悪化を防ぐためである。
“ジャパンブルー”と称され、日本の伝統色であり、武士道とも深く結びつく藍染。その藍染の染め場を訪れた際に見たのは、まるで生き物を世話するように藍を育て、糸を丁寧に染める光景だった。
「藍は生きている」
創業110年の歴史を持つ藍染の老舗、野川染織工業・五代目の野川雄気氏は語る。
「折る」「畳む」「揃える」「結ぶ」──藍染の剣道着をケアする所作の中には、日本人が大切にしてきた“日々を整える心”が宿っている。
本記事では、野川染織工業五代目・野川雄気氏と、いばらき中央認定こども園の園長として働く、教育者であり藍染の長年の愛用者、雨谷水紀氏(剣道七段)との対話を通して、現代の暮らしのなかで日本人が失いつつある“生きる力”と”人の強さ”について考えていく。

(左)野川染織工業 五代目 野川雄気氏(右)いばらき中央認定こども園 園長 雨谷水紀氏
“色落ちの味わい、着心地が全く違う”。藍染の魅力を探して
「藍染」と聞くと「日本の伝統工芸」というイメージを持っている人がほとんどではないだろうか。その藍染が、剣道の道着・袴にも使われていることはあまり知られていないかもしれない。
実際に剣道を続けている人たちでさえ、近年では洗濯しやすく、安価で扱いやすいジャージ素材の道着を選ぶ人が増えている。試合会場や審査会場に行けば、多くの剣士がジャージ素材の剣道着を身につけている。
そんなある日、茨城県のとある少年剣道道場に、外の国から来た剣士を案内する機会があった。筆者が数年前、オランダに住み剣道をしていた縁から、日本帰国後は外国出身の剣士と日本の剣士をつないでいる。
その際、指導者である雨谷水紀氏にこんなことを言われた。
「私は藍染の、特に『武州』と呼ばれる地域で作られた『武州一』の剣道着しか着ないんです」
その簡便さから、ジャージ道着を選んでいた私は思わず尋ねた。「何がそんなに違うんですか?」と。すると先生は、一枚の写真を差し出した。
「この写真の中で、綿で藍染の道着を着ているのは私だけなんですよ。色落ちの味わいや着心地は、まったく違います」
そこまで言われると、がぜん興味が湧いてくる。しかし、小売店に行ってみたところ、「いや、ジャージの方がいいですよ。安くて洗いやすいですから」と勧められるばかり。
ジャージはジャージでとても便利で筆者は好きだが、藍染剣道着の本当の魅力とは何なのか。自分が知り得ない何かがあるような気がしていた。そしてちょうどその頃、知人を通じて紹介された野川染織工業が直営店を構えたと知り、訪ねてみることにしたのだ。
藍は生きている。染め場で見た驚きの光景
藍の染料は、ただの植物から生まれるわけではない。藍の植物の葉っぱを乾燥させ3ヶ月間発酵させた後、形を整えて再び乾燥させると「藍玉」になる。藍玉の中では、微生物が仮眠状態で眠っている。この微生物たちをもう一度、目覚めさせることで発酵が進み、藍染めの染液が作られる。まるで生き物の命を、ゆっくりと呼び起こすような工程である。

藍玉
染液を入れる甕(かめ)は染め場に全部で13個あり、いくつかの甕に藍染液が仕込まれている。染める際には、熟成された古い甕から順に使って糸を染め上げていく。

染液を入れる甕(かめ)


空気に触れると、藍は色が変わる。藍の中では、今も微生物が生きているという。
工場というと無機質な印象だったが、生き物の世話をしているという表現がぴったりなように感じた。その印象は、筆者の手元に道着や袴が届いた後も変わらなかった。「衣類が生きている」「まるで生き物のようだ」と感じたのは、これが初めての体験である。

染められた糸は同じ敷地内の工場で布として織られ、ベテランの職人の手で剣道着や袴になっていく。
生き物を世話するように、人の手によって丁寧に作られたものだと知ると、不思議と、自らの剣道着への向き合い方にも変化が生まれる。袴を畳むとき、自然と作り手の顔が思い浮かぶことがあった。
「折り目正しく」という言葉があるように、剣道においては袴も道着も、美しく整えられていることが望ましい。しかし、それには手間がかかるし、畳み方や扱い方を身につけるための訓練も必要である。「これだけ便利な世の中で、そんなことに時間をかけなくても……」という言葉が聞こえてきそうだ。けれど、その“手間”の中にこそ、ものと人との関係性を丁寧に結び直す時間があるように思う。

日常の所作が、人の強さを作る
テクノロジーの進化により、スマートフォンを開けば、たいていの「正解」は瞬時に手に入るようになった。今後はAIによる応答も、より個別最適化されていくだろう。だがその一方で、すぐに成果が出ないことに耐えきれず、途中で諦めたり、取り組みを放棄してしまう人が増えているという指摘もある。
その点について、剣道道場だけではなくこども園も経営する雨谷氏は、次のように語った。
雨谷氏「紐を自分で結ぶという、ほんの小さな成長でも子どもは本当に変わります。そして、そうした小さな所作こそが、すごく大事な教育だと思うのです。結び目を丁寧に、しっかり縛る。それだけで『今日もがんばろう』と思えるんですよ」
「結ぶ」「整える」という行為は、日本人にとっては何気ないことかもしれない。しかし、それらが持つ静かな美しさや所作の流れは、外の国の人々から「美しい」「儀式のようだ」と評価されることがある。それは、スイッチのように人の心を切り替え、姿勢や表情にも影響するのではないだろうか。
野川氏「“結ぶ文化”自体は剣道だけに限ったことではありませんが、武道を学ぶ中で出会える面白さの一つですよね。『結ぶ』『畳む』……それらの日常の所作に、どれだけ気と胆力を込めたか。その過程の中にこそ、“人の強さ”が織り込まれていくのではないでしょうか」
実際、外国製の剣道着には、マジックテープで留める仕様のものもある。それが便利だと思う反面、利便性を追い求めすぎることで、知らず知らずのうちに失われていくものもあるのかもしれない。

不便さ、非効率が包含する価値
雨谷氏「私は時々、保護者の方に『道着と袴だけでもいいので、自分で洗わせてあげてください』と伝えています。私自身、かつて武州一の藍染の袴をお風呂場で踏み洗いしていました。道着も袴も、手洗いすると、藍が落ちてお風呂場が青く染まるんですよ。すると親に叱られたり、一緒に掃除したり……そういうことも大切な教育になると思うんです。
しかも、綿でできた剣道着は乾きにくい。天候や時間によっては洗濯が間に合わないこともあるし、少し匂いが残ることもあるかもしれない。でも、そうした不便さや不完全さも含めて、『これが剣道なんだ』と感じることも、時には大事だと思うんです」
社会がどんどん便利になる今のような時代だからこそ、あえて少しの不便さを残すことに意味があるのかもしれない。便利さ自体は悪いことではないが、至れり尽くせりのサービスや環境だけでは、感情の揺れ幅や、心が動く経験が少なくなってしまう。
雨谷氏「生きていると、物事は簡単に進まないことの方が多いです。すぐに答えが出ない状況を、自分で感じ、考え、受け止める……そうした日々の積み重ねが、きっと自分自身を整える力につながっていくのではないでしょうか。
それは『濡れたままでいいから着て、稽古しなさい』と無理に求めるのは違うと思っています。でも、子ども自身が『このまま乾かさなかったらどうなるんだろう』とか『濡れていて嫌だな』と感じ、自分で考えてみること。そのプロセスこそが大事なのです。そうした経験の中で、忍耐力や自分なりの工夫が育まれていくのではないでしょうか」

野川染織工業 五代目 野川雄気氏と、教育者であり藍染の長年の愛用者、雨谷水紀氏(剣道七段)

雨谷氏の藍染剣道着。一番色のさめた道着は20年以上着続けているという。長く使い続けることで、味わいが生まれる。
色が変化する過程に、品格と美しさが宿る
藍染には独自の工程があり、何度も染めを重ねることで、色に深みが増していく。藍の色には「褐色(かちいろ)」「濃紺(のうこん)」「浅葱(あさぎ)」など、実に48もの色味があると言われている。だからこそ、藍染の衣は長く着れば着るほどにその色が変化し、味わいを楽しむことができる。経年変化を楽しむという美意識はまさに、日本人が古くから大切にしてきた「侘び寂び」の感覚にも通じているのではないだろうか。
雨谷氏「藍染の道着は、自分がこれまで稽古を積んできた過程そのものを表現してくれます。色の味わいや風合い、布の変化。それらすべてを、袖を通すたびに日々感じることができます」
海外で剣道をした際、紫や茶色に変色してしまった道着を目にしたことがある。どのような工程で作られたのかはわからないが、これらは藍の青が持つ奥深い色落ちの美しさとはまったく異なるものだ。本来の藍染めは、時間とともに色が落ち、青の濃淡が移ろう過程にこそ品格が生まれる。そのことを、私たち日本人自身がもっと自覚し、伝えていくべきではないだろうか。
藍染が示す、新たな「強さ」のかたち
日本刀というかつての殺傷の道具を、芸術としてまで昇華させた文化を持つ国は他に例がないという。そして、武士たちにとって“戦闘服”だった藍染の剣道着もまた、「生きる力」や「本当の強さ」といった、時代を超えた価値を私たちに問いかけてくれるのかもしれない。
雨谷氏「藍染の道着には、作る過程に職人さんの思いが詰まっています。それを身に纏うことで、いいことも悪いこともすべて含めて、“生きる力”が育まれるのだと思います。
教育の現場にいて、これからは『生きる力』がより一層必要になると感じます。世界にはいまもなお戦争が続いている国もあります。でも、日本人は、戦争の恐ろしさを一番よく知っているはずです。本当の強さとは、誰かを攻撃する力ではなく、人に優しくできる力です。本当に強い人は、颯爽とした佇まいで、人に優しくできる。
そこが今、忘れられている気がしますし、藍染のような伝統文化を通して、今一度考えていくべきなのではないでしょうか」
野川氏「礼や型の意味、殺し合いから始まった武道としての本質……どこに魅力を感じるかは人それぞれですが、僕らが藍染の剣道着を作っているのは、そういう歴史や意味を、次の世代に伝えたいからなんです。
武州一として残したいのは、職人たちの技術と思いです。一度作るのをやめてしまったら、もう一度同じものを作るのは簡単ではありません。だからこそ、続けていくことに意味があるんです。たとえ、結果として出来上がるものが剣道着でなくても構わない。例えばコースターや衣類でもいい。そのような思いから、私たちは剣道着以外の商品も作り、直営店で販売しています。
ただ、これまでずっと剣道着と一緒に歩んできたからこそ、やはり剣道着も残していきたい。そのためにアプローチを変えながら、挑戦を続けていきたいと思っています」


野川染織工業の直営店の名前は「甕覗き(かめのぞき)」。これは48色ある藍染のうち、薄い色の名前の一つだという。「藍の世界を少しでも覗いてみてほしい」──そんな願いが込められているそうだ。
筆者も実際に、直営店で購入した藍染のTシャツやコースターを、この記事で触れた物語と一緒に海外の友人に贈るととても喜ばれ、共感された。“思い”や“意味”は、国境を越えて人の心に届くのだ。私たちはこうした文化や言葉をこれからも大切に守り、伝えていくべきだと改めて思う。
Text & Photos by Mariko Sato
Edited by Erika Tomiyama