サーキュラーエコノミーの実現は、一国だけで完結するものなのか?
資源も、製品も、人の知恵も、国境を軽々と越えて動くいま、オランダはその問いに真正面から向き合っている。
「サーキュラーエコノミーへの移行は、犠牲ではなく進歩であり機会です。先をゆく起業家やパイオニアこそが、これからの市場を導くことになるでしょう」と語るのは、ホランド・サーキュラー・ホットスポット(以下、HCH)のCEOであり、欧州循環経済ステークホルダープラットフォームの共同主催者(※取材当時)でもあるFreek van Eijk(フレーク・ファン・アイク)氏だ。
世界各地で循環の連鎖を生み出してきた彼に、サーキュラーエコノミーの現在地と、そこに至るために必要な「協働のかたち」、そして日本が今考えるべきことを聞いた。

2025年6月、ブリュッセルの欧州委員会が開催したEUグリーンウィーク「サーキュラーエコノミー」にて登壇するフレーク氏(撮影:西崎こずえ)
話者プロフィール:フレーク・ファン・アイク
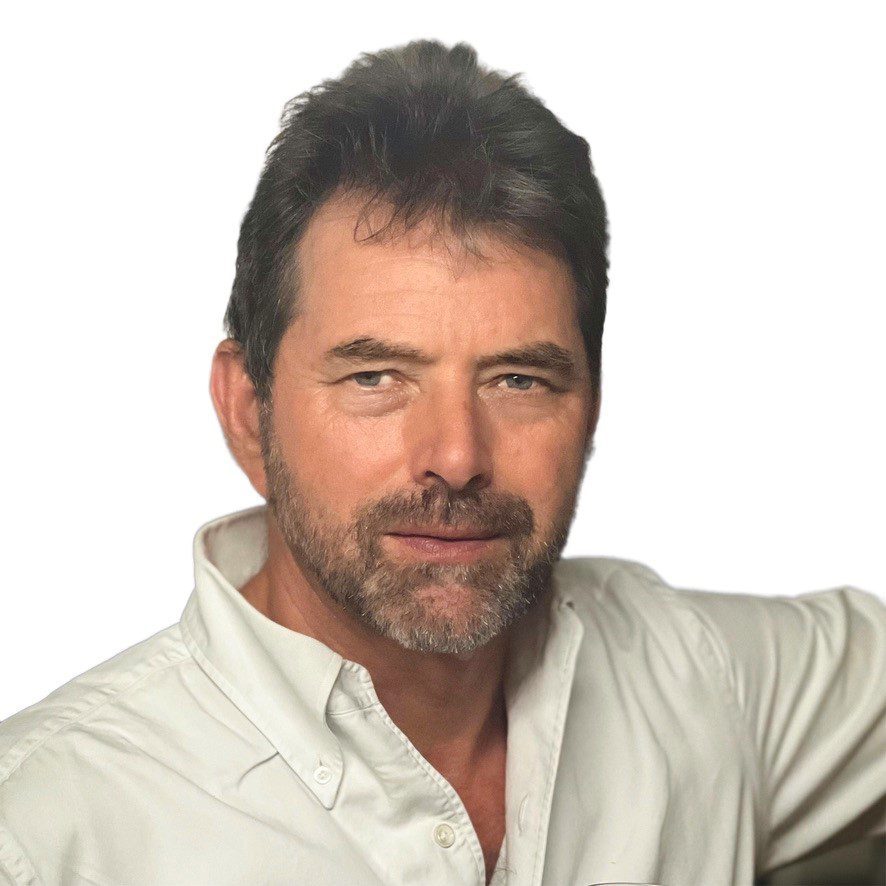 地オランダのサーキュラーエコノミー推進機関「ホランド・サーキュラーホットスポット(HCH)」のCEO。HCHは政府機関や大学・研究機関、そして特に企業を結び付け、国際レベルでのサーキュラーエコノミーへの移行を促す民間・公共連携のプラットフォームとして機能し、知識共有や起業家精神の育成を支援。オランダの州や企業、研究拠点が集まって持続可能な循環型・バイオベース経済を目指すアライアンス「Circular Biobased Delta」の副会長や欧州連合の関係者を束ねサーキュラーエコノミーの実現を目指す「欧州循環経済ステークホルダープラットフォーム(Circular Economy Stakeholder Platform)」の共同主催者。
地オランダのサーキュラーエコノミー推進機関「ホランド・サーキュラーホットスポット(HCH)」のCEO。HCHは政府機関や大学・研究機関、そして特に企業を結び付け、国際レベルでのサーキュラーエコノミーへの移行を促す民間・公共連携のプラットフォームとして機能し、知識共有や起業家精神の育成を支援。オランダの州や企業、研究拠点が集まって持続可能な循環型・バイオベース経済を目指すアライアンス「Circular Biobased Delta」の副会長や欧州連合の関係者を束ねサーキュラーエコノミーの実現を目指す「欧州循環経済ステークホルダープラットフォーム(Circular Economy Stakeholder Platform)」の共同主催者。
HCHの誕生と使命。循環の「知」と「実装」をつなぐ仕組み
オランダは、世界に先駆けて「100%サーキュラーエコノミー国家」を目指す方針を掲げた(※)。その実現を支えるために、政府・企業・研究機関をつなぐ場として生まれたのがHCHだ。
「私たちのミッションは、ビジネス・知識機関・政府を結びつけ、サーキュラーエコノミーへの国際的な移行を加速させることです」とフレーク氏が語る通り、HCHでは、成功事例の発信を通じて知見を広げるとともに、企業の国際展開や資金調達の支援、政策協調を促しながら、人材育成にも力を注ぐ。
中でも、変革を担うリーダーを育てる「サーキュラー・アクセラレーター・トレーニング」では、参加者がリニアエコノミーの課題を見つけ出し、循環型の機会を発見して製品やビジネスモデルを再設計し、サプライチェーン全体を巻き込む手法を学ぶという。
また、HCHはテキスタイルやバッテリー、農業・バイオマス、ケミカルリサイクル、循環型建築など、多様な分野に関する報告書も発行している。たとえば、オランダの循環型繊維産業を扱った出版物では、現状と将来の可能性を分析し、国際的な対話と協力の重要性を訴えている。
「私たちは早い段階で気づいたのです。オランダ一国だけで完全なサーキュラーエコノミーを達成することは不可能だということに。人やもの、自然、文化、企業は国を越えてつながっています。だからこそ、オランダの移行を実現するためには、世界全体の移行を促す必要があるのです」
世界のホットスポットが示す、循環の連鎖と協働のかたち
サーキュラーエコノミーの移行を加速させるうえで、いま世界に欠けているのは何なのだろうか。
「私たちは、世界が完璧に循環しはじめるのを待ちたくなるものです。しかし、必要なのは“まず始めてみること”。サーキュラーエコノミーを実現するためには、傍観して理想論を語るのではなく、実際に行動することが力になります。勝つか学ぶことがあるだけで、負けることはありません」
彼の言葉どおり、HCHは“実践を通じて学ぶ”という哲学を掲げ、各国の官民と協働して循環の仕組みを実装してきた。
一方で、理想の実現には多くの構造的な課題が立ちはだかる。欧州では国ごとに規制や税制が異なり、製品カテゴリーによって標準やリサイクル義務も違う。単一市場の確立は容易ではない。「リサイクルだけでは問題を根本的に解決できません。だからこそ、“廃棄物を出さない設計”と“ビジネスモデルそのものの転換”が必要なのです」とフレーク氏はそう語る。
EUは現在、デジタル製品パスポート(Digital Product Passport:DPP)の導入や職業教育投資を進め、企業と労働者の能力向上を支援している。2025年に発表された「クリーン産業ディール」では1,000億ユーロ超を投じ、産業競争力と循環経済の融合を図る計画だ。

Imagei via Holland Circular Spot
一方で、「包装や繊維分野への配慮が不足している」との指摘もあり、政策と産業界の対話が課題となっている。
「私たちがサーキュラーエコノミーに必要なのは、著作権(コピーライト)ではなく“コピーする権利”です。皆が得た知識を共有し、学びながら前進していくことが不可欠です。勝つか学ぶか──負けはありません」
欧州では、こうした考え方が少しずつ浸透しつつある。サーキュラーエコノミーはもはや“ニッチな概念”ではなく、産業政策の中心へと移行しつつあるのだ。
フレーク氏が共同で運営する欧州循環経済ステークホルダープラットフォーム(ECESP)も、政策・企業・研究・市民社会を横断して知を共有するネットワークとして機能し、「世界に光を放つ灯台(lighthouse)」の役割を担っているという。
「灯台とは、単に道を照らすだけではありません。人々が自ら進む方向を見出すための“共通の座標”なのです」
日本への示唆。連携の輪にどう加わるか
日本でも、サーキュラーエコノミーへの舵切りは避けられない。資源制約や気候危機、サプライチェーンの再編が迫るなか、従来型の大量生産・大量廃棄モデルはすでに限界を迎えつつある。フレーク氏は、日本の現場改善やものづくり文化の中にこそ、循環移行のヒントがあると見る。
「私たちが提唱する“実践しながら学ぶ”“共有する権利”という考え方は、日本の現場文化ととても相性が良いのです。地域単位の取り組みは素晴らしいですが、国全体として一貫した支援と政策の枠組みが必要だと思います」
国際的なサーキュラーネットワークに参加することは、日本が政策形成の現場に立ち、国境を越えた公共調達や評価指標づくりを主導する機会をもたらす。
欧州では、オランダ国道管理局(RWS)とベルギー公共廃棄物庁(OVAM)が循環型調達で協力しており、公共調達を通じた基準の国際調和が進みつつある。日本もこうした二国間協力を広げることで、他国のエコシステムや企業と結びつく足がかりを得られるだろう。
「循環型インフラは国際協力なくして成り立ちません。知識やイノベーションを育み、共通のプロトコルと基準を整えるために、国同士が連携する必要があります」
製造業にとっては競争力を高めるチャンスだ。自動車や電子機器、航空機など輸出産業を強みに持つ日本では、電気自動車への移行や年間300万台を超える使用済み車両のリサイクルに備えて、再生材の回収やリマニュファクチャリングの需要が急増している。

Imagei via Holland Circular Spot
オランダ側の分析でも、日蘭連携による資本財の再製造やリファービッシュは有望分野とされ、航空機や風力発電設備などでも協働の余地が大きい。こうした取り組みは、希少資源の安定供給を確保しながら国内産業の付加価値を高めることにつながる。
さらに、サーキュラーエコノミーでは製品を「売る」から「使い続ける」へと転換するサービス化モデルが重要になる。製品の寿命を延ばすためには、保守・アップグレードを含むサービス提供が求められ、逆物流や回収・リユース・リサイクルを担うロジスティクスの役割も大きい。
サービス産業でも、修理や再販、サブスクリプション、資産管理、データ分析など、ライフサイクル全体を支える新たなビジネスが広がっている。デジタル製品パスポートなどの技術を活用すれば、消費者との関係性はより長期的なものへと変わるだろう。
「こうしたビジネスモデルは、もともとアフターサービスやリースに強い日本企業にとって大きなチャンスです。国際基準づくりに関わることで、海外市場に適合したサービスを展開しやすくなるはずです」
循環経済の議論には、欧州だけではなくアジアや北米など多様な地域の視点が必要だ。アジアの製造業はいまや世界の供給網の中心を担っており、資源安全保障と競争力の両立が求められている。
「日本が国際ネットワークに加わることで、アジアの経験やニーズを世界の議論に反映させることができます。国際基準づくりや市場開拓に貢献することが、日本の次の役割だと思います」
編集後記
取材を通して印象的だったのは、オランダが早い段階で「自国だけではサーキュラーエコノミーを実現できない」と認め、その事実を出発点として「世界とともに進む覚悟」を固めたことだ。
循環型インフラは、もはや一国の努力では完結しない。知識やイノベーションを共有し、共通の基準やプロトコルを整え、再生材の国際市場を育てるには、国境を越えた協調が欠かせない。HCHはまさにそのための中核として、各地の政府や企業、研究機関をつなぎながら、サーキュラーエコノミーを「理念」から「実装」へと変えている。
波紋のように広がるホットスポットのネットワークは、産業、物流、サービスを巻き込み、新しいビジネスと雇用の芽を生み出している。リマニュファクチャリングや逆物流といった分野はその象徴だ。
「コピーライトよりも“コピーする権利”を」──フレーク氏のこの言葉は、知を独占するのではなく、共有することで循環を加速させようとする思想の表れでもある。
日本にとっても、この「共有の哲学」をどう社会実装につなげていくかが、これからの競争力を左右する鍵となるだろう。
※ Circular Dutch economy by 2050
【参照サイト】Holland Circular Hotspot
【関連記事】サーキュラーエコノミーの実装に欠かせない「共通語」とは?ドイツ・機械工業連盟が語る脱炭素のカギ
Edited by Megumi












