All posts by Okazaki Akiko

座るだけのSOSサイン。孤独を感じる子どものための対話型ベンチ
いま北米を中心に世界で広がっているのがベンチを活用した、子どもたちの「居場所」づくり。ベンチに座るだけで、周囲に心のSOSを発していることを知ってもらえるというものです。

政治への失望を期待に変える?ヨーロッパで広がる民主主義の刷新
世界で大きな潮流となっている「民主主義の刷新」。政治を政治家だけに任せるのではなく、市民の発案で法律や予算を提案したりする市民の動きを見ていきます。

気候危機時代に「神話」を読もう。いま学びたい古代の哲学とは
「気候変動時代の環境倫理を模索するために、神話を読もう」。いま、神話が、単なるファンタジーではなく、人間を自然のなかの一つの構成要素として位置づける、実用的なツールだと注目されています。

AIが低予算のレシピを提案してくれる「インフレ時代のクックブック」
世界で加速するインフレ。カナダでは、食料品の買い物をする際に価格を抑えたものを選び、それらお得な食料品でレシピの作成をすることを助けてくれるAIが誕生しました。

レストランの「秘密のメニュー」で知る、労働者の不都合な真実
コロナによってQRコードからレストランのメニューにアクセスできるお店が増えましたが、外国人労働者の権利問題を訴えるカナダの団体が、これを装った「秘密のメニュー」キャンペーンを開始しました。

思わずリサイクルしたくなる、世界のナッジ事例5選
「思わずラベルを剥がしたくなる」「自然に分別したくなる」そんなナッジをつかった、リサイクルを促進する世界のアイデアをご紹介します。

“死んだら、木になろう”。アメリカの墓地で始まる「樹木葬」とは?
アメリカで、亡くなった人々を「木」にする「樹木葬」が2023年春から開始します。人々の眠る墓地を森林に変えて、地球の環境を再生しようというものです。

世界の「都市×生物多様性」クリエイティブ・アイデア5選
生物多様性を実現するための取り組みは、どこか遠くにいる生物のために「しなくてはならない」「大変なもの」とネガティブに捉えられがち。今回はちょっと前向きになれるような、クリエイティブな生物多様性実現のアイデアをご紹介。

アメリカの高校に、「生徒が働ける」カフェがオープンした理由
米ウォーカー・ハイスクールの校内には、コーヒーショップやピザショップ、信用組合の支店などがあり、職業訓練プログラムを展開しています。一体、生徒にどんな影響を与えているのでしょうか?

家事や介護に追われる女性を支援するまちづくり。南米・コロンビアの「ケアリング・シティ」とは?
南米のボゴタでは、徒歩30分圏内で日常に必要なサービスを受けることができる「30分間都市」にするという計画のもと、公的サービスの集約を行うことでジェンダー平等を実現するまちづくり「ケアリング・シティ」が進んでいます。
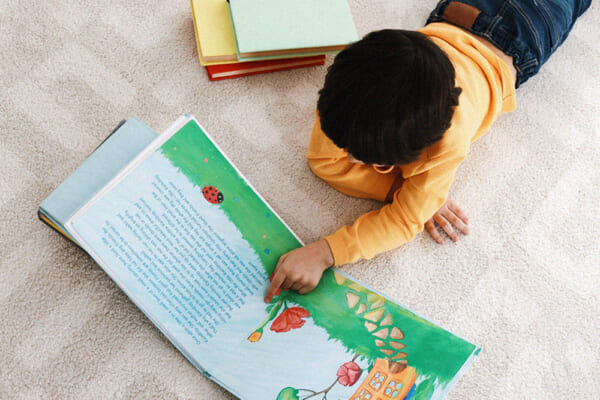
月に1冊、本を届けます。アメリカの教育格差を縮める「想像図書館」
米国をはじめ世界各地で広まる「イマジネーションライブラリー」。0歳から5歳までの子どもであれば誰もが、専門家選りすぐりの本を毎月無料で受け取ることができます。

気候変動を食い止めるカギは女性?ジェンダーと環境問題の深すぎる関係
女性は気候変動に対して無力な「犠牲者」なのだろうか?そうではない。女性こそ、サステナブルなコミュニティづくりをリードできる存在なのである。カギとなるのは、妊娠・出産など女性特有の事情に対して、法制度など不足している部分を補うことだ。ここで、いくつかの成功事例をご紹介する。
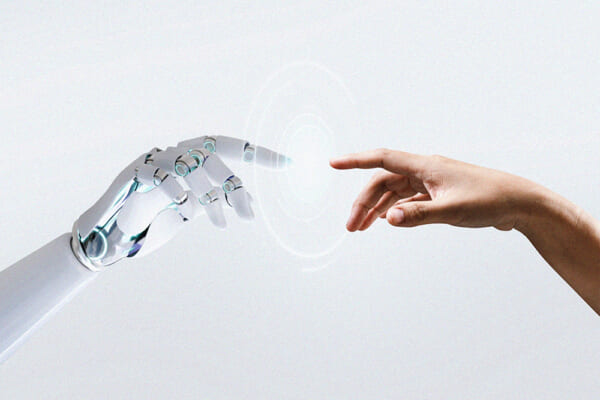
デンマークで、AI主導の政党が誕生。民主主義はどう変わっていくのか
デンマークにAIが主導する政党「人工党」が誕生しました。ロボットやAIは、民主主義やサステナビリティなど私たちの社会を豊かにする存在となるのでしょうか?

アートやサーフィンを“処方”する。メンタルヘルスをケアする「社会的処方箋」アイデア7選
アート鑑賞から森林浴、サーフィンまで──薬ではなく社会や自然と人々をつなぐ“処方”するアイデアが世界各国で広がっています。

貧困層の若者へのベーシックインカム、米国ロサンゼルスで開始へ
アメリカ・ロサンゼルスでは、2022年8月末から若者に月1,000ドル(約15万円)を3年間無条件に支給する、ベーシックインカム・プログラム「TAY portunity収入保証プログラム」を開始しました。対象となるのは、経済的に困窮している18歳から24歳までの若者で、ロサンゼルスの就労支援サービスに登録している者のうち無作為抽出された300人です。

COP27の注目ワード。気候変動の「損失と損害」の責任を、デンマークが世界で初めて負う国家へ
デンマークが気候変動によって引き起こされた途上国の「損失と損害」に対し約19億円の資金拠出を確約。同テーマは、11月にエジプトで開催されるCOP27でもメインテーマとなっています。
