Tag Archives: 社会

気候危機を歌う曲が、英国チャートで史上初の一位を獲得
気候危機を歌った曲「We Tried」が、史上初の英国iTunesチャート一位を獲得しました。いま多くの人々に聴かれるこの曲をつくったのは、若き環境活動家でした。

スーパーで孤独解消。オランダの「おしゃべり歓迎」買い物かご
緑の買い物かごは「話しかけてOK!」のサイン。オランダの食料品店・アルバート・ハインで、人々の孤独を解消するため「おしゃべり歓迎」買い物かごを設置するキャンペーンが始まりました。

私たちは成長し続けなきゃいけないの?資本主義への疑問を歌う音楽アルバム
拡大し続ける資本主義経済からの脱却を目指す、脱成長論。この脱成長について歌う音楽アルバムが、イギリスのレーベルからリリースされました。

2024年1月からフランスで生ごみの分別義務付け開始。現地の様子は?
家庭ごみの約30%の割合を「生ごみ」が占めているフランスで、2024年1月1日から、すべて

2050年までに完全サーキュラーシティを目指すアムステルダム、2026年までの新たな中期計画を発表
2050年までに完全サーキュラーシティを目指すアムステルダム市が、2026年までの新たな中期計画を発表しました。本記事では、今後4年の中期計画書となるこのアジェンダについて解説します。

海からテーブルへ。タイの漁村が始めた、地域経済を盛り上げるエコツーリズム
海洋汚染によりかつて盛んだった漁業が衰退してしまったタイの漁村アンシラに現れたパビリオン。とったカキをそのまま海の上で食べることができ、地元の地域経済も盛り上げています。【エコ・ツーリズム】

【3/31〆切】今こそ世界をリデザインする。オランダ発のWhat Design Can Doが気候危機をテーマにコンペを開催
WDCDが1月17日、IKEA Foundationとのパートナーシップのもと、気候危機をテーマとしたグローバル・デザイン・コンペティション「Redesign Everything Challenge(すべてをリデザインする挑戦)」の募集を開始しました。

学費は「ごみ」で支払い。環境問題を学びながらスキルを身に着けるカンボジアの学校
カンボジア「ココナッツスクール」では、子どもたちが教育を受ける機会を創出するだけでなく、環境と貧困の課題を同時に解決する取り組みをおこなっています。

イベント業界は循環型へ移行できるか?環境負荷ゼロへの道のり
イベント産業はリニアの典型?その理由と、国内・海外でイベント産業を変える取り組み事例をまとめました。

建築の背景にある植民地主義に向き合う。イギリスの“不快な“街歩きツアー
イギリスの各都市で開催されている、“不快な“街歩きツアー。ガイドを担当する学生たちが街の歴史的背景を様々な角度から伝え、それに関するディスカッションを促しています。

そのほくろ、皮膚がんじゃない?いびつな形のクッキーが教えてくれること
ブラジルで生まれた、いびつな形のクッキー。陽がさんさんと降り注ぐブラジルで、医師がこのお菓子をプロデュースした理由は?【皮膚がんの早期発見を助けるクッキー】

グアテマラ先住民族に学ぶ、善き生き方「ブエン・ビビール」とは?
グアテマラ先住民族の女性たちが実践する、地域に根差したメンタル・ウェルビーイング・コミュニティと、その根底にある「ブエン・ビビール(善き生活)」という考え方を紹介します。

【現地参加レポ】オランダのデザインウィークが掲げた「5つのミッション」から見る。気候変動時代のデザイナーが果たすべき役割とは?
毎年オランダで開催されるダッチ・デザイン・ウィーク。アイントホーフェン市内110以上の会場で革新的なデザインの展示会やトークセッションなどのイベントが開催されます。この記事では、そんなDDWで掲げられた5つのミッションと注目作品を紹介します。

若者だけの問題にしない。気候変動に立ち向かう、シニア・コミュニティがアメリカで発足
気候変動のアクションをするのは若者だけじゃない?60歳以上の人たちで構成された気候変動に対するアクションをする組織「Third Act」がアメリカで発足されました。
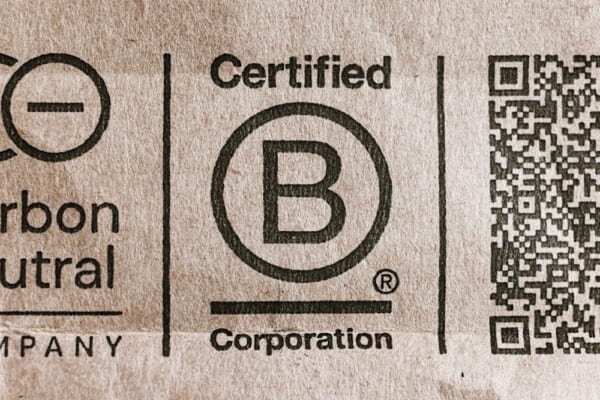
B Corp取得企業は経済危機に強い?改めて考える、収益と社会性の関係
B Corporationの認証団体であるB Labが、B Corpの収益力に関する興味深い調査レポート「Financial Performance and Resilience of B Corps(Bコーポレーションの財務パフォーマンスとレジリエンス)」を発行しました。

今、自分にできることを。能登半島地震の被災地を支援するアクションまとめ
【能登半島地震】2024年1月11日現在、被災地への支援に向けて動き出している団体や企業の取り組みをまとめました。
