2018年9月6日午前3時7分、北海道胆振東部を震源とするマグニチュード6.7の地震が発生した。この地震により、道内最大の発電所である苫東厚真火力発電所が停止し、約295万世帯が停電。北海道のほぼ全域が大規模停電(ブラックアウト)に陥った。これだけの広範囲に及ぶ大規模停電は、日本で初めての出来事だった。
このブラックアウトを受け、「これまで以上に町民が安全・安心に暮らせる、災害に強いまちづくりが重要」という考えのもと、2023年、北海道小清水町に誕生したのが、小清水町防災拠点型複合庁舎「ワタシノ」である。
ワタシノには、身のまわりにあるモノやサービスを、日常時にも非常時にも役立つようにデザインする、「フェーズフリー」の考え方が組み込まれているのが特徴だ。フィットネスジムやカフェ、ランドリーといった日常的に利用できる施設が併設しており、行政の枠を超えた「地域の交流拠点」としての機能を持つ。これが、非常時にはフィットネスジムとスタジオが一時避難場所に、コミュニティスペースとカフェが炊き出しスペースになり、ランドリーは衣類の洗濯など衛生保持に活用できる。また、温泉熱を利用した床暖房があり、停電になっても暖かく過ごせるのだ。

ワタシノ外観|Image via 小清水町役場
2025年1月には、ワタシノの全館停電を想定した防災訓練を実施し、通常稼働から非常時の運営に移行する方法の検証を行った。役場の職員や一般の人など、200名ほどが防災訓練に参加したという。
ブラックアウトという経験が公共施設をフェーズフリーにする発想につながった経緯や、防災訓練で実際に見えた課題などについて、小清水町役場産業課の課長である石丸寛之さんに話を聞いた。

小清水町役場産業課の課長・石丸寛之さん|Image via 小清水町役場
大規模停電で抱いた、雪国が抱える災害リスクへの危機感
ブラックアウトの際、小清水町では北海道の端に位置していることもあり、停電から復旧するまで約40時間を要した。経済産業省の報告によると、北海道全体の停電復旧率は発生から24時間後に58%、48時間後に99%に達したが、地域によって復旧に大きな差があった。小清水町の役場などには非常用発電設備が備えられていたものの、想定以上に停電時間が長引いたことで、灯油の備蓄が不足するリスクを実感したという。
これをきっかけに、石丸さんは「非常時に役場がもっとできることはないか」と考えるようになったという。
「このときは9月にブラックアウトが起きたため、北海道が寒くなる前で、まだ良かったとも言えます。ただ、もしブラックアウトが、気温がマイナス20度になる季節に起きていたらどうだったか。寒さで亡くなってしまう人もいたかもしれないと、危機感を抱きました」
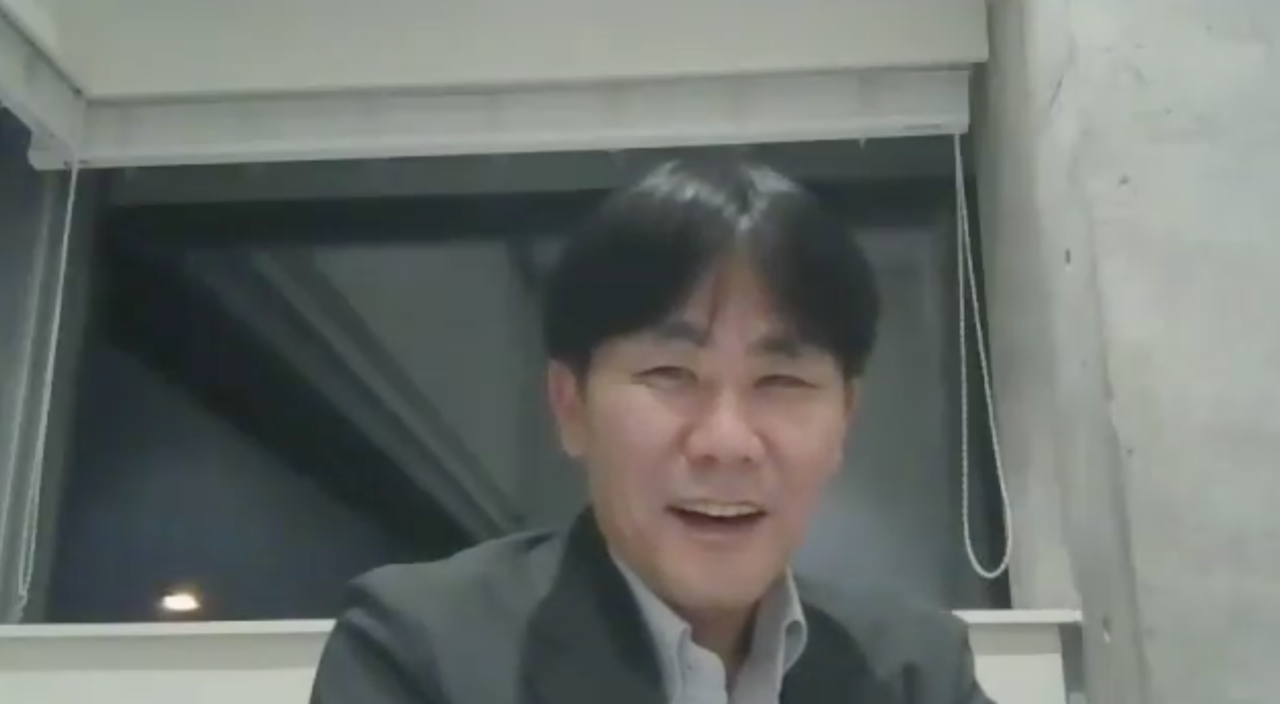
石丸さん 取材はオンラインで行った。
この経験を経て、その後小清水町役場の建て替え時期が迫った際に、防災拠点としての機能を強化する方向でアイデアが固まっていった。
非常時の寒さ対策としては、温泉熱を活用した床暖房が大きな役割を果たしている。北海道の冬は寒さが厳しく、特に停電時には暖房が機能しなくなるリスクがあるが、この温泉熱を利用することで、停電時でも一定の暖を確保できるという。また、普段から温泉熱を利用して施設全体を暖めており、これにより年間のCO2排出量も削減できる。潤沢に温泉が出る、小清水町の土地柄を活かしている。
また、温泉から熱を取り出し、残ったお湯を捨てずに活用する方法が検討されている。たとえば、非常時にお湯をろ過して飲料水として提供し、分離した温泉の成分を使って入浴剤をつくるというアイデアを深めているそうだ。
全館停電を伴う防災訓練。これだけ備えても、見えた課題
「非常時におけるフェーズフリーの機能性などを検証したい」という想いから、2025年1月、ワタシノで初めての防災訓練を実施。訓練では、施設の防災機能を実際に試し、課題を洗い出すことが目的とされた。特にカフェでは、停電時にお湯を確保できるかを重点的に検証。日産自動車の協力のもと、ハイブリッド車から電源を供給し、電気ポットでお湯を沸かすことに成功したという。

2025年1月に実施された、ワタシノで初めての防災訓練の様子 |Image via 小清水町役場
フィットネスジムでは、温泉熱を利用した床暖房の効果を検証。停電時の暖房手段として、温泉熱が有効であることが改めて明確になった。また、シャワールームでは、お湯の供給が継続できるかを検証したところ、温泉熱で温めた水を非常用発電でボイラーで更に加温することで通常と変わらず利用可能であることが確認できた。これにより、非常時でも最低限の衛生環境が確保できるという期待通りの結果を得られたのである。

フィットネスジム |Image via 小清水町役場
ランドリーでは、衣類の洗濯と乾燥が問題なく行えたが、新たな課題も浮かび上がった。
「万一、断水したときのことを考えると、ランドリーで水を使い過ぎてしまい飲料用やシャワーの水が不足したらどうするのかという懸念が浮かびました」
非常時には水の確保が最優先課題となる。つまり、ランドリーで使用した水もできるだけ捨てずに再利用できる仕組みが求められるのだ。現在、小清水町では温泉熱を活用した施設運営を進めているが、今後は洗濯で使った水をろ過し、再び洗濯に利用できるシステムの構築を検討している。

ランドリーの様子| Image via 小清水町役場
防災訓練には、能登半島地震の際に医療支援に従事した医師も見学に訪れていた。実際の被災地で医療活動を行った専門家の視点からも、今回の訓練がどのように評価されるのか、石丸さんは特に関心を持っていたという。
「お医者さんに、『これだけ大規模な防災訓練を行ったことがすごいですし、復旧にかかる時間が長期化することを想定し、徹底して備えている点が安心感につながりますね』と言っていただけて、自信になりました」
特に、能登半島地震では停電や断水が長期化し、避難生活が厳しいものになったことを踏まえると、長期的な視点で防災計画を立てることの重要性を再認識する機会となった。
企業と連携する役場。有事のときに住民を守るためのまちづくり
石丸さんは、企業誘致と掛け合わせたフェーズフリーの推進に積極的に取り組んでいる。その一例が、2024年にワタシノの近隣に誘致した「サッポロドラッグストアー」だ。このドラッグストアは、日常時には地域住民の健康を支える店舗として機能しながら、有事の際には「備蓄庫」としての役割を果たす。全国から支援物資が届いた際の受け入れ拠点としても機能することを見越しているのだ。

サツドラ|Image via 小清水町役場
さらに、石丸さんはアウトドアブランドの「株式会社モンベル」と、ワタシノのランドリーを監修する「株式会社OKULAB」の企業間連携を促し、洗濯物の撥水機能を向上させる「モンベル撥水コース」の開発を後押し。ワタシノのランドリーに導入している。この撥水コースでは、アウトドアウェアや作業着などに撥水加工を施し、雨や泥汚れを防ぐ機能を強化できる。特に、小清水町では農業に従事する人が多く、日常時は農作業後の衣類の泥汚れを落とす目的で利用されることが多いという。
石丸さんは、小清水町の財政が限られている中で、持続可能な地域運営の仕組みを模索してきた。小清水町の人口は約4,500人(2023年時点)と少なく、行政予算も大都市に比べると限られているため、防災や公共サービスの運営には創意工夫が求められる。
「住民の方たちには普段、こういった企業のサービスを利用していただくのですが、有事の際には、それが住民の皆さんをお守りする資産になる。これが、ワタシノにおける考え方です」

カフェ|Image via 小清水町役場
ワタシノでは、日常時に企業と連携してサービスを運営しながら、必要時だけ稼働するため経費が少なく運営できるランドリーや会員制のフィットネスジムなどを展開し、その収益を災害時の備えに活用するという変化に備えた土台づくりをしている。
これまで、役場庁舎は「用事があるときだけ訪れる場所」として認識されてきた。しかし、それが「日常的に訪れたくなる場所」へとリデザインされたことで、町民が自然と集まり、地域との新たな関係が生まれつつある。
この変化を生み出したのは、企業や団体との連携だけではない。防災を軸に、役場という公的な存在が多角的に「市民のためにできること」を形にしてきたことが、大きな役割を果たしている。日常と非常時をつなぐ場としての役場のあり方は、単なる行政機関を超え、地域の持続的な支え手となる可能性を秘めている。その在り方に、学ぶべきことは多い。
【参照サイト】小清水町防災拠点複合庁舎「ワタシノ」公式ホームページ
【関連記事】備えない防災。日常で使うものを非常時にも役立てる「フェーズフリー」
【関連記事】今、自分にできることを。能登半島地震の被災地を支援するアクションまとめ
Edited by Erika Tomiyama












