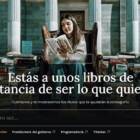AIに「ありがとう」と言ったことはあるだろうか。
依頼に対して満足のいく成果物をAIが作成してくれたときや、相談に寄り添う返事をくれたとき、何気なく聞いた質問に面白い答えが返ってきたとき。ふと気がつくと、私たちはAIに向かって「ありがとう」と口にしている。相手は感情を持たない機械に過ぎないのに、だ。
それは、なぜだろうか。なぜ私たちは、AIと良い関係を築こうとするのか。
ChatGPTをはじめ、日常に浸透したAIとのやりとりを手がかりに、この素朴な問いを考えてみたい。
なぜAIに感謝してしまうのか
AIとのコミュニケーションにおいて、感謝の言葉や丁寧な言葉使いを意識している人は多い。イギリスの出版社・Future plcが2024年12月の調査では、AIを使用している回答者のう地、イギリスで71%、アメリカで67%が、AIに対しThank you(ありがとう)や、Please(お願いします・〜してください)など礼儀正しい言葉遣いでやり取りをしており、その割合は同年9月からそれぞれ11%と3%増加していた(※1, 2)。
ではなぜ、私たちはAIに感謝するのだろうか。あくまでもAIは機械であり、感情は持たず、良いことをした見返りもないはず。それでも私たちが「ありがとう」と言いたくなってしまう理由は、3つほど考えられる。
一つ目に、感謝を伝えることで、AIからの返答も丁寧で質の高いものになることを期待しているから。特に仕事の助けとしてAIを使用している場合、自分一人ではできない短時間でのリサーチや文章の校正などを依頼することがある。そのとき、心の内でAIを擬人化し、「前向きな言葉で良い関係を築けば、良いアウトプットが返ってくるのでは」と期待をしてしまうのも無理はないだろう。
二つ目に、「何かしてもらったのに感謝を伝えない自分」という傲慢なイメージに耐え難いからかもしれない。相手が機械とはいえ、自分を大いに助けてくれる存在に対して冷たく接する自分を俯瞰して、それを避けたくなり感謝を伝えている可能性もあるはずだ。たとえ、AIとのチャットが誰にも見られなかったとしても。
また三つ目に、返答の有無や質にかかわらず、自己満足的に感謝を伝えている可能性もある。同調査でも、AIに礼儀正しくする理由について最多であったのは「ただ気分が良いから」という回答だったそう。
以上の理由のうち、どれがより確からしいかは不明だ。ただし、組織文化として普段から同僚に「ありがとう」と伝えている人は、同僚に近い役割を果たすAIに対しても「ありがとう」と伝える傾向にあるとの指摘もあり(※3)、AIとの関係をめぐる研究が進む中で理由が明らかになる可能性はある。
現時点で少なくとも言えるのは、私たちはAIとの何かしらのより良い状態を期待して、つい「ありがとう」と言ってしまうということだろう。
なぜテクノロジーの中で「AIには」感謝してしまうのか
もう一つ疑問であるのは、現代社会にはたくさんの機械がある中で、なぜ特にAIに対しては感謝するのかという点である。洗濯機や電子レンジも人のために何か役割を果たしてくれるのに、感謝の言葉をかけることは少ないのではないだろうか。
AIがほかの機械類と異なる特徴として、ほぼ制限のない言語コミュニケーションであることが挙げられる。AIを導入したモノやサービスは、チャットボット、スマートスピーカーなどからChatGPTへと発展。どれも物理的なスイッチや画面上のクリックなどで特定の動きを一方的に指示するだけではなく、文字や声で自由に表現し、多様な依頼・伝達ができるデザインだ。表現や伝達方法に厳しい制限がないことは、人が「ありがとう」と言える余白を残しているとも言える。
さらにAIは、人が「ありがとう」と伝えると、その言葉を受け取り、言葉の意味を踏まえた応答をしてくれる。ほかの機械では感謝しても何の反応もないことと比べると、ユーザーの心理面で違いを生むだろう。またその言語が、暗号のような文字列ではなく、普段使用する言語そのままであることも、あえて感謝を伝えようとする姿勢に影響しそうだ。
こうした言語や柔軟な応答といった特徴は、少なからず人がAIを擬人化しやすい要因でもあるだろう。これが土台となり、前章で挙げた3つの理由のような期待や感覚を持ってしまうのではないだろうか。
AIに感謝することで何が起きるか
それでは、AIに感謝を伝えることに何か効果はあるのだろうか。LinkedInのソフトウェアエンジニアであるMaitreyi Chatterjee氏によると、AIに感謝を伝えることは、その返答の方向性を前向きに捉えていることを伝える要素になり、AIがその方向性でのさらに詳しい情報を出す判断材料になるという(※4)。また、無礼な表現や過度に丁寧な言い回しと比較すると、程よい丁寧さの言葉を使うとより精度の高い返答が得られるとの研究結果もある(※5)。
一方で、全く反対の意見も挙がっており、感情ではなくアルゴリズムによって動く機械にとって、感謝の言葉は余分な情報が無駄なエネルギー消費になるとの考え方もあるのだ(※6)。
実際に、同じプロンプトで「ありがとう」と伝えて敬語でやり取りするチャットと、「ありがとう」や敬語を使わずやり取りするチャットに分けて使用してみた。
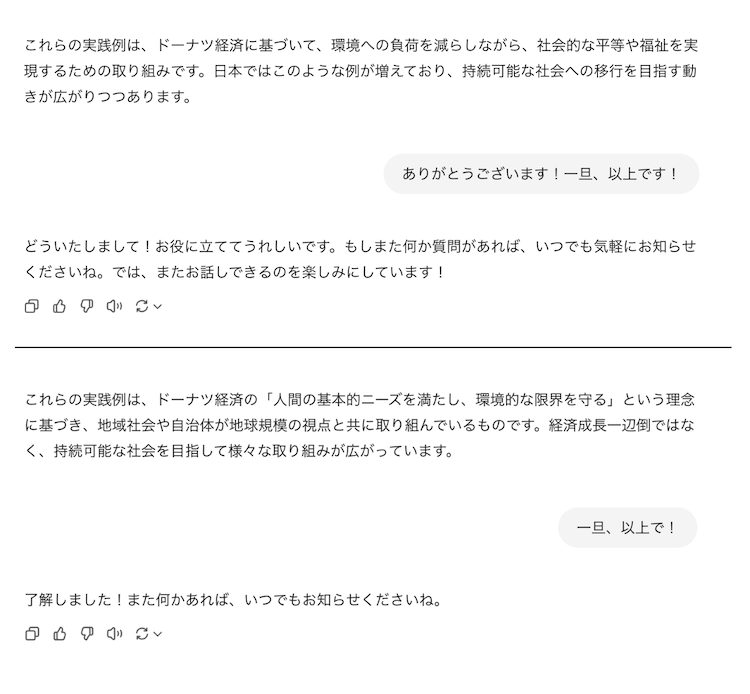
環境問題に関連する政策やドーナツ経済の実践例について、筆者からChatGPTにいくつか質問をしてみた。感謝の言葉や敬語を使って何度かやり取りしたチャット(上)と、それらを一切使わなかったチャット(下)|筆者作成
現在のところ、その2パターンの間でアウトプットには大きな差がないように感じられた。ただし、「お役に立ててうれしいです」「またお話しできるのを楽しみにしています」という言葉のように、AI側にあたかも感情があるかのような返事が返ってくる点は、「ありがとう」など感謝の気持ちを伝えるかどうかに左右されうるかもしれない。これはAIがユーザーのトーンを反映させることとも関連するだろう(※7)。
このように、AIとの向き合い方を改めて考えてみると、私たちは明確な理由がなくても感謝の言葉を伝えているなど、AIとのより良い関わり方を模索している段階にあるようだ。長期的な視点に立つと、現在はAIが社会に馴染んでいく初期段階でもあり、現時点での舵取りは少なからず人間と現代テクノロジーとの関係性を形作るだろう。AIとの本質的に良い関係は、どのようなものなのだろうか。
AIとの関わり方を考えるヒント「コンヴィヴィアル・テクノロジー」
AIとの向き合い方を考える上で、手がかりの一つとなる概念が、コンヴィヴィアル・テクノロジーだ。豊橋技術科学大学の岡田美智男教授は、ロボットと人が互いに弱みを補い、強みを引き出す関係を築くロボットを、コンヴィヴィアル・ロボティクスと呼ぶ。
岡田教授によると、現在主流である自己完結型のロボットは、より多くの機能、より高い性能を追求することで、かえって人の創造性や主体性を奪っている。これは現代社会が個の能力向上を過度に求めていることが原因で、これが「生きづらさ」にも繋がっているとも考えられるという。
だからこそ、個体の能力重視から脱却し、不完全なロボットとの緩く依存し合った関係性を評価していくことが、人の創造性や主体性を取り戻し、より「生きづらさ」が和らいだ社会への後押しとなりうるのだ。その対象を、AIを含めテクノロジーに拡張することも可能であり、コンヴィヴィアル・テクノロジーの模索が重要であることも意味するだろう。
その緩く依存し合う関係を実際に構築するためには、人とテクノロジーが「対峙する関係」ではなく「並ぶ関係」を築くことが大切だという。AIを例に取ると、AIを、プロンプトへの完璧な返事や成果物を出し続けるツールではなく、課題やテーマに対して共に悩み考え対話する存在・仲間と捉えることが、並ぶ関係への一歩なのだ。
AIへの感謝は社会への働きかけ
この観点から、私たちがAIに感謝してしまう現象を捉え直してみると、私たちは無意識のうちに、AIをコンヴィヴィアル・テクノロジーとして扱おうとしているのかもしれない。個々人がAIを単純な生成ツールとして捉えているか、同じ目線に立って物事を考えてくれる仲間と捉えているかは実際には分からないものの、比較的後者の捉え方をしているからこそ、同僚と話すかのように「ありがとう」という言葉が出てくるのではないだろうか。
わずかな差ではあるが、感謝を伝えなくてもAIの機能上大きな問題はないにもかかわらず、数秒・数文字の手間を加えてわざわざ感謝を伝えるその行動は、AIとの並びあう関係を能動的に生み出そうとしているかのようだ。
それは、完璧さや効率の良さが求められる現代で、多かれ少なかれ生きづらさを感じながらも、不完全さが受け入れられる関係を築こうとする行動でもある。つまりAIへの「ありがとう」という言葉は、自身にとって少しでも生きやすい環境を作ろうとする働きかけであるのかもしれない。
※1, 4 イギリスからは518人、アメリカからは510人が調査に回答した|Are you polite to ChatGPT? Here’s where you rank among AI chatbot users|TechRadar
※2 I stopped saying thanks to ChatGPT – here’s what happened|TechRadar
※3 Why It’s Important to Say Please and Thank You to Robots|IDEO
※5 Ziqi Yin et al (2024) Should We Respect LLMs? A Cross-Lingual Study on the Influence of Prompt Politeness on LLM Performance
※6 The pros and cons of saying ‘thank you’ and ‘good morning’ to AI|Technology|EL PAÍS English
※7 Why Using a Polite Tone with AI Matters|Microsoft
【参照サイト】Should You Be Nice to AI Chatbots Such as ChatGPT? |Scientific American
【参照サイト】Hard Evidence That Please And Thank You In Prompt Engineering Counts When Using Generative AI|Forbes
【関連記事】“できない”を隠さない「弱いロボット」。開発者の岡田教授と考える、テクノロジーと私たちのコンヴィヴィアルな関係
【関連記事】アフリカで深刻化するメンタルヘルスの問題。AIが助ける匿名相談アプリ