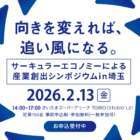近年、新たなライフスタイルを実現する手段として「移住」が注目されている。総務省によると、2022年度における移住相談の件数は約37万件にのぼり、前年度から約4万6千件増加していると同時に、調査を開始した2015年度以降、最多の相談件数を記録した。この背景には、コロナ禍をきっかけとした地方移住への関心の高まりや、テレワークの普及等による「転職なき移住」への関心の高まりがあるという(※1)。
実は、この記事を書いている筆者自身も新型コロナ禍によるライフスタイルの変化をきっかけに地方移住した一人だ。実際に、筆者が拠点とする埼玉県と県内市町村においても、2022年度に受けた移住相談は約3,700件と、前年度より約700件増え、過去最多を更新した。なかでも市町村別で移住相談が最も多かったのは小川町(926件)であった(※2)。
和紙の生産地としても有名な小川町は、化学肥料や農薬に依存せず、自然の力を借りる循環型の農業への取り組みが盛んだ。小川町で有機農業を学んだ人たちが自立し有機農業の輪を拡げるなど、「有機農業の里」としても知られている(※3)。
そこで、今回は近年移住先として注目され、有機農業をはじめサステナブルな暮らしを体現できる小川町の魅力に迫っていきたい。小川町ではいまどのような変化が起こっているのだろう。実際に東京都から小川町へ移住し、地域に根ざした活動を次々に展開する柳瀨武彦さんに、移住したからこそわかる、そして現地で活動をしたからこそわかる小川町の特徴を聞いた。
話者プロフィール:柳瀨武彦(やなせ・たけひこ)
 企画編集者。1986年東京都練馬区生まれ。早稲田大学スポーツ科学部在学中、貧乏旅行に明け暮れる中でコミュニケーションに興味を持ち、広告会社に入社。イベントプロデューサー、コピーライターを経て2016年に独立、2019年にP inc.を設立、喫茶PEOPLEを開業。二拠点生活を経て、2022年埼玉県小川町に拠点を移し、2022年に古本屋BOTABOOKS、クリエイティブスタジオUNE STUDIO、コレクティブファームUNFARM、2023年にPodcast「おがわのね」開始。趣味は移動と運動と音楽鑑賞。天パ。
企画編集者。1986年東京都練馬区生まれ。早稲田大学スポーツ科学部在学中、貧乏旅行に明け暮れる中でコミュニケーションに興味を持ち、広告会社に入社。イベントプロデューサー、コピーライターを経て2016年に独立、2019年にP inc.を設立、喫茶PEOPLEを開業。二拠点生活を経て、2022年埼玉県小川町に拠点を移し、2022年に古本屋BOTABOOKS、クリエイティブスタジオUNE STUDIO、コレクティブファームUNFARM、2023年にPodcast「おがわのね」開始。趣味は移動と運動と音楽鑑賞。天パ。
「オーガニックビレッジ」を宣言した埼玉県の小川町
埼玉県の中央部に位置する小川町。歴史的に和紙の産地として知られ、自然豊かなこの地域は、1970年代から有機農業が営まれており、化学肥料や農薬に頼らず、自然の力を借りた循環型農業が実践されてきた。

2023年5月2日、小川町は埼玉県内で初めて「オーガニックビレッジ」を宣言。この宣言は、農林水産省が進める「みどりの食料システム戦略」に基づき、有機農業の生産から消費までを地域全体で推進するという取り組みだ。これには農家だけでなく、事業者や地域内外の住民も巻き込むことが明言されている(※4)。小川町では有機農業を通じて地域の食の安全・安心を確保し、環境への配慮が強化されることで、魅力ある地域づくりが目指されているのだ。
自然が近くにあり、都市部との距離感がちょうど良い小川町にポテンシャルを感じると話す柳瀨さん。小川町では、有機農業やサステナブルな暮らしに興味がある人が多いという。
「有機農業の第一人者である金子美登さんが、長年小川町を拠点に活動されていたこともあり、この地域には1970年代から有機野菜が根付いています。山が近く、小川が流れ、生態系も豊かであること、地産地消が可能なコンパクトなエリアであることも、小川町の特徴です。また、堆肥づくりなど自然循環が目に見える形で行われていることも、小川町がサステナブルだと捉えられている背景として大きいのではないでしょうか」
こうして、小川町は県内でも有数の有機農業が盛んな地域となり、持続可能な農業のモデルケースとして注目されているのだ。
通っていたら移住してしまった?小川町との出会い
そんな小川町と柳瀨さんはどのようにして出会ったのだろう。
東京都出身、大学卒業後は広告会社で働いていた柳瀨さんは、30歳のときに独立し、企画や編集の仕事を始めた。当時からリモートワークを通して場所にとらわれずさまざまな地域で働く中で、地方移住に関心を持つようになったという。
「以前からリモートワーカーだったので、仕事でいろんな地域へ行くことがありました。長い期間にわたって仕事で関わる地域もあり、仕事がひと段落してその地域を離れると寂しい気持ちもありました。そのため、『都内から通える田舎』を探したいと思い、神奈川や千葉などの地域を訪問していました」
移住先を探していた柳瀨さんは、その後小川町と出会う。小川町は埼玉県の中央に位置し、山に囲まれている。都内から電車で通いやすく、自然が豊かな小川町の環境に触れた柳瀨さんは、徐々に小川町へ通うようになった。
「小川町の有機農法を学ぶ機会もあり、町へ通う中でご縁をいただいて喫茶店『PEOPLE』を小川町でオープンすることになりました。初めは都内の自宅から小川町へ通っていたのですが、新型コロナウイルスが流行し、世の中が変わる中で、小川町との二拠点生活を始めました。その後、子どもが生まれ、2022年に小川町へ引っ越しました」

柳瀨さんが手がける喫茶店「PEOPLE」
普段は企業や自治体のブランディングやプロモーションなど多岐にわたって仕事をしている柳瀨さん。彼が手がける仕事の一つはコミュニケーションが生まれる「空間づくり」だ。
「小川町では、インテリアデザインや映像制作の仕事をする人たちと『UNE STUDIO』というシェアオフィスを構えながら、コワーキングスペース『NESTo』を作ったり、廃校を利活用したりする活動もしています」
小川町の街の魅力を最大限に引き出す、柳瀨さんの活動
また、柳瀨さんは小川町に住む人たちとのつながりを大切にしながら、町の魅力を引き出す活動も展開している。
「他にも、自分が食べる食材を少しでも自ら育てたいという気持ちから、『UNFARM』という共同農業を営むプロジェクトや、(小川町には空き家が多いので)古民家を宿泊施設にする活動『小川まちやど』のお手伝いをしています。最近では、小川町に住む人たちにインタビューするポッドキャスト『おがわのね(Spotifyにて配信)』も始めました。その人たちがどのように小川町に辿り着き、どのような思いを持って活動しているのかをインタビューしています。このラジオを通して、私自身も小川町についてよく知ることができますね」

小川町に根ざした形で多種多様な人たちと活動をともにしている柳瀨さんは、近年移住してきた若年層の人たちと会話をする中で、少しずつ小川町の変化を感じているそうだ。
「私が8年前に初めて小川町へ来た時は、若い人が小川町へ移住したりお店をやっていたりする雰囲気はあまりありませんでした。その後、地元や移住者の同世代の人たちがお店を始めたり、仲間が引っ越してきたりするなど少しずつ動きがあるように思います。新型コロナウイルスがきっかけで通勤がなくなったり減ったりして、暮らしや仕事に対する価値観が変わり、自然と距離の近い暮らしに移行する人も増えたのだと思います」
海外での視察を通して改めて見えた、小川町の魅力。小さな循環で「愛町心」を育む

サステナビリティをキーワードにスウェーデンの町を散策
小川町での暮らしの中で人々や自然環境とのつながりを感じてきた柳瀨さんは、サステナブルな暮らしについて探究すべく、2023年夏に、欧州においてサステナビリティに関する先行事例を多く生み出しているスウェーデン・マルメとデンマーク・コペンハーゲンにてサステナビリティラーニングツアーに参加した。そこで、スウェーデンとデンマークの人々のサステナビリティに対する意識の高さを感じたという。
「印象的だった点は、町全体で情報がミニマルなところや、サステナビリティに対する意識がベースにあり、それらが教育にも組み込まれていることです。自然体で、常識の中に『サステナビリティ』が埋め込まれている。サステナブルな暮らしに向けて意識的に行動することは自分でもやっている方だと思いますが、まだ『当たり前』とまではいかないので、こうした意識の違いは大きいと感じました」
海外での視察を通して、サステナビリティを体感した柳瀨さんは、サステナブルな暮らしは小川町でも実践しやすいと感じたという。
「徒歩圏内で野菜が取れ、水も流れていて、町の中で自給自足できる点は小川町の強みだと思います。そういった小川町のコミュニティの存在や、農家さんのお手伝いなど困った時に助け合いもみられます」

コワーキングロビー「NESTo」
「小川町は、大学のキャンパスのようで、いろんなサークル活動やゼミがあり、みんなそれぞれ好きなことをやっている町のように感じます。全員と面識があるわけではないけど、すれ違って挨拶できる距離感ですし、みんな適度に放っておいてくれるけど、同じ地域に住んでいるという連帯感もあります。特に、移住してきた人たちには小川町に対して『愛町心』があると思いますね」
今後は、これまで小川町で展開してきた活動をより活性化させていきたいと話す柳瀨さん。特に小川町の空き家問題や、後継者不足に悩まされている和紙などの伝統文化・技術を多くの人に知ってもらうためのツアーを企画したいという。
「移住してきた人は、自分で選択して地域に入ってきているので、小川町に対する想いが強いと感じます。小川町にもともと住んでいる農家さんや職人さんも、一緒に何かやろうと言ってくれますし、盛り上げてくれて嬉しいと感じてくださる方もいるので、今後も良い融合が生まれるといいなと思います」
編集後記
有機農法をはじめオーガニックな活動が注目されている小川町。今回はサステナビリティを構成する要素の一つでもある「地域のつながり」をテーマに、小川町へ移住し地域に根ざした活動を多岐にわたって展開する柳瀨さんを取材した。
実際に地方に移住した筆者も感じているところだが、地方での暮らしは、日常生活の中で生産者と直接コミュニケーションをとりながら買いものをしたり、農業を通して自然と触れ合ったりする機会が多い。「サステナビリティ」という言葉に頼らずとも、日々の暮らしを通して地域の人たちや自然とのつながりを強く感じられる。
地方への移住は、近年問題視される人口減少や少子高齢化問題の解決に向けたアプローチの一つであり、「地域の持続可能性」を模索する上でも重要な視点だ。引き続き筆者も日本各地における地域の魅力を再発見し、新たな取り組みを生み出す人々と出会っていきたい。
※1 総務省「令和4年度における移住相談に関する調査結果(移住相談窓口等における相談受付件数等)」
※2 埼玉新聞「埼玉への“移住相談”過去最多を更新 市町村別で相談多かった街は3位が飯能市、2位は秩父市、気になる1位は」
※3 埼玉県 農林部 農業ビジネス支援課 農地活用担当「小川町」
※4 埼玉県内初!小川町がオーガニックビレッジ宣言を行いました。
【参照サイト】PEOPLE
【参照サイト】UNE STUDIO
【参照サイト】NESTo
【参照サイト】UNFARM
【参照サイト】小川まちやど
【参照サイト】おがわのね
【関連記事】東海地域に根付く「地場産業」。株式会社RWが再発掘する、サステナブルなものづくりのヒントとは
Edited by Megumi