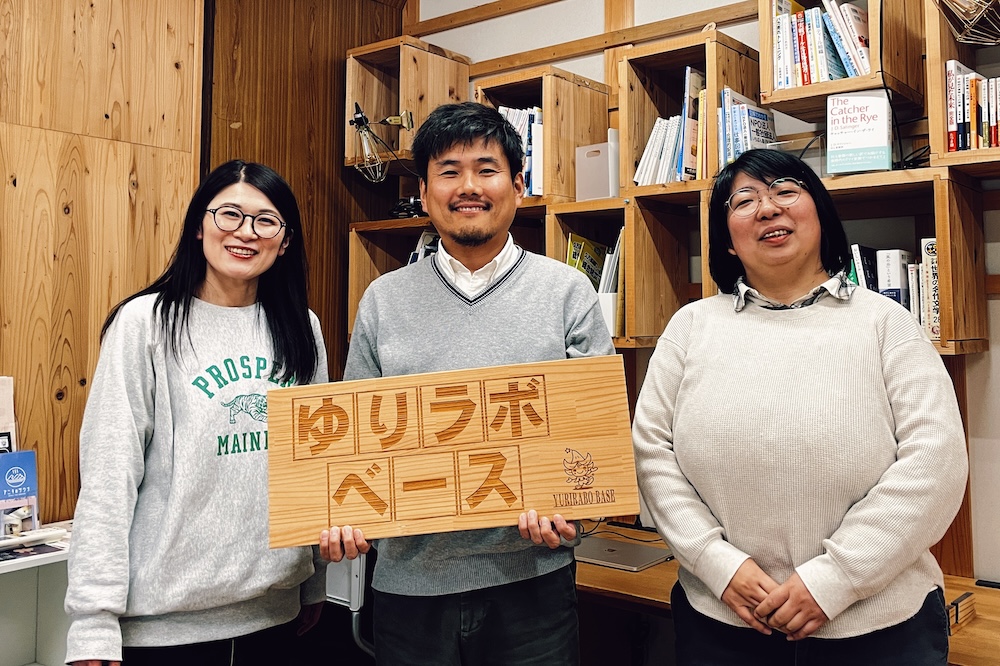Sponsored by 四国経済産業局
人口減少率が年間5%に迫り、住民の半数以上が65歳を超える。香川県高松市の山あいにある塩江町は、多くの日本の中山間地域が直面する現実の一例だ。2017年に2,800人だった人口は、今や2,077人。2030年代には1,000人を割るとの推計もある。

こうした状況で叫ばれる「地方創生」は、多くの場合、失われたかつての賑わいを取り戻そうとする成長と拡大の物語をなぞる。しかし、一般社団法人トピカの代表理事・村山淳氏は、その考え方に疑問を投げかける。
「物理的に不可能な成長を目指すのではなく、私たちは『幸福なダウンサイジング』を選ぶべきだと思っています」
それは、膨張してしまった地域社会を、住民の手で主体的に管理できるサイズまで、誇りを持って「畳んでいく」という、新しい地域運営の思想である。代表理事の村山淳氏が地域おこし協力隊の任期後に立ち上げた「トピカ」は、里山学校や放置林の活用、アートプロジェクトといった多様な活動を通じて、地域の困りごとを事業化し、資本主義の論理だけではない新たなコミュニティのあり方を模索している。
「資本主義経済の矛盾が地方に押し付けられているときに、それを資本主義経済の中で回収するのが果たして合理的なのかという問いを、ずっと持っています」

村山氏
なぜ、村山氏は成長ではなく「縮小」に希望を見出すのか。その背景には、過去から未来の針路を読み解く歴史学者としての洞察と、東日本大震災のとき東京の電力のために故郷・福島が犠牲になる構造を前に自らの「加害者性」とも向き合った経験にあった。
歴史を手がかりに、資本主義の負の要素がしわ寄せされた小さな町で、社会のあり方を内側から問い直す「トピカ」の試みについて村山氏に取材した。
話者プロフィール:村山(立川)淳氏
 一般社団法人トピカ代表理事。大学時代からスコットランドゲール語やラテン語を学ぶ言語オタク。趣味は釣りやテレビゲームなど。様々な講座で講師や案内を務める。経歴:福島県いわき市生まれ。中央大学文学部人文社会学科西洋史学専攻(古代ローマブリテン史)在学中に英国スコットランド、グラスゴー大学に留学(スコットランドゲール語専攻)。帰国後、一橋大学大学院言語社会研究科修士課程に進み、修士(学術)を取得。研究内容は『ゲド戦記』の作者として有名なアーシュラ・K・ル=グウィンのSF、ファンタジーの中の思想、言語論。大学院修了後、高松市塩江町地域おこし協力隊として移住し、2020年7月に任期満了。現職。
一般社団法人トピカ代表理事。大学時代からスコットランドゲール語やラテン語を学ぶ言語オタク。趣味は釣りやテレビゲームなど。様々な講座で講師や案内を務める。経歴:福島県いわき市生まれ。中央大学文学部人文社会学科西洋史学専攻(古代ローマブリテン史)在学中に英国スコットランド、グラスゴー大学に留学(スコットランドゲール語専攻)。帰国後、一橋大学大学院言語社会研究科修士課程に進み、修士(学術)を取得。研究内容は『ゲド戦記』の作者として有名なアーシュラ・K・ル=グウィンのSF、ファンタジーの中の思想、言語論。大学院修了後、高松市塩江町地域おこし協力隊として移住し、2020年7月に任期満了。現職。
「参照点」を変え、未来の針路を描く
村山氏の活動の根幹には、歴史への深い眼差しがある。移住当初、地域の会合で語られるまちおこしは、団塊の世代が経験したバブル期の成功体験が色濃く反映されたものだった。
「塩江町がよかった時代を知っている方々なので、まちおこしとなると、『あのときをもう一度』とは言わないまでも、とにかく上を目指そう、盛り上がりを目指そうという雰囲気がありました」
人口が9,600人を超え、土地が1億円で取引された時代もあったが、それは塩江の長い歴史の中では一時的な現象にすぎない。村山氏は、そんな過去の栄華を基準にしないこと、つまり地域の歴史の「参照点」を意識的に変えることを提案した。

「参照点をバブル期や戦後の高度成長期に当てるのではなく、もっと昔の、安定して低空飛行で回っていた時期に当てるのです」
歴史をノスタルジーの対象としてではなく、未来を構想するための比較対象として活用する。この視点の転換こそが、「幸福なダウンサイジング」への第一歩だった。
その思想を最も象徴するのが、「大きな歴史」と「小さな物語」を意図的に接続する試みだ。村山氏はまず、町の誰もが知る「大きな歴史」に光を当てた。1929年、地元の有力者たちが宝塚市を模して温泉郷開発を進めた「塩江温泉鉄道」の歴史だ。埼玉の鉄道博物館に残された設計図をもとに復元模型を展示し、町外からも含め1ヶ月で3,000人を集める成功を収めた。しかし、村山氏の分析はそこでは終わらない。
「大きな歴史をやったからには、小さな社会史や物語的な歴史を語らないと一面的になると思ったのです」
村山氏にとって、塩江温泉鉄道のような公的な記録に残る華々しい歴史は、いわば町の「骨格」だ。しかし、それだけでは住民にとって「自分ごと」にはなりにくい。本当に地域の誇りを醸成するのは、骨格に血肉を通わせる、名もなき人々の暮らしの記憶なのだ。
そこで、空き家を舞台にしたアートプロジェクト「いにしによる」で、家の持ち主が「骨組みだけにして古民家風に」と想像していた空間に眠る、生活道具の一つひとつを「塩江の来歴」として展示。古い民具から平成のプラスチック製品まで、そこに残されたモノたちは、華々しい歴史の裏側で営まれていた日々の暮らしという「小さな物語」を雄弁に語り出す。
「大きな歴史」と「小さな物語」が並び立つことで初めて、住民は「あの輝かしい時代に、私たち自身の普段の暮らしもそこにあった」という、立体的で手触りのある誇りを手にすることができる。それこそが、村山氏が「一面的な見方になってしまってはいけない」と語る真意なのだ。
加害者性の自覚から始まった、社会への問い
村山氏の思想の根源には、同氏が探究し続けてきたあるテーマがある。それが、古代ローマ史だ。同氏は大学で古代ローマ史を学ぶ中で、勝者であるローマ人ではなく、文字を持たなかったがゆえに歴史を主体的に描くことができなかったケルト語話者などの「抑圧された側の民族」に次第に惹かれていった。
「もともとマイノリティ、大きな存在に抑圧され少数派とされる立場の人々の声にずっと興味があったのだと思います」
その視点は、2011年3月11日の東日本大震災で決定的な意味を持つことになる。福島県いわき市出身の村山氏にとって、福島第一原子力発電所の事故は故郷を襲った悲劇だった。しかし当時、東京の大学に住んでいた村山氏は、ある構造に気づき、衝撃を受ける。
「東京のエネルギーを福島でつくっているという構図です。これ自体は福島の人も知っていて、産業にもなっていたから諦めて受け入れていましたが、それが生み出す大きなひずみに直面しました。私自身、当時は東京に住んでいたので、一方では加害者であり、一方では被害者でもある。すごく複雑な心境になりました」
故郷の人々の暮らしが見捨てられたという怒りから、一時は「棄国」を掲げてイギリスへ留学した。しかし、皮肉にも異国の地で自らの「日本人性」を強く意識し、帰国を決意。その後、大学で原発被害者の声を東京に届けるシンポジウム活動に傾倒するが、そこで新たな壁にぶつかる。
「言説だけでは変えられない、という感覚がありました。『原発反対』と叫んだところで、オルタナティブを示さなければ原発はなくならない。それが実感としてあったのです」
どうすれば、誰かの犠牲の上に成り立つ社会構造を変えられるのか。村山氏が行き着いた一つの答えが、「コミュニティの一つひとつが自立し、自律している姿」だった。東京のエネルギーは東京で、福島のエネルギーは福島でつくる。そんな小さな経済圏が無数に生まれ、有機的につながる社会。そのビジョンを試すために、村山氏は塩江町に地域おこし協力隊として着任した。

言葉の前に、身体で価値を示す
「私はもともと言葉の人、思想の人ですが、思想は前に出さず、行動で表現していくほうが地域では受け入れられます」
そう語る村山氏は、資本主義が見捨ててきた価値を、まず自らの行動で示してみせる。今、力を入れる林業では、たとえばエネルギーを使うチェーンソーだけでなく、地域に眠っていた古い斧を地域の方から譲り受け、自ら研ぎ澄まして木を伐り倒す。
「私が古い斧を磨いて木を切り倒しているのを見かけると、地域の方がどんどん昔使っていた斧を持ってきてくれて、それぞれがおぼろげに覚えているおじいちゃんの木こりの話を語ってくれるのです」

共に汗を流し、体を動かす中で、古い暮らしの知恵が持つ価値が伝播していく。
「考え方が全く違う人も含めてコミュニティを動かすには、まず一緒に草刈りをして、同じ釜の飯を食うことです」
さらに村山氏は、地域における「幸福の分配」という独自の哲学を実践する。それは、物理的なモノを分け与えることではない。この哲学は、地域で暮らす人々の、特に高齢の男性たちの心の奥にある痛切な声から生まれたのだという。
「『自分がつらいと思うのは、社会のどこにも自分が必要とされていないとわかった瞬間だ』そういう趣旨のことを言われる方が、特に男性に多いのです」
会社で培った経験も、長年培った暮らしの知恵も、求められなければ宝の持ち腐れになってしまう。そして、心理的にも塞ぎ込む要因にもなりうる。その状況を覆す村山氏の処方箋は、意外なほどシンプルだ。それは、自らが「教えを請う」側に回ることだった。
村山氏は、自分が知っていることであっても、敢えて「ナタの使い方を教えてほしい」と地域の先輩に頼る。その瞬間、頼られた側には「教える」という明確な役割が生まれ、眠っていた知識や経験に再び光が当たる。
それは、相手の存在価値そのものを肯定する、何より力強いメッセージとなるのだ。他人とできるだけ関わらない方が楽と考えがちな現代社会の価値観とは逆の、頼ることの積極的な意味がここにある。
「地域の中で頼ることは幸福の分配になります。全部自分でやろうとするのではなく、互いに頼り、頼られる共依存の編み目が濃くなれば濃くなるほど地域はつながっていくし、幸せになっていくのです」

水源地の森へ、都市の心を呼び戻す
この「つながり」を編み直す試みは、塩江町の外へも向けられる。その象徴が、高松市内の人々を対象に毎月開催している「しおのえ里山学校」だ。
「都市部の人からは『森や山に入る方法を教えてほしい』とよく言われます。山育ちからすると『そこにあるから入ればいい』となるのですが、多くの人は『勝手に入るのは怖い、人の持ち物だから入ってはいけない』と思っているんですね」
しおのえ里山学校は、そんな都市生活者に、川遊びやキノコ観察などを通じて、塩江の自然と触れ合う入口を提供する。しかし、その目的は単なる自然体験ではない。村山氏には、もっと切実な狙いがある。
かつて高松市の主要な水源は塩江だったものの、今では愛媛県や徳島県を挟んだ先にある高知県のダムから水が引かれ、都市住民の意識からその存在は薄れている。水という恩恵を受けながら、その源泉であるコモンズの維持管理に関わらない。この断絶こそが、様々な社会問題の根源にあるのではないだろうか。
「高松の市民は、塩江の自然環境に対する意識が薄くて、来たことがないのが当たり前。自分たちが飲む水の源がどうなっているかに関心がない状態は、生命として危ないのではないかと感じます」
里山学校は、失われた関係性を結び直すための、百年先を見据えた投資なのだ。子どもたちが何度もこの森で遊び、原体験として心に刻むことで、将来、高松市の水政策が語られるときに「塩江のことを忘れていないか」と声を上げる市民が一人でも増えてほしい。村山氏は、そんな希望をこの活動に託している。

時給7円の森から、コモンズ中心の経済圏を構想する
村山氏の挑戦は、心地よいコミュニティづくりに留まらない。その先に見据えるのは、資本主義とは異なる価値基準で動く、新たな経済圏の創出だ。塩江町の面積の84%を占める山林は、その実験場となる。
かつてこの森は、薪や炭を供給することで「高松の人たちの熱エネルギーの需要を満たす」重要な役割を担っていた。しかし1960年代に化石燃料が普及すると、その役目を終えた広葉樹林は放置された。これを現在の市場価格で木材として売ろうと試算すると、時給はわずか7円にしかならないという。
「私たちの目的は、山でお金を稼ぐことではなく、この山をどう生かすか。お金にならないからやめるという選択肢は、そもそも持っていません」
木を一本売れば数千円でも、その手入れされた美しい森に人を案内すれば、一日で数万円の観光収入が生まれる。さらに、地域の温泉施設が消費する莫大な化石燃料を、森の資源で代替できないかと、木質バイオマスの導入も真剣に検討した。ビジネスとしては成立しなかったが、地域の熱エネルギーを地域で賄うという視点は、村山氏の活動の根底にあり続けている。そして究極の目標が、「切らない林業」という、林業のあり方そのものを根底から覆すものだ。それは、これまで資本主義が見過ごしてきたコモンズの価値を、経済の中心に据え直す試みでもある。
「植えた木が収穫できるのは50年後なんて、資本主義ではありえない。だからこそ、木の値段だけで評価してはいけないのです」
村山氏が構想するのは、現在の経済システムでは「無料」とされている森の「見えない価値」を可視化することだ。森が水を育み、空気を浄化し、災害を防ぐ。その多面的な価値を、ブロックチェーンなどの技術を用いて一種の「計算可能な物語」へと転換し、環境貢献に関心を持つ企業や個人がそれを購入できる仕組みを創る。そうすれば、森の所有者は商品として木を切ることはなくとも、森を健全に保つこと自体で収益を得られるようになる。
「切ってもいいし、切らなくてもいい。その選択のどちらにも経済的価値が結びつく林業をつくっていきたいです」
それは、自身が向き合い続けてきた「東京のエネルギーを福島でつくる」という構造に対する、具体的なオルタナティブの提示でもあるのだ。都市の利益のために地方がコストを負担する構造も、社会全体の利益のために働いている森の杣人が報われない構造も、村山氏にとっては根が同じ。だからこそ村山氏は、地域の資源価値が地域に直接還流する、自立した循環経済をこの森から始めようとしている。

小さな町の羅針盤が、社会の未来を指し示す
なぜ、あえて人口減少が進む塩江町で活動を続けるのか。村山氏は「規模の問題」だと語る。
「自分のしたことに良い意味でも悪い意味でもフィードバックが返ってくる。そのサイズ感が何かをするうえでは大事なのです」
「アメリカの思想家フレドリック・ジェイムソンは『資本主義の終わりを想像するより世界の終わりを想像するほうがたやすい』と言いましたが、塩江町の規模で見たとき、資本主義の終わりは想像できます。実現できるかは別として」
人口1,000人規模のコミュニティであれば、新たな社会システムの姿を具体的に想像し、実装できる可能性がある。塩江町という小さな点で始まった実験が、やがて有機的につながり、社会全体に波及していく。村山氏が示す歴史という羅針盤は、単に塩江町の未来を照らすだけではない。それは、成長の限界に直面し、新たな豊かさの定義を模索する、私たち自身の未来を指し示す希望の指針なのかもしれない。

「社会運動は、社会によって自分が変えられるのを防ぐためにやる」
取材中、村山氏が、過去にガンジーが語ったという言葉をつぶやいた。村山氏の活動の根底にあるのは、声高な社会変革の主張というより、理不尽なシステムの前で、自らの人間性を守ろうとする切実な祈りのようなものなのかもしれない。そして、そこには常に、福島で芽生えた「加害者性」への問いが付きまとう。
「半分加害者である自分自身に向き合うために、その罪と向き合って何かをしておかないと、私自身がもたないのです」
「今の日本の社会では、あまりにも多くのものを踏みつけないと生きていけない。他の生命もそうだし、人権もそうかもしれない。例えば遠いガザ地区で起きている問題も、日本とは無関係ではないのです」
村山氏の視線は、塩江町という小さなコミュニティから、世界を覆う大きな構造へと向けられる。私たちの便利な生活や経済活動が、知らず知らずのうちに誰かの犠牲の上に成り立っている。福島と東京の関係で村山氏が直面したその構造は、形を変えて世界中に偏在しているのだ。
「ただ暮らしているだけなのに多くの加害行為に加担してしまう状態を、少しでも減らせる社会にしたい。自分自身の幸福が他人の不幸を土台にするのではなく、自分自身の幸福が他人の幸福とつながっている社会をつくろうとしています。それって、そんなに悪い社会ではないのではないかと思うのです」
ただ目をつむり、便利な生活を享受することもできたはずだ。しかし村山氏は、その罪悪感から逃げずに、オルタナティブな社会を模索し続ける道を選んだ。
村山氏の語る歴史の見方は、過去のどの地点を「参照点」とするかで、未来の描き方が変わることを示していた。私たちは今、どんな過去を手がかりに、どんな未来を見つめているのだろうか。
【参照サイト】一般社団法人トピカ
聞き手:株式会社ダン計画研究所