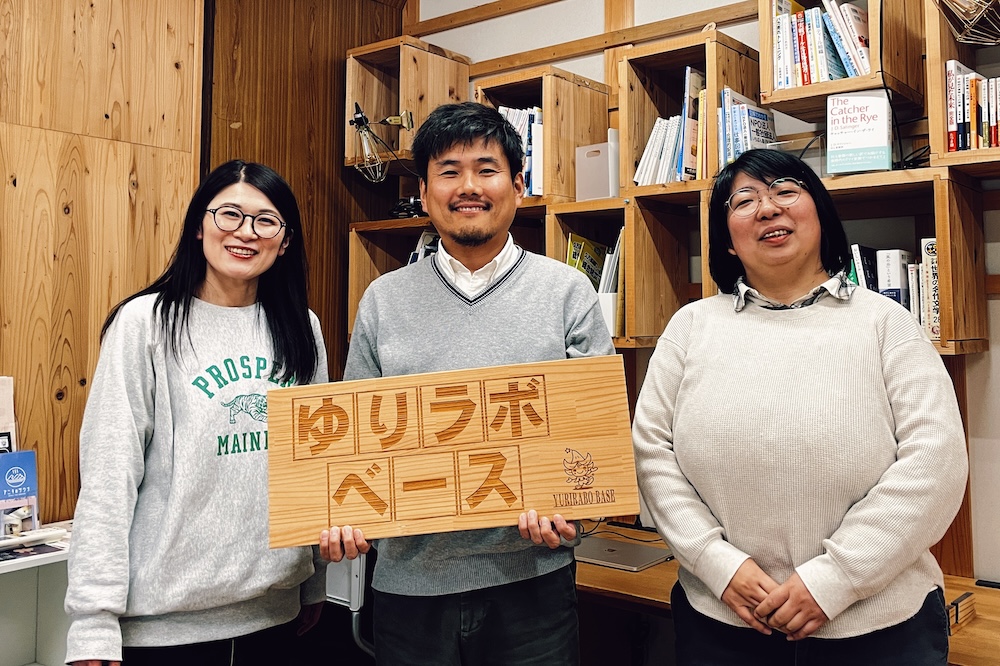Sponsored by 四国経済産業局
蛇口をひねれば、当たり前のように透明な水が出る。
この瞬間、その水がどこで生まれ、どのような旅をして手元に届くのか、そして誰がその源を守っているのかを想像する人は、都市にどれだけいるだろうか。
「中国に『飲水思源(いんすいしげん)』という言葉があります。水を飲むときは、その源を想え、と。現代の都市生活は高度な分業で成り立っていて、道路の掃除も、水の管理も誰かがやってくれる。でも、その『誰か』が見えなくなったとき、都市は実はとても脆いものになるように思います」
そう語るのは、高知県土佐町にある「一般財団法人もりとみず基金」の事務局長、尾崎康隆氏だ。一般財団法人もりとみず基金とは、四国の水がめ・早明浦(さめうら)ダムを擁する嶺北(れいほく)地域の4町村(土佐町、本山町、大豊町、大川村)と、利水地域(水を使う地域)にある香川県高松市が連携し、2024年に設立した広域プラットフォーム(中間支援組織)である。山と水を起点に、上流域の自治体だけでなく、その恩恵を受ける下流域の都市や民間企業をも巻き込み、水源保全活動と経済的な循環を両立させることをミッションに掲げている。
尾崎氏はここで、町役場の職員として働きながら、公民協働型の取り組みを進める財団法人の事務局長として、上流の町と下流の都市、そして行政と民間企業をつなぐ仕組みづくりに奔走している。
民間企業勤務、県庁職員を経て基礎自治体に転職した経歴を持つ地方公務員。尾崎氏が見つめるのは、単なる環境保全にとどまらず、水を軸に都市と地方の関係性を捉え直し、流域全体での持続可能なあり方を模索する視点だ。

尾崎さん
話者プロフィール:尾崎康隆氏
一般財団法人もりとみず基金 事務局長。高知県出身。都内民間企業勤務を経て、高知県庁に入庁。主に地域振興、企画、起業促進等を担当。より手触りのあるフィールドを求め、2019年に土佐町役場に転職。企画部及びSDGs推進を担当し、2021年からSDGS推進室長。2025年4月から、もりとみず基金に出向中。水源地としての立地や森林と水の関係に着目し、都市と山村の共生を目指す。
民間企業を経て公務員へ
尾崎氏は、民間企業、県庁、そして基礎自治体と、異なる立場を経験しながらキャリアを重ねてきた地方公務員だ。
就職氷河期世代として東京の大学で社会学と人類学を学んだ後、都内の民間企業で勤務した。時間外勤務も多くハードな現場ではあったが、人の暮らしが凝縮された場に立ち会う機会が多い仕事内容を通じて、社会の奥行きと、人間の暮らしのリアルな側面に触れる経験を重ねていったという。
「世の中にはいろんな人がいて、いろんな暮らしがある。社会的に課題を抱えた人もいれば、きれいごとだけでは済まない現実もあります。そうした課題の解決に取り組むことも大事ではありますが、個人的には、それらの良し悪しを軽々しく決めつけることはできないと思いました。それぞれの暮らしの“営み”はただそこにある。当時感じていたことや経験したことの中に、今の私の活動のベースになっている部分はあるかもしれません」
その後、故郷の高知に戻り、県庁の臨時職員を経て正規職員に採用されると、畜産、福祉、地域支援、そして起業促進と多岐にわたる部署を渡り歩いた。その後、土佐町役場に転職し、現在は「水源の危機」という課題に取り組んでいる。
土佐町を含む嶺北地域は、四国の重要な水源地だ。しかし、過疎化と高齢化で山に入る人は減り、手入れが行き届かない人工林は荒廃の危機にある。一方で、川下の都市部は人口も多く経済活動も盛んだが、自分たちの生命線である水源の現状に関与する術を持たない。

「行政界」という区分を越えて
大きな問題のひとつは、森や水はつながっているのに、それを守る仕組みが分断されていることだった。
「水や生態系は自治体の境界を越えて流れていることが往々にあります。しかし、行政の予算や権限は『土佐町』や『高知県』といった自治体の中で完結してしまう。土佐町だけで水源を守ろうとしても予算的な限界はあるし、逆に下流の香川県や高松市が手伝おうとしても、越境して予算をつけるのは簡単ではありません。この『行政区分から生じる壁』を越えて機能する仕組みが、いま改めて必要とされています」
行政区分は山や川といった自然環境の境界と必ずしも一致するわけではない。このため、行政区分を越えた環境保全や経済循環がかたちになりにくい。
「環境的なサステナビリティを考えると、都道府県域でも収まらないことが往々にあります。滋賀県のように琵琶湖という水瓶が県内で完結している事例もありますが、日本の河川の多くは県境をまたぎます。流域でモノを考えようとすれば、必然的に『上下流』を含めた広域の話にならざるを得ません。しかし、現在の日本には、その双方を巻き込んで意思決定する仕組みがうまく機能できていない」
水源地から河口の都市まで、当事者意識を持ったままつなぐ仕組みが欠落しているのだ。
「海外を理想化するわけではありませんが、例えば英国の『リバートラスト』のように、流域単位で保全し、資金を回していく仕組みが世界には存在します。日本にも、このような仕組みをつくっていく必要があるように思います。もりとみず基金は、そうした仕組みを作っていくことを目指しているのです」
この財団は、特定の単独自治体のものではない。同じ流域にある嶺北地域の4町村(土佐町、本山町、大豊町、大川村)と、利水地である高松市などの連携自治体、そして民間企業をも巻き込んだ、広域連携のプラットフォームである。
ウェブサイトを見ると、その事業内容は多岐に渡る。地域住民や企業向けの環境教育プログラム、水源涵養機能と林業を両立する森林整備事業の模索、そしてそれらを支えるための調査研究。これらを単一の自治体事業ではなく、流域全体のプロジェクトとして機能させる「受け皿」なのだ。
「行政は単体では何もできません。自分で資金を稼げるわけでもない。住民や民間企業など、事業や暮らしを実際に担う人たちが存在することで初めて成立する仕組みです。だからこそ、民間企業や他の自治体とも連携し、彼らが動きやすい『理由』と『場所』を作る必要があるのです」

一番右が、尾崎氏
50年の森と、四半期の経済をつなぐ翻訳機能
しかし、理念という「器」ができても、そこに「水(資金)」が流れなければ意味がない。尾崎氏が次に直面したのは、「時間軸のズレ」という資本主義の難問だった。
「企業は儲けを出さないと倒産してしまいますから、短期的な経済合理性から逃れられません。四半期、あるいは1年で成果を出さなければならない。一方で、森づくりは植えてから木材になるまで50年かかる世界です。この2つの時計の時間軸を合わせていくことは、とても難しいと思います」
もりとみず基金は当初から「SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)」の導入を検討してきた。これは、民間資金を活用して社会的課題を解決し、成果に連動して資金を償還していく仕組みだ。しかし、ここで壁にぶつかる。「成果の証明」だ。
ある山を整備したとして、それが具体的にどれだけ水をきれいにし、洪水を防いだのか。自然環境は複雑なので、その因果関係を短期間で科学的に立証し、経済的リターンとして返すことは困難である。それでも、同氏は諦めない。現時点では厳密な投資モデルが難しいなら、別の言語で翻訳すればいい。
「現時点で完全な科学的立証は難しくても、企業との相対契約でお互いが納得できる価値交換が成り立つことはあり得ると思います。例えば、森林整備によるCO2吸収量を『J-クレジット』として認証し、脱炭素を目指す企業に購入してもらう。あるいは、企業の社員研修のフィールドとして嶺北地域の森を提供し、社員のエンゲージメント向上や環境意識の醸成という『成果』を返す。様々な手段で、短期的な経済合理性と、長期的な環境合理性の間にある溝に橋を架けることを目指しています」
現在、基金には林業の現場を知る森林総合監理士、工学博士号を持つ大手重工メーカーからの出向者、大学院修士課程に在学中のインターン、高松市内で活動するコーディネーターといった、多様なバックグラウンドを持つメンバーがいる。専門知見と現場のリアリティを組み合わせ、企業と地域の新しい関わり方を模索している。

「お互いさま」の生態系をデザインする
尾崎氏の話を聞いていると、同氏が目指しているのは単なる森林保全ではなく、現代社会で失われつつある「関係性の修復」であることに気づかされる。
「日本国内のほとんどの地域の自治体財政は、地方交付税交付金に代表される『外部資金』が入ってくることで成り立っています。地方自治体間の財政力には格差があるので、全国どの地域に住む住民にも一定水準の行政サービスを提供できるよう、国税として国が徴収し地方に再配分する仕組みですが、人口減少が進み国自体が余裕を失ってきている中で、こうした仕組みがこれからも続いていく保証はありません。
『地方は都市からの輸血に依存している』と言われることに、地方として危機感を持つ必要があると思います。一方で、都市と地方は、本来は「別個の体(輸血する/される)」ではないはずです。一つの生命体として機能するためには身体を構成するそれぞれの部位が必要なように、国土として山側は水を守り、都市部は水(経済)を循環させる。どちらが偉いわけでもなく、片道切符でもない。健全なギブアンドテイク、本当の意味での『お互いさま』の関係を取り戻すことができれば」
「お互いさま」という言葉は、「日本の“村社会”における情緒的な助け合い」と受け止められがちだ。しかし尾崎氏が描くのは、もっと強靭なシステムとしての互恵関係。都市は地方の自然資源がなければ生存できず、地方は都市の経済力がなければ維持できない。この相互依存関係を可視化し、循環させることなのだ。
「誰一人取り残されない」というSDGsのこの言葉を、尾崎氏はきれいな理想ではなく、痛みを伴う調整のプロセスと捉えているという。
「何かを優先すれば、短期的には誰かが損をするかもしれない。若者への投資と高齢者の福祉、開発と保全。往々にしてトレードオフが発生します。だからこそ、対話し、長期的な未来において『全員が得をする』シナリオを共有し続けるしかないように思います」
もりとみず基金がハブとなり、上流の住民と下流の企業、そして未来の世代をつなぐ。例えば、同財団では、水源の機能を維持するために必要な森林整備を、下流の受益者負担や企業のCSR活動とリンクさせる試みが目指されている。これは、見えなくなっていた「恩恵」と「負担」の関係を結び直す作業に他ならないのだ。

尾崎さん
意志なき「運河」として
特定の「正義」を振りかざすのではなく、清濁併せ呑み、複雑なものを複雑なまま受け入れながら、それでも少しだけ未来が良くなるように仕組みを整える。
「私はWill(意志)という言葉が嫌いです」と尾崎氏は笑う。
「自分自身のWillにはあまり興味がありません。何か特別な原体験があるわけでもないし、個人として実現したいビジョンもありません。でも、世の中にはいろんな人がいて、もがきながら生きている。そのこと自体が面白いと思います。その営みが続いていくための『器』をつくりたいだけなのかもしれませんね」
自らを「運河に流されているだけの人間」と称し、流れに身を任せながらも、確実に水を届けられる仕組みづくりを目指す。そのあり方は牽引型ではなく、周囲の力を活かす「浸透型」であるように映った。
水は、高いところから低いところへ流れる。しかし、蒸発して雲となり、再び山へ雨となって降り注ぐことで循環は完成する。尾崎氏が描く「もりとみず基金」という仕組みは、下流に流れっ放しになっていた「感謝」や「資源」を、再び上流へと還流させる、見えないポンプのような存在なのかもしれない。
蛇口をひねるとき、その向こう側に広がる50年の森と、そこに関わる人々の営みを想う。
その想像力こそが、私たちの都市と未来を守る、最初の一滴になるはずだ。
編集後記
取材のなかで、尾崎氏は自身の歩みを「流されるままに行き着いた」と表現した。その言葉どおり、特定の理念や強い意志を前面に掲げる語り口ではない。しかし、個々の制度や現実を丁寧に見つめ、無理に単純化しない姿勢からは、現場に立ち続けてきた行政の実感が伝わってきた。
「都市の人間ほど、自分の暮らしが何に支えられているかを自覚しないと危うい」という言葉は、決して声高な批判ではない。むしろ、流域という具体的な単位から社会を捉え直そうとする実践の中で、にじみ出てきた実感なのだろう。
「もりとみず基金」の取り組みは、環境保全という言葉だけでは捉えきれない。都市と山村、上流と下流の関係を、制度と実務のレベルで結び直そうとする、ひとつの試行錯誤のプロセスとして映った。
【参照サイト】一般財団法人もりとみず基金
聞き手:ダン計画研究所