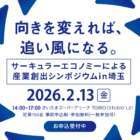シーズンごとに商品が次々と生み出され、店頭には数々の新製品が陳列される。同時に、売れ残った商品の多くはごみ箱へ。いつからか、“当たり前”に行われるようになった大量生産・大量消費型のものづくり。日本の化粧品メーカーでプロダクトデザイナーをしていた鮫島弘子(さめじま・ひろこ)さんは、その現状を目の当たりにして、こう思った。
「私は、『綺麗でキラキラしたごみ』をつくっているだけなのかも……」

ファストファッションのようなものづくりではなく、丁寧につくられたものが長く大切にされる「スローなモノづくり」をしたい。そう思うようになった鮫島さんは、2012年、あるブランドを立ち上げた。エチオピアの羊の革を使ったレザーブランド「andu amet(アンドゥアメット)」だ。

目指すのは、人や動物、環境、コミュニティなど、「かかわるすべてが幸せになるモノづくり」。これまでエチオピアでは、食肉の副産物として出る牛や羊の皮を活用しきれていなかった。そこで、できるだけ環境負荷の少ない方法でなめされた皮を、現地で直接雇用されたエチオピアの職人たちが縫い合わせてバッグや小物に生まれ変わらせることに。生産や販売の過程で消費される電力は、再生可能エネルギーでまかなわれ、売上の一部はアフリカで活動するNGO団体へ寄付される。そうしたモノづくりの根底には、「素材、デザイン、技術のすべてが揃い、さらに社会や環境にも配慮されたものこそが本当に良いもの」という考えがあった。
だが、単にサステナブルなブランドであるだけではない、鮫島さんには、andu ametというブランドを通して、人々に伝えたい「ある想い」があるという。
「フェアトレードだから、環境に配慮されているからと興味を持ってくださる方もいると思いますが、私はそれらは手段でしかないと思っていて。本当に大事なのは、その先にある『豊かさ』だと考えているんです。使う人も作るひとも満たされて、幸福を感じられて、自分のことを誇りに思える。そんなモノをつくりたい。そういうもので世界中を満たしたいんです」

andu amet代表・鮫島弘子さん
サステナブルの先にある豊かさ、使う人が特別な気持ちになるモノとは、一体何なのだろうか。そもそもなぜ、日本から遠く離れたエチオピアの地でモノづくりを行うのか。鮫島さんに詳しく話を伺った。
「綺麗なごみ」づくりをやめて、エチオピアへ
人類発祥の地と言われ、美しい自然や文化を有する一方で、世界で最も貧しい国のひとつとしても知られるエチオピア。同国の失業率はアフリカの中でも高く、特に若年層の就業機会の少なさが大きな課題となっている。そんなエチオピアと日本の2つの国を拠点にandu ametを立ち上げた鮫島さん。そのきっかけは何だったのだろうか。
「日本でデザイナーをしていた頃、大量生産・大量消費のものづくりに疑問を抱き、『綺麗なごみ』をつくるのをやめて違うことをしたいと思いました。でも、しばらくは具体的な行動には移せずにいました。周りには医師や検察官を目指している友人がいて、彼らが頑張っているのを見たとき、『自分は人や社会の役に立つために何ができるんだろう?』と悩んでしまったんです。そんなふうに迷いながら自分にできることを模索していたとき、たまたま出会ったのがJICA協力隊のOBの方でした」
自らの持っている知識や技術、経験などを生かして途上国で約2年間活動をする「JICA協力隊」。JICAが実施するこのボランティア事業の経験者に出会った鮫島さんは、「大好きなデザインの仕事で誰かの役に立てるかもしれない」と思った。それからJICA協力隊に応募し、合格したのちに行くことになったのが、当時は縁もゆかりもなかったエチオピアだった。

「当時、エチオピアで任された仕事は工芸品センターでのものづくり指導でした。そこで色々なものが作られていたのですが、品質が低いため、なかなか売れていない状況だったんです。そこで売れる商品を作り、外貨獲得を目指すというのが私の任務でした。
でも、実際に現地に行ってみると、そこは想像していた環境とは大きく違っていました。職場に行くと、みんな出社はしているけれど、お茶を飲んでお喋りしているだけで、仕事していないんです。『弘子、なんでそんなところで一人で机に座ってるの?こっちに来て一緒に踊ろうよ』と言われることも。その組織には、長年にわたって援助が入り続けていたため、それに依存してしまっていたんですよね。一生懸命考えて仕事を辞めてきたけれど、自分がここで何かすればするほど彼らの援助漬けを助長してしまうのでは……?そう思うと、一歩も動けなくなってしまいました」
そんなエチオピア赴任中、鮫島さんは同じ東アフリカのタンザニアを訪れた。そこで目にしたのは、人々が活発にモノをつくって売っている光景。そのとき、「タンザニアでもできるなら、エチオピアでも絶対できるはず」と感じたという。
「それまでは、エチオピアだから、途上国だからできないんだと思い込んでいましたが、たまたま自分がいた組織がたまたま働く意欲をなくしていただけだと気づいたんです。それなら、やる気のある人たちと一緒にやってみようと思い、職場に行くのをやめて勝手に色々なプロジェクトを企画、実行し始めました。その一つがファッションショー。エチオピアの自然や文化からインスピレーションを得て私がデザインし、現地の職人さんにエチオピアの素材を使ってドレスや靴をを作ってもらう。今のビジネスの元になるようなことをやったんです」

エチオピアでのファッションショーの写真
「それがすごくすごく楽しくて。小さいけれど当時の私なりにインパクトが出せたと感じ、そのときに『これをビジネスにできないかな』と思ったんです」
エシカルでラグジュアリー。みんなが憧れるものを「アフリカ産」で
エチオピアでの経験を通して、事業のイメージを膨らませていった鮫島さん。そうして生まれたandu ametのコンセプトは、「エシカルかつラグジュアリー」だ。何万人もの現地の人を大量雇用するスタイルのフェアトレード会社でも、多額の金銭や物資を寄付をする非営利団体でもない。自分の目がきちんと行き届くこと、そして本当にいいものを作ることにこだわりたかったと鮫島さんは言う。

表参道にあるandu ametコンセプトストア
「エチオピアのあと、ガーナの職業訓練校でファッション学科の先生として働いたのですが、生徒たちが作ったビーズのネックレスを近所のカフェやJICAオフィスなどで販売してもらいました。売上はすべて制作した本人に渡していたのですが、やはりどれも均一に売れるわけではなく、出来が良いものばかりが売れていたんです。丁寧で、色遣いなどを工夫できる子とそうでない子。その売上には、かなり差がありました。
そんな現実を目の当たりにして、最初はあまり熱心に授業に出席してくれていなかった生徒たちも、だんだんと目の色を変えて授業を受けてくれるようになったんです。きちんと売れるもの=良いものを作る体験が、現地の人たちを動かしていく。その姿を間近で見たからこそ、色々な形があるなかで、私はビジネスでやっていきたいと思いました」

表参道のコンセプトストアでのインタビューの様子
エチオピアでの経験を通して起業を決意した鮫島さんだったが、デザイン一筋でやってきたこともあり、資金調達や物流、販売方法といったビジネスについては未知の世界だった。そこで、一念発起してラグジュアリーブランドに入社。マーケティング部でビジネスについて学びながら、少しずつ事業の構想を考えていった。そんな鮫島さんはなぜ、シンプルなフェアトレードブランドではなく、「ラグジュアリー」であることにこだわったのか。
「とにかく私は、アフリカの人々が常に『支援される対象』であるサステナビリティやエシカルが嫌でした。彼らがつくったものをお情けで買ってもらいたくなかったんです。例えば、有名な高級ブランドのバッグはもらったら嬉しいし、大切にする人が多いかもしれません。そういうみんなが憧れるような本当にいいものを『アフリカ産』でつくりたいと思っていたんです。それに、どんなに素晴らしい背景で作られても、品質が悪ければすぐに捨てられて、結局また“綺麗なごみ”を作ることになってしまいますから」
自分の心が満たされる、「豊かな」モノづくり
アフリカの人々が「支援される対象」にならない、「真の持続可能なモノづくり」を実現したい──エチオピアで、現地の人々と共に暮らしてきた鮫島さんのそうした想いに加えて、andu ametというブランドにはある願いが込められていた。それが、ブランドのパーパスにもなっている「真の豊かさと美しさをすべての人が感じられる社会をつくる」という信念だ。
「豊かさと言ってもその定義はいろいろあるし、一人ひとり違うものだと思います。私にとって豊かさとは、『心が満たされること』。以前、当社のバックパックを買ってくださったお客様からお手紙をもらったのですが、そこにはこんな言葉が書かれていました」
これまではワンシーズンごとに新製品をとっかえひっかえしていたけれど、このバッグを買ってからは目移りしなくなりました。これがすごく良いものって思えるから、お手入れしながらこの先もずっと使っていきたいです
「これこそ、私がずっと目指していたことでした。かわいいから、たくさん入るからというだけでも、あるいはフェアトレードだから、サステナブルな素材でできているからというだけでもなくて、心が満たされたからこそ、その方は長く使いたいと思ってくれたのだと思います。デザインや縫製技術を工夫することも、社会や環境に配慮することも、自然エネルギーを使うことも全部大事。だけど、それらはすべて手段でしかなくて。私にとっては、その先にある『使う人が満ち足りて豊かな気持ちになれる』ことがゴールなんです」

andu ametのバックパック
本当に心が動いて満たされたもの、「これが好き!」というお気に入りのものは、大切に大切に長く使い続ける。それこそが究極のサステナビリティであり、豊かで幸せなことなのではないだろうか──そう話しながら鮫島さんは、取材中に出してくれたエチオピアのコーヒーが入ったカップを指さしてこう言った。
「このカップ、実は私の父が作ったものなんです。これで誰かにコーヒーを飲んでもらっているとき、ちょっと誇らしい気持ちになるんですよ」と。それからこう続けた。
「父がつくったこのカップは、私にとってはすごく大事なもの。だから、割れてしまっても、自分で金継ぎをして長く大切に使いたいと思うんです。よく身につけている祖母の形見のネックレスも同じで、それを身につけているときは、別のネックレスをしているときよりも幸せな気持ちになれます。そういうもので満ち溢れる社会が本当に豊かだと感じるから、すべての工業製品がそういう特別なものになっていってほしいんです。それが、次の時代の豊かさになっていくと思うんですよね」
長く使い続けたくなる「特別なモノ」に
高価なものを持っていることや、量をたくさん持ってることではない。幸せな気持ちになれるもので溢れる世界こそが、豊かな世界──そう考える鮫島さんは、「誰かにとって特別で、大切なものになってほしい」という想いでモノづくりを行ってきた。

エチオピアに咲く花々をイメージした“ブルーム”と名付けられたバッグ
「andu ametの製品には、それぞれ名前がついています。例えば、『ナイルブリーズ』というシリーズは、エチオピアが源泉のナイル川が想像されるような青いバッグ。『ブルーム』は、雨季と乾季の境目に花開くアフリカの花々をイメージしたピンク色のバッグです。エチオピアの天気は分かりやすくて、雨季は毎日雨、乾季は半年くらい一滴も雨が降らないのですが、雨季と乾季の間にパラパラと雨が降り出すと、干からびていた大地にアフリカの花がたくさん咲くんです。そんな美しい風景を感じてもらいたいと思ってつくっています。
それからこのバッグは『Hug Hug』という名前なのですが、触ったらとてもふわふわで、名前の通り、本当に抱きしめられているような気分になるんです。その取っ手の部分の縞模様は、日本の伝統である寄木細工の技法で革で再現したもの。羊革が一枚一枚積み重ねられていて、一つとして同じものがありません」

Hug Hug ナイルブリーズ
そこにいなくても、目の前に鮮やかな花の風景が広がったり、作り手の心意気が伝わったり。血が通っていないはずの「モノ」であっても、人や自然のぬくもりが感じられる。均一な工業製品ではなく、自分のためだけのオンリーワンの作品だと感じられる。そうしたandu ametのあたたかいモノづくりにはまた、大切に長く使い続けられる仕組みもあった。
「andu ametでは永久保証という独自の制度を用意しています。商品が壊れたとき、長めにお預かりさせていただくことを条件に、状態にもよりますが原則何度でも無料で修理を承るのです。修理品はエチオピアに持ち帰り、その商品をつくった本人に戻します。職人たちは通常、出来上がったばかりの新品の状態のバッグしか知りませんが、自分がつくったものを修理することで、『3年経つとこうなるんだ』『ここが破れやすいんだ』『前のお客さんのときもここ破れていたな』などと気づくことができます。職人にとっても貴重な学びになるので、お礼として無料で修理しているんです」
「成長のジレンマ」を乗り越えるための研修事業
立ち上げ当時、たった一人のエチオピア職人とともに始めたandu ametの従業員数も、2024年には20人にまで増えた。入社時、就業や就学の経験をほとんど持たずに来たエチオピアの若者たちは、革製品の製造技術を習得し、今では自分自身だけでなく家族を支えられるまでになったそうだ。またその間、andu ametは東京・表参道に「アフリカのホテル」をイメージしたコンセプトストアをつくり、社会・環境へのポジティブなインパクトを創出している企業に対して与えられる国際認証のB Corp認証も取得。ますます多くの人を巻き込むブランドとなった。
だが、そうした成長を遂げる一方で、鮫島さんは、常に「成長」するジレンマを抱え、頭を悩ませてきた。

鮫島さんとエチオピアの職人
「もともと大量生産・大量消費の流れに逆らいたくてはじめたブランドだし、事業を急激にスケールさせたいわけじゃない。だけど年々責任は増えていくし、ソーシャルインパクトも拡大していきたい。生産量を極端に増やさず、でも事業として成長させるにはどうしたらいいんだろう、と模索するなかで思いついたのが、企業向けのサステナビリティ研修という新規事業でした。
私はエチオピアに移り住み、現地の人たちと10年以上にわたりものづくりを続ける中で途上国の現場の課題やニーズを見聞きしました。気候温暖化による旱魃や洪水、戦争、疫病などの脅威にさらされているエチオピアでは、生き残るために常に変化が求められます。それらを映像を通じてバーチャルに体験してもらい、自分ごととして考えてもらうことが、日本や世界の未来を考える大きなヒントになるんじゃないかと思ったんです」
そう、andu ametがたどり着いたのは、バッグを今よりたくさん作って販売するのではなく、バッグを作る中で得た知見を販売する、という新しいビジネスモデルだ。参加企業の従業員たちは、まるで自分がその場にいるような映像を通じて、エチオピアにバーチャルトリップ。現地の実例を通じてさまざまな気づきを得ていく。
「旅に出ると、色々新しい発見があるじゃないですか。それは、サステナビリティへの理解だけでなく、VUCA(ブーカ)の時代のリーダーシップなどにも繋がると思っていて。日本が舞台だと、それぞれの立ち位置によって見えづらくなってしまう部分もあると思うのですが、エチオピアという多くの人にとって無縁の国だからこそ、客観視して見えてくることがあると思っています。
私は経験しただけで、答えを持ってるわけではありません。そもそも、これからの時代これという一つの答えがあるわけでもないですし。だから、動画やレクチャー、ワークなどを通して、参加者に自分自身で考えてもらうんです。例えば、現地で実際に起きている『グリーンウォッシング』の動画をみたあと、チームでディスカッションする。そんなふうに、一人ひとりに考えてもらうきっかけになる研修にしたいと思ってつくっています」

エチオピアにあるandu ametの工房の様子
お客様にできる限り一つのモノを長く大切に使ってもらおうとすると、当然ながら新しいモノは売れなくなる。そのジレンマを解消し、生産量を増やすことなく売上やインパクトを拡大する手段として生まれたのが、モノではなくナレッジを売る研修事業なのだ。このように事業成長やインパクトと生産量を切り離す考え方は、モノづくりと環境負荷のジレンマに悩む企業にとっても参考になるのではないだろうか。
最後に、鮫島さんにとって「満たされる」とは何か尋ねると、こんな答えが返ってきた。
「私は新しいことにチャレンジしてわくわくしているときに、充足感を感じます。ソーシャルインパクトのためとか、職人さんのためといった使命感や目標ももちろんあるけど、それが自己犠牲ではなく、むしろ自分の幸せとかやりがいになっているんです。自分がやりたいこと、やるべきだと強い信念をもっていることをやっているときって忙しくても楽しいし、むしろ力がみなぎってくる感じがあります。だから、これからも自分の使命を見つけて試行錯誤しながら突き進んでいきたいと思っています」
編集後記
「とにかく、使う人に幸せになってもらいたいんです。世界中の人たちが満ち足りて豊かな気持ちになれることをブランドを通じて実現したいんです」
取材中、鮫島さんは繰り返しこう言った。その言葉を訊きながら感じたことがある。それは、「心が満たされている」ことが、私たちの人生においていかに大切かということだ。今回は、「モノ」について伺ったが、日々行う仕事やかかわる人、食べるもの──そのすべてにおいて、「心が満たされる選択」をしていくことが、人生を豊かにしていくのではないかと感じた。毎日、誰もが何度も行う小さな選択。その一つひとつが変われば、人生が変わる。大げさかもしれないが、一人ひとりが幸せになっていけば、誰かを傷つけたり、もっと多くを求めたりすることはなくなるのかもしれない。そうして、少しずつ幸せな世界が広がっていくような気がするのだ。
まずは、自分にとって、近くにいる誰かにとっての幸せや豊かさについて考えてみる。その一歩が、今より明るい未来につながると信じて。

【参照サイト】andu amet