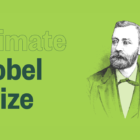教科書はない。雨でも雪でも、子どもたちは一日中、外で過ごす日がある。プロジェクトの主役は常に子どもで、大人はあくまでサポーター。これは、ニュージーランドのタラナキ地方に広がる森の中に佇む「Green School(グリーンスクール)」の日常風景だ。
グローバルなコミュニティを作り、世界をサステナブルにすることを使命に掲げる「Green School(グリーンスクール)」。自然に囲まれたキャンパスで、環境教育や起業家精神の育成に力を入れており、絶えず変化する世の中で子どもたちが目的を持って成長することができるような教育モデルを提唱している。
2025年6月時点でインドネシアのバリ島、南アフリカの西ケープ、ニュージーランドのタラナキに3校が開校している。筆者はタラナキ校のキャンパスツアーに参加した。
本記事では、実際に訪れたキャンパスの様子や校長先生へのインタビューを通して、その教育方針や実践を紹介していく。

KINAという名前の建物。世界初の試みである、認知機能や感情的な幸福感を高めることを目的とした設計 |Image via Green School NZ
なぜ、学びの場は「60ヘクタールの農地」なのか?グリーンスクールが育む“本当の力”
タラナキ地方は、ニュージーランドの北島に位置している。牧畜や酪農が盛んなほか、同国内で唯一の炭化水素の生産地として経済を支えている。人口は2023年時点で約12万6千人で、そのうち22パーセント近くが先住民族であるマオリ族の人々だ(※1)。
タラナキ校は60ヘクタールの農地を環境への影響を最小限に抑えて開発し、5歳〜18歳までの生徒たちの学びの場を創っている。使命は、持続可能な世界の実現に向けて活躍できる人材を育てること。そのためには、地球市民として社会的責任を持ち、自分で課題を見つけて創造的に解決する力、つまり「起業家精神」を育むことが不可欠だと考えているという。
起業家精神を育むうえで大切にされているのが、「子どもの好奇心こそが人類の進歩のはじまり」という考え方。子どもたちは、自分の行動が周りの世界に大きな影響を与えることを実感しながら学ぶ。そうすることで、「学ぶことが楽しい」と感じ、生涯にわたって学び続ける力も育まれると考えているのだ。
雨でも雪でも、外に出る。「Nature Day」が教える自然との向き合い方
グリーンスクールには、大自然の中に佇むキャンパスだからこそできる野外教育や、自然環境への理解を深める仕組みが豊富にある。
例えば、敷地内には「パーマカルチャーガーデン」や「トロピカルハウス(温室)」などがあり、学校でのキャンプや来訪者向けの体験プログラムもある。近い将来には「グリーン・ヴィレッジ」という居住スペースができ、家族も子どもと一緒にグリーンスクールを体感できるようになる予定だ。
中でも特徴的な野外教育の1つが、小学1年生から4年生を対象に毎週水曜日に行われる、「ネイチャー・デー」だ。その日、子どもたちは全く教室に入らず、雨が降っていても雪が降っていても、1日中外で過ごすという。トロピカルハウスで植物について学んだり、庭の手入れや堆肥作りを行なったりするのだ。
「悪天候は存在しない。適切な服装がないだけ」という「Nature is Nature(自然は自然)」の考えに従って、身体への危険がない限り、どんな天候でも野外で学びを深めるという。

ニュージーランドのタラナキ地方にある、大自然に囲まれたキャンパス|Image via Green School NZ
子どもがリーダーで、大人はサポーター。教科書のない「プロジェクト教育」とは
グリーンスクールでは、起業家精神に基づき、世界に変革を起こすような「チェンジメーカー」になる方法を学び、実践することができる。
例えば、変化が早く起こる環境に柔軟に対応するために、教科書は使わずに学びを展開。鳥類に関心のある子どもたちがいれば、近くにあるキウイ(※)の保護団体から講師を招くなど、子どもたちの声に寄り添いながら地元の団体と連携した学習プログラムを実践しているという。
※ 個体数が減少している、ニュージーランド固有の鳥。
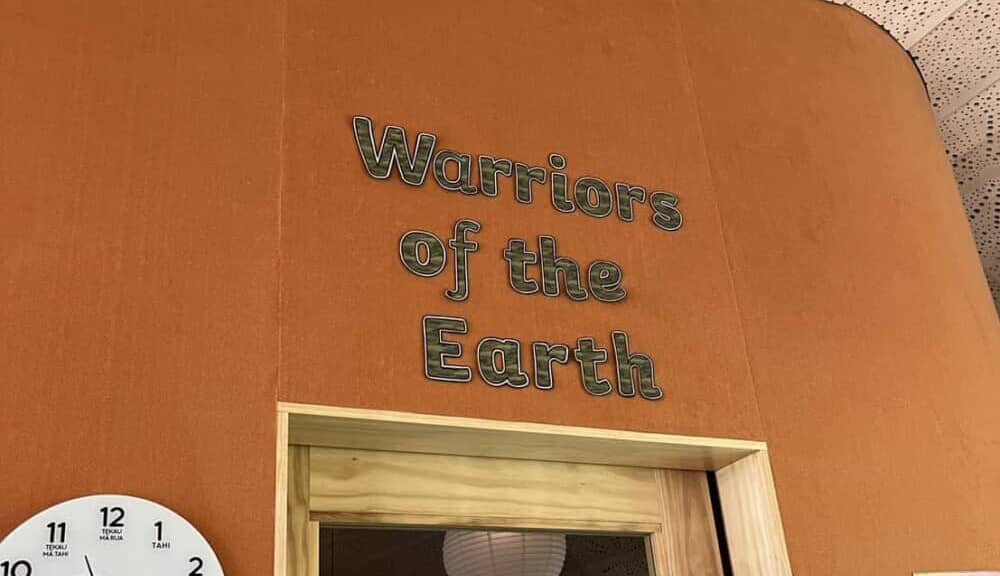
教室内の掲示「Warriors of the Earth」|Photo by Shiho
さらに、グリーンスクールでは全生徒が自主企画のプロジェクトに取り組むことが必須となっている。生徒が自身の興味関心に沿って立案し、資金調達の方法を考えたり、地域に頼れる専門家を探したりするのだ。
企画が完成したら、校長や学校のオーナー、理事会に向けてプレゼンテーションを行うこともある。プレゼンテーションに対して、ときには追加調査が必要な部分を指摘し、プロジェクト実行の承認を出さないこともあるが、基本的には前向きに応援。あくまでも主導権を握っているのは子どもであり、大人の役割は、アイデア実現の手助けをすることなのだ。
一人ひとりの情熱から生まれたプロジェクトたち
では、実際にどのようなプロジェクトが行われているのだろうか。ここではその一例を紹介していく。
例えば、海洋汚染に関心のある生徒は、子ども向けの絵本を制作。文章の執筆、イラストもすべて自身で手がけた作品だ。絵本では、魚が海の中を旅しながら、子どもたちに海を守る大切さを伝えるストーリーが描かれている。すでにドラフト版が出版されており、続編の制作も予定しているそうだ。

絵本と共に映る卒業生Jess|Image via Green School NZ
キャンパスの空きスペースを活用したプロジェクトもある。これまでに、再生木材や中古のグリップなどの素材を使った馬術コースやジップライン、ロッククライミングの設置が進んでいる。安全基準を満たすためにやむをえず金属やコンクリートを使用する場合は、その分環境へのプラスの影響を生み出すため、100本の木を植えることを常に目指しているという。このプロジェクトは中学生が主導し、他の生徒や保護者を巻き込み、多くの人が協力したそうだ。

ジップラインを楽しむ様子|Image via Green School NZ
マオリ族の習慣を大切にした、タラナキ校ならではのイベント
他のグリーンスクールと異なる特徴の一つが、ニュージーランドの先住民族であるマオリ族の習慣を反映させたお祝い「Puanga(プアンガ)」を行う点だ。
プアンガとは、マオリの新年を告げる星の集まり「マタリキ」の兄星のことを意味し、冬の始まりを知らせる重要な役割を持っている。 5月から7月は先祖への感謝と収穫の終わりを祝い、新しい年の準備をする。グリーンスクール・ニュージーランドでは、生徒の家族などコミュニティ全員が集まり、プアンガの夜明けを見届けた後、ハンギ(※)をみんなで準備して味わう。食事は多めに作って地域の人々に分けるなど、地域とのつながりを大切にしながらお祝いするのが特徴だ。
※ 伝統的なマオリ料理。かぼちゃやラム肉などの具材を地中で4時間ほど蒸したもの

ハンギを準備する様子|Image via Green School NZ

出来上がったハンギを振る舞う様子|Image via Green School NZ
「社会でやっていけるの?」グリーンスクール校長が語る、”変革者”を育てる教育の真価
ここからは、校長へのインタビューを通して、起業家精神を身につけた子どもたちとグリーンスクールの未来を考えていく。
話者プロフィール:Nigel Barrett(ナイジェル・バレット)
 ニュージーランドのネルソン出身。イギリス、ケニア、ボルネオ、フィリピン、アラブ首長国連邦、ウガンダ、中国のさまざまな学校で働く。海外滞在中に教育学の修士号を取得し、バイリンガルスクールを創設するなどの経験を積む。教育哲学は「学びは子どもを中心に据え、魅力的で、関連性があり、周囲の世界とシームレスにつながっているべき」であり、「学校は誰もが分かち合い、学ぶ場所」であると考える。
ニュージーランドのネルソン出身。イギリス、ケニア、ボルネオ、フィリピン、アラブ首長国連邦、ウガンダ、中国のさまざまな学校で働く。海外滞在中に教育学の修士号を取得し、バイリンガルスクールを創設するなどの経験を積む。教育哲学は「学びは子どもを中心に据え、魅力的で、関連性があり、周囲の世界とシームレスにつながっているべき」であり、「学校は誰もが分かち合い、学ぶ場所」であると考える。
Q. グリーンスクールのどのような点を魅力に感じますか?
ここで働いている人々の情熱だと思います。この学校を創設した2人の起業家が教育のあるべき姿を信じているからこそ、こうした場所が生まれました。各地から集まってきた先生たちも、地域の伝統やサステナビリティ、子どもたちの成長のために熱意を持って働いています。受付スタッフたちもキウイの保護に取り組むなど、全員がグリーンスクールでの学びに関わっていると実感しています。その結果、素晴らしいエネルギーが生まれていると感じます。

生徒と本を読む校長|Image via Green School NZ
Q. 起業家精神を育むユニークな教育は、現実社会とのギャップを生む可能性があると考える人もいるかもしれません。例えば、日本からグリーンスクールへ留学していた生徒は、帰国したときに現実の社会にうまく適応できるのでしょうか?
プレゼンテーションやプロジェクト実現力を身につけることで、生徒たちはどこへ行ってもスキルを活かせると考えます。特別な環境ではあっても、学んだスキルは世界中の異なる状況で応用できるためです。
また、起業家精神を養うことだけではなく、基礎的な学問の習得にも重点を置いています。私たちは「ただ屋外で地球を守ることだけに取り組んでいる」という見方をされることもよくありますが、実際はそうではありません。例えば数学に関しては、アメリカのコンサルタント会社の協力を得て開発した独自のプログラムに沿って教えています。これはニュージーランドの一般的なプログラムよりも難易度が高いものです。識字についても同様の取り組みを行っています。変革者になるためには、皆の前で話す力も、読み書きする力も必要だからです。
また、高校に進むと「グリーンスクール・ディプロマ」というプログラムがあります。これは長期間にわたるプロジェクトや校外での学びが多いことが特徴で、ニュージーランド国内のすべての大学だけでなく、アメリカやオーストラリアの大学にも出願できる、国際的に認められた大学入学資格を得ることができるプログラムです。つまり、大学に進学する準備としても、起業家や変革者など持続可能な活動をするための育成としても役立ちます。
さらに、生徒の40パーセントはメキシコ、ブラジル、日本といった様々な国から来ていて、その多くが家族でこの地域に移住しています。保護者の中には起業家も多いため、そんな保護者やグローバルなコミュニティと関わることも、生徒にとって現実世界に出ていくための準備となります。

卒業生たちと先生たち|Image via Green School NZ
Q. 将来子どもたちにどのように育ってほしいですか?
自信を持った変革者として育ってほしいと思っています。やりたいことを信じて、自分の道を歩むことができると感じてほしい。子どもたちは、他の人が期待する道を選ばなければならないと感じる必要はありません。失敗から学び、再挑戦し、変化していくことが大事です。また、地球や人類を本当に大切に思い、どこに行っても周囲と交流できる力を持つことが大切だと考えています。

校長と生徒|Image via Green School NZ
取材後記
大人を相手にプロジェクトの提案を行ったり、興味のある分野を学ぶために自ら専門家を招いたりして培う行動力とコミュニケーション能力。これらは、どのようなフィールドにおいても周りを引き付ける人間性のベースとなり、絶えず変化していく社会で自信を持ってあらゆることを選択していく力になっていくだろう。
また、「異世界にある最先端の教育施設」なのだろうと期待して訪れたニュージーランドのグリーンスクールだったが、ゼロウェイストタウンとして有名な徳島県の上勝町と、「農業」「食」「アート」を軸にサステナビリティを体験しながら学ぶことのできる千葉県のクルックフィールズをかけ合わせた雰囲気を感じ、意外にも親近感が沸いた。
また、タラナキ地方も、鹿児島県の屋久島を彷彿とさせる環境で心が安らいだ。これは、ニュージーランドと日本がどちらも島国で山がちな地形が似ているからかもしれない。つまり日本でも、自然の中で自然から学ぶグリーンスクールのような教育を行うことは、環境的には十分可能である。
自然とのつながりを身体的に持ったうえで社会を変革していける起業家精神を持った人材は、これからますます求められるようになるだろう。そう考えると、これからの教育現場は、都市から自然に近い場所へと広がっていくのかもしれない。

Green School, NZがある、タラナキ地方の景色 |Image via Green School NZ
※1 2023 Census Data Highlights: Taranaki Region
【参照サイト】green school NEW ZEALAND
【参照サイト】green school ABOUT
【参照サイト】The Taranaki region|Taranaki Regional Council
【関連記事】「つながり」を取り戻す教育。バリ島にある、竹でできた学校「Green School」
【関連記事】ニュージーランド議会、タラナキ山の”人格権”を可決。マオリへの補償と世界観の尊重へ
【関連記事】自然界から「生きる」を学ぶ。愛媛に生まれた通信制高校・あめつち学舎
Edited by Motomi Soma