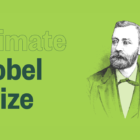「価格」は、誰が、どこで、どのように決めているのだろうか。
原材料費や流通マージン、効率化の影に隠れた労働。複雑な仕組みの中で形づくられる価格は、多くの人にとって「知りようのないブラックボックス」として存在してきた。しかしいま、フランスではこの不透明さを市民の手で書き換え、日々の買い物を民主的な意思決定へと変える動きが広がっている。
その中心にあるのが、小売ブランド「C’est qui le patron?!(ボスは誰?!:以下、CQLP)」である。商品の仕様も、公正な報酬の額も、最終的な価格までも、このブランドではすべてが市民の投票で決まる。企業が市場調査を行い、利益計算をもとに商品を設計するのではない。生活者自身が「こうあるべきだ」と考える基準を掲げ、その多数意見がひとつの商品となり、フランス全土のスーパーに並ぶのである。

Image via C’est qui le patron?!
この「市民がつくる商品」という発想は、創業者ニコラ・シャバン氏の一つの体験から始まった。2016年、彼が訪れた酪農家の台所には、疲労と諦めが漂っていた。市場価格が生産コストを下回り、休む暇もなく働いても赤字が膨らむ現実。廃業を考える若い農家。「消費者は、この苦しみを知らないだけだ。もし知れば、きっと選び方は変わるはずだ」シャバン氏はそう感じ、意思決定権そのものを市民に返すというモデルをつくり上げた。
CQLPの仕組みは至ってシンプルである。まず、誰でも無料でオンラインアンケートに参加し、商品の基準を決めることができる。原料の選び方、放牧期間、遺伝子組み換え飼料を避けるか、生産者が休暇を取れる報酬水準にするか。そうしたひとつひとつの項目に票が入れられ、最も支持される基準が採用される。興味深いのは、これらの選択がそのまま商品の価格構造に影響を与える点だ。アンケートでは、消費者が希望する品質に対して「どれだけ支払う意思があるか」も同時に問われる。こうして消費者が選んだ基準をもとに、生産者との協議や流通コストなどを踏まえて最終価格が調整され、その結果が店頭の価格として提示される。現在では、1,500万人以上がCQLPの商品を購入しているという。
さらに、意思決定により深く関わりたい人は、1ユーロでsociétaire(組合員)になれる。組合員は商品の最終仕様についての投票に参加するほか、生産者訪問や現場の監査、ブランドの方向性を定めるミーティングにも加わることができる。参加の仕方は自由で、時間があるときは議論に参加し、忙しいときは投票だけ。それでも“1人1票”という平等の原則は揺るがない。この柔らかな参加モデルが、16,800人以上もの市民を巻き込む原動力になっている。

Image via C’est qui le patron?!
CQLPの画期性は、その意思決定が直接、生産者の生活を支える点にある。市場価格に左右されず、生産者と市民が合意した保証価格が支払われる仕組みのもと、これまでに2,500以上の家族農家が支援を受けている。生産者は市場に怯えずに働ける安定を手にし、消費者は自分が支える未来を選択できる。
投票結果、価格の内訳、ブランドの利益、選ばれなかった選択肢まですべてが公開されており、広告費はゼロ。消費者が語り、消費者が支え、その結果を商品として受け取る。この循環が、ブランドを「過去10年で最も売れた新ブランド」へと押し上げた。

Image via C’est qui le patron?!
いまではこの仕組みは牛乳だけにとどまらない。バター、卵、ヨーグルト、リンゴジュース、ピザ、パスタ、サクランボ、タマネギ。生活に欠かせない18品目が同じプロセスでつくられ、総販売数は6億点を超えた。どの商品にも市民の意思から生まれていることが、ブランド全体の信頼を支え続けている。

Image via C’est qui le patron?!
価格は、ただの数字ではない。それは「誰の生活を支えたいのか」という、私たちの意思の表現である。「ボスは誰?!」という問いに、CQLPは明確な答えを返す。
“ボスは、私たち市民だ。”
この小さな革命は、消費の意味をもう一度考え直すきっかけを世界にもたらしつつある。
【参照サイト】C’est qui le patron?!