全ての産業が土をよくする社会を目指して2020年に設立された、国際コンソーシアム「JINOWA」。株式会社GEN Japanが中心となり、イタリアや日本の企業が参画。土に安全に還る生分解性の製品や循環型のサービス設計はもちろん、土を豊かにする有機物の循環デザインやテクノロジーを、その土地の環境条件や風土に適するようつなぐことで、コミュニティレベルでの土の循環と食糧自給が可能な社会を目指す。
そんなJINOWAとIDEAS FOR GOODがソーシャルグッドな体験「Experience for Good」の一環として提供するのが、「土」について考え学ぶ国内外でのフィールドワークの機会だ。それは、従来の観光では出会うことが叶わなかったような、ローカルコミュニティに深く根ざした人たちとの対話と体験。お互いの環境再生への取り組みの理解とリスペクトを深め、国境を超えたつながりを生み出していく。

Photo by Masato Sezawa.
JINOWAが昨年秋に先行して行った旅では、グリーンビジネス分野の起業家や研究者たちが、北イタリアを6日間かけて巡った。
IDEAS FOR GOODでは、そんな参加者たちの体験やイタリアのローカルで活躍する活動家について、全4回に分けてご紹介していく。第2回目の今回は、イタリアの名門ワイナリーが生態系拡張の一つとして小学校を作った話をお届けする。
土とリジェネラティブ 連載
【第1回】環境教育の未来形は”手を動かす”ことにある。イタリアの「命あふれる土」をめぐる旅
【第2回】ワイン造りで環境再生。イタリアの名門ワイナリーが小学校を開校した理由
【第3回】誰もがプロフェッショナルな能力を備え、共同体の中で役割を持って生きていく。多様性と真のインクルージョン
【第4回】オーバーツーリズムのヴェネツィア本島の隣で、人々が暮らしを紡ぐジュデッカ島というコミュニティ。地域資源を循環させる、自給自足への挑戦
人間が生態系の一部であることを、日々の営みから理解する子どもたち
土をめぐる旅の一行が2日目に向かったのは、ワインメーカーにして自社の敷地内に小学校を設立したエンリコ・リヴェット氏が営むワイナリーだ。9月半ばの日中の気温はまだ30℃近くあり、照りつける陽射しの下、標高400メートルの丘の上にあるリヴェット社を目指す。
道中目に入るのは、道沿いに立ち並ぶ立派な門構えのワイナリーの数々と、一面に広がるぶどう畑。この夏はヨーロッパ全体が記録的な猛暑に見舞われ、イタリアでも1979年以来の観測史上においてかつてない最高気温となった。加えて雨不足も危機的なレベルで、車窓から見えるぶどう畑の地肌は乾燥し白く剥き出しになっていて痛々しい。

谷の手前側がエンリコ・リヴェット氏の畑 Photo by Masato Sezawa.
イタリアのトップワインの産地であるピエモンテ州の中でもこの辺り一帯はランゲの丘と呼ばれ、ユネスコ世界遺産にも登録されている。広大なぶどう畑は圧巻だが、整然と並ぶワイン用のぶどうの木以外がほとんど存在しない極めて人工的なモノカルチャー(単一栽培)の光景が広がる。地元の人々にとって、ぶどうの樹はお金になるが、それ以外のものを植えてもお金にならないからだ。
実際にバローロ生産地区は、イタリアワインの格付け最上等級に当たるDOCG(統制保証原産地呼称)に登録されたぶどう畑の地価が、国内で最も高い地域の一つである。1ヘクタールあたりの地価は少なくとも150万ユーロ(約2億1,735万円)、クリュ(フランス語で「級」「畑」を意味する)によっては250万ユーロ(約3億6,395万)以上というケースもあり、ぶどう畑の不動産価値の高騰はこの先当分続くだろう。
「チャオ!僕のワイナリーにようこそ」
人懐こい笑顔で参加者を迎えてくれたエンリコ氏は、日本のアニメやプロレスを観て育ち、底抜けに明るい。子ども3人を持つ父でもある。しかしここまでの道のりは平坦ではなかった。

エンリコ氏 Photo by Masato Sezawa.
ワイナリーに小学校を建てる──そんな無謀にも思える夢に向かい、パンデミック中も奔走したエンリコ氏。財団を設立し、自ら資金を投じた。ワイナリーに併設していたゲストハウスを教室に改装し、ようやく生徒が集まりスタートしたのは2022年9月だった。
生産システムそのものがひとつの生命体。バイオダイナミック農法を導入
そもそもエンリコ氏が営むワイナリー、リヴェット社の創業は1902年、現当主の曽祖父の代に遡る。前代までに既に質の高い製品づくりと安定した売り上げを確立していたにもかかわらず、2009年から自社で100%を賄う原料のぶどう栽培を有機農法に転換する一大決心をする。その後2015年からは、さらにバイオダイナミック農法の導入を決意。
バイオダイナミック農法とは、オーストリアの哲学博士「ルドルフ・シュタイナー」が提唱した農法で、畑の土壌に対して化学肥料や、除草剤などの化学薬品の使用を禁止する農法だ。最低3年間の有機農法を続けていることや、太陽や月、惑星や星座の運行のリズムに調和して、種まきや施肥、収穫などの農作業を行うことなどが求められ、ヨーロッパを中心に研究・実践が行われている。
通常の有機農業とは異なり、生産物が有機的であることだけでなく、生産システムそのものが生命体(organic)であることが意識される。農場という有機体空間において人間を一つの構成要素に過ぎないものと捉え、作物以外の植物の有用性や、家畜以外の動物の有用性を認めるという、既存の自然と人間の関係や、農業における人間中心主義に抗う姿勢を取るものである。

Processed with VSCO with j2 preset
リヴェット社は2019年、世界で最も基準の厳しいオーガニック認証の一つとされる「デメター(demeter)認証」をバローロ・バルバレスコ生産エリアで初めて取得。現在もこの地域では唯一の存在である。そのような変革を牽引してきたエンリコ氏を、「バローロの異端児」と呼ぶ人もいる。土地が高騰し、ほとんどのワイナリーが点在するぶどう畑を所有しているのに対し、エンリコ氏は4つの森を含む丘を丸ごと持っていることも幸運だった。
エンリコ氏は、ビオ認証の取得はワインの価値を高めるためだけではなく、自分と一緒に働くチームの意識を変えていくために重要な歩みだったと言う。
「ワインという製品を作ることは自分にとってゴールではありません。自分の想いを伝え、議論していくためのツールだと思っています」
モノカルチャーの危うさ。生態系は複雑であるべき
エンリコ氏が最も苦労して挑戦してきたのは、もともとモノカルチャーであったぶどう畑に生物多様性を取り戻し、健全なエコシステム(生態系)を作り出すことだ。エンリコ氏は、モノカルチャーの弊害をこのように語る。
「モノカルチャーは確かに経済的に効率は良いですが、生物多様性を減少させ、森林や多くの命が息づく場所を奪っています。モノカルチャーは耕作物が何であれ、その生産方法が環境に配慮した最善の方法で行われていたとしても問題が残ります」
この旅の参加者の一人、ソニーコンピューターサイエンス研究所で協生農法を世界に普及する研究者である舩橋真俊さん。協生農法とは、土地を耕さず、肥料や農薬も使用しない、多種多様な植物を混生・密生させたまさに複雑な生態系を作り出すことで、人間の食料自給も向上させる拡張生態系の手法である。いま世界各国で主体的に拡張生態系を実装する組織を広げる活動をする中で、このぶどう畑を訪れた。
舩橋さんが見ても、エンリコ氏のぶどう畑の、包括的でオープンな取り組みとその実践場所である丘の立地は、まさに生態系拡張にも好条件だと言う。実際にリヴェット社が所有するリラーノの丘では、多種多様な菜園や果樹園、穀物畑や牧草地が広がっている。

Photo by Masato Sezawa.
「生態系は複雑であるべきで、単純化すればするほど脆いのです。みんなが同質でいたら、害虫や病気に一瞬でやられてしまいます。そして生態系の危機は人間社会のリスクに直結します。その土地の水や土壌にとっても多様な有機物供給が出来ないということは、私たちの命を支えるミネラルや栄養素を得られないということなのです」
エンリコ氏は長年かけて、このモノカルチャーのワイナリーを、さまざまな命が交わる多様性に満ちた場所に変化させてきた。古代種の穀物やスペルト小麦、野菜、ジャムやジュース用の新鮮な果物、エッセンシャルオイル用の薬草など、混作混在に基づいた昔の農場を思い描き、その姿を少しずつ取り戻していった。
花やハーブを混植した約2キロメートルの生垣には、ミツバチや蝶、さまざまな昆虫に、カエルやトカゲのような両生類、鳥が来て巣をつくり住み着くこともある。薬草からは抗菌作用のある成分が分泌され、ぶどうのツルに付く赤や黄色のハダニ対策に有効だという。
ぶどうの株の間には、80〜90年前まではこの辺りのどこにでも生息していた高木を1000本以上植えた。オーク、ダイオウ、ターキーオーク、イチイ、リンデン、白樺、トチ、ファルニア、クルミ、トネリコ、柳、ブナ、銀杏などである。木の葉は野生動物の隠れ家となり、その根は土壌の浸食や流出を防ぐ。こうして土中の微生物が豊かに活性化し、生物多様性が高まる中でぶどうが健やかに成長するのを助けている。

Photo by Masato Sezawa.
土着酵母とミツバチによる微生物の交換
ワイン醸造において、アルコール発酵の工程では大多数の生産者が工場で製造された培養酵母を使う。培養酵母は、元々は自然界にあった菌株の中からワイン醸造に適した種を厳選し、既に培養させているので発酵を促す力も強くて扱いやすく、ある程度予測する味に近づくことができるという利点があるからだ。しかし中には、自然にぶどうの果皮に付着する、あるいは醸造所内に棲息する土着酵母に価値を見出す生産者もいる。エンリコ氏も天然の土着酵母を利用する一人だ。
最近の農学研究では、森の近くで育つぶどうは、果皮に独特で多様な酵母が付着した状態で醸造所に入ってくることがわかっているという。これらは「森の酵母」であり、ワインの発酵と味わいに影響し、そのテロワール(風土、土地の個性)と、ワインの結びつきを強める土着株である。
そして、ここで忘れてはならないのがミツバチだ。畑の一角に並ぶ6つの巣箱ではそれぞれ、約4万匹の働きバチ、200匹の雄バチ、1匹の女王バチが飼育されている。ミツバチは受粉作業を行うことで、植物やその他のすべての生物のつながりを確かなものにしている。
「私たちの目には見えないけれど、花から花へと採餌することで、草とブドウの間で酵母を含む微生物が交わっているんだ」
ワインの世界で最高の褒め言葉の一つに「コンプレックス(複雑さ)」がある。複雑でありながらも、それぞれが調和していることを「ラウンド(丸みがある)」と表現することもある。まさにミツバチが行うような自然の交わりが、この複雑でありながら調和した土着酵母のまろやかな味わいの礎になっている。
人間も複雑な生態系の一部。生態系のバランスの要となる子どもたち
エンリコ氏はミツバチはもちろん、自分自身やワイナリーで働く従業員、ここに関わる一人一人の人間も複雑な生態系の一部であり、そのバランスや調和が大事だと考えているという。
同様に、日本の味噌や糠床などの発酵の世界では、どんなに良い原材料と微生物が働くよい環境を作りだしても、人間の手によってかき混ぜられなければ本当に良い発酵食品にはならない。
だからこそエンリコ氏が、育む生態系をより良くかき混ぜるために、絶対に不可欠だと考えたのが「子どもたち」だった。
このエンリコ氏が営む小学校は、気候変動やサステナビリティに特化して教えているわけではなく、公立の小学校と変わらない一般的なカリキュラムを扱っている。もちろん教室は屋内だけでなく広大なワイナリーと、森のすべてを使って行われる。

子どもたちの日常には、ラベンダーの周りにミツバチが飛び交う傍らで、のんびりとロバが草を喰む姿がある。ロバや牛の排泄物や、庭や畑での作業、醸造課程から出る残渣を、じっくり2年の歳月をかけ発酵させて堆肥をつくり、これをまた畑に還す。人間が生態系の一部であることを、日々の営みから理解する、という学び方だ。まだ慣れないのか、保護者から「校長先生」と呼ばれるたび、エンリコ氏はどこか照れ臭そうだが、その言葉は力強い。
「想像したり夢見たりすることをやめないこと。既存のスキームを破ることを諦めないこと」
化学肥料と農薬を駆使して少しでも多くの原料を収穫し、安定した培養酵母と薬剤による制御でワイン造りだけに集中すれば、経済的には苦労しない恵まれた場所だ。その道をエンリコ氏は選ばなかった。小学校という新しい挑戦はまだ始まったばかりで生徒の数は少なく、資金も十分ではない。
ピエモンテ人の気質なのか大胆な変革にも慎重さが必要だと、できる限りこの学校もゆっくりと着実に成長していくことを望んでいる。そのため、最初から派手な宣伝や投資家を集めたりはしたくないという。
「一人で世界を変えることはできないけれど、自分の周辺の小さな世界にルネッサンスを起こし、少しずつ変えることはできると信じているんだ。そのためにどうしてもチャレンジしたかったのが教育。子どもたちは未来そのもの。子どもたちに自然の美しさや命の素晴らしさを、手で触れて感じて体得し、育っていって欲しい」
子どもたちという新しい共存者を迎え入れて更なる調和を願いながら、本物の知識や信念を未来の世代へ循環させたいというエンリコ氏は、これからもきっと夢に向かってもがき続けるだろう。
彼の住む生態系はより複雑に、より良くなっている。旅の参加者たちと共にエンリコ氏と出会い、一緒にこの命があふれる丘に立ち、見えないものも含むさまざまな命がゆっくりと、しかし健やかに満ち足りて循環しているという感覚に不思議と包まれていくのを覚えた。
生態系の一部であることを、日々の営みのなかの体験から理解する、という学び方。環境教育に本当に必要なのは、教室という調えられた場所や一般論を語る教材ではなく、まずは自然の中に身を置くことからではないだろうか。

日本国内で、多様な土を使った体験に参加できる循環型農園 「ReDAICHI」
今後、IDEAS FOR GOODはJINOWAと連携し、土をめぐる人と自然とコミュニティのための循環する暮らしのあり方を実践する様々なプログラムを展開予定だ。
舞台になるのは、多様な土を通した体験に参加できる場所、埼玉県三芳町にある循環型農園 「ReDAICHI」だ。この石坂オーガニックファームが運営する循環型農園 は、「土」を通して地球規模の環境について感じ、日常の中で学べる機会を与えてくれる。

ReDAICHIは肥沃な土に触れながら、固有種の種を育てたり、世界の食糧問題や農業について知ることができる会員制シェアファームである。従来の農業の枠組みを超え、どうしたらもっと良い土を生み出す社会に転換できるのか、世界的に活躍する専門家から、学生から地元のお年寄りまで、多様な人々が土を通して交わる場所となる。
また、ReDAICHIは土の国際的なイノベーションハブでもある。その分野は、食産業に携わる生産者や料理人、建築家やアーティスト、都市開発や建設業、ITやファッションなど、多岐に渡る。
ウェブサイトでは、土をめぐる世界の情勢や、各国の土の活動家の取り組み「母なる大地のはなし」も発信している。興味がある方は、こちらも読んでみてはいかがだろうか。
※今後のプログラム情報は、随時IDEAS FOR GOODサイト内でお知らせいたします。
【2/25イベント開催!】生きている土と微生物と共に生きる Living Soil, Living Food 発酵と土壌の国際フォーラム
埼玉県三芳町には日本農業遺産にも認定された「落ち葉堆肥」をつかった農業文化があり、江戸時代から目に見えない微生物に育まれた豊かな土や種を守る農業や食文化が根付いています。
このような歴史ある土壌への取り組みを学ぶために、イタリアやスペイン、フィンランドから微生物や発酵食、循環型農業などに取り組む専門家十数名が埼玉県を訪れます。
外国人専門家と日本の土壌や発酵食文化を代表するトップ研究者や生産者をお招きし土壌と発酵を学び交流する公開型の国際フォーラムを開催します。当日は埼玉県内の発酵食品や発酵飲料 (日本酒、ワイン、ビール)などが一同に集まるグローバル交流会も同時開催。県内を代表する地元生産者の方々の解説を聞きながら、お食事やお飲み物もお楽しみ頂けます。
▶︎詳細・お申し込みはこちら:生きている土と微生物と共に生きる Living Soil, Living Food 発酵と土壌の国際フォーラム

執筆者:岡崎 啓子(おかざき けいこ)氏
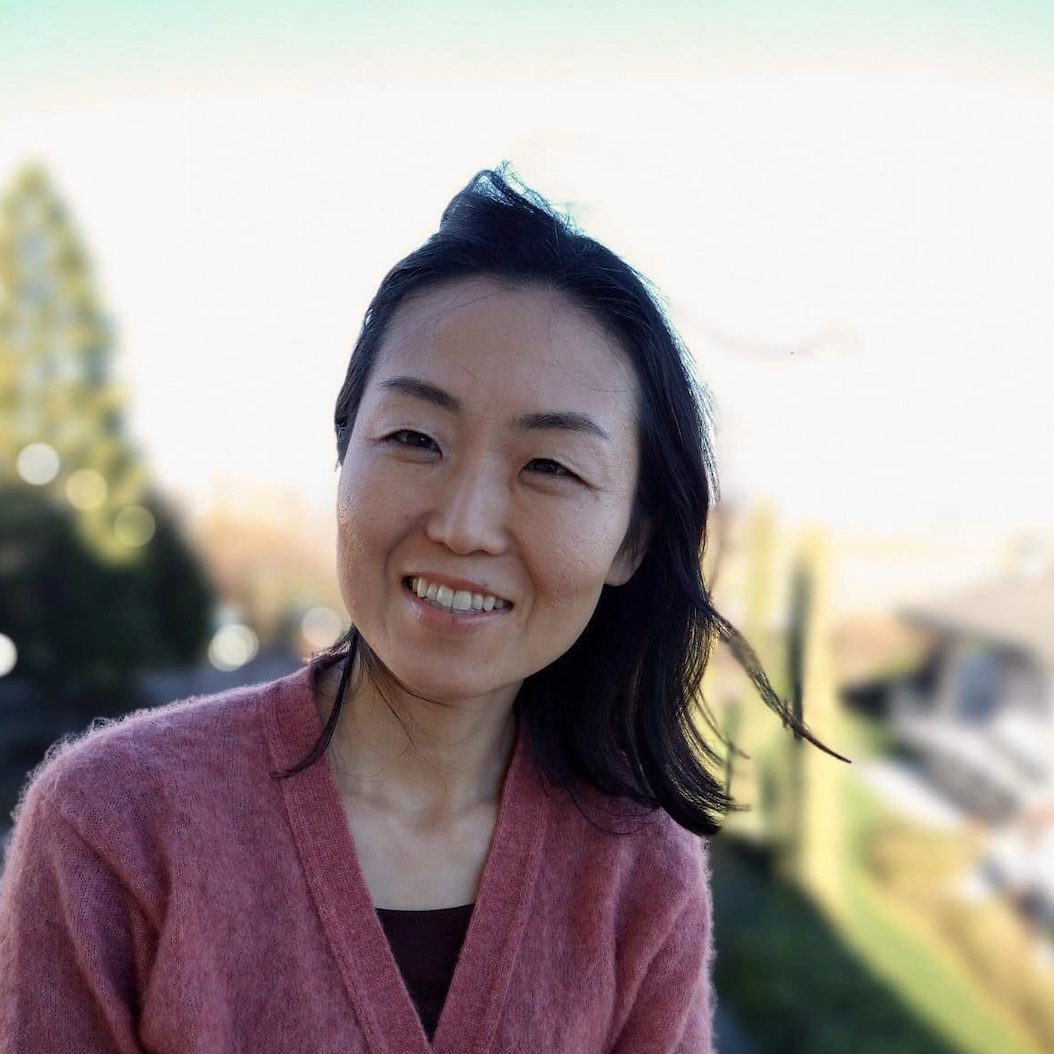 岡崎 啓子(おかざき けいこ)。埼玉に代々続く農家を兼業で継いだ父、料理が得意な母の元に生まれ、里山の営みを身近に育つ。大学卒業後イベント企画・制作業界で働いたのち、「食と農」を自分の専門にすべく、スローフード協会設立の食科学大学を目指して2004年に渡伊、第一期生として3年間学ぶ。卒業後はイタリア・EATALY社にて、日本出店を中心とする海外事業展開の黎明期に携わる。2児の出産・育休を経てGEN・JINOWAメンバー。
岡崎 啓子(おかざき けいこ)。埼玉に代々続く農家を兼業で継いだ父、料理が得意な母の元に生まれ、里山の営みを身近に育つ。大学卒業後イベント企画・制作業界で働いたのち、「食と農」を自分の専門にすべく、スローフード協会設立の食科学大学を目指して2004年に渡伊、第一期生として3年間学ぶ。卒業後はイタリア・EATALY社にて、日本出店を中心とする海外事業展開の黎明期に携わる。2児の出産・育休を経てGEN・JINOWAメンバー。
Supported by Ishizaka Organic Farm
Photo by Masato Sezawa.
Edited by Erika Tomiyama















