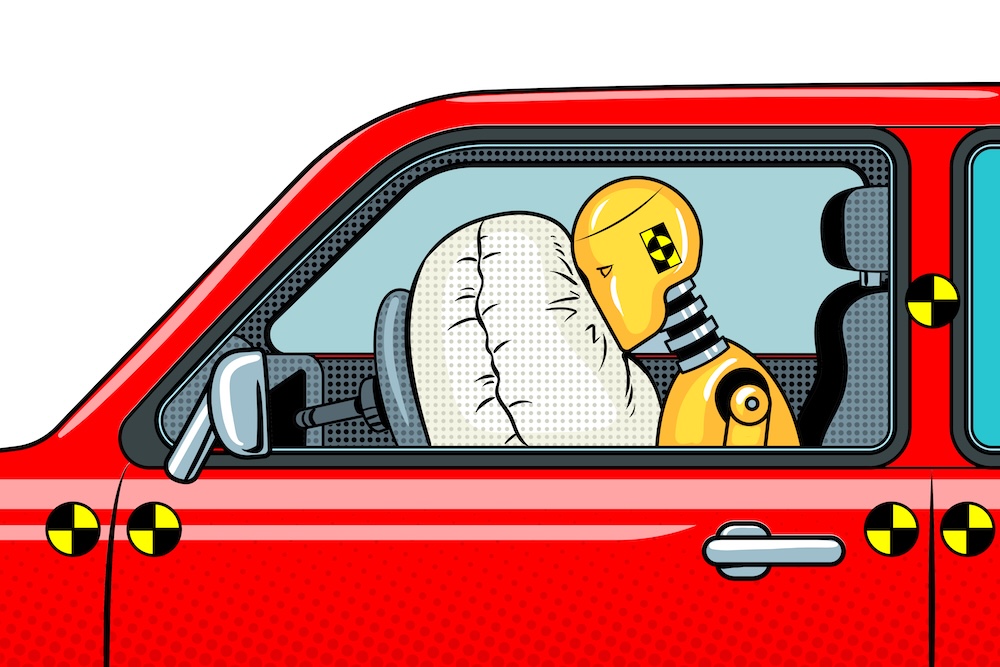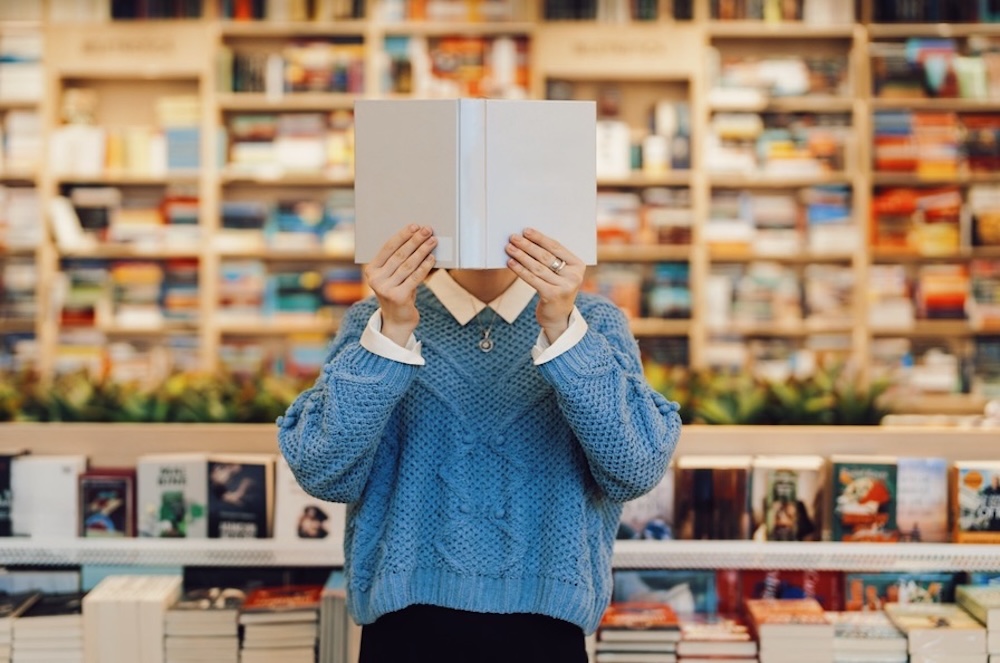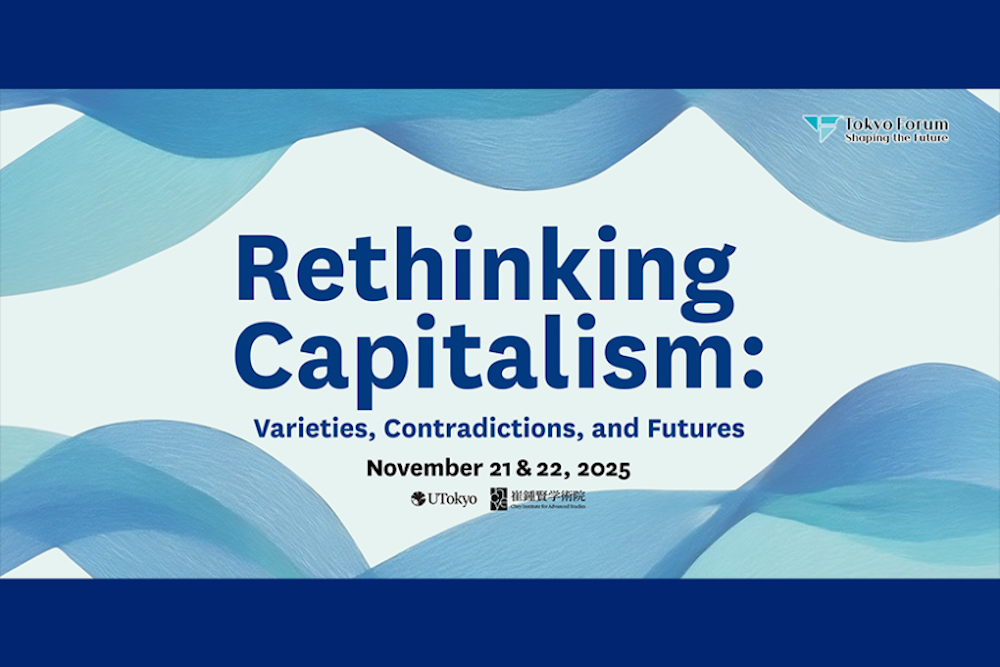【まとめ】サステナブル素材で作られた、世界の文房具5選

Image via Unsplash
日常で使う文房具。これまでは価格やデザインが選ぶときの決め手になっていたかもしれないが、身近なものだからこそ、環境に配慮したアイテムを選びたいと思っている人も多いのではないだろうか。日々使うものがサステナブルなものであることは、私たちの心を豊かにしてくれる。
最近では世界各国、日本でもサステナブルな文房具を作るブランドが増えてきている。今回は、サステナブルな文房具アイデアをご紹介する。
01. 下水から文房具をつくる、NY流サーキュラーデザイン
Sum Wasteは、ニューヨーク市内の台所やトイレなどの水が流れ込む下水処理場で発生したバイオソリッド(下水汚泥)を使い、環境負荷の低いペンを作るプロジェクトである。ペン本体はバイオソリッドをバクテリアに与えることで生成される生分解性プラスチックからできており、インクはバイオソリッドを炭化して生じた木炭から作る顔料だ。部品が他のペンと比べて少なく、廃棄物を活用することで製造工程の環境負荷を抑えている。また、インクボトルを簡単に詰め替えられるので長く使うことができ、捨てるときが来たら本体はコンポスト(堆肥化)、インクボトルは再利用に回すことで無駄のない循環が生まれる。
- 国名:アメリカ
- 団体(企業)名:Sum Waste
02. ネスプレッソの使用済みカプセルから作られたボールペン
大手コーヒーメーカーのネスプレッソがスイスの文房具メーカーカランダッシュとコラボレーションして誕生したボールペン。ネスプレッソの「セカンドライフプロジェクト」というリサイクルプロジェクトの一貫で、「リサイクル」をコンセプトとしたボールペンには、ネスプレッソの使用済みコーヒーカプセルが使われている。ボールペン本体だけではなく、ボールペンが入っている箱も100%リサイクル可能なボール紙でできている、サステナブルなアイテムである。
- 国名:スイス
- 団体(企業)名:ネスプレッソ
03. 海洋プラごみをリサイクルした再生樹脂使用ボールペン

Image via 株式会社パイロットコーポレーション
株式会社パイロットコーポレーションが作った、海洋プラスチックごみをリサイクルした再生樹脂を使った国内初の油性ボールペン「スーパーグリップG オーシャンプラスチック」。使用する海洋プラスチックごみは、リサイクル事業を展開するテラサイクルジャパン合同会社が日本国内で回収したものである。ボディの一部に海洋プラスチックごみをリサイクルした再生樹脂を使用しており、その他のパーツにもリサイクル材を使用。消耗部分を除いた全プラスチック重量中の74%が再生材で構成される、エコマーク認定商品およびグリーン購入法適合商品である。
- 国名:日本
- 団体(企業)名:株式会社パイロットコーポレーション
転載元:パイロット、国内初の海洋プラごみをリサイクルした再生樹脂使用ボールペンを発売
04. 堆肥化可能なマーカー「Scribit Pen」

Image via CRA
すべてのパーツが環境に配慮されたうえでつくられたScribit Pen。ペン先とカートリッジには天然繊維が、胴軸には木材とバイオプラスチックおよび陽極酸化アルミニウムが使用されている。ペン先とカートリッジは交換可能であるため、同じ胴軸を半永久的に使用できる。さらに、食用としても認定されている無毒の水ベースのインクを使用している。
- 国名:イタリア
- 団体(企業)名:CRA
転載元:世界初の堆肥化可能なマーカー「Scribit Pen」、画材業界のサーキュラーエコノミー推進を目指す
05. 安心な素材、自然な色にこだわった野菜とお米のクレヨン
この投稿をInstagramで見る
お米と野菜から作られたクレヨン、「おやさいクレヨンstandard」と「おこめのクレヨンstandard」。米ぬかから採れた米油とライスワックスをベースに、収穫の際に捨てられてしまう野菜の外葉などを原材料に使用。小さな子どもも安心して遊べるように、野菜の色を補う顔料は、食品の着色に使用されるのと同成分のものなどを採用している。万が一、口に入れても安全な素材だけでできている。
- 国名:日本
- 団体(企業)名:mizuiro.inc
まとめ
いかがだっただろうか。海洋プラスチックや下水まで、国内外でさまざまな素材から文房具が作られており、どれも環境に優しいだけでなくデザインや機能までもが魅力的だ。
また、こうしたユニークな背景を持つ商品は、ストーリーを誰かにシェアしたくなったり、持つ人の気持ちまでも楽しくしてくれたりする。使うほどに愛着が湧き、長く大切に使用したいというマインドが生まれるだろう。
文房具という身近なものをサステナブルなものに変える。小さな一歩かもしれないが、その積み重ねが社会を変えていくのだ。