Tag Archives: 生物多様性

【8/28開催】クリエイティビティを引き出す、これからの時代の自然コミュニティ。都市だからこそ生まれる「森づくり」の価値とは?(Climate Creative Cafe.14)
クリエイティビティで気候危機に立ち向かうプロジェクト「Climate Creative」。今回のイベントテーマは「これからの時代の自然コミュニティ」。ぜひご参加ください!

海を壊さず再生しよう。サンゴ礁に“栄養を与える”日焼け止め
世界で初めてサンゴに栄養を与えることが実証された日焼け止めが登場しました。この商品は、環境を「守る」から「再生する」時代へと変化する兆しになるでしょうか。

「草花」が、歩きたくなるまちのリズムをつくる。都市デザインにおける植物の重要性
従来型のハード・経済活動重視のまちづくりから、あらゆるジェンダーに向けた包括的なまちづくりが進んでいます。新しい建物を建てることなく、都市デザインに寄与するのが「植物や花」。その効果とは?

今こそ私たちが、利他的に生きるとき。生物学者・福岡伸一先生が「いのちとは何か」を問い続ける理由
「いのちをつなぐ学校」で、生物学者である福岡伸一先生は、「生命とは何か?」という問いに対して、「生命は流れであり、動的平衡なもの」と話しました。そこに垣間見える生命の「利他性」。それこそが、環境破壊や紛争など、さまざまな危機に直面する私たちにとって、立ち返るべき生き方なのではないか──福岡先生はそう話しました。

スマホを生物多様性の観測拠点に。ネイチャーポジティブを実現するプラットフォーム【鎌倉投信×バイオーム対談】
現在、世界の動植物約100万種が絶滅の危機にあるとされている中、生物と人間の架け橋になることで「環境を守ることが利益を生む」新たな仕組みの構築にチャレンジする「バイオーム」。同社のユニークなビジネスモデルと、鎌倉投信との出会いとは?

ブレードを黒く塗るだけ?渡り鳥の衝突を防ぐ風力発電機のデザイン
風力発電機に衝突することで、毎年多くの鳥が命を落としていることをご存じですか?今回は、そのシンプルで意外な解決策を紹介します。

【パリ現地レポ】環境イベント「ChangeNOW」で見つけた、欧州の生物多様性スタートアップ5社
今年で7回目を迎える、パリで開催された環境イベントに参加してきました。生物多様性に関する革新的技術を持つスタートアップ企業に焦点をあてて、現地の様子をレポートします。
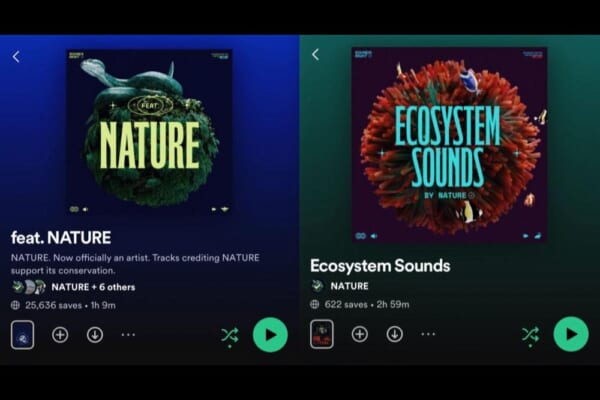
地球が、音楽ストリーミングの公式アーティストに。自然音再生の収益を環境保全へ
日々私たちを癒してくれる、自然の音。そのクリエイターである「地球」が音楽ストリーミングの公式アーティストになりました。音楽を楽しみながら、地球に恩返しをしてみませんか?

魚のために扉を開けて。市民が“オンライン観察”で産卵を支援する、オランダの「フィッシュ・ドアベル」
オランダの生態学者が生み出した「The fish doorbell(フィッシュ・ドアベル)」プロジェクト。水中カメラとオンラインプラットフォームを通じて、魚が産卵のためにヴェヒト川からクロメ・ライン川などへと移動する際に魚が水門に近づくと、人々がそれを視覚的に確認し、水門の開門をリモートで操作できるようにしています。

沈黙する「自然のオーケストラ」が、私たちに教えてくれること
減っていく森林、CO2排出量を示すデータ……私たちは、視覚情報や知識を通して環境問題を知ることが多いかもしれません。しかし、自然の音を聴くことが、今地球に何が起こっていることを知るために有効な手段となりそうです。

光害を減らして、渡り鳥を守ろう。北米「街の消灯」が、マルチスピーシーズの実践に
都会の眩しい光は、人間だけでなく鳥にも大きく影響を与えています。特に、長距離を移動する渡り鳥たちにとって、慣れない場所での強い光は、命を奪う危険も伴うのです。これを解決するべくアメリカでは渡り鳥のために消灯する取り組みが広がっています。

ベルリンの空港跡地を「気候中立都市」に。すべての生き物が住みやすい街を目指す
かつて利用されていたベルリン・テーゲル空港は2020年に閉鎖しましたが、その跡地はカーフリーで、そして持続可能な新しい地域として生まれ変わる予定です。

微生物と共に社会をつくる?人間中心ではない「マルチスピーシーズ」の社会がもたらす喜びとは【多元世界をめぐる】
「マルチスピーシーズ」という言葉、聞いたことがありますか?「多種」を意味するこの言葉が今、人間中心のデザインから脱却する一助になるとして注目されているのです。愛媛大学のルプレヒト教授にお話を伺ってきました。
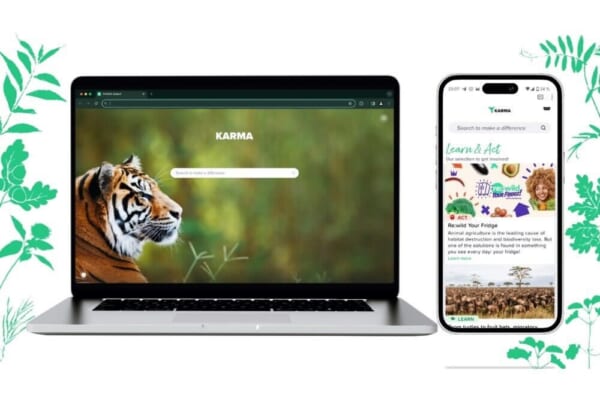
調べるだけで生物多様性に貢献できる検索エンジン「KARMA」
検索するだけで生物多様性の保護に貢献できる検索エンジン「KARMA」をご紹介。日常の「調べる」行為を、ソーシャルグッドなアクションに変えてみませんか?

「先住民の科学」は、気候変動対策への道を拓くか
世界から注目されている、先住民の科学「伝統の生態的知識」。この先住民族の科学が、気候危機を止めるヒントになりうるとされています。

企業が「ネイチャーポジティブ」に正面から向き合うには?国内事例5選
2030年までに生物多様性の損失を食い止め反転させる「ネイチャーポジティブ」が国際社会の共通目標となっています。目標達成に向け、企業ができることとは?
