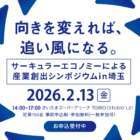▶️ニュースレターの詳細・登録はこちらから!
脱炭素、そしてサーキュラーエコノミーが気候変動対策として広がってきた中、次なる重要テーマとされているのが生物多様性だ。特に近年は「ネイチャーポジティブ」という表現も多く聞かれるようになってきた。
ネイチャーポジティブとは、自然や生物多様性の損失に歯止めをかけるだけではなく、むしろそれらの指標を向上させていくことを意味する。例えば、生態系を傷つける土地開発の手法や素材の使用を止めるだけではなく、土壌がより豊かになる農法や土地利用に切り替えたり、生態系の回復を促進するような自然素材を採用したりすることが挙げられる。こうした回復に寄与する特性は「再生的(リジェネラティブ)」とも表現される。
こう聞くと、生態系に良いことをしていたらネイチャーポジティブ──と思いそうになるが、果たしてそのポジティブとは、何をもってしてポジティブと言えるのだろうか。
たしかに、失われつつある動植物が守られ、その個体数が増えたらポジティブかもしれない。しかし、ポジティブの解釈については逃れようのない難しさも潜んでいる。生態系における事象について、人間へのメリットがあるかどうかで、評価が大きく変わってしまうためだ。
こちらの記事でも紹介した例を見てみよう。2024年、ダークチョコレートなどカカオを含む食品に、鉛やカドミウムなど人体に「有毒な」重金属が含まれていることが米国NGOの研究によって明らかになった。一方で、こうした金属類を取り込む作用のある植物を、汚染された土壌に植えて浄化する手法・ファイトレメディエーションは、土壌を「再生」する方法としても認知されている。
チョコレートに重金属が入っていたら「有毒」、植物に入っていたら「再生」……このように、人間にとって利益があるかどうかによって、真逆の認識に至ることがある。こうした状況で私たちは、生態系が回復しても、人間へのメリットがなければネイチャーポジティブではないと評価する、または、人間視点に偏った「ポジティブ」によって、結果的に生態系全体の損失を生むというリスクを持っているのだ。

他の生き物は、同じ世界で全く違う世界の捉え方をしているかもしれない|Image via Shutterstock
ネイチャーポジティブが、特定の誰かの指標を優先して測られる──それは人間同士の間でも起こりうる。環境課題への意識の高まりから都市の緑化が進んでいるが、緑化によって立ち退きを求められる人や、土地が高騰して居住地を変えざるを得ない人がいると指摘されているのだ。
こうした現象は気候ジェントリフィケーションと呼ばれ、その緑地化が「誰にとって」豊かな環境をもたらすのかを考える必要がある。これは、生物多様性を回復する環境づくりとして緑地化が進むこともあり、ネイチャーポジティブの文脈にも大きく関わる問題だ。
そのポジティブは、誰にとってのポジティブなのか。「人間にとって良いかどうか」という視点だけで評価してしまい、他の生態系の存在や役割を見落としている可能性はないか。そんな問いを、投げかけるべき社会フェーズに入っているかもしれない。
たしかに、これを議論するのが人間である以上、どうあがいても人間の主観を除くことはできない。それでも、地球を「唯一の株主」にしたパタゴニアの例などに倣い、人間の主観に偏らないための仕組みづくりは可能だ。
その上で、人間視点という限界があることを自覚し、その自覚があることを言葉やデザインで伝えようとする実践が重要となる。
例えば、オランダの「DommelPolitics(ドメル川の政治)」というプロジェクトでは、ドメル川に暮らす生き物が出馬したらどんな政策を提案するかを言語化。実際に投票すると、投票先に応じてスクリーン上の川の映像に変化が起きる。生き物を一括りに扱うのではなく、一つひとつの種に光を当てることで、種の数だけ特有のニーズがあると理解していることを伝えられるだろう。
ネイチャーポジティブが広がりつつあるがゆえのこうした課題。それが制限となるのではなく、「どうすればより多様ないのちと豊かな自然を共有できるだろう」と想像をめぐらせる入口となることを願う。
【関連記事】人間以外の生物が、街をデザインしたら?植物やきのこの住処「Urban Reef」が都市環境を再生
【関連記事】微生物と共に社会をつくる?人間中心ではない「マルチスピーシーズ」の社会がもたらす喜びとは【多元世界をめぐる】
ニュースレターの無料登録はこちらから
IDEAS FOR GOODでは週に2回(毎週月曜日と木曜日の朝8:00)、ニュースレターを無料で配信。ニュースレター読者限定の情報もお届けしています。
- RECOMMENDED ARTICLE: 週の人気記事一覧
- EVENT INFO: 最新のセミナー・イベント情報
- VOICE FROM EDITOR ROOM: 編集部による限定コラム
編集部による限定コラムの全編をご覧になりたい方はぜひニュースレターにご登録ください。