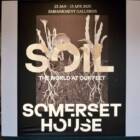IDEAS FOR GOODでは、サステナビリティやサーキュラーエコノミーに関連するホットなトピックや、取材や視察で感じた現場のジレンマ、会議で交わされたリアルな議論、その他限定情報などを無料のニュースレターでお届けしています。今回の記事では、10・11月に配信された編集部コラムの中から一部を抜粋して掲載します。ぜひご覧ください。
▶️ニュースレターの詳細・登録はこちらから
目次
成長を目的にしない「繁栄」の社会。ゼブラ企業が日本で受け入れられる理由
Written by Erika Tomiyama

Image via Shutterstock
「ゼブラ企業は、想像以上に日本にフィットしました」
この言葉は、11月19日にIDEAS FOR GOODが開催したイベント「ゼブラ企業と欧州動向をもとに考える、成長至上“じゃない”社会と経済システム」で、株式会社Zebras and Company(Z&C)共同創業者の田淵良敬氏が語ったものです。
「ゼブラ企業」は、ユニコーン企業への過剰な期待と、それに伴う現実離れした成長目標に疑問を抱いたアメリカの女性起業家たちが、2017年に草の根的に提唱したのが始まり。短期的な利益追求ではなく、持続可能性や社会的影響を重視するもので、急成長を目指すユニコーン企業とは対照的に、ゼブラ企業は現実に存在する動物のように地に足をつけ、社会全体に恩恵をもたらす成長を目指す意味が込められています。
ゼブラ企業という概念自体はアメリカで生まれたものではありますが、日本でのその浸透スピードと独自性は、アメリカの主要メディアでも取り上げられ、いまや世界でも注目を集めているといいます。2024年3月には経済産業省・中小企業庁が「ローカルゼブラ推進政策」を立ち上げるなど、政府の支援も浸透を後押ししているのです。
興味深いのは、日本でのゼブラ企業が単なるアメリカの輸入モデルにとどまらず、「日本的ゼブラ企業」として再定義されつつある点。たとえば、アメリカでは個人主義的な起業家がゼブラ企業を立ち上げるケースが多いのに対し、日本では地域社会や伝統産業との連携を重視する動きが顕著だといいます。
もともと日本には、創業100年以上の企業が約33,000社、200年以上が3,000社超、1000年以上が世界14社中8社という独特の経済基盤があり、日本の老舗企業は急成長を目指すのではなく、地域社会と共存しながら持続的な経営を重視していることが特徴です。この「急成長を求めない価値観」が、ゼブラ企業の哲学に自然に適合しているといえるのかもしれません。
イベントで紹介されたのは、Z&Cの投資先第1号である「陽と人」。福島県国見町で、農産物の活用と地域課題解決に取り組む企業です。廃棄されていた柿の皮を活用し、女性のデリケートゾーンケア製品「明日わたしは柿の木にのぼる」を展開。フェムテックの迅速で農業の持続可能性と女性支援を両立しています。
Z&Cの記事の中では、「陽と人」の代表である小林味愛氏が、取引先である農家の家で、おばあさんと1時間、2時間と話しこむエピソードが挙げられています。よくIDEAS FOR GOODでソーシャルグッドな事例を取り上げる際、「経済合理性はあるのか」という質問を受ける機会が多くあるのですが、記事には、こんなことが書かれていました。
非合理な行動として映るというのは、あくまで短期的な利益の最大化を目的とした時の話。閉じられた地方社会で持続的にビジネスに取り組むには、信頼こそが不可欠になります。ですから、それは経済的な利益とも矛盾しない。長期で見れば、そちらの方が合理的と言えるのです。
農家のおばあさんと1・2時間話し込む行為は、生産重視の視点では効率的ではありません。しかし、顔の見える地域社会で持続的な関係を築くには、このような時間をかけた信頼構築が不可欠です。短期的な利益を追求するモデルでは見過ごされがちな「信頼」という要素こそが、長期的には地域全体の活性化や事業の安定性を支える土台となります。非合理に見える行動の中にこそ、ビジネスの本質的な合理性が潜んでいる可能性があります。
今回のイベントのテーマとなった「成長至上主義」からの脱却プロセスのヒントは、私たちが本来持っている「人間らしさ」を取り戻すことにあるように感じました。人間関係や地域経済の再構築に向けた、新しい道筋を示しているのがゼブラ企業であり、その拡大は単なるビジネスモデルの転換にとどまらず、自分自身や足元にある地域との「出会い直し」とも言えるかもしれません。
【関連記事】英国で「屋外広告のない街」を求める声。広告が心身にもたらす影響が明らかに
【関連記事】B Market Builder Japan始動。日本のB Corpムーブメントの舞台裏とこれから
地方と都市の共依存。共倒れしないために何ができるのか
Written by Natsuki

Image via Shutterstock
コロナ以降、東京など都会で暮らす人々の間で地方移住への関心が高まっています。SNSには、「田舎暮らし」「古民家暮らし」「地方移住」……などのハッシュタグと共に、ゆっくりとした暮らしの魅力が切り取られているようです。自然があり、食に恵まれ、人があたたかく、心地よい静けさがある──その田舎像は「間違ってはいない」と、人口1,300のまちに暮らす筆者は思います。
しかし実際のところ、いわゆる“のんびり田舎暮らし”は、生活の中で心が落ち着くほんのひとときに過ぎません。本当に地域に根ざして生きる人々は、その豊かな時間を実感する裏で、道路に伸びた雑草を刈り、農作業に勤しみ、自治会で話し合いを重ねているのです。これは田舎移住の“幻想”には描かれることのない、実直に人や自然と向き合い折り合いをつけて生きる姿だと感じます。
一方で、地方から見た都会像にも偏りがあるかもしれません。地方で暮らすうちに、筆者自身が「都会の人は利益を優先する。買っては捨てる暮らしをしている。自然に触れていない……」と思い込んでいることに、ふと気が付きます。これだけ多様な人が生きる都会なのに、一緒くたにしてしまうのです。
双方のそうした理解不足は、地方(中都市も考慮すべきですが)と都市のあいだにおける関係性の希薄さや、協働の浅さが背景にあるのではないでしょうか。地方創生という名のもと、資金提供やプロジェクト創出が促進されているものの、一方向かつ短期的なものが多いように思われます。
それと同時に、地方と都会は構造としては共存関係にあります。都市は、地方からの食料の供給に頼っているでしょう。一方で地方は、地方交付税交付金や国庫支出金がなくては地域行政を担っていくことが難しいはず。各々の現在の役割を守らなくては、日常は保たれないかもしれないのです。
つまり現在の社会は、地方と都市が互いを必要とする存在でありながら、相互理解や支え合いが不足する実態があるように見えます。結果として、地方は人口が減り文化の継承は危ぶまれ、都市では土地・自然・人への負荷がかかり、不健康な社会へと突き進んではいないでしょうか。
これから真に持続可能な社会体系を考えていく際、地方と都市がコミュニケーションを丁寧に重ね、役割を尊重しつつ知見を共有することは欠かせないでしょう。このように地域内で特有の自然や人、モノの循環を促し、地域間で補完し合う社会は地域循環共生圏とも呼ばれ、環境省が中心となって推進されています。互いの文化や経済をただ消費し合っていてはならないのです。
地方と都市、どちらが良いとも悪いともありません。異なる存在の異なる価値に対して敬意を払い、両者が能動的に支え合おうとする社会が求められるのではないでしょうか。そこには、金銭だけではない、継続的な人の交流や対等な学び合いの場が生まれているはずです。
【関連記事】池袋発、ごみ拾いとコーヒーが居場所をつくる。心を癒すつながり「地域内関係資本」とは?
【関連記事】トランジションタウン運動の実践者に聞く。ローカル経済活性化のヒント【ウェルビーイング特集 #35 新しい経済】
「死を語る場」から生まれる、生への眼差し
Written by Motomi

Image via Shutterstock
誰にでもいつかは訪れる、死。高齢化が進む日本ではこの先、2040年頃をピークに死者数が増えていく時代に突入すると言われています。
こうした社会は「多死社会」と呼ばれ、医療体制や看取りの場所、残された家族の心のケアなどが大きな課題となっています。一方で、そんな死が“タブー視”され、オープンに語ったり、向き合ったりしにくいものとなっているのも事実です。
筆者は先日、そんな「死」についてあえて対話する「デスカフェ」というイベントを、宮城県の気仙沼という地域で、地元の方々と一緒に開催しました。デスカフェは、死をタブー視せずに受け入れ、語り合う場。宗教や国籍、年齢、性別等に関係なく、お茶やコーヒーを飲みながら自由な形式で行うのが特徴です。スイスの社会学者がパートナーノの死をきっかけに始め、その後イギリスの社会起業家によって世界中に広まりました。
気仙沼で行ったデスカフェでは、身近な人を若くして亡くしたときの辛い気持ちから、宗教的な価値観を大切にしながら前向きな気持ちで亡くなっていったという家族の話まで、死を起点にさまざまな話題が自由に共有されました。時には、「自分のお葬式は絶対外でやってほしい」「パーティーみたいにして遺体の周りで参列者に踊り回ってほしい」といったように、普段であれば“縁起でもない”会話が、笑いながら楽しく交わされる場面も。
地域によって死者の弔い方・悼み方にさまざまな方法や習慣があることも話題になりました。例えばモンゴルやチベットには、鳥や野生動物に遺体を食べてもらう鳥葬や曝葬と呼ばれる文化があります。日本でも、気仙沼では数年間に一度、それまでに亡くなった同級生を共に供養する「物故祭(ぶっこさい)」という地域行事が行われていたり、沖縄にはお墓でお花見のように楽しく宴会をする「シーミー」という風習があったりと、死に対する考え方や価値観が、地域や文化によって多様であることがわかりました。
そうした対話を1時間半ほど続け、会はお開きに。話した人々はほとんど初対面だったにもかかわらず、死をテーマにしたことで、普段は語らないような人生に対する価値観が語られただけではなく、悲しいイメージが先行しがちな「死」について、一歩引いた視点で、俯瞰的に考えてみることができたのです。
何より死について語ることは私たちに、「自分の人生がいつか終わるのだ」ということを強く実感させます。そしてそれは、「自分はどう生きていきたいのか」という「生」に対する眼差しにつながっていくのです。また、この大きな視点が、その場にお互いの存在を深く受容するような心地よい雰囲気を生み出してくれていたように感じます。
こうした現象は、多くのデスカフェで起こっているそうです。2021年に出版された、デスカフェ開催の方法やさまざま実例をまとめた『デスカフェ・ガイド〜「場」と「人」と「可能性」〜』という書籍には、こんな言葉があります。
私たちは生きています。つまり、私たちはいずれ必ず死ぬということです。それは明日かもしれないし、50年後かもしれません。(略) でも、誰にとっても当事者となる死について対話する事は、私たちがいずれ必ず死ぬ存在だということを思い起こし、『生』について、生きていることについて、より深く考えるきっかけになるはずです。
本書では、デスカフェがきっかけで地域に新たな交流が生まれたという事例も数多く紹介されていました。お互いを気にかけ合う気持ちを醸成するこうした場は、多死社会と呼ばれる今後の日本社会で必要とされている、「医療機関で完結しない地域でのケア」の可能性も開いていくのではないでしょうか。
死について気軽に話してみたり、誰かの考えを聞いてみたりすること──それが生きている今をより充実させ、お互いを優しく受け止め合える地域やコミュニティを生み出していくのかもしれません。
【参考書籍】デスカフェ・ガイド〜「場」と「人」と「可能性」〜 執筆代表・企画 吉川直人/執筆・編集 萩原真由美
【関連記事】音楽にカラフルな装飾。最期を祝う“ポジティブな葬儀”がイギリスでトレンドに
【関連記事】多死社会における幸福論。富山県上市町と矢野和男さんから学ぶ、「終わり」から考える幸せ【前編】
アルゴリズムによる社会の分断をどう乗り越えるか。欧州で進むX離れとそのオルタナティブ
Written by Erika Tomiyama

「X(旧Twitter)をやめる」──フランス・パリ市は先週末、約220万人のフォロワーがいるXのアカウントを、1月20日付で削除すると発表しました。これは単なるSNS戦略の見直しではなく、欧州全体で広がる「X離れ」の象徴的な動きといえます。
こうした背景には、Xのアルゴリズム変更がもたらした深刻な影響があります。イーロン・マスク氏による買収後、X上ではヘイトスピーチや偽情報の拡散が加速し、対立を助長する「エコーチェンバー」(同じ意見の人ばかりが集まり、異なる意見を排除する空間)が形成されやすくなってしまったのです。さらに、Xのアルゴリズムには透明性がなく、特定の思想や立場が優遇されている懸念も根強くあります。これにより、公共の議論が偏った情報によって歪められるリスクが高まっているのです。
実は、パリ市のアンヌ・イダルゴ市長は2023年の時点ですでに自身のXアカウントを削除し、「Xは巨大な地球下水道」と痛烈に批判していました。そして今回、市の公式アカウントの削除という形でこのスタンスを明確にしたのです。
この動きは、フランスを中心に広がるXからの離脱運動「#HelloQuitteX」にも付随しています。そして、これを支えているのが、仏国立科学研究センター(CNRS)の研究者であり、『Toxic Data』の著者でもあるDavid Chavalarias氏らが開発したサイト「HelloQuitteX」です。
このサイトは、「民主主義の非常口」をつくることを目的としており、Xを離れたいユーザーがスムーズにBlueskyやMastodonといった代替SNSに移行できるよう設計されており、フォロー・フォロワーリストもそのまま移行できるようになっています。現在、同サイトのアクセス数は1,000万件を超え、Xの影響力に対する根本的な疑問を投げかける運動として注目されています。
偽情報の拡散がもたらす影響は政治や社会にとどまらず、気候危機にも深刻な影響を及ぼしています。現在も続くロサンゼルスの山火事を例にとると、災害そのものの脅威だけではなく、SNS上で流れる大量の偽情報が問題となっています。科学者らの調査によると、気候変動による乾燥化が火災を助長していると指摘されていますが、X上では「放火犯の仕業だ」という意見やAIが生成した偽の火災画像が急速に拡散されました。結果として、本来焦点を当てるべき「気候変動による森林火災の増加」や「適切な火災対策」の議論がかき消されてしまっていることも事実です。
Xの離脱はフランス国内にとどまらず、欧州各国でも同様の動きを加速させています。スペインの有力紙「バングアルディア」はXでの投稿を停止し、英国では「ガーディアン」が同様の決定を下しました。
冒頭で紹介したパリ市のX離脱は、単なる一自治体の決定ではありません。これは、デジタル空間の信頼性をめぐる社会全体の課題を浮き彫りにする動きであり、今後のSNSの在り方に対する重要な問いかけでもあります。情報の真偽を見極める力がますます問われる時代、私たちは何を信じ、どのプラットフォームに身を置くのか──その選択が、これからの情報社会のあり方を決めるといっても、過言ではないかもしれません。
【関連記事】「学校でのスマホ禁止」広がる。子どもとデジタルの程よい距離感を探る
【関連記事】“デジタル格差”の解消へ。ネット上での人種差別に立ち向かう、アメリカの情報サイト
ニュースレターの無料登録はこちらから
IDEAS FOR GOODでは週に2回(毎週月曜日と木曜日の朝8:00)、ニュースレターを無料で配信。ニュースレター読者限定の情報もお届けしています。
- RECOMMENDED ARTICLE: 週の人気記事一覧
- EVENT INFO: 最新のセミナー・イベント情報
- VOICE FROM EDITOR ROOM: 編集部による限定コラム
編集部による限定コラムの全編をご覧になりたい方はぜひニュースレターにご登録ください。