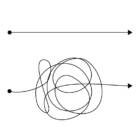気候変動。海洋汚染。エネルギー問題。いま、世界には解決されるのを待っている社会課題が山のようにある。一方で、世界にはそれらの課題を解決し、新しい未来を形づくる可能性を秘めつつも、いまだ実用化されることなく誰かがユースケースを見つけてくれるのを待っているテクノロジーもたくさんある。
これら二つをデザインの力でつなぎ、最先端のテクノロジーを社会に実装可能なイノベーションへと転換することを目的として活動しているプロジェクトが、東京大学・駒場リサーチキャンパスの片隅にある。それが、英国ロンドンにある芸術大学、RCA(ロイヤル・カレッジ・オブ・アート)と東京大学生産技術研究所(IIS)が協同で2016年12月に立ち上げたデザインラボ、「RCA-IIS Tokyo Design Lab」だ。

RCA-IIS Tokyo Design Lab。東京大学生産技術研究所(IIS)内にある。
同ラボは、RCAが持つ世界最高峰のデザインエンジニアリングノウハウと、国内最大規模の大学附置研究所として約110の研究室を抱えるIISの最先端テクノロジーを掛け合わせることで、未来の社会を形づくるイノベーションの創出を目指すとともに、デザイナー、エンジニア、研究者らによる開かれたコミュニティづくりや将来を担うクリエイティブ人材の育成を目的としている。
ここ最近では、「VUCA(Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguity)」の時代とも表現されるように変化が速く先行き不透明な時代となりつつあることを背景に、ビジネスの現場でも「デザイン思考」という言葉を頻繁に聞くようになった。「デザイン思考」という言葉の安易な独り歩きに対しては批判的な意見も聞かれるが、少なくとも「デザイン」の力に対する社会からの期待が高まっていることは間違いない。
しかし、社会の課題を解決し、理想の未来を作り上げるために、デザインはどのような役割を果たすことができるのか。デザイナー、あるいはノンデザイナーとして、デザインの力をどのように活用することができるのだろうか。デザインはテクノロジーとどのように関わっていけばよいのだろうか。それらについて明確な答えを持っている人はあまり多くはないはずだ。
そこで、今回IDEAS FOR GOODではRCA-IIS Tokyo Design Labを主導するお二人、マイルス・ペニントン教授と森下有助教に、現在のデザインラボの取り組み、そしてデザインが持つ力とその役割についてお話をお伺いしてきた。
話者プロフィール:ペニントン リチャード マッキントッシュ マイルス 教授
 1992年Royal College of Art(RCA)イノベーション・デザイン・エンジニアリング(IDE)学科を修了。翌年からセキスイデザインセンター(大阪)勤務。1997年英国に戻り、デザイン会社「Design Stream」設立。2009年、RCAの IDEプログラム学部長に就任し、2013年からは新設のGID(Global Innovation Design)プログラム学部長も兼任。2017年、東京大学生産技術研究所の教授に就任。
1992年Royal College of Art(RCA)イノベーション・デザイン・エンジニアリング(IDE)学科を修了。翌年からセキスイデザインセンター(大阪)勤務。1997年英国に戻り、デザイン会社「Design Stream」設立。2009年、RCAの IDEプログラム学部長に就任し、2013年からは新設のGID(Global Innovation Design)プログラム学部長も兼任。2017年、東京大学生産技術研究所の教授に就任。
話者プロフィール:森下 有 助教
 東京大学生産技術研究所助教。東京大学学際情報学府にて博士、ハーバード大学院にて建築理論・歴史の修士、ロードアイランド・スクール・オブ・デザインにて建築と芸術の学士を習得。サステイナブルな地球環境のための建築情報と環境技術を研究、開発中。RCA-IIS Tokyo Design LabではTreasure Hunterを務める。
東京大学生産技術研究所助教。東京大学学際情報学府にて博士、ハーバード大学院にて建築理論・歴史の修士、ロードアイランド・スクール・オブ・デザインにて建築と芸術の学士を習得。サステイナブルな地球環境のための建築情報と環境技術を研究、開発中。RCA-IIS Tokyo Design LabではTreasure Hunterを務める。
RCA-IIS Tokyo Design Labがはじまったきっかけ
そもそも、英国が世界に誇る芸術大学であるRCA(ロイヤル・カレッジ・オブ・アート)と、東京大学とのユニークなコラボレーションはどのように始まったのだろうか?
ペニントン氏:RCAはアート・デザインの大学としてとても成功していますが、その規模は比較的小さく、将来に向けた戦略的な転換を進めるなかで、どのような分野を強化すべきかを模索していました。RCAは特にデザインという観点では絵画から産業デザインにいたるまであらゆる分野を網羅できていますが、いわゆる「STEM(Science・Technology・Engineering・Math)」の分野とは十分なつながりがありませんでした。そのため、RCAとしては戦略的にそれらの分野とデザインをつなぎ、研究活動もさらに充実させるために、よりオープンな関係で異なるパートナーとコラボレーションしながら世界中でラボを創りたいという計画があったのです。
その計画が日本で実現するきっかけとなったのは、RCAの客員教授を務めるTakramの田川欣哉氏です。彼はもともと東京大学の卒業生で、かつてインダストリアルデザイナー時代に現在の東京大学生産技術研究所(IIS)の山中俊治教授のもとで働いたこともありました。山中教授はIISで藤井輝夫教授(当時IIS所長、現在東京大学執行役・副学長)とともに、「Desing-Led X」というデザイン思考を教育や研究活動に取り入れるイニシアティブを主導していました。
政府のクールジャパン委員会に属していた田川氏は、日本のクリエイティブ産業を盛り上げる方法を探していたのですが、RCAの意向を知った彼は、山中氏とのつながりもあったことからRCAとIISと共同で東京にインターナショナルなデザインラボを立ち上げることで、面白いイノベーションを起こせるのではないかと考えたのです。
田川氏がRCAと東京大学という全く異なる2つの機関をつなぐ触媒の役割を果たしてくれ、はじめて両者が会合をしたときは、まるで恋に落ちたような感覚でした(笑)。お互いがお互いの求めるものを持っていたのです。その場で「ぜひそのデザインラボをやろう」という話になり、「ここのスペースを使っていいよ」となり、ちょうど余っている国の予算があるという電話までかかってきて、その日のうちにデザインラボが立ち上がったのです。まさにデザインプロジェクトでよくあるような感じでしたね(笑)。
東大の研究室を「トレジャーハンティング」する
その4ヶ月後、デザインラボには、森下助教も含む4人のメンバーがいたという。がらんとしたラボに座り込んだ彼らがまずはじめに取り組んだことは、IISにある110近い研究室をすべてマッピングすることだったそうだ。
森下氏:約110ある研究室には、より応用に近いものからまだ基礎研究の段階で商業化の目途はたっていないものまで様々にあります。私たちはその中からいくつかの研究をピックアップし、「3ヶ月間で何らかのプロトタイプを創りだしてこのラボが実際に機能することを示そう」と話しました。

森下氏は、自らの仕事を「トレジャーハンター」と話す。「トレジャー」とは、東大の研究室に眠っている、いまだ基礎研究の段階にあるものの将来は大きく社会の役に立つ可能性を秘めたテクノロジーたちのことだ。
宝の山の中からダイヤの原石となるテクノロジーを探し出し、RCAが持つデザインエンジニアリングのノウハウを活用しながらその原石を磨き上げ、社会へと送り出す。それがRCA-IIS Tokyo Design Labのミッションなのだ。
デザインとテクノロジーの交差点に生まれる革新的なアイデアたち
実際にRCA-IIS Tokyo Design Labが手がけたプロジェクトをいくつか紹介したい。最先端のテクノロジーをデザインの力でプロトタイプ化することで、私たちに未来の社会のありかたを考えさせる、スペキュラティブなアウトプットが生まれている。
「BIoT」バイオ×IoT×AIで、自然と人間との関わりを可視化する
環境省が推進する、地球温暖化防止に向けて環境に優しく賢い選択を呼びかける取り組み「COOL CHOICE」のためのアイデアとして生み出されたのが、「BIoT – Associated Nature / よりそう自然」だ。BIoTは「バイオ」と「IoT」を掛け合わせた造語で、このプロジェクトの目的は「自然」という曖昧な対象について、またその自然に人間がもたらしている影響に対して私たちがより意識的になり、結果として行動変容を起こすことにある。
BIoTプロジェクトでは、「ファンガルネットワーク」と呼ばれる、多くのキノコ類が植物同士をつなぐ地中のネットワーク、いわば自然界に存在するインターネットに「BIoT」デバイスを接続し、自分が住む近隣エリアの「自然の健康状態」を可視化するという仕組みが構想された。BIoTデバイスを通じて近隣の樹木のCO2吸収量や水分・栄養の状況、天候によるストレスなどをデータとして収集し、AIにより可視化、デバイス画面上から常時モニタリングできる仕組みとなっている。また、このデバイスに冷蔵庫や暖房器具といった自宅のIoTデバイスを接続し、自身の生活から生まれるCO2排出量と周囲の自然のCO2吸収量を比較することもできる。このBIoTによって自分が自然にどれだけの影響を与えているのかが可視化されるため、省エネなどの具体的な行動をとるきっかけになるだけではなく、その結果もしっかりと分かるのだ。

緑がBIoTにつながれた植物のCO2吸収量、赤がIoTにつながれたCO2排出量を表す。
その滑らかな流線型のフォルムとは裏腹に、キノコをモチーフとして3Dプリントで形作られたBIoTデバイスの内部には自然科学の知見と最先端のIoT、AIテクノロジーが詰め込まれている。
「JINZO SKIN」人がロボットを着るのか、ロボットが人を着るのか?
2018年2月から4月にかけて行われた、RCA-IIS Tokyo Design LabのメンバーとIISの研究者らがチームとなって短期集中で取り組むマイクロラボの3回目のテーマ、「Re: Thinking the robot(ロボットを再考する)」から生まれたのが、非常にユニークなロボットの肌、「JINZO SKIN」だ。
コンセプトは、「表現するスキン」。プロジェクトでは、スキンを単にロボットの表面にかぶせる肌として捉えるのではなく、人間の肌と同様にその人の感情や状態を表すリアルな肌として捉え、そのありかたを模索した。将来、人とロボットが共存する時代が訪れたとき、両者が自然にコミュニケーションをとるうえでは、ロボットにも言葉では伝えられない微妙な感情を伝える何かが必要なのではないか、という問いかけが出発点だ。
実際のプロトタイプとして作られたのは「GAOH(ガオー)」「ZUKI(ズキ)」「ISHIKI(イシキ)」という3つの肌の動き。例えば、怒りを表す「GAOH」では、ロボットが操作間違えなど「不当な扱い」を受けたと感じたときに肌の表面のとげを逆立て、威嚇する動きを見せる。肌を通じて反射的な怒りを人に伝えるのだ。

このプロトタイプのデザインを手がけたのは、RCAファッションの出身のAbbie Stirrup氏。ファッションデザイナーとしての斬新なアイデアとテクノロジーが融合され、未来のロボットと人との関り方について新たな視座を与えてくれる。
最近では「ウェアラブルデバイス」と言われるように人が機械を装着することは珍しくなくなった。ウェアラブルから一歩進み、スウェーデンなどではマイクロチップのインプラントも進んでいる。人がロボットを着るのか、ロボットが人を着るのか。ロボットが感情を持ち、表現できるようになったとき、人とロボットの線はどこで引くべきなのか。そもそもその線は必要なのか。
このプロトタイプを眺めていると、テクノロジーが作り出す未来をただ待っているだけではなく、どのような未来が欲しいのかを自分自身で考えながらテクノロジーと付き合うことの大事さを痛感させられる。
「誤解」も、クリエイティビティの源泉になる。
上記のように革新的なプロジェクトを複数展開しているRCA-IIS Tokyo Design Labだが、そのクリエイティビティの源泉となっているのが、プロジェクトメンバーの多様性だ。RCAからやってきたデザインのプロフェッショナルに加え、エンジニアや研究者にいたるまでメンバーの職域は様々で、一言で研究者といってもその研究領域は多岐にわたる。もちろん、一人一人の国籍の違いもある。
一般的に「多様性はクリエイティビティの源泉」とはよく言われるが、実際には異なるバックグラウンドを持つ者同士がプロジェクトに取り組むうえでは、共通言語がなく相互理解が難しいなどのハードルもある。この点について、RCA-IIS Tokyo Design Labはどのように考えているのだろうか?
森下氏:私たちは、プロジェクトを行うとき、よく文字を書くのではなく絵を描いて伝えるように促しています。ビジュアル・ランゲージですね。これはデザイナーが得意とすることではありますが、エンジニアや教授陣に対しても同じく絵で描くように伝えています。日本語でも英語でも技術用語でもなく、ビジュアルでコミュニケーションすることができるようにすることが大事です。
ペニントン氏:私は、共通言語を持たないということには2つのメリットがあると考えています。一つは、共通言語がないことで生まれる「誤解」は、クリエイティビティをもたらすからです。例えば、誰かが描いた絵を異なる人が異なった見方で理解すれば、そのぶん多くのアイデアが生まれます。これはポジティブな側面ですね。
一方、共通言語がないことは時としてタフな状況を生み出します。その状態でチームワークを維持するのは難しいのですが、” the grit in your oyster leads to a pearl(貝の中の砂粒が、真珠になる)”という言葉もあります。ここでのGritは「困難さ」です。もしチームがお互いによい関係のままあまりに長い時間を過ごしてしまうと、そこから真珠を得ることはできません。Gritはチームワークの難しさであり、それは不快なものでもありますが、そうした状況を乗り越えるタフさが真の意味でクリエイティブなプロセスを促進するのです。
そもそもデザインはその性質上、いつも異なる答えを探し続けるものです。もしあなたがエンジニアリングのチームにいれば、おそらく正しい答えは一つであることに皆が同意してくれるはずです。もちろん、技術的な側面でいえばそれは時にとても重要なのですが、ことデザインにおいては、異なる答えを持っていること自体が正しい答えでもあるのです。

RCA-IIS Tokyo Design Labには多様な国籍・バッググラウンドのメンバーが集まる。
RCA-IIS Tokyo Design Labが考える、「デザイン」の力とは?
ペニントン氏が語るように、デザインは一つの決まった答えを探し出すものではない。そしてそれこそが、もはや正解が一つではなくなった現代にデザインの力がビジネスの現場で求められている理由でもある。
一方で、この「デザイン」という言葉が持つ曖昧さが、ノンデザイナーにとってデザインに対する理解を深めるうえでの壁ともなっている。一般的に「デザイン=問題解決」と語られることも多いが、最近では問題解決としてではなく問題提起としてのデザインである「スペキュラティブデザイン」という概念も注目を集めており、より頭の整理が難しくなっている方も多いかもしれない。
これらの異なる「デザイン」に対し、“Using Design to Turn Technology into Deployable Innovation(テクノロジーを実装可能なイノベーションに転換するためにデザインを活用する)”というミッションステートメントの中で明確にその役割を定義しているRCA-IIS Tokyo Design Labは、デザインという言葉やデザインが持つ力、その役割についてどのように考えているのだろうか?
RCA-IIS Tokyo Design Labにとっての「デザイン」とは?
ペニントン氏:「デザイン」という言葉は多くのことを意味します。この20年でデザイン自体が進化し、成熟してきました。あらゆる種類の異なるニッチな分野があり、アプローチがあります。我々がここで取り組んでいるもののうち、いくつかとてもスペキュラティブですし、いくつかはとても問題解決にフォーカスしています。
私は、デザインは「イノベーション」という意味を強く持つものだと思います。イノベーションは使い古されている言葉ではありますが、アイデアを現実世界の中で形にし、実装し、実際に商業化まで持っていくという意味です。

マイルス・ペニントン教授
「デザイン」が果たす役割とは?
森下氏:私が8年前にアメリカのデザインスクールを卒業して東大に戻ってきたとき、大学の中では「デザイン」という言葉が人々の心の中にあまり浸透していませんでした。もちろん、建築デザインやヒューマン・インタラクション・デザインといった言葉はありましたが。その意味で、私たちの機関において「デザイン」という言葉が持つ役割は、それがスペキュラティブなものであれ、実際にプロダクトやイノベーションにつながるものであれ、様々な異なる関心をひきつけ、様々な異なる人々を呼び込み、以前とは異なる新たな扉を開いたという点にあるのではないかと思います。
ペニントン氏:とてもよいポイントですね。私も、デザインプロセスが持つ利点は、一つの仕事を完成させるために異なる能力やスキルを引き寄せる力にあるのではないかと考えています。デザイナーは人々をつなぐことが得意な人だと思います。異なるタイプの人々をつなぎ、チームを結びつけるのに長けた人ですね。イノベーションをファシリテートするといった感じです。これは絵を描くといった伝統的なデザインスキルとは異なります。デザイナーは人をつなぎ、物事を形にするのが得意なのです。

森下氏:かつてデザインは問題解決の手法として認識されていましたが、実際には物事はもっと複雑で、問題と問題が互いに結びついていることもあります。そのため、まずは問題を解決する前に何が問題なのかをしっかりと定義し、ときには再定義することが大事になってきます。以前であれば、もし私が「この問題を創造的に解決してくれ」と言われていたら、「わかりました。全力を尽くします」と答えていたでしょう。しかし、今では、「わかりました。それでは適切な人を連れてきて、適切な手法で問題を再定義してみましょう。もしかするとそれは問題ではないかもしれませんが、もし問題だとしたら、解決しましょう」と答えます。こうしたアプローチはまだ一般的ではないかもしれませんが、私たちが取り組むべきことだと思います。
ペニントン氏:まさにそうですね。つまり、デザインが成熟しているということだと思います。かつては単なる問題解決のサービスプロバイダーだったデザインが、より戦略的な領域となっているのです。
「デザイン」に限界はあるのか?
異なる者同士をつなぎ、イノベーションを生み出す触媒としてのデザイン。デザインのRCAとテクノロジーのIISという全く異質の機関をつなぐRCA-IIS Tokyo Design Lab自体がその象徴でもある。一方で、デザインは本当にイノベーションの創出において万能なのだろうか?デザインの限界についても聞いてみた。
「デザイン」という言葉の失敗
ペニントン氏:デザインの限界は、「デザイン」という言葉そのものにあると思っています。デザインという言葉は「私はこのペンの形をデザインしたい」というときも使えます。もちろん、美しい形を作り出すことも重要ですし、素晴らしいことです。しかし、「私はデザイナーで、美しいものを作ります。」「私はデザイナーで、世界について再考しています。」「私はデザイナーで、世界中の人々の生活を変えています。」これらすべてがデザイナーと言えてしまい、実際に誰もがデザインをしているわけですね。
どうして一つの言葉がここまで幅広い意味を持ってしまったのでしょうか?この「デザイン」という言葉自体が「限界」であり、私たちはこの言葉ゆえに、デザインができることについて人々が理解できないという事態に毎日のように直面しているわけです。誰の失敗なのでしょうか?おそらくデザイン自体の失敗なのだと思います。私たちがしていることについて、もっとうまく説明する必要があったわけです。
森下氏:ケイパビリティの問題もありますね。デザインが扱う範囲は広く、ひとたびその扉を開ければ、たくさんの異なる言葉を学ぶ必要があります。例えば法律家と仕事をする場合は彼らの言葉に、金融の専門家と働くときは彼らのデザインに対する考え方やロジックを理解し、慣れる必要があります。デザイナーは法律のプロフェッショナルにも金融のプロフェッショナルにもなれませんが、彼らと協働し、ゴールに向かって何かをデザインするためには、彼らについて深く理解する必要があるのです。
そこがデザイナーの難しい部分です。特に学術の世界では「専門分野が広すぎると、プロフェッショナルにはなれない」と言われます。デザイナーはより広大なスキームにおけるプロフェッショナルなのですが、その役割は現状では学術的にも世界的にも定義されていません。その意味で、デザイナーは自分の限界を自分で決めることができ、それこそが限界だとも言えますね。
「デザイン」が必要ない仕事もある
ペニントン氏:また、最近では「デザイン思考」に対する関心が高まっていますが、このこと自体はとても素晴らしいことであり、私もその一翼を担ってきました。多くの人が関わってくれるのは嬉しいことです。一方で、世の中にはデザインのプロセスが必要ない仕事もたくさんあるということを忘れてはいけません。これもデザインの限界です。実際に、ただ物事を適切に行うだけのほうがよい仕事もあるのです。デザインはとても混沌としたプロセスで、たくさんの失敗をもたらします。そして、それこそがよいアイデアにたどりつく方法でもあるのです。もし外科医が私を手術するとすれば、私は彼にデザイナーになってほしくはありません。彼には外科医でいてほしいのです(笑)。
デザイナーに求められる資質とは?
ペニントン氏の「全員がデザイナーになる必要はない」という指摘は、デザイン思考という言葉が溢れる昨今、ついつい私たちが忘れてしまいがちな盲点だ。森下氏も、「デザイン思考を学ぶ」ということと「デザイナーになる」ということは全く別だと強調していた。
その線引きをしたうえで、デザイナーとして活躍する上では一体どのようなスキルやマインドセットが求められるのだろうか?
森下氏:それはデザイナーの最も素晴らしい点の一つでもあります。彼らはみな異なり、私はそれこそが最も重要なことだと考えています。どのようなマインドセットが求められるにせよ、デザイナーはそれぞれが異なるべきです。
ペニントン氏:まさに、多様性こそが重要です。一方で、そうですね。私はいつも「好奇心」が共通して大事なことだと考えています。誰もが異なっていてよいのですが、彼らは全員が好奇心旺盛であるべきですね。

いよいよ始まる最高峰のデザインスクール「DESIGN ACADEMY」
RCA x IIS Tokyo Design Labは、2018年からデザインラボの持つ知見を広く世の中に還元し、未来を形作る人材を育成するための新しいデザイン・イノベーション教育プログラム、「DESIGN ACADEMY」を開講する。
このプログラムはデザイナーだけではなく、企業の新規事業開発担当者や商品・サービス開発担当者、行政・自治体関係者、大学生など誰もに対して開かれたプログラムとなっている。
世界最高峰のデザイン・アートに関する大学院大学であるRCAの最先端デザイン手法と、国内外から1,000人以上の研究者らが集まり基礎から応用まで工学のほぼすべてをカバーする分野の最先端研究を行っているIISの知見をベースとして、グローバルな視点からイノベーションやデザインを取り巻く動向や方法論について学べる貴重なプログラムだ。
このプログラムには、どのような想いが込められているのだろうか?最後にペニントン氏に尋ねてみた。
ペニントン氏:私たちがデザインラボを始めたときのミッションは、素晴らしいプロジェクトを閉ざされた環境の中で行うのではなく、よりオープンに展開するというものでした。世の中に対して何が起こっているのかを伝え、変化を生み出す触媒となるよう人々に働きかけたかったのです。
大学の中であればそれは比較的簡単なことで、学生を巻き込むこともできます。しかし、大学の中は守られていて、誰もが入ることはできません。私たちは大学のキャンパスの中に閉じこもるのではなく、外の世界に飛び出して、街中に出て、普段大学では関わることができない人々にもリーチしたいと考えたのです。それがDESIGN ACADEMYのアイデアです。
また、大学のモデルは2年ないし4年というのが伝統的ですが、DESIGN ACADEMYはそれらの伝統的なモデルを超えて、異なる方法で人々に働きかけ、大学の中で起こっているエキサイティングなことを伝えようと試みています。一年目となる現在は試験的にワークショップを提供していますが、来年以降は、仕事や子育てをしながらでも参加できるような5~10セッションほどのショートプログラムを提供する予定です。
そして、最終的には街のなかに校舎を用意し、フルタイムの生徒とパートタイムの生徒を受け入れるのが目標です。複数の層にまたがった教育システムを用意し、異なるエントリー手段を持つことで、異なるタイプの人々を集めるためです。異なる様々な国々から生徒を受け入れます。
また、いまではグローバルな教育マーケットが盛り上がっていますが、誰もが北米やヨーロッパに行ける余裕があるわけではありません。私たちはよりアクセスしやすいモデルを必要としています。まずは小さく初めて、数年以内には実際の校舎を持ちたいですね。

左:ペニントン・マイルズ 教授、右:森下有 助教
インタビュー後記
ペニントン氏、森下氏のお二人の話から浮かび上がるのは、「つなぐ」というキーワードだ。RCA-IIS Tokyo Design Lab自体が、デザインに長けた英国ロンドンのRCAと、テクノロジーに長けた東大のIISをつなぐことでイノベーションの創出を目指している組織だが、実際にそこで行われているプロジェクトを見てみると、バイオとIoT、テクノロジーとファッションデザインなど、異なる二つの分野をつなぎ合わせることで生まれているユニークなアウトプットが多い。
ペニントン氏も「デザイナーの役割とは異なる者同士をつなぎ合わせること」だと言っていた。そこで生まれる誤解や衝突、失敗などがクリエイティブなデザインプロセスには必要不可欠ということだ。
新しい価値を生み出す必要があるとき。創造的なアイデアが必要なときは、異なる二つのものをつないでみる。そしてそこから生まれる正のエネルギーも負のエネルギーも大切にし、アウトプットに集約させる。チーム内で生まれる誤解すらも、クリエイティビティにとっては大事な栄養なのだ。
お二人の話からは、デザイナーであるかないかに関わらず、誰もが少しでも創造性を高めるために意識できるヒントをたくさん得られたのではないだろうか。RCA-IIS Tokyo Design Labに興味を持った方は、ぜひDESIGN ACADEMYの扉を叩いてみてほしい。次は、あなたが新たなイノベーションの触媒になる番だ。
【参照サイト】RCA-IIS Tokyo Design Lab
【参照サイト】DESIGN ACADEMY
(Photo: Nagisa Mizuno)