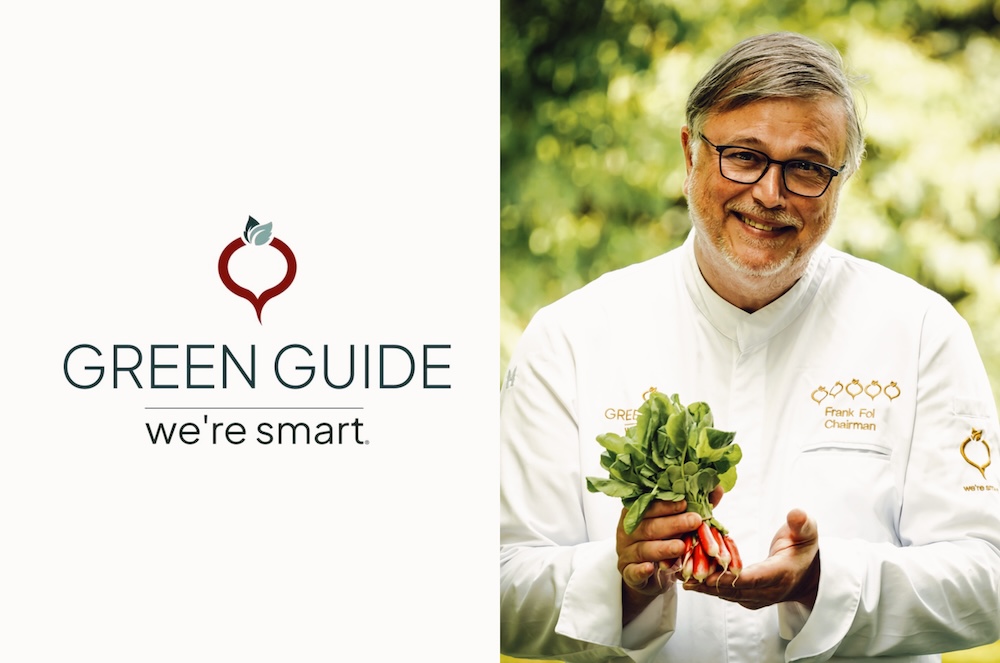Social Food Gastronomy(ソーシャルフード・ガストロノミー)を提唱し、活動を広げる杉浦仁志シェフが、食の分野におけるサステナブルな未来を目指すキーパーソンを紹介し、これからの食の在り方を社会に伝えていく連載「持続可能なガストロノミー」。第9回となる今回とりあげるのは、東京都・南麻布の中国料理店「茶禅華(さぜんか)」の川田智也(かわだ ともや)シェフだ。

茶禅華
「和魂漢才」をコンセプトに掲げ、中国料理に日本料理のエッセンスを調和させた独自の世界観を追求する茶禅華。大枠は中国料理ながら日本の水や食材の良さを最大限に活かしたそのユニークな料理の数々は、訪れる人々を魅了してやまない。店は予約が取れないことで知られ、日本の中華料理店で唯一ミシュランガイド三つ星を獲得するなど、国際的にも高く評価されている。
そんな茶禅華を生み出した川田シェフの話には、素材や自然、そして調和といった言葉が度々出てくる。人間の身体が喜ぶのは素材の“声”が聞こえる料理であり、その素材を育むのは天や地、すなわち自然。そして、料理とはそうした自然と自分の技術との調和である──中国と日本、2つの文化や宗教観に裏打ちされた川田シェフの言葉は、シンプルながら深く揺るぎなく、それでいて不思議と心地よい。
今回は、川田シェフの料理へのこだわりやベースとなる精神性から、サステナビリティの本質を探っていきたい。
話者プロフィール:川田智也(かわだ・ともや)シェフ
 1982年、栃木県生まれ。 調理師専門学校卒業後、中国料理店【麻布長江】に入店し10年間修業する。その後日本料理を学ぶため、2011年に【龍吟】へ。5年間の修業中、台湾の【祥雲龍吟】の立ち上げにも参画し副料理長を務める。帰国後、準備期間を経て2017年2月【茶禅華】をオープン。
1982年、栃木県生まれ。 調理師専門学校卒業後、中国料理店【麻布長江】に入店し10年間修業する。その後日本料理を学ぶため、2011年に【龍吟】へ。5年間の修業中、台湾の【祥雲龍吟】の立ち上げにも参画し副料理長を務める。帰国後、準備期間を経て2017年2月【茶禅華】をオープン。
聞き手プロフィール:杉浦仁志(すぎうら・ひとし)シェフ
 2009年に渡米し、料理業界のアカデミー賞とされる「ジェームス・ビアード」受賞シェフであるジョアキム・スプリチャル氏のもと、 LA・NYCのミシュラン星つきレストランで感性を磨き技術を習得。海外で培った国際的な食経験を通じ、日本におけるヴィーガン・プラントベースの第一人者として貢献し多数の受賞歴を持つ。“Social Food Gastronomy”を提唱し、より多角的な視野から社会貢献とイノベーションを展開し2050年に向けた次世代のシェフモデルとして国内外で活躍。日本サステイナブル・レストラン協会プロジェクト・アドバイザー・シェフに就任。
2009年に渡米し、料理業界のアカデミー賞とされる「ジェームス・ビアード」受賞シェフであるジョアキム・スプリチャル氏のもと、 LA・NYCのミシュラン星つきレストランで感性を磨き技術を習得。海外で培った国際的な食経験を通じ、日本におけるヴィーガン・プラントベースの第一人者として貢献し多数の受賞歴を持つ。“Social Food Gastronomy”を提唱し、より多角的な視野から社会貢献とイノベーションを展開し2050年に向けた次世代のシェフモデルとして国内外で活躍。日本サステイナブル・レストラン協会プロジェクト・アドバイザー・シェフに就任。
コンセプトは「和魂漢才」。日本ならではの中国料理店、茶禅華ができるまで
幼い頃から中国料理に魅了され、その世界を追求し続けてきたという川田シェフ。修行の途中で日本の素材やその素材を活かしきる日本料理の素晴らしさに気づき、日本料理店「龍吟(りゅうぎん)」で5年間学んだ。そこで目の当たりにした日本料理ならではの調理法の精密さや緻密さは、今の川田シェフの料理人としての礎になっているという。
「もともとは中国に憧れて中国料理の勉強に没頭していたのですが、10年近く修行したころ中国の方に言われたんです。『日本にはあんなに素晴らしい料理や文化があるのに、どうして君はそれを知らないんだい?』と。そこから、日本料理の勉強を始めることにしました」

川田シェフ
「龍吟で見せていただいた鱧(はも)の骨裁きの技術は、日本料理の特徴を非常によく表していると思います。朝、泳いでいる鱧を神経締め(しんけいじめ)し、死後硬直を迎える手前のふわっとした状態の魚を骨ぎりしていく。日本料理で大事なのは、『全てに時がある』という精神、そして、その『時を捉える』技術。そうした緻密さや精密さに、日本料理の素晴らしさを見たのです」
こうした伝統を当てはめていくことによって、日本の中国料理はさらにアップデートできるのではないか。そうした考えのもと、「和魂漢才」を掲げる現在の茶禅華を2017年にオープンした。

茶禅華店内 Image via 茶禅華
和魂漢才とは、日本固有の精神を保ちながら中国伝来の学問の才も備えることを意味する、日本の思想史上で生まれた言葉のひとつ。茶禅華の料理は、まさにその言葉を体現している。
例えば、店の顔でもある「仔鳩胸肉台湾香辛料〈馬告〉焼き、腿肉五香脆皮仕立て」は、台湾の香辛料をまぶした鳩のムネ肉を、日本料理の修行で体得した炭火焼きで仕上げる。また、「清淡干鮑(チンダンカンパオ)」は、中国でも最高峰とされる岩手県大船渡市吉浜産の干しアワビを、中国料理の技術で煮たシンプルな一品だ。

仔鳩胸肉台湾香辛料〈馬告〉焼き、腿肉五香脆皮仕立て

清淡干鮑 Image via 茶禅華
目指すのは日本語のような世界。2つの文化を「調和」させる料理
こうした料理を作り上げるときに川田シェフが意識しているのは、2つの異なる文化を尊重しながら調和させることだという。
「異なる2つの何かを掛け合わせるとき、融合という表現がよく使われると思います。しかし、自分が追求したいのは『調和』です。『融合』と『調和』は明らかに違うものだと考えています。
円の中に白と黒の勾玉が2つ入っている、中国の「陰陽太極図」を思い浮かべてみてください。『融合』は、その円の中の白と黒を思いきり混ぜて灰色の玉を作るようなイメージ。一方で『調和』は、中国料理と日本料理、それぞれがその良さがしっかりと保たれながら、ひとつの円の中に綺麗に収まっているイメージ。伝統と伝統の共鳴とも言えるかもしれません」

Image via Shutterstock
中国料理と日本料理の調和。そこで目指すのは「日本語のような世界だ」と、川田シェフは続ける。
「日本語はもともと文字を持たない言語だったと言われています。そこへ中国から漢字が入ってきて、はじめは漢字だけで漢文のように言葉を書き表わしていた。そこから日本人はひらがなやカタカナといった文字を生み出していき、日本古来の訓読みに、中国語由来の音読みを組み合わせていくことで独自の言語となっていった。
そんな風に2つの文化が共存する世界観や、伝統を大事にしながらも新しいものを取り入れて柔軟に発展していく日本語の独特な豊かさを、茶禅華では表現したいと思っているんです」

雉雲吞湯 Image via 茶禅華
日本の食材の魅力は、清らかな水から生まれる“淡さ”にある
「日本の気候、風土、そして、日本の精神性の中で育まれてきた食材。それらが本来持っている性質を中国料理では、『天性』という言葉で表現します。それをいかに尊重し活かしていくかを、一番大切にしています」
日本料理で一番大事なのは素材だと語る川田シェフ。日本の食材には、独特な“淡み”がある。そうした食材を生み出し、また茶禅華の料理の大事な要素のひとつでもあるのが、日本の水なのだという。
「日本列島の特異性は、山脈と海の距離が短いこと。そのため、清らかなお水がたくさん使えるのです。そして、綺麗なお水が豊富だからこそ、みずみずしい食材や清らかな料理がたくさん生まれてきたのだと思います。茶禅華の料理にも、日本のお水が柔らかさを与えてくれています」

Image via Shutterstock
そんな水や、水があるからこそ生まれる日本の素材の特徴が最も活きるのが、茶禅華という店の名前の由来でもある「お茶」の世界なのだという。
茶禅華には、それぞれの料理に合ったお茶を出す「ティーペアリング」というサービスがある。常時40から50種類以上用意するお茶は季節によって銘柄も変え、ひとつのコースの中で中国茶、台湾茶、日本茶を織り交ぜながら、様々な温度で提供する。

茶禅華のお茶の一例 Image via 茶禅華
「例えば、中国のジャスミンはとても香りが強いため、お茶自体にジャスミンの香りを纏わせていきます。かたや日本の静岡で採れるジャスミンは、香りが柔らかく非常に華奢で、はんなりという言葉が似合います。それを日本のお水で出した時に、独特な香りが生まれます。
この柔らかさやみずみずしさ、淡み、しなやかさ……そうした特徴が、日本の食材の良さではないかと思うのです。日本の野菜は味が薄いとよく言われることもありますが、その薄さは『淡さ』と捉えることもできる。そして、水っぽさは『みずみずしさ』と捉えることもできるわけです。その淡みを活かしてきたのが日本料理であり、そうした食材の特徴を最も活かせるのも、やはり日本料理だと思うのです」

(左)ジャスミンスパークリング (右)ジャスミン茶

静岡のジャスミンを使ったジャスミンティー。
水や素材の繊細さを丁寧に扱い届けるお茶の世界は、自然との調和を強く感じさせるものだと川田シェフは続ける。
「料理とは、大自然で育った食材と自分自身の技術を調和、共鳴させていくこと。つまり、料理は『自然との調和』であり、お茶はその最たるものだと考えています。
まず、天気や大地、水といった自然があり、そこに、発酵や熟成といった人間の叡智を介在させて、良いものが生まれる。ここで、砂糖や酢といった調味料を一滴でも入れたらお茶ではなくなってしまう。ですから、それらを使わずに香りや余韻を作り出す。お茶には、そうした世界観があるのです」

1階のメインダイニング奥にある、さまざまな茶器を揃えたスペース。
「辛さ」を大切に扱い、素材の持ち味を活かしきる
中国料理の中で川田シェフが専門とする四川料理は、麻婆豆腐や棒棒鶏、坦々麺といった辛い料理で知られる。そうした辛い料理が生まれた背景には、寒暖差が大きく、食材も限られた四川の地域性があった。厳しい気候に耐えたり餓えを凌いだりと、身体を守るための料理として生まれてきたのが、胡椒や唐辛子をふんだんに使った辛い料理だったのだ。そうした辛さの中毒性は多くの人を虜にする一方、塩分や油分も多いため、食べ過ぎると身体に負担を与えてしまうものでもあるという。
一方で、何よりも食材を尊重する日本料理の精神は、一流の中国料理の中にも存在するという。それを示すのが、中国料理の本場で語り継がれ、川田シェフも大事にする「真味只是淡」という言葉だ。直訳すると、「真の味は淡に宿る」。中国料理の本質は、巧みな調理・調味によって素材の持ち味を活かしきるところにある、という意味である。
「現地で出会った一流の料理人たちは、辛さをやみくもに用いることはなく、むしろ素材を尊重し生かす、日本料理と近い哲学を持っていました。『辛い』というのはあくまで四川料理のひとつの側面でしかないということです。ですから、いたずらに辛さを扱い、口だけを喜ばせて健康を害する料理になってはいけない。あくまで食材が尊重される形で、辛さを大切に扱う。身体へのダメージを極力減らし、口にとっても身体にとっても美味しく楽しい四川料理を表現したいのです」

その一例が、辣子鶏(ラーズージー)だ。一般的には唐辛子を半分に切り辛さを効かせるが、茶禅華では唐辛子をあえて切らずに丸々使い、そこから出現した香りを手羽先に纏わせる。
「素材の声が聞こえる最低限の味付けをした料理が、人間の身体にとっては一番負担が少ない。そのうえで、先人が作ってきた四川料理の美味しさや面白さは、自分なりに形を変えて受け継いでいきたいと思っています」

辣子鶏 Image via 茶禅華
クリエイティビティを高める、もどき料理の面白さ
その料理を食べて健康になれること。川田シェフは、それが何より大事だと強調する。その精神は、お店でお客さんに提供する料理のみならず、スタッフのまかないにも反映されているようだ。
「茶禅華では金曜日を『精進料理の日』とし、まかないをヴィーガンにしているんです。月曜日から木曜日まで頑張ると、金曜日は胃腸が疲れてくる。そこで一度お肉を遮断することにより、次の日からまた活力が戻ってくるようになるのです。実際に、週に一度の菜食を取り入れてから、スタッフたちがそれまで悩んでいた眠さやだるさ、集中力の低下などの問題がなくなりました。
お肉にはもちろん栄養はありますが、消化しにくく内臓へのダメージが大きい。毎週スタッフたちの様子を見ていても、やはり肉食の持つエネルギーがいかに大きいかを実感します。そうした意味で、菜食は生きていくためにとても重要なものだと考えています」

ヴィーガンの雲白肉。
「また、これは逆説的ですが、菜食は『命を大切にする』という精神にもつながると思うのです。菜食を取り入れると、日頃からいかに自分たちが生命をいただいているのかを意識させられます。そうすると、動物をいただくことへのありがたみをより感じられるようになり、『いただきます』という言葉も、より深いものになっていく。
ちなみに、土曜日は冷蔵庫にあるものを屑や端まで全て使い切る日。金曜日は身体の精進、土曜日は心の精進と定めています」

お豆腐で作ったヴィーガンフカヒレ。
中国では、最古の王朝と言われる殷(いん)の時代に精進料理が生まれる。その後精進料理は清の時代に最盛期を迎え、特に宮廷ではさまざまなもどき料理の出来が競われた。一方日本では、13世紀に曹洞宗の開祖・道元がそうした中国の精進料理を学び、調理の心得を示した「典座教訓(てんぞきょうくん)」に記したところから、さまざまな仏教宗派がそれぞれの精進料理を発展させてきた。
茶禅華の通常の料理には肉も魚介類も用いるが、菜食を希望するゲストがいた場合は、リクエストに応える。その際に出す菜食料理では、中国と日本が発展させてきたもどき料理の遊び心を大切にしていると川田シェフ。それは、全ての人に茶禅華での食事の時間を最大限に楽しんでもらうためでもあるという。

「レストランは、誰にとっても癒される、楽しい場所であるべきだと考えていて。そんな中でお肉が食べられないお客様のお皿をただお魚に変えてしまうのではなく、見た目はそっくりだけれども実はお肉ではないという、ちょっとしたサプライズを仕掛けようと作ったのが湯葉のスペアリブ。
実は、ジャスミンスパークリングも同じ発想から生まれています。お酒を飲めない人が申し訳なさそうに烏龍茶を飲んでいるのを見ていて、なんだか寂しいなと思って。それで、シャンパンのように注いで楽しめるドリンクを作ったのです。
サッカーが手を使えないという制約をかけるから面白いように、菜食における制約は、クリエイティビティを高める要素だと考えています。いかに面白く楽しくできるか。そんな心構えで、菜食料理を作っています」

湯葉で作ったスペアリブ。

しいたけで作った鰻のもどき料理。「弟子がしいたけで作ってきた鰻もどきに、私が先人に教わった手綱まきのアイデアを組み合わせて作りました」
サステナビリティの本質は、全てのものを大切にする心
美しく洗練された佇まいで、食するものに静かに染み渡るような感動を与える料理の数々。取材当日に振る舞っていただいた菜食料理やサービスに感嘆の言葉を伝えると、「今日来てくださるお客さまのために、自分ができることをやっているだけですから」と川田シェフは眉尻を下げて笑う。
高い志や技術を持ちながら、常に謙虚さと周囲へのリスペクトを欠かさない。何事も大切に、丁寧に扱う川田シェフの姿勢は、忙しない世界に生きる私たちが失ってしまっている持続可能性の本質なのではないだろうか。
「日本にはさまざまな宗教がありますが、その中でも日本神道の、全てのものに神が宿っているという『八百万の神』の考え方がすごく好きで。そこには、全てのものを大切にしていくという精神があると思うんですよね。器や包丁といった調理道具から、食材や関わる人、そして自然もそう。
昔の人たちは皆、そうした精神を持っていたのではないかと思うんです。しかし、近代化により経済の波に飲み込まれ、支配されるようになったことで、自然のあげている悲鳴を聞けなくなってしまっている。それが今の私たちが生きる世界なのではないでしょうか」

Image via Shutterstock
「神社で手を合わせるときに、昔から思っていたんですよ。神様っていったいどこにいるんだろうなって。でも実は神様って、どこか遠くではなく、自分の心の中にいるものなのだと最近は思うのです。
中国料理をやるために学んだ仏教・儒教・道教の全てに共通するのが、自分自身の心の中にしっかりとした考えを持つということでした。そしてその根底にあるのは、やはり大自然への畏怖の念のようなものだと感じるのです。
ですから、大事なのは自分の心としっかりと向き合うこと。そこから日常の中の行動が変わり、それが社会や地球にとって良い結果に、自然とつながっていくのではないでしょうか」

(左)杉浦シェフ (右)川田シェフ
【参照サイト】茶禅華 sazenka – Minamiazabu Tokyo –