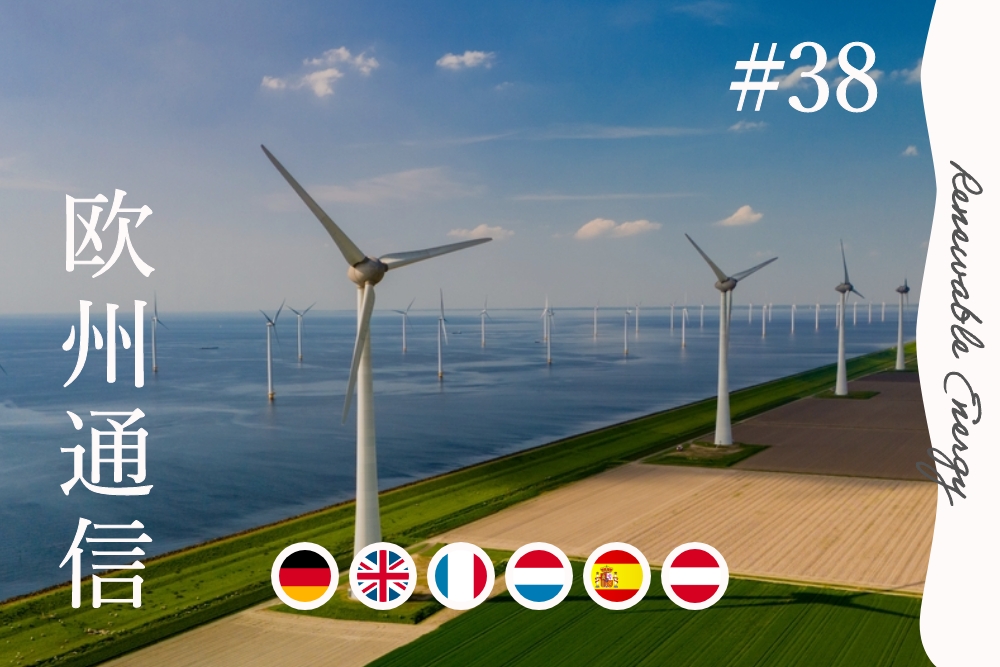近年ヨーロッパは、行政およびビジネスの分野で「サステナビリティ」「サーキュラーエコノミー」の実践を目指し、さまざまなユニークな取り組みを生み出してきた。「ハーチ欧州」はそんな欧州の最先端の情報を居住者の視点から発信し、日本で暮らす皆さんとともにこれからのサステナビリティの可能性について模索することを目的として活動する。
ハーチ欧州メンバーによる「欧州通信」では、メンバーが欧州の食やファッション、まちづくりなどのさまざまなテーマについてサステナビリティの視点からお届け。現地で話題になっているトピックや、住んでいるからこそわかる現地のリアルを発信していく。
前回は「再エネ」をテーマに、欧州各都市のエネルギー事情を取り上げた。今回の欧州通信では「ネイチャーポジティブ」をテーマに、欧州各都市の制度や取り組みを深掘りしていく。
【ドイツ】動物支援設計を採用した都市開発。建物の外壁に動物の住みかをつくる
ドイツでは現在、動物支援設計(Animal-Aided Design:以下、AAD)手法を活用した都市開発が複数進められている。AADはミュンヘン工科大学が2015年に開発した手法で、自然保護を都市計画プロセスに積極的に統合することを目指す。
2019年、ミュンヘン市中央部にAADのコンセプトを実装した住宅が完成した。同プロジェクトは1950年代に建設された2つの中庭を有する3つの住宅棟(住宅99戸)の再開発で、次のような取り組みが実施された。
まず、対象種の選択だ。再開発前に同敷地および近隣に住んでおり、ミュンヘン市が保護する価値があると認めるハリネズミ・スズメ・アオゲラ(キツツキ科の鳥)・コウモリが選ばれた。
建物の屋上は緑化された。ミュンヘン市は100平方メートル以上の適切な屋上の緑化を義務づけていることから、プロジェクトはハーブなどを植栽。緑化された屋上は湿気を高め、対象種の生存に役立つ。

Image via Shutterstock
同プロジェクトで特徴的なのが、動物の「住処」の設置だ。再開発前の建物の外壁にコウモリとスズメが巣を作っていたため、新しい建物の外壁にコウモリとスズメの住処とともにハリネズミ用の住処を、庭にキツツキ用の巣箱を設置した。そのほか、庭にはスズメが砂浴びできる場所や、全4種用に植物と樹木を植栽し、草地を設けた。
AADは、ミュンヘン市やドイツの他都市のプロジェクトで複数活用されている。
【参照サイト】Animal-Aided Design
【参考記事】THE WORLD’S FIRST PROJECT WITH AAD METHOD COMPLETED IN MUNICH
【オランダ】自然と都市の共生を再設計。国土ビジョン「NL2120」と企業のネイチャーポジティブ経済戦略
オランダでは、自然を都市や経済の構造に取り込む新たな国土ビジョン「NL2120」が注目されている。これは2022年に、気候危機や生物多様性の喪失に直面する中で、ワーゲニンゲン大学などの研究機関と政府系団体が共同で発表したもので、2050年までの国土再設計を目指している。
NL2120は、湿地や運河の再生、都市緑化、アグロフォレストリー導入など、自然を基盤とした解決策(Nature-Based Solutions)を広域で展開する構想で、2024年に建築都市賞を受賞するなど高く評価されている。
さらに、オランダの持続可能な経済推進ネットワークMVO Nederlandは、2023年に企業向けの診断ツール「NEx」を導入し、ネイチャーポジティブ経済への移行を政策提言と支援で後押し。官民連携によって自然と共に生きる都市の実現を目指す。
【参照サイト】De Nieuwe Economie Index (NEx)©
【フランス】パリ市が生物多様性フットプリントを測定。市民参加型緑化計画でネイチャーポジティブを推進
フランス・パリ市は、2025年4月に生物多様性を保護・強化するための新たな「バイオダイバーシティ計画」を発表した。この計画は、2025年から2030年にかけて、市内の自然環境を一層充実させることを目的としており、具体的には、500キロメートル以上の多様な植物が共存する生け垣の設置や、保育所や学校周辺の自然空間整備、緑地や歩行者専用街路の新設などが進められる。さらに、100か所以上の生物多様性保護区域や動物保護のための地域が設けられる予定だ。
特に注目すべきは、パリ市が生物多様性フットプリントの測定に取り組む点である。カーボンフットプリントの測定に続き、パリは公共調達やその他の活動を通じて、生物多様性への影響を評価する新たなアプローチを採用する国内初めての都市となる。これによって、都市の消費や活動が生物多様性にどのような影響を与えているかを明らかにし、その影響を減らすために、より環境に優しい商品やサービスを選ぶようにする仕組みを作ることができる。
View this post on Instagram
さらに、2025年3月23日には、市民参加型の緑化計画に関する市民投票が実施され、500の新しい街路を緑化し、歩行者専用にすることに対して、66%の市民が賛成の意見を示した。何事も市民の意見を取り入れた決定を行うことは、パリ市らしいアプローチだ。このように、市民一人一人をまちづくりに積極的に関与させることで、より持続可能でネイチャーポジティブな都市へと変革を進めているのである。
【参照サイト】Découvrez le nouveau Plan Biodiversité en 10 mesures phares
【イギリス】開発時に生物多様性を積極的に改善する、イングランドの「Biodiversity Net Gain」
イギリス・イングランドの「Biodiversity Net Gain(生物多様性ネットゲイン)」制度は、開発活動が生物多様性を損なうことなく、むしろ改善させることを義務付ける法制度だ。この制度により、2019年に施行された環境法に基づき、全ての新規開発プロジェクトに適用され、開発者は生物多様性に与える影響を評価し、改善措置を講じることが義務化されている。具体的には、開発によって失われる生態系の価値を補うため、緑地や湿地の創出、植生の回復、自然生息地の保護などが求められる。
この制度は、特に都市計画やインフラ開発において顕著な影響を与える。建設業界、都市開発業界、不動産業界などでは、プロジェクトの初期段階から生物多様性の評価と改善措置を組み込むことが必須となり、さらに生態系の価値を示す「ネットゲイン」を実現するための具体的な対策を取る必要がある。

Image via Shutterstock
環境保護団体や持続可能な開発を目指す企業は、この制度を重要な一歩だと認識しており、開発活動の環境への影響を最小限に抑え、自然回復を促進する仕組みとして評価している。しかし、一部の開発業界からは、実施に伴うコストや規制の複雑さについて懸念の声も上がっている。
生物多様性ネットゲイン制度は、開発活動と自然環境の共生を促進する一つの重要なアプローチとなっている。今後の効果的な実施には、業界の適応と協力が求められていくだろう。
【参照サイト】Biodiversity Net Gain – UK Government
【参照サイト】英国イングランドにおける生物多様性ネットゲイン政策の現状と評価
編集後記
今回のテーマは「ネイチャーポジティブ」。再エネの文脈では、エネルギーの脱炭素化が主軸だったが、今回はもう一歩踏み込み、「自然そのものとどう共に生きるか」という問いに対する欧州各地のアプローチを紹介した。
ドイツでは、動物の生息空間を都市設計に組み込む「AAD」というアプローチが進行中。オランダは、2050年の国土全体を自然と共生する形に再構築する「NL2120」を構想。フランス・パリは、生物多様性フットプリントの測定を導入し、市民参加型の緑化も本格化。イギリスでは、新たな開発に“生物多様性の改善”を義務づける制度が動き出している。
こうした取り組みに共通するのは、「自然を守る」ではなく「自然を取り戻す」視点と言えるだろう。単なる保護や制限ではなく、都市や経済、暮らしの中にいかに自然を再接続できるか。人と他の生きものたちが共存することを前提とした仕組みが求められている。
気候変動や生物多様性の喪失が急速に進むなかで、「共生」を本気で制度や空間に埋め込もうとする欧州の動きは、決して理想論ではない。未来の都市や暮らしの形を模索するための、実践的な試行だ。
Written by Ryoko Krueger, Kozue Nishizaki, Erika Tomiyama, Megumi
Presented by ハーチ欧州
ハーチ欧州とは?
ハーチ欧州は、2021年に設立された欧州在住メンバーによる事業組織。イギリス・ロンドン、フランス・パリ、オランダ・アムステルダム、ドイツ・ハイデルベルク、オーストリア・ウィーンを主な拠点としています。ハーチ欧州では、欧州の最先端の情報を居住者の視点から発信し、これからのサステナビリティの可能性について模索することを目的としています。また同時に日本の知見を欧州へ発信し、サステナビリティの文脈で、欧州と日本をつなぐ役割を果たしていきます。
ハーチ欧州の事業内容・詳細はこちら:https://harch.jp/company/harch-europe
お問い合わせはこちら:https://harch.jp/contact